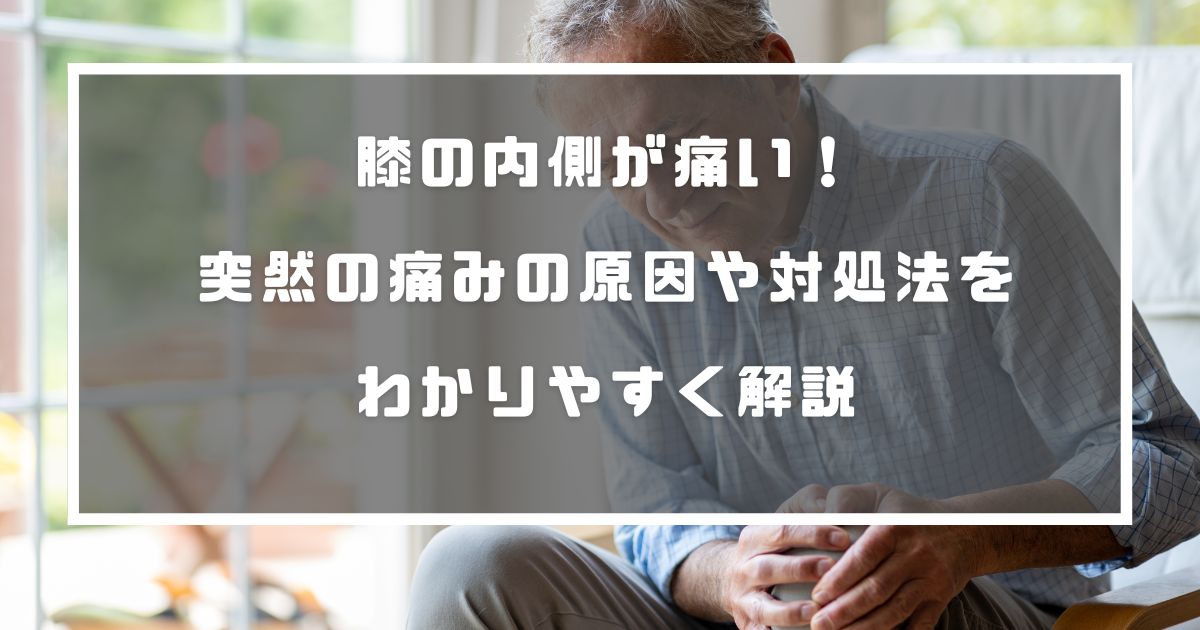簡単な膝の曲げ伸ばしや、日常生活で感じる「膝の内側」の痛みは、心身ともに蝕む症状のため、できる限り早く解決したいところです。
この記事では、膝の内側が突然痛くなった方に向けて、原因や考えられる症状、対処法についてわかりやすく解説していきます。休日や夜遅くに痛みが出たとき、応急処置として有効な方法も紹介していくため、参考にしてください。
膝を曲げると痛いなら鵞足炎(がそくえん)

鵞足炎は、膝から5cmほど下にあるスネの内側にある脛骨を形成する縫工筋、薄筋、半腱様筋を総称した「鵞足(がそく)」と呼ばれる部分が炎症を起こしている状態です。
スネの内側を押したとき、運動後、膝の曲げ伸ばしをしたときに痛みが出るのが主な症状です。
また、痛み以外にも、腫れや熱を持って炎症を起こしているケースも見られます。
原因
鵞足炎の原因は、膝の曲げ伸ばしを繰り返し行っていたり、下半身をひねる動作がある運動を継続的に行っていたりすることが挙げられます。
先述したとおり、鵞足は、縫工筋、薄筋、半腱様筋の3つの筋肉から形成されており、膝関節の動きの負荷が集中しやすい部位です。
日常生活で発症するよりは、運動する方やアスリートに多く見られるため、次のような要因に気をつけてください。
- 足のサイズに合っていない靴を使って運動をしている
- 間違ったフォームで運動している
- 準備運動、クールダウンを行っていない
- 運動不足の解消のため過度に運動を始める
- 柔軟性がない
- 膝に疾患を抱えている
ただし、中年以上の年齢の場合、変形性膝関節症の可能性があり、それぞれ異なる治療が必要になるため、医療機関で診察を受けることを推奨します。
発症しやすい方の特徴
鵞足炎は、日常的に運動をしている方やアスリートで身体に負荷をかけてトレーニングを行っている方が発症しやすいです。
適度な運動は、健康に効果的ですが、過度な運動は、身体への負荷が大きくなるため、無理のない範囲で行うようにして、必要に応じて休息を挟みましょう。
治療法
鵞足炎の治療法は、主に次の3つです。
- 薬物療法
- アイシング
- ストレッチ
鵞足炎は、炎症を引き起こしている状態のため、痛み止めや消炎鎮痛剤を塗ることで、痛みを最小限に抑えて、炎症の改善を試みます。
また、応急処置としてアイシングをすることで、外側から炎症を抑えることも可能です。
炎症と痛みが静まり、ある程度自由に動かせる状態になったら、ストレッチをして、鵞足周辺の筋肉を伸ばして、ストレスがかからないように改善します。
硬直した筋肉が伸び切ると、炎症につながるため、柔軟性を高めるためのストレッチを継続的に行いましょう。
動き始めると痛いなら変形性膝関節症
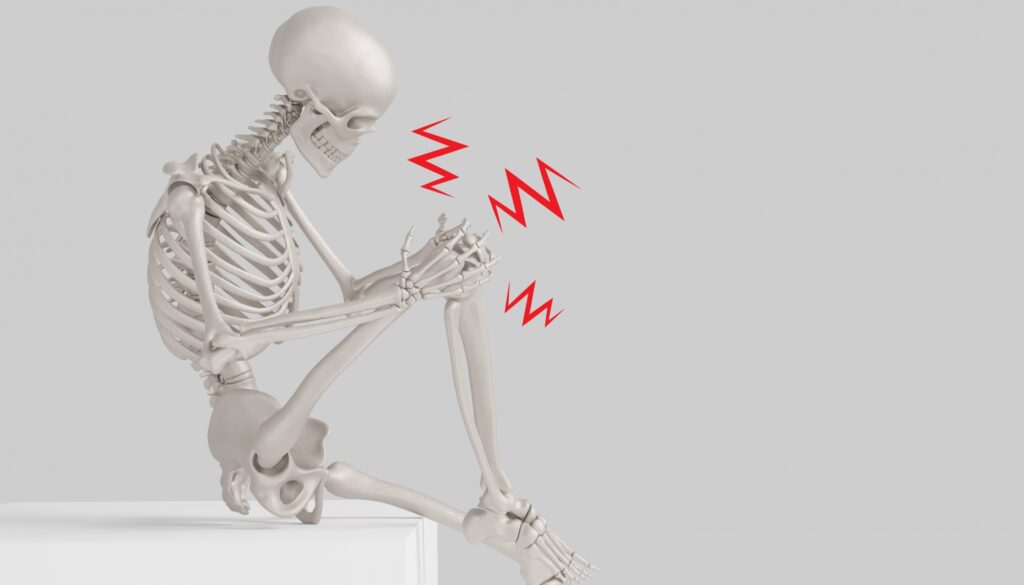
変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ったり、損傷したりすることで、歩行時に痛みを引き起こす病気です。
軟骨には血管が通っていないため、一度損傷すると自然治癒は見込めません。平坦な道を歩く分には問題なくても、階段の上り下りや過度な運動によって痛みや炎症、腫れを引き起こすケースも多いです。
原因
関節軟骨は、老化とともに衰えていき高齢になるほど発症しやすいです。
加齢による変形性膝関節症は、関節軟骨が弾力を失ったり、すり減ったりすることで、変形するため、手術が必要な場合が多いです。
その他にも、肥満、運動不足、過度な運動、遺伝などの要因も関与しているといわれています。さらに、靭帯や半月板損傷などの外傷を患った際に、化膿性関節炎と呼ばれる感染症の後遺症として変形性膝関節症を引き起こすこともあります。
発症しやすい方の特徴
変形性膝関節症を引き起こしやすい方の特徴は、高齢であることが1番に挙げられます。
さらに、発症者の数値を見ると、男性よりも女性の方が多く発症していることから、高齢女性は気をつける必要があります。
また、遺伝因子と環境因子の相互作用によって引き起こされるといわれているため、変形性膝関節症を患っている家族がいる場合、早くから予防をすることが重要です。
治療法
変形性膝関節症の治療法は、主に次の3つです。
- 保存療法
- 手術
- 再生療法
医療機関を受診して、変形性膝関節症と診断された場合、まずは薬物療法、運動療法、装着療法などの保存療法を実践して、改善を試みます。
保存療法に効果が見られなかった場合、骨の損傷部分を取り除いたり、人工関節に取り替えたり、大きな手術をして治療することがあります。
手術に抵抗がある方は、最新医療として手術をしないで改善を試みる再生療法の選択肢もあるため、医療機関に相談してみてください。
内側を押すと痛いなら内側側副靭帯損傷

内側側副靭帯損傷は、膝にある主要な4つの靭帯のうちの1つが傷つく怪我です。
内側側副靭帯は、他の靭帯よりも大きく、膝の外側からの外反ストレスに抵抗しながら関節の内側が開きすぎることを防止する役割を果たします。
膝が過伸展(伸びすぎること)したり、通常では曲がらない方向に曲がったりした際には、内側側副靭帯損傷を疑いましょう。
原因
膝の外側から強い打撃を受けたとき、衝撃によって膝の内側が自然と開いてしまい、内側側副靭帯が伸びたり、切れたりします。
コンタクトスポーツと呼ばれる衝突の多いプレイをしていると、試合中やトレーニング中に、内側側副靭帯損傷を患うケースが多いです。
また、衝突が少ないスポーツであっても、膝が内側に入るような衝撃を受けたり、強く膝をひねってしまったりすると、損傷につながります。
発症しやすい方の特徴
内側側副靭帯損傷は、膝への衝撃が大きいスポーツをしているアスリートが発症しやすいです。
具体的には、次のようなスポーツをやっている方は要注意です。
- アメフト
- ラグビー
- アイスホッケー
上記のように、他の選手と勢いよくぶつかり合ってプレイをするスポーツをコンタクトスポーツと呼んでいます。
ただし、コンタクトスポーツ以外であっても器具を用いる場合は、膝に衝撃が加わり内側側副靭帯損傷につながるケースも少なくありません。
治療法
内側側副靭帯損傷の治療法は、原則的に保存療法で改善を試みます。
症状の重度によりますが、消炎鎮痛薬の服用、超音波、低周波等の物理療法による痒痛対策で痛みや腫れが緩和されるケースが多いです。
一方、保存療法で改善が見られなかった場合は、靭帯の縫合手術とリハビリを行って、回復を待ちます。
水がたまるなら半月板損傷

半月板損傷とは、膝関節の中にある半月板が欠けたり、亀裂が生じたりした状態のことを指します。
慢性化すると、変形性膝関節症を引き起こすリスクがあるため、早期発見で治療を進めることが重要です。
半月板損傷になると、半月板がある膝周辺に強い痛みが生じ、曲げ伸ばしや歩くなどの動作をするだけでも違和感を感じるようになります。
損傷した部分には、関節液が溜まりやすくなるため、膝が動かなくなる「ロッキング」と呼ばれる激痛に悩まされるケースも少なくありません。
原因
半月板損傷は、スポーツや運動をしている最中に、強い衝撃が膝に加わることで、膝の内部にある半月板が傷つくことが原因といわれています。
運動、スポーツをしている方は、日常的にサポーターを装着して、膝を衝撃から守る工夫をすると安心です。
さらに、半月板は加齢とともに劣化して軟弱化したことが原因で、半月板損傷になるケースもあります。
中年〜高齢の方は、軽くつまずくような、日常生活の何気ない動作で半月板が傷つくことがあるため、適度な運動で筋力を高く保つようにしてください。
発症しやすい方の特徴
半月板損傷は、膝に衝撃が加わりやすい運動、スポーツをやっている方が発症しやすいです。
とくに、サッカーやバスケットボールなど、急に動いたり、急に止まったりする動作が多いスポーツをしている方は、準備運動やストレッチを入念に行ってください。
高齢者の場合、筋力低下や半月板の軟弱化が進みやすいため、運動、スポーツをしていなくても発症しやすい傾向にあります。
治療法
半月板損傷の治療法は、次の2つです。
- 保存療法
- 手術療法
保存療法では、炎症を抑える薬物療法や、リハビリ等の運動療法で、半月板損傷の痛みや腫れの改善を試みます。
ただし、必ずしも保存療法で改善するとは限らないため、痛みやロッキングの症状が続くのであれば、手術の検討が必要です。
手術療法は、損傷部分を切り取る切除術と、損傷部分を縫いつける縫合術の2種類の2種類から、症状に合わせて選択します。
半月板切除術では約3か月間、半月板縫合術では約6か月間のリハビリが必要で、松葉杖を使ったり、ギブスを使って可動域を広げたりするトレーニングを行います。
急な膝の内側が痛いときにすぐできる対処法
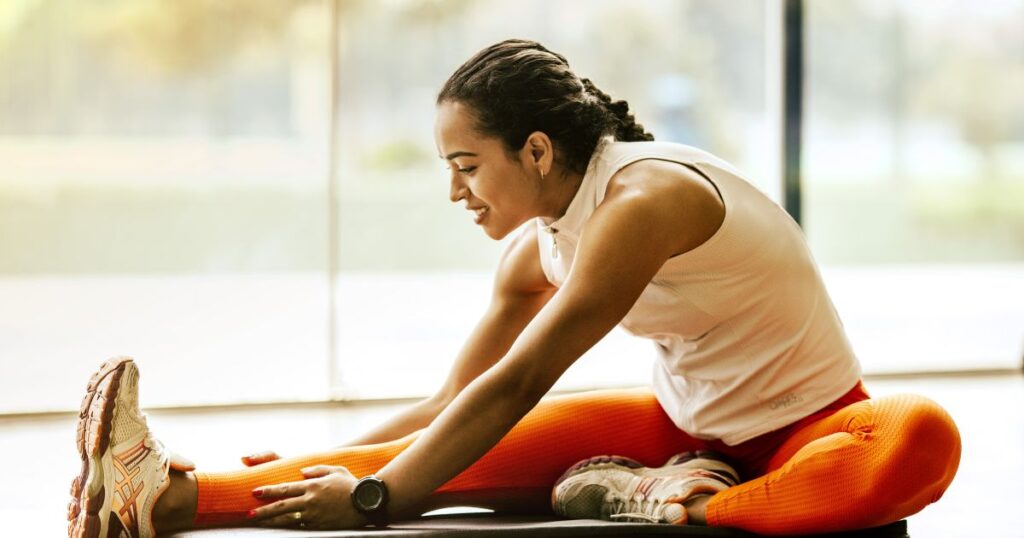
急な膝の内側が痛いときにすぐできる対処法は、次のとおりです。
- ストレッチ
- 冷やす
- 湿布を貼る
- テーピング
- サポーター
それぞれの対処法について解説します。
ストレッチ
膝の痛みを和らげるためには、ストレッチで筋肉を柔軟に保つことが大切といわれています。
痛みを緩和するために安静にする方も多いですが、全く動かさないと、膝周辺の筋肉はさらに硬直して可動域に制限がかかります。
無理にストレッチをして伸ばすことは推奨しませんが、膝関節周辺の太ももやふくらはぎ、足首などをゆっくりと伸ばして可動域を広げましょう。
冷やす
膝の痛みは、「冷やしたほうがいい」といわれたり「温めたほうがいい」といわれたりさまざまですが、急に痛みが出てきた場合は、まずは冷やして応急処置をするのが適切です。
医学的には、痛みが出てきた急性期は冷やして、慢性期は温めることが推奨されています。
急性期は、患部が炎症を起こして、熱を帯びていたり、血液量が増加したりするため、まずは沈静化するために冷やすことが重要です。
急に痛みが出たときに、温めると炎症を促進させて、さらに痛みや腫れがひどくなる可能性があるため気をつけてください。
湿布をはる
湿布には、痛み止めの成分が含まれているため、急な膝の痛みには有効です。
患部を軽く押して痛みを感じる部分を中心に、湿布を貼ると一時的に痛みを緩和できます。
テーピング
膝の痛みが出たときに、テーピングを巻くことで、過度な動きの制限や負荷の軽減サポートに繋がり、痛みや炎症を最小限に抑えられます。
スポーツや登山など、膝に痛みを感じたもののすぐに休息を取れない状態には、テーピングが有効です。
湿布とは異なり、テーピングには痛み止めの成分は含まれておらず、筋肉や骨の固定が目的のため、患部に限らず患部の周辺を巻くように貼ってください。
適切な位置にテーピングを巻けば、一時的に痛みを感じることなくスポーツや登山などを続けられます。
サポーター
テーピング同様に、サポーターを使うことで、膝の痛みを最小限に抑えられます。
サポーターには、圧迫機能がついているため、膝関節用のサポーターを装着すると、膝関節付近の可動域を制限できます。
テーピングは、適切な位置に巻かなければ効果がないのに対して、サポーターは装着のみで効果が期待できるため、難易度の低さが魅力です。
普段からテーピングの使用に慣れていない方は、サポーターを使って膝関節を守りましょう。
【ランキング】痛みが引かない場合は整形外科へ

ここまで、膝の痛みの原因やよくある症例、セルフケアについて紹介しましたが、数日経っても痛みが引かない場合は、整形外科を受診してください。
膝の痛みといえば、整形外科と整骨院のどちらに行くべきか悩む方も多いでしょう。原則的に、整形外科を推奨する理由として、医療機関である点が挙げられます。
整形外科では、医師の判断の元、レントゲン撮影、CT等の画像検査、血液検査を通して、治療方法や薬の処方を行います。
一方、整骨院は、国家資格を持った柔道整復師が診察、施術を行いますが、柔道整復師は医師ではありません。また、整形外科を受診すると保険診療となりますが、整骨院を受診すると保険適用外のため自費診療となります。
そのため痛みが長引くようならば、整形外科を受診して患部の状態を見てもらうことが大切です。
1位:ひざ関節症クリニック
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
急な膝の痛みに関してよくある質問

急な膝の痛みに関するよくある質問について回答します。
マッサージは効果ある?
マッサージは、筋肉の緊張を緩和させて、血流の流れを良くするため、急な膝の痛みに効果があるといわれています。
患部を直接マッサージするのではなく、大腿二頭筋周辺をマッサージすることで、徐々に痛みが緩和されていくため試してみてください。
疲労骨折の可能性はあるの?
スポーツや運動をする中で、同じ動作を何度も繰り返ししている方は、疲労骨折の可能性を疑いましょう。
疲労骨折とは、1度の衝撃で骨が折れる一般的な骨折とは異なり、同じ部位に負荷が蓄積されていくことで発症する骨折のことを指します。
一般的な骨折ほど強い痛みや大きな腫れを伴わないため、気付くのに遅れる方も多いですが、症状が進行すると、完全な骨折に至るケースもあるため要注意です。
疲労骨折特有の症状がないため、膝の痛みが継続的に続く場合は、医療機関を受診して、患部の状態と原因を診断してもらいましょう。
おすすめのストレッチは?
膝の痛みを緩和するために有効といわれている膝周りの筋肉を柔軟にするストレッチを2種類紹介します。
【大腿四頭筋ストレッチ】
- 壁に片手をついた状態で、片足の膝を曲げて、壁に手をついていない方の手でつま先を掴む
- つま先をお尻側に寄せて、前太ももが伸びていることを確認する
- ゆっくりと息を吐きながら30秒間キープする
- (1)〜(3)を左右逆で2〜3セット繰り返す
【前脛骨筋と腓腹筋ストレッチ】
- 両足を伸ばした状態で床に座る
- 妻脇を前に倒しながら伸ばして、スネが伸びていることを確認する
- つま先を手前に引き寄せて、ふくらはぎが伸びていることを確認する
- (1)〜(3)を左右逆で2〜3セット繰り返す
膝の痛みを緩和するためには、適度に筋肉を動かすことが大切です。
ここで紹介した2種類は、どちらも膝関節を支えるために使われている筋肉をほぐせるため、痛みの緩和や負担の軽減につながります。
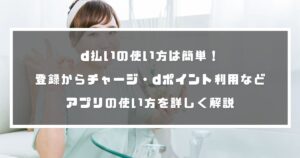
まとめ

この記事では、急に膝の痛みを感じた際に知っておくべき原因、考えられる症状、セルフケアについてわかりやすく解説しました。
一概に「膝の痛み」といっても、セルフケアで完結させられるものから、大きな手術を要するものまでさまざまです。
違和感程度の痛みであれば、セルフケアや応急処置で改善の経過を見るのもよいですが、症状が重いと感じている場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
膝の痛みは、放っておくと悪化する一途を辿るため、早期受診をして原因を突き止め、適切な治療を行うことが大切です。
※本記事の情報は2022年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。