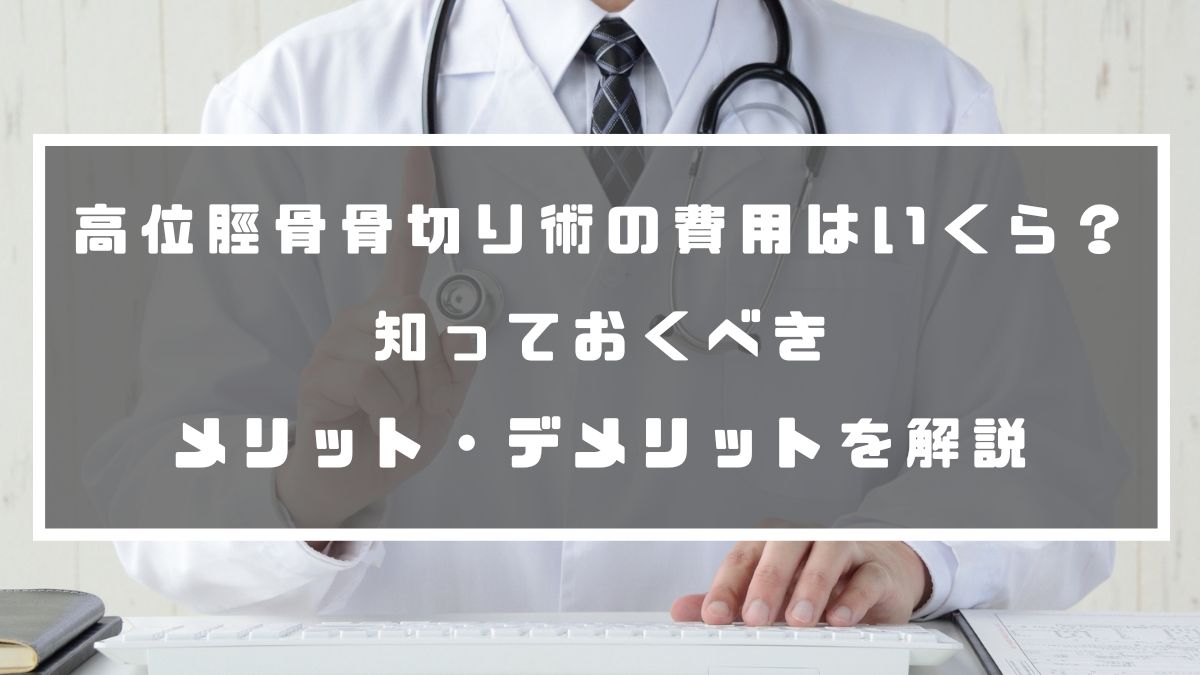高位脛骨骨切り術は、O脚に変形した脚を矯正できる手術です。変形性膝関節症の進行を遅らせる効果も期待でき、思うように生活できないストレスを軽減できます。
しかし、手術は高額になる傾向があるため、費用面を不安に感じている方も多いでしょう。
そこで本記事では、高位脛骨骨切り術の種類や費用を詳しく解説します。種類ごとのメリットやデメリットもわかるため、高位脛骨骨切り術を検討している方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
高位脛骨骨切り術の大まかな費用・負担額

高位脛骨骨切り術の大まかな費用は150万円前後です。
ただし、同じ手術でもクリニックによって料金が異なるため、クリニックを選ぶ前によく調べ、カウンセリングの際に見積書を出してもらうことが重要です。
手術を含めた治療費用の計算方法は、保険診療にかかった費用(1〜3割負担)+保険適応外診療(ベッド代や食事代)です。自己負担額は3割負担の場合45万円前後、1割負担の場合15万円前後となり、別途で入院中のベッド代や食事代がかかります。
また、保険内診療の自己負担額が定められた金額を上回る場合、「高額療養費制度」の対象となり費用の軽減が可能です。
具体的には、所得ごとに1か月あたりの自己負担限度額が設定されており、最高でも1か月10万円前後で受けられます。
※ベッド代や食事代などは別途負担
そもそも高位脛骨骨切り術って何?

高位脛骨骨切り術とは、O脚に変形した脚を、膝下にある脛骨の一部を切除して角度を調整し、X脚に矯正する手術です。
自身の関節を残して症状を改善でき、術後には正座や激しいスポーツができるメリットもあります。手術から切除した骨がつながるまでは、半年以上の時間がかかりますが、痛みも軽快するため生活が楽になるでしょう。
手術は矯正の角度が大きい中程度の症状に適用されます。年齢に制限はありませんが、50歳〜75歳に適用されることが一般的で、比較的若い方にすすめられています。
適用になるかは医師の判断となりますが、重症化するとほかの治療が必要になるため、早めのクリニック受診が大切です。
高位脛骨骨切り術の種類

高位脛骨骨切り術の種類は次のとおりです。
どちらも脛骨を切断して矯正する治療ですが、大きな違いは骨の切開方法です。適用となる症状や体への負担も異なるため、よく理解してから治療法を選択する必要があります。
それぞれ詳しく解説するので、高位脛骨骨切り術を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
Open Wedge HTO(オープンウェッジ法)
Open Wedge HTOは、脛骨の内側から外に向けて切り込みを入れ、人工骨や自家骨を移植して変形を矯正する治療法です。矯正の角度が比較的小さい方に適用されます。
手術にかかる時間は個人差がありますが、約1時間半と短めで、体への負担が少ない点が特徴です。
近年ではOpen Wedge HTOが高位脛骨骨切り術の主流ですが、矯正の角度に限度がある点はデメリットといえます。
Hybrid Closed Wedge HTO(ハイブリッドクローズドウェッジ法)
Hybrid Closed Wedge HTOは、脛骨の外側から内側に向けて楔状に切り込みを入れて短縮させ、矯正する治療法です。
ある程度矯正する角度が大きい方や、膝蓋大腿関節症を合併している方などの手術に用いられています。
脛骨の隣にある腓骨も一部切除する必要があり、Open Wedge HTOに比べ、体の負担が大きくなりやすい点はデメリットといえます。
Open Wedge HTOの特徴

ここでは、Open Wedge HTOの特徴を解説します。主な特徴は次のとおりです。
高位脛骨骨切り術の主流として普及していますが、症状によっては適用にならない場合もあるため、しっかり確認しておきましょう。
自身の関節は温存され機能維持
Open Wedge HTOの特徴には、自身の関節は温存され機能維持できる点が挙げられます。
高位脛骨骨切り術が適用される変形性膝関節症の治療には、人工膝関節置換術という治療法もあり、自身の関節を取り除き、人工の関節に置き換えます。
痛みや歩行能力を改善できますが、正座や激しいスポーツはできず、10〜15年で交換が必要です。
Open Wedge HTOであれば自身の関節を温存できるため、経過がよければ再手術の必要はなく、正座やスポーツも可能になったケースがあります。
元の生活を取り戻したい方にとっては嬉しいメリットでしょう。
日常生活に制限がない
Open Wedge HTOの特徴には、日常生活に制限がない点も挙げられます。先述したとおり、関節機能が温存されるため、健康時と同じように正座やスポーツが可能です。
また、重労働もおこなえるため、病気の影響で長期間仕事を休んでいた方も復帰が期待できます。
手術1週後から歩行訓練が可能
Open Wedge HTOは、手術1週間後から歩行訓練が可能です。Hybrid Closed Wedge HTOに比べ体への影響が少なく、術後は比較的早い回復が期待できます。
手術のために入院が必要になりますが、3週間程度で歩いて退院できるため、自宅での生活も不自由はないでしょう。
固定のために埋め込む金属プレートは約1年後に再手術で取り除きます。再手術の際は、数日で歩行でき、生活に大きな支障はでません。
人工骨は2~3年で自身の骨に置換
Open Wedge HTOは、挿入した人工骨が2〜3年で自身の骨に置き換わる点も特徴です。施術では切除した骨の隙間にβ-TCPという人工骨を挿入します。
β-TCPは体への親和性が高く、骨を形成する骨芽細胞に吸収され、手術から3〜5年で自身の骨になります。感染症のリスクが少なく、最終的には自身の骨に置換されるため、異物を体内に入れる抵抗感も緩和できるでしょう。
また、固定に使用する金属のプレートやボルトは、約1年後に再手術で取り除き、骨に開いた穴は自然に埋まります。
Hybrid Closed Wedge HTOの特徴

Hybrid Closed Wedge HTOには次のような特徴があります。
メリットやデメリットが両方あるため、適用となる場合はよく理解してから手術を受けることが大切です。それぞれの特徴を詳しく解説します。
腓骨の一部切除が必要
Hybrid Closed Wedge HTOでは、腓骨の一部を切除する必要があります。
腓骨とは、脛骨の隣にある細い骨で、歩行時の衝撃吸収や足関節をいろいろな方向に動かすための骨です。Hybrid Closed Wedge HTOは脛骨を外側から切除する治療であるため、腓骨もあわせて切除する必要があります。
そのため、Open Wedge HTOに比べ体への負担が大きくなります。
矯正する角度が大きい場合に適用
Hybrid Closed Wedge HTOは、矯正する角度が大きい場合に適用となる施術方法です。
Open Wedge HTOは矯正できる角度に制限がありますが、Hybrid Closed Wedge HTOであれば変性が強い方でも治療できます。
また、膝蓋骨がずれたり動かなくなったりする膝蓋大腿関節症を合併している方にも適用となります。
重度のO脚は、歩行や膝の曲げ伸ばしが困難になるなど生活に支障が出るため、Hybrid Closed Wedge HTOを受けることでQOLが向上するでしょう。
リハビリまでに時間がかかる
Hybrid Closed Wedge HTOは、矯正する角度が大きくなるため、リハビリが不要になるまで時間がかかります。
主流となるOpen Wedge HTOのリハビリ期間は約1年となり、Hybrid Closed Wedge HTOはもう少し時間がかかる可能性があります。手術翌日から少しずつリハビリを始め、退院後は外来リハビリテーションの継続が必要です。
回復までの期間は個人差があるため、回復までの期間が不安な方は医師と相談のもと、ほかの治療法も検討するといいでしょう。
Open Wedge HTO手術の流れ

ここでは、高位脛骨骨切り術で多く用いられるOpen Wedge HTOの手術の流れを解説します。大まかな流れは次のとおりです。
- 関節鏡にて関節内を観察
- 不要な骨や組織を取り除く
- 皮膚を切開し脛骨を露出
- レントゲンで角度を確認
- 人工骨挿入
- 金属プレート・スクリューで固定
- 縫合
上記の手術の前には、医師から詳しい手術の説明があり、術後回復の具体的例が提示されます。
患者が手術内容や効果、リスクに納得したうえでおこなわれるため、不安がある場合は事前にしっかり相談しておきましょう。
1:関節鏡にて関節内を観察
全身麻酔や局所麻酔をおこなった後、関節付近に数ミリの穴をあけて関節鏡を挿入し、関節内を観察します。
関節鏡とは、関節用の内視鏡のことです。カメラがついた器具を関節内に挿入し、モニターで内部の確認が可能です。関節鏡を使用し、不要な骨や組織がないかや、骨の位置を確認します。
2:不要な骨や組織を取り除く
関節鏡で関節内を観察した際に、不要な骨や組織が確認できた場合は取り除きます。
3:皮膚を切開し脛骨を露出
皮膚を数センチ切開して、切り込みを入れる脛骨を露出します。骨にくっついている組織を剥がす作業も同時におこないます。
4:レントゲンで角度を確認
レントゲンを撮影し、あらかじめ予定していた脛骨の切り込みを入れる角度を確認します。
5:人工骨挿入
角度を確認できたら、脛骨の一部に切りこみをいれて、脚の荷重バランスの矯正を調整します。調整できたら切り込んだ隙間に人工骨を挿入します。
6:金属プレート・スクリューで固定
安定させるために金属のプレートを使用して、スクリューで固定をします。
7:縫合
金属プレートを装着できたら十分に洗浄し、切開した部分を縫合して手術は完了です。
術後は傷口に血液がたまるため、専用のドレーンを挿入して外へ流し出れるようにします。麻酔がきれて意識が回復したら、足の動きや血圧、体温などを確認します。
また、痛みがある場合は、痛み止めや麻酔で緩和できるため、無理せず看護師へ伝えましょう。
手術にかかる時間は矯正が必要な角度によって異なりますが、1時間半〜2時間程度が一般的です。
高位脛骨骨切り術の治療をおすすめできる方

高位脛骨骨切り術による治療は、次のような方におすすめです。
とくに、変形性膝関節症を患っていてO脚が進行している方は、高位脛骨骨切り術が適用となる可能性が高いといえます。
それぞれ詳しく解説するので、医師から高位脛骨骨切り術を提案されている方はぜひ参考にしてみてください。
適用年齢は50歳〜75歳
高位脛骨骨切り術の適用年齢は50歳〜75歳で、実際に治療を受けている方の平均年齢は65歳弱です。とくに、仕事やスポーツなどで体をよく動かす方や、年齢が若い方にすすめられる傾向があります。
年齢制限はなく、健康状態が良好であれば誰でも適用となる可能性があり、中には80代の方で治療を受けている方もいるようです。
一方で、変性が強く10度以上膝が伸びない方や、骨密度や筋力の低下、関節のかたさが認められる高齢者は人工膝関節全置換術をすすめられます。
とくに、80歳以上の高齢者は術後のリハビリについていけない可能性もあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
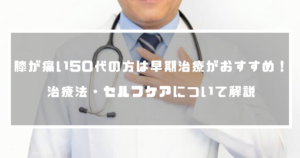
変形性膝関節症の方
高位脛骨骨切り術は、変形性膝関節症の方にもおすすめの治療です。変形性膝関節症は、膝関節のクッションの役割をはたす軟骨が、老化や肥満で少しずつすり減る病気です。
歩行時や階段の上り下りで痛みを感じ、正座もできなくなる症状があり、進行するとO脚に変形していきます。
O脚になるまで進行すると歩行も困難になり、高位脛骨骨切り術による治療がすすめられます。
ただし、年齢や健康状態によっては人工膝関節置換術が適用となる場合もあるため、治療方法が適しているかは医師としっかり相談しましょう。
運動・肉体仕事を続けたい方
高位脛骨骨切り術は、運動や肉体仕事を続けたい方にもおすすめです。高位脛骨骨切り術の大きな特徴として、自身の関節を温存できる点が挙げられます。
関節が残ることで機能維持や軟骨の修復が期待でき、膝の可動域が改善されます。
完全に回復するまで1年ほどの期間を要しますが、スポーツや重労働の仕事も復帰できる可能性が高いでしょう。
O脚で悩んでいる方
高位脛骨骨切り術はO脚で悩んでいる方にもおすすめです。そもそも高位脛骨骨切り術は、O脚に変形した脚を矯正するための治療です。
O脚になる原因には、変形性膝関節症や関節リウマチなどの病気と、姿勢の悪さが影響する場合があります。
病的なO脚を治療する唯一の方法は、高位脛骨骨切り術といわれており、重症になる前に受けることで早期の回復も可能です。
一方、姿勢の悪さによるO脚は、ストレッチや筋トレで改善が期待できます。
ただし、何もせず悪化させると、半月板や軟骨のすり減りを招き、変形性膝関節症に進行する可能性があるため対策が必要です。
高位脛骨骨切り術のメリット

高位脛骨骨切り術には、次のようなメリットがあります。
それぞれ詳しく解説していきます。高位脛骨骨切り術を受けるか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
O脚をX脚ぎみに矯正できる唯一の方法
高位脛骨骨切り術は、O脚をX脚ぎみに矯正できる唯一の方法とされています。
変形性膝関節症や関節リウマチなどの骨自体が変形する病的なO脚は、整体や保存治療での改善は困難です。
手術療法においても、矯正する角度が大きいO脚を治療できるのは高位脛骨骨切り術のみであるため、できる限り年齢が若いうちに受けると早い回復が期待できます。
O脚の進行を遅らせることが可能
高位脛骨骨切り術は、O脚や変形性膝関節症の進行を遅らせることが可能です。
変形性膝関節症は、老化や肥満以外にも、O脚によって重心が内側に偏り引き起こされることがあります。内側の軟骨に重心がかかることで劣化が進み、さらにO脚の角度が大きくなります。
高位脛骨骨切り術はO脚を矯正し、重心を元の位置に近づけられるため、病状の進行を防げます。
ただし、術後に膝の負担となる生活を続けていると、再発する可能性があるため、正しい姿勢や歩き方を身に付けることも大切です。
人工関節を使わずに症状を改善可能
高位脛骨骨切りは、人工関節を使わずに症状の改善が可能です。
膝関節の手術には、半月板や軟骨がすり減っている関節を人工関節に置き換える人工膝関節置換術という治療法があります。膝関節の変性が強い方に適用されますが、自身の関節を失い、膝を完全に曲げられなくなります。
高位脛骨骨切り術であれば、骨の一部を切除してO脚を矯正し、すり減った軟骨の修復が期待できるため、自身の関節を残しつつ機能維持も可能です。
ただし、症状が重度まで進行し、骨まで破壊されている場合は、人工関節置換術が必要になります。
そのため、自身の関節を温存するなら、早めに高位脛骨骨切り術を受けることが大切です。
体への影響が少ない
高位脛骨骨切り術は、関節機能が温存できるため体への影響が少ない点もメリットです。個人差はありますが、術後は1〜2週間程度で松葉杖をついて歩けるようになり、1か月程度で歩いて退院できます。
しっかりとしたリハビリが必要となりますが、体への負担が少なく、術後の回復も比較的早いため、デスクワークであれば退院後すぐに復帰できます。
ただし、人工骨が癒合するまでに3〜6か月程度、運動や過重労働ができるまでには1年程度かかるため、完全に回復するまで根気強くリハビリが必要です。
術後の運動制限がない
高位脛骨骨切り術は、術後の運動制限がない点もメリットといえます。人工関節置換術とは異なり、自身の関節を温存して機能維持できるため、回復すれば膝の曲げ伸ばしが可能になります。
正座はもちろん、激しいスポーツや重労働も制限なくできるようになり、快適な生活を取り戻せるでしょう。
高位脛骨骨切り術のデメリット
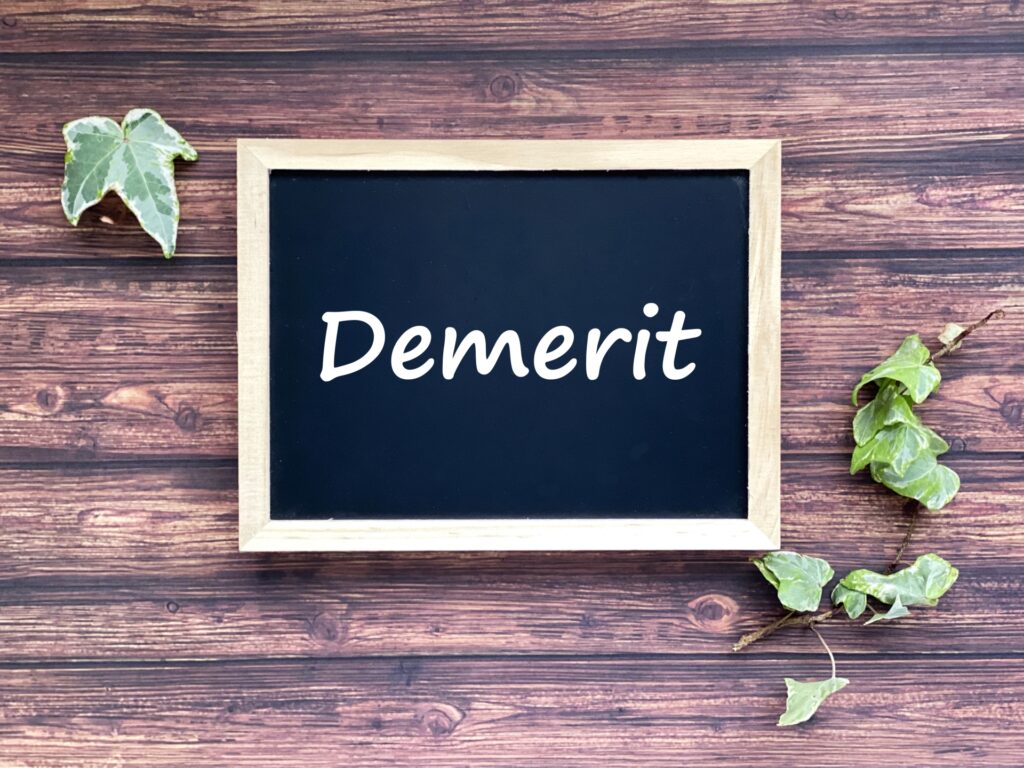
高位脛骨骨切り術には、多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
手術であるためリスクが伴うことは前提となりますが、病状や生活スタイルによっては高位脛骨骨切り術が適さない場合もあります。
それぞれのデメリットについて詳しく解説するので、病的なO脚に悩んでいる方は理解したうえで高位脛骨骨切り術を検討してみてください。
ある程度の入院期間が必要
高位脛骨骨切り術のデメリットは、ある程度の入院期間が必要となる点が挙げられます。
個人差はありますが、一般的な入院期間は4〜6週間程度です。手術の2日目以降から、膝に負担をかけない状態でリハビリを開始し、1週間位から少しずつ体重をかけていきます。
術後3〜4週間ほど安定した歩行ができるようになり、階段の上り下りや日常生活の動作ができるかなどを確認した後、退院となります。
他院後の生活に慣れるまでを考慮すると、2か月程度の休暇が必要となるため、仕事を長期間休めない方は慎重に検討する必要があるでしょう。
骨が癒合するまでは痛みが続く
高位脛骨骨切り術は、骨が癒合するまでは痛みが続く点もデメリットです。
切除した骨が癒合するまでに3〜6か月程度の時間がかかります。癒合するまでは、歩いたり体重をかけたりすると痛みを感じます。
ただし、高位脛骨骨切り術が適用されるのは症状が中程度以上からとなり、手術を受ける時点で強い痛みがあります。時間はかかりますが、手術を受ければ少しずつ痛みは改善していくため、治療前より生活しやすくなるでしょう。
骨が癒合までに期間がかかる
高位脛骨骨切り術のデメリットには、骨の癒合までに期間がかかる点も挙げられます。
先述したように、切除した骨が癒合するまでに3〜6か月程度の時間がかかり、それまでは痛みを感じやすく、激しい運動はできません。運動制限がない治療法ではありますが、骨癒合が完成するまでは不便に感じる場面もあるでしょう。
無理に動かそうとすると炎症が起こる可能性があるため、術後の活動については事前にきちんと確認してから治療を受けるか検討してみてください。
合併症を発症する可能性もある
高位脛骨骨切り術は、比較的体への負担が少ないといわれていますが、合併症を発症する可能性もあります。考えられる合併症は次のとおりです。
- 腓骨短縮
- 麻痺症状
- 持病の悪化
- 肺炎
- 膀胱炎
- エコノミークラス症候群
- 感染症
- 血栓塞栓症など
腓骨の近くには神経が通っており、手術中に傷つけてしまうと、痺れや下垂足などの麻痺症状が残る可能性があります。
合併症については手術前に医師から説明があるため、十分考慮したうえで検討が必要です。
有痛性偽関節になることもある
高位脛骨骨切り術は、有痛性偽関節になるリスクもあります。有痛性偽関節とは、切除した部分の骨が再生途中で止まってしまい、きれいに癒合せず、関節のようになる状態のことです。
偽関節は癒合不全とも呼ばれ、癒合していない部分が不安定になり、再手術が必要になる場合もあります。再手術になれば回復や退院までの期間が伸びるため、患者にとって大きな負担となるでしょう。
まとめ

高位脛骨骨切り術の費用は、クリニックによって異なりますが、概算で150万円前後です。保険適用となるため、自己負担額は3割負担の場合45万円前後、1割負担の場合15万円となり、ベッド代や食事代がかかります。
治療費は決して安くなく、治療した骨が癒合するまでに長い期間がかかるため、他の治療法も加味して決めることが大切です。
ただし、O脚を矯正する唯一の手術であり、次のようなメリットもあります。
- O脚の進行を遅らせることが可能
- 人工関節を使わずに症状を改善可能
- 体への影響が少ない
- 術後の運動制限がない
とくに自身の関節を残して治療できる点は、膝の機能維持ができ運動や従労働など、以前のような生活を取り戻すことも期待できます。
重症になると高位脛骨骨切が適用されず、工膝関節置換術が必要になる場合もあるため、早めに医師に相談しましょう。
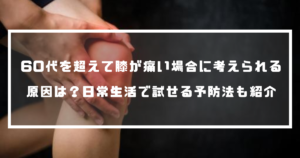
※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。