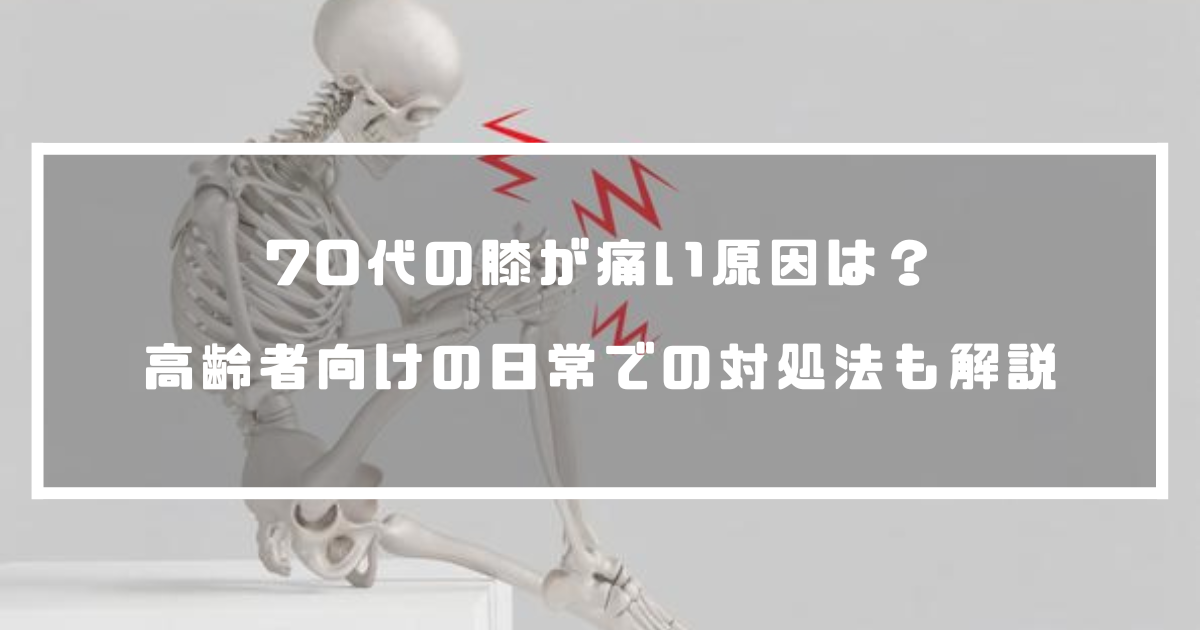高齢になると膝に痛みを感じやすくなりますが、年齢のせいだからとそのまま放置する方も少なくありません。しかし、膝の痛みの多くは何かしらの病気が原因であり、放置しておくと歩けなくなるほど症状が進んでしまう場合もあります。
とくに、70代の4〜5割が膝関節症を患っているといわれており、早い段階で治療を始めることが大切です。
そこで本記事では、70代で膝が痛む原因や、治療法を解説します。日常で取り組める痛み対策もあわせて紹介するため、膝の痛みに悩んでいる70代の方は、ぜひ参考にしてみてください。
高齢者に膝の痛みが出たとき

年齢を重ねると多くの方が膝の痛みを経験しますが、70代の4〜5割は変形性膝関節症が原因であるといわれています。
膝軟骨がすり減ることで関節が変形する病気ですが、中には痛みが強くなく、知らない間に症状が進行するケースもあります。
すり減った軟骨は元に戻ることはないため、早期発見と治療が必要です。そこで次では変形性膝関節症の原因や症状を解説します。
変形性膝関節症の可能性
膝関節には、大腿骨と脛骨の間に関節軟骨とよばれる組織があり、膝にかかる負担を和らげるクッションや、動きをスムーズする役割があります。
変形性膝関節症は、関節軟骨が老化や肥満、外傷などによってすり減ることで発症する病気です。膝軟骨のすり減りが進むと次のような症状が現れます。
初期:膝のこわばり、膝を動かすと鈍い痛みがある
中期:階段を上り下りが困難になる、膝関節の熱感や腫れ、安静時にも痛む
末期:激しい痛み、歩行困難、膝を伸ばせない
初期症状は時間が経つとおさまることが多いため、中期以上になってからクリニックを受診する方も少なくありません。
しかし、病状が進むほど元の状態に戻ることが困難になるため、違和感を感じた時点で医師に相談しましょう。
膝の痛みが出たときの治療法

変形性膝関節症の痛みには、次のような治療法があります。
とくに、運動療法と薬物療法は、変形性膝関節症のはじめにおこなう基本的な治療法です。しかし、症状が進行していると手術が必要になる場合もあり、状況に応じて治療法を選ぶ必要があります。
そこで次では、それぞれの治療法の特徴やメリット、デメリットを解説します。
運動療法
- 筋肉を鍛えて膝の安定性を高める
- 膝の動きをよくする
膝に痛みを感じると運動を避けるようになり、筋力が低下したり、膝の可動域が狭くなったりします。膝の負担が大きくなるため、病状が悪化してさらに運動不足になる悪循環に陥る方も珍しくありません。
運動療法は、適度な運動をおこなうことで、病状の進行を遅らせ痛みを緩和させる効果が期待できます。
しかし、誤った方法で運動をおこなうと、症状の悪化や痛みが増す可能性もあるため、医師や理学療法士の指示に従って適度におこなうことが大切です。
薬物療法
- 薬を用いて炎症や痛みを抑える
- 外用薬、内服薬、座薬、注射薬な種類が豊富
薬物療法は、外用薬や内服薬、座薬など薬物を用いて、炎症や痛みを抑える治療です。即効性に優れた薬もあるため、慢性的な痛みに悩まされている方は楽になるでしょう。
ただし、あくまで炎症や痛みの緩和が目的であり、根本的な治療にはなりません。また、膝関節の負担を軽減するために、体重管理や運動療法を並行しておこなう必要があります。
手術
- 重度の症状でも治療できる
- 3つの施術方法から症状にあわせて選択
変形性膝関節症における手術は、運動療法や薬物治療でも改善されなかった場合に検討される治療法です。
施術方法には関節鏡視下手術、高位脛骨骨切り術、人工膝関節置換術の3種類があり、症状や患者の希望にあわせて選択されます。
中でも人工膝関節置換術は、変形性膝関節症の最終的な治療として、骨まで変形している方や、体力が落ちている高齢者などにおこなわれます。
重度まで進行している場合でも治療できる点が大きなメリットですが、一方で入院が必要になる点や合併症のリスクがある点はデメリットといえるでしょう。
膝が痛いときに実践できる日常での対策

痛みは医療の力のみでなく、日常での対策で緩和させることが可能です。具体的には次のような対策があります。
それぞれ詳しく解説するため、痛みに悩んでいる方はぜひ参考にして今日から取り入れてみてください。
ストレッチや軽い運動
膝の痛みにはストレッチや軽い運動が効果的です。痛みで関節を使わないようになると筋力が低下し、余計に膝の負担となります。痛みを悪化させないためにも、ストレッチや軽い運動で膝関節周りの筋肉を柔軟に保つなどの対策が大切です。
次のストレッチは自宅でも気軽にできるため、ぜひ取り組んでみてください。
1:壁に向かって立ち、両手をついて足を前後に開く
2:前に開いた脚の膝を曲げて体重を前に移動させる
3:後ろに開いた脚の膝もかかとを床から離さないようにゆっくり曲げ、アキレス腱を伸す
4:20〜40秒間キープし、同じ流れを左右5回ずつおこなう
※つま先が外側や内側を向かないように意識しましょう。
1:壁に片手をついて立ち、片足の膝を曲げ、壁についていない方の手でつま先をつかむ
2:つかんでいるつま先をお尻の方へ引き寄せ、太ももの前側を伸ばす
3:息を吐きながら30秒キープし、同じ流れを左右2〜3回ずつおこなう
姿勢を正しくして歩く
膝の痛みには、姿勢を正して歩くこともおすすめです。姿勢が悪いと膝への負担が増し、関節症を悪化させてしまう可能性があります。
とくに、女性に多い内股は足の筋肉をゆるめてしまうため、猫背や足先に力が入らなくなり、結果的に膝の負担になります。そのため、日頃から正しい姿勢を意識して生活するよう心がけてください。
正しいウォーキングをするためには、立っているときの姿勢を正すことから始めましょう。正しい姿勢のポイントは次のとおりです。
- 顎をひく
- 横から見て耳、肩、くるぶしが一直線にする
- 肩の力をぬく
- 下腹部に力を入れる
- お尻の筋肉を意識して肛門に力を入れる
正しい姿勢になったら、次のポイントを押さえて歩きましょう。
- 背筋を伸ばす
- 膝を伸ばす
- 腕は自然に降る
- 足の親指でしっかり蹴り出し、かかとで着地する
日常的に意識すれば、膝の負担にならないように歩けるため、ぜひ継続してみてください。
自身に合った靴を選ぶ
靴は固い道を歩く際の衝撃をやわらげ、膝の負担を抑える役割があります。
自身にあった靴を履くことで、歩行時の衝撃から膝を守り、変形性膝関節症の予防や進行抑制にも繋がるため、きちんと選ぶことが大切です。
靴選びのポイントは次のとおりです。
- 足長と足囲のサイズにあっているか
- フラットで軽いか
- 足の甲を紐やベルトで固定できるか
- かかと部分が硬く、型崩れしにくいか
とくに、足長はあっていても足囲があっていない靴を履いている方は多いため、まずは自身の足をきちんと計測してみてください。
そのほかのポイントも膝を安定させながら歩くために重要なポイントになるため、商品をしっかり比較しながら選びましょう。
膝を温めて血流をよくする
膝を温めて血流をよくすると痛み対策に繋がります。
冷えによって血流が悪くなると、筋肉をこわばり痛みを引き起こしやすくなります。そのため、日常的に保温サポーターを活用したり、お風呂にゆっくり入ったりして膝を温めるようにしましょう。
また、ストレッチやマッサージなどでも血流は促進されるため、あわせて取り入れてみてください。
膝用のサポーターをつける
膝の痛み対策には、膝用サポーターも効果的です。サポーターには次のような役割があります。
- 膝を安定させてる
- 触圧覚を刺激して痛みを和らげる
- 膝の冷えを防ぐ
このように、サポーターは膝の負担を軽減させて痛みを和らげる効果が期待できます。
固定や保温、通気性など商品によって特徴が異なるため、使用するシーンにあわせて選んでみてください。
ただし、サポーターを長時間つけると筋力が低下する場合があるため、歩行時や家事をするときなどに使用し、安静時にはできる限り外すようにしましょう。
シニアにもおすすめの膝サポーター3選

シニアにもおすすめの膝サポーターは次の3つです。
上記のサポーターは膝をしっかり固定でき、機能性にも優れているため、初めて購入する方にもおすすめです。それぞれの特徴を詳しく解説していくため、サポーターを購入したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
バンテリンサポーター【膝専用】
バンテリンサポーターは、興和が販売する特許技術のテーピング構造を採用しているサポーターです。
膝を下と横から持ち上げるようにしっかり支えてくれるため歩きやすくなり、触圧覚を刺激して痛みを緩和できます。通販やドラッグストアでも購入できる人気商品であるため、気軽に始めたい方にもおすすめです。
| メーカー | 興和 |
| 形状 | 筒型 |
| 素材 | ナイロン、ポリウレタン |
| サイズ展開 | 小さめSサイズ:31~34cm ふつうMサイズ:34cm~37cm 大きめLサイズ:37cm~40cm ゆったり大きめLLサイズ:40~43cm |
パテックス機能性サポーター【膝用ハイグレードモデル】
パテックス機能性サポーター【膝用ハイグレードモデル】は、膝関節から大腿四頭筋までサポートできるサポーターです。
独自のクロステーピング構造と、ずれ防止機能でしっかり膝関節を固定できます。膝にかかる衝撃を緩和し、左右のふらつきも抑えてくれるため、運動する際に使用するのもおすすめです。
| メーカー | 第一三共ヘルスケア |
| 形状 | 筒型 |
| 素材 | ポリエステル、ポリウレタン |
| サイズ展開 | 男性用 Mサイズ:34cm~37cm Lサイズ:36cm~39cm LLサイズ:38cm~41cm 女性用 Mサイズ:33cm~36cm Lサイズ:35cm~38cm LLサイズ:37cm~40cm |
FCひざガードサポーター
FCひざガードサポーターは、程よく膝関節を圧迫できるサポーターです。膝裏にはメッシュ素材が使用されているため揮発性に優れており、汗をかきやすい方も快適に使用できるでしょう。
また、屈伸時の食い込みも軽減できるため、歩行時や家事をする際など、日常的なシーンにもおすすめです。
| メーカー | 白十字 |
| 形状 | 筒型 |
| 素材 | ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン |
| サイズ展開 | Mサイズ:30cm~34cm Lサイズ:34cm~38cm LLサイズ:38cm~42cm |
膝の痛みが出たときの注意点

膝の痛みが出たときの注意点は次のとおりです。
上記のポイントを押さえておかないと、症状が悪化して痛みが強くなる可能性もあります。痛みをしっかり改善したい方は、ぜひチェックしてみてください。
放置しない
膝の痛みが出た際は、放置せずにクリニックに相談しましょう。
とくに高齢者は、痛みが出ても年齢のせいだからと我慢する方も珍しくありません。高齢者の膝の痛みは変形性膝関節症のような病気が原因である可能性が高く、放置すると症状がどんどん悪化していきます。
症状が悪化すると選択できる治療の種類が限られてしまうため、痛みや違和感を感じたら早めにクリニックを受診してみてください。
ハードな運動は避ける
膝に痛みがある場合はハードな運動は避けてください。痛み対策には運動療法が効果的と先述しましたが、ハードな運動はかえって膝に負担をかけ、症状を悪化させる可能性があります。
まずは医師に相談し、どの程度の運動であれば問題ないか指示をもらってから適度な運動をおこないましょう。
飲酒や喫煙は控える
過度な飲酒は軟骨の弾力性を低下させるうえ、喫煙は軟骨の生成に必要なビタミンCを減少させる作用があります。変形性膝関節症を発症している場合、痛みが増す可能性もあるため、飲酒や喫煙は控えてください。
急にやめられない方は、少しずつ量を減らして摂取しすぎないようにしましょう。
膝の痛みがひかないときはクリニックを受診しよう

膝の痛みがおさまらないときは、早めにクリニックを受診しましょう。
膝の痛みには、変形性膝関節症のような病気が隠れていることが多く、クリニックを受診すれば症状の軽減や、生活の質を維持するための対策を知れます。
痛みを軽減する治療には、運動療法や薬物療法などがあり、生活習慣の改善に必要なことも提案してもらえるでしょう。しかし、症状が悪化してからでは治療の選択肢が狭くなるうえ、大掛かりな手術が必要になることもあります。
そのため、安静にしたり薬を飲んだりすると痛みが軽減する場合でも、クリニックに相談した方がよいでしょう。
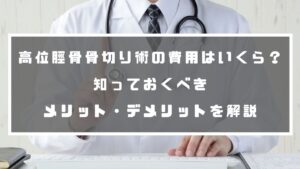
70代の膝の痛みに関するよくある質問
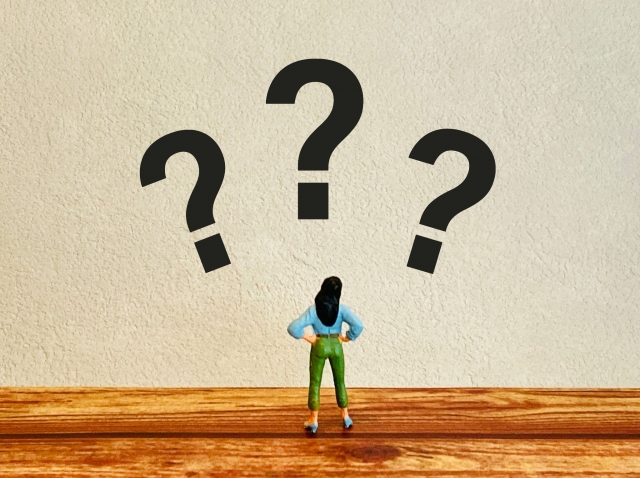
70代の膝の痛みに関するよくある質問は次のとおりです。
それぞれの質問に詳しく解説するため、同じ悩みや疑問を抱いている方は、ぜひチェックしてみてください。
膝の痛みが突然出たら変形性膝関節症?
突然現れる膝の痛みにはさまざまな原因が考えられますが、60代以降の方であれば変形性膝関節症の可能性もあります。
変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで痛みがあらわれる疾患であり国民病の1つです。関節軟骨は年齢とともに少しずつすり減っていくため、気づいた頃には症状が進行している場合もあります。
もちろん、ほかの病気が原因の可能性もあるため、痛みを感じた場合は早めにクリニックを受診してみてください。
膝が痛くて歩けないときはどうすればよい?
膝が痛くて歩けないときは、自己判断で対処しようとせず、クリニックを受診して医師の診断を受けましょう。歩けないほどの痛みがある場合は、変形性膝関節症を含む、何かしらの病気にかかっていることが考えられます。
万が一、病気が原因であるにもかかわらず放置すると、さらに病状が進み、立ち上がれなくなる可能性もあります。そのため、まずはクリニックを受診し、詳しい検査を受けてください。
膝の手術ができる年齢は何歳まで?
膝の手術を受けられる年齢の上限は決まっていませんが、適正年齢は施術方法によって異なります。施術ごとの適正年齢は次のとおりです。
- 節鏡視下手術:とくになし
- 高位脛骨骨切り術:40代以降
- 人工膝関節置換:60代以降
とくに、人工膝関節置換術は、体力や長期のリハビリにも耐える意欲があれば何歳でも受けられます。
ただし、あくまで目安であり、症状や患者自身の体力によっては適正年齢でも受けられない場合があるため、早めに治療を始めることが大切です。
まとめ
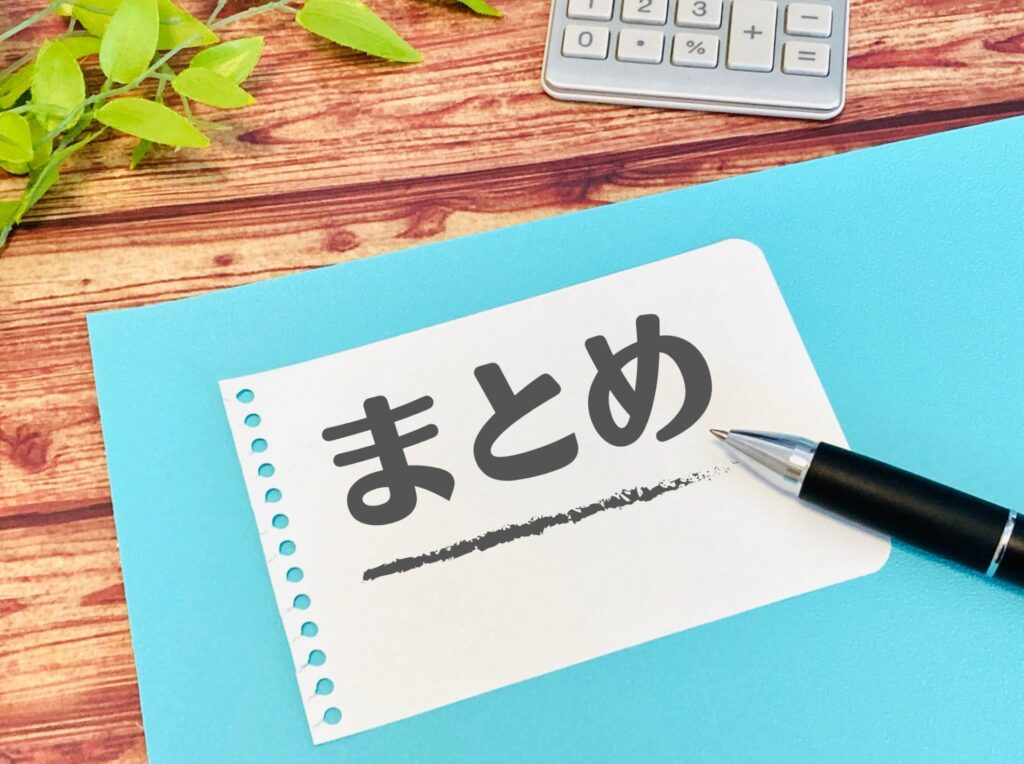
70代の多くは膝の痛みを抱えており、4〜5割の方は変形性膝関節症を患っているといわれています。
変形性膝関節症の場合、症状が軽度であれば運動療法や薬物療法で痛みの改善が期待できます。また、本記事で紹介したように、日常生活の中でもストレッチやサポーターなど、痛みを和らげる対策が可能です。
しかし、症状が重度まで進行すると大掛かりな手術が必要となり、回復までに長い時間とお金を費やすことになります。そのため、痛みを感じ始めたらできる限り早くクリニックを受診し、適切な治療を受けましょう。
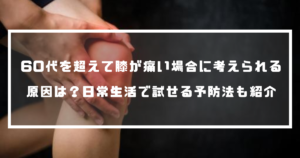
※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。