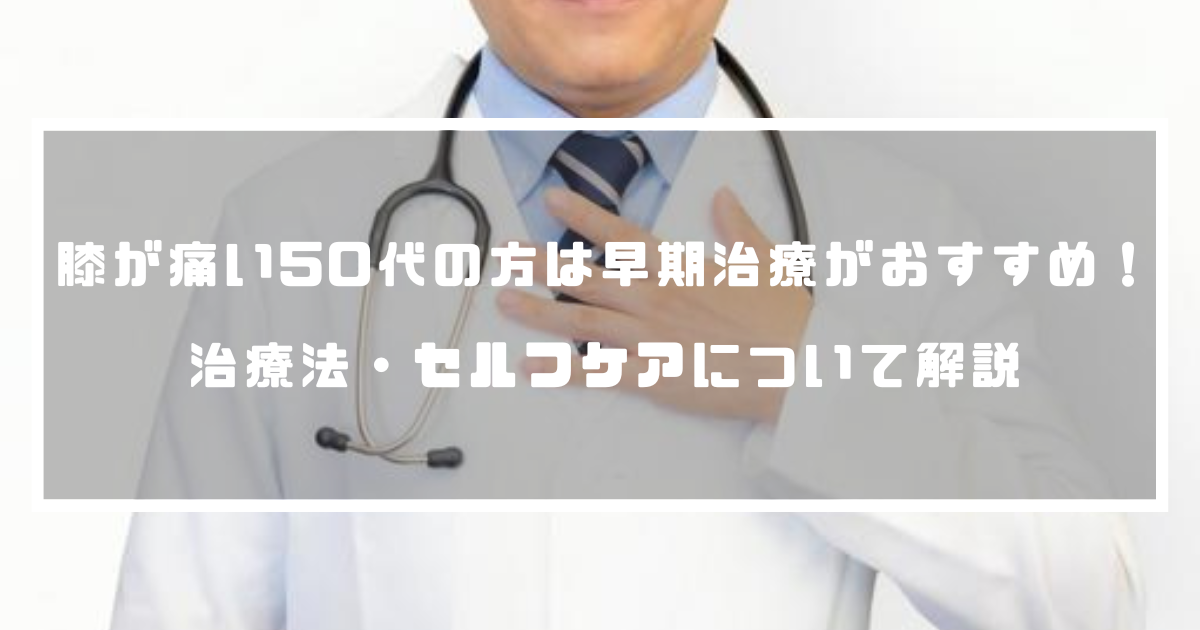加齢とともに膝に痛みを感じる方は多くなるでしょう。膝に痛みがあってもとくに怪我もなければ、クリニックの受診はしない方も多いのではないでしょうか。
しかし膝の痛みで多い変形性膝関節症はゆっくりと進行し、放置すると徐々に症状がひどくなります。そのため、症状が軽いうちに早期治療を受けることが大切です。
今回は、膝が痛い50代の方に向けて、症状や原因、治療法について解説します。セルフケアの方法もあわせて紹介するため、膝の痛みに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
膝が痛い50代の方に多い症状

50代以降に多い膝の痛みですが、痛みを感じるシチュエーションはさまざまです。どのようなときに痛みを感じるかによって、症状の進行具合がある程度わかります。
ここでは膝が痛い50代の方に多い主な症状を5つ紹介します。
歩行中に痛む
1つ目は、歩行中に痛む症状です。
歩行中の痛みは症状が進行しているケースもあり、膝に何らかの損傷があると考えられます。歩行中に痛むと外出も億劫になり、運動量が減ってさらに痛みが大きくなる悪循環に陥る方も多いです。
痛みを放置するとやがて日常生活さえ困難になる可能性もあるため、早めに治療を開始しましょう。
階段の上り下りで痛む
階段の上り下りは、膝に大きな負担がかかります。そのため、階段の上り下りの際に膝の痛みに気が付く方も多いです。
階段の上り下りが困難になると、日常生活にも支障をきたします。無理に上り下りすると踏み外す危険性もあるため、痛みがひどい場合は早めに対策をおこないましょう。
正座ができない
膝を過度に曲げる正座は、膝に大きな負担をかけます。そのため、正座ができない症状も初期にあらわれることが多いです。
正座は痛みを悪化させるため、可能であれば高い椅子に座り、膝を曲げすぎないように注意しましょう。
長時間座ったあとに立つ際に痛む
長時間膝を固定していると、動きはじめに痛みを感じます。長時間座ったあとに立つ際の痛みは、最も初期に現れる症状です。
その他、起床時や歩き始めるときの痛みもあります。動いていると気にならなくなるケースが多いため、放置されることも多いでしょう。
しかしそのうち上述のように階段の上り下りや歩行時に痛みを感じるようになります。早期に対策をして進行を遅らせることも非常に重要です。
足を伸ばす際に痛む
膝の痛みは曲げ伸ばしの際に現れることが多いですが、人によっては伸ばす際により大きな痛みを感じる方もいます。
膝を伸ばす際の痛みは、膝関節の炎症や筋肉の緊張が原因です。ストレッチや膝を温めるなどの対策も効果的ですが、根本的な改善には整形外科の受診をおすすめします。
膝の痛みは50代の女性に多い症状

50代の膝の痛みで最も多い原因は、変形性膝関節症です。
変形性膝関節症は、女性に多く見られる傾向があります。女性に多い原因は、筋肉量や骨盤の形状などの違いです。
女性は男性と比べると筋肉量が少なく、さらに骨盤が広い方が多いです。日常生活でも膝にかかる負担が男性より大きくなり、結果的に女性の患者が多くなります。
50代で膝が痛くなる5つの原因

膝の痛みの原因となる病気には、いくつかの種類が考えられます。また、怪我による痛みも考えられるため注意が必要です。
ここでは、50代で膝が痛くなる原因を5つ紹介します。
順に解説していきます。
変形性膝関節症
中高年の膝の痛みで最も多い原因は、変形性膝関節症です。変形性膝関節症は、加齢や筋肉量の低下によって、膝関節の軟骨がすり減ってしまう病気です。
膝の関節にある軟骨はクッションのような役割を担っており、骨を保護してスムーズな動きを可能にしています。軟骨がすり減ることで骨と骨が直接ぶつかり、やがて炎症を起こして痛みが生じる仕組みです。
変形性膝関節症の日本国内の患者数は、自覚症状がある方で約1,000万人、潜在的な患者数では約3,000万人とされています。50歳以上では、2人に1人の割合です。女性の方が発症しやすく、男性の1.5倍~2倍も多いこともわかっています。
最初は軽い痛みから始まりますが、末期症状になると日常生活に支障をきたすようになる可能性もある病気です。一度すり減った軟骨は元には戻らないため、早いうちに治療を始めることが大切です。
更年期関節症
更年期とは、閉経の前後5年を合わせた10年間のことです。
更年期中にはホルモンバランスが不安定になりやすく、ほてりや発汗、動悸やめまいなどの症状があらわれるうえに、関節痛が起こる可能性もあるでしょう。
更年期の関節痛は手指にあわわれるケースが多いですが、膝に痛みや腫れが出る場合もあります。更年期の関節痛は、2年~3年のうちに自然と治ることが多いです。
そのため、痛みがそれほど気にならないのであれば、とくに治療の必要はありません。痛みがつらい場合は関節が変形する危険性もあるため、クリニックを受診しましょう。
半月板損傷
膝の関節には、半月板と呼ばれる繊維軟骨が内側と外側に1枚ずつあります。衝撃を和らげたり膝の動きを安定させたりする機能があり、さらに軟骨の保護も担っている重要な部位です。
半月板は外的な衝撃で亀裂が入ったり、断裂したりするケースがあります。半月板が損傷すると膝の曲げ伸ばしがしにくくなり、痛みや腫れが現れます。
また症状がひどい場合には膝に激痛が走り、急に膝が動かなくなる「ロッキング」現象を起こす可能性もあるため、放置すると危険です。
半月板は、年齢が若いうちは基本的に損傷する可能性は低いでしょう。しかし、半月板は加齢によってもろくなるため、とくに40歳以上では少しの衝撃でも損傷するケースがあります。

靭帯損傷
関節にあるヒモ状の組織で、骨と骨をつなげている部位が靱帯です。関節が必要以上に動きすぎるのを防ぎ、関節を安定させる役割を持っています。
靱帯は、スポーツに伴う怪我や交通事故などで強い衝撃を受けると損傷します。靱帯が損傷すると痛みや腫れが生じ、膝を動かしにくくなります。
また断裂した場合には激痛が生じ、簡単に動くこともできません。そのため、すぐに治療が必要です。
痛みや腫れは、適切な治療を受ければ次第に回復します。ただし、膝に不安定感が残ることが多いです。不安定感が改善するケースはほぼないですが、放置すると膝が変形するケースがあるため、引き続き適切な治療を受けましょう。
また靱帯には「前十字靭帯」や「内側側副靱帯」などいくつかの種類があり、どの靱帯を損傷したかによって症状や治療法が変わります。
膝軟骨の摩耗
膝軟骨は脛骨と大腿骨の間にあり、骨と骨が直接ぶつかるのを防いでいる組織です。水分が多く柔らかい軟骨が間にあることで、関節がスムーズに動きます。
膝軟骨が摩耗すると骨を保護できなくなるため、骨と骨がぶつかって炎症を起こすようになり、やがて痛みや腫れが生じます。
膝関節の摩耗が起こる主な原因は、加齢によって軟骨の成分が変わることです。水分やコラーゲンが少なくなり、摩耗しやすくなります。そのため、年を重ねると誰にでも起こる可能性がある病気で、患者数も多いです。
膝の痛みが悪化する生活習慣

変形性膝関節症の場合、普段の生活習慣が膝の痛みに影響します。痛みがひどくなければ、生活習慣の改善によって症状を改善させることも可能です。
ここでは、膝の痛みを悪化させる生活習慣を2つ紹介します。
順に解説していきます。
運動不足
1つ目の生活習慣は、運動不足です。最も患者数が多い変形性膝関節症は、運動不足が原因になる可能性がある病気です。
人間が歩行で膝の曲げ伸ばしをする際には、膝周りのみでなく、臀部や背中などのさまざまな筋肉が動きを支えています。そのため、運動不足によって筋力が低下すると膝の動きを支える力が弱まり、膝にかかる負担が大きくなります。
また、身体を動かさない生活を続けると関節が固くなります。関節の柔軟性が低下すると自然な動きができなくなるため、体を動かさないことも膝への負担を大きくする原因です。
運動不足が続くと日常生活で膝にかかる負担が大きくなり、膝軟骨の摩耗を早めます。
肥満
肥満も膝の痛みを悪化させる原因のひとつです。人間は歩行時には1本の足で体重を支えます。さらに運動によるエネルギーも加わるため、歩くのみで体重の何倍もの負荷が膝にかかります。
そのため体重が増えるほど膝への負担は大きくなり、これにより膝軟骨の摩耗が早まります。膝の痛みを軽減するためには、体重のコントロールも重要です。
肥満は他のさまざまな不調や生活習慣病の原因にもなるため、自身の適正体重を把握して、過度に体重を増やさないように心がけましょう。
自宅でできる膝の痛みを和らげるセルフケア方法

根本的な治療のためには通院をおすすめしますが、普段の生活で痛みを軽減するための方法も知っておくと安心です。
ここでは、自宅でできる膝の痛みを和らげるセルフケアの方法を紹介します。
膝関節を温める
1つ目のセルフケア方法は、膝を温めることです。身体が冷えると血行が悪くなりますが、血行が悪くなると筋肉が固まって痛みが大きくなります。
そのため、膝関節を温めることは痛みの軽減に効果的です。すぐできる簡単な方法には、使い捨てカイロや蒸しタオルを患部に当てる方法があります。持続的な効果はないものの、応急処置として最適です。
カイロの場合は長時間当てると低温やけどを起こす危険性もあるため、気を付けましょう。また、普段から身体を冷やさないような生活を心がけることも大切です。
シャワーで済まさず入浴する、身体を温める食物を積極的に摂る、適度に運動する、服装を工夫するなどの対策ができます。冬はもちろん、夏場でも冷房で冷えすぎないよう注意しておきましょう。
膝に負担のかかる座り方を避ける
膝は曲げ伸ばしすると負担がかかるため、普段の座り方によって膝にかかる負担が変わります。そのため、膝に負担がかかるような座り方を避けることも大切です。
座り方で最も重要なポイントは、できるだけ高いところに座ることです。床や座椅子などの低いところに座ると膝を過度に曲げることになるため、負担が大きくなります。
とくに正座は膝への負担が非常に大きいため、注意が必要です。座る際は膝の角度が90度になるように気を付けることで、痛みを抑えられます。
サポーターを装着する
膝にサポーターを着けての生活も効果的です。サポーターには膝の動きを支えて安定させる機能があり、無理な動きを防止できるため痛みを軽減できます。また、膝に巻くことで保温機能も期待できるため、一石二鳥です。
サポーターは運動用と生活用の大きく2種類に分かれるため、日常の痛みを和らげる目的であれば生活用を選びましょう。巻くタイプか着けるタイプか、洗濯機で洗えるかなど点をチェックし、サイズの合ったサポーターを着用してみてください。
ストレッチ
筋力の衰えや筋肉のこわばりが膝の痛みの原因となることがあります。とくに運動習慣がなく、体力の衰えを感じるような方は要注意です。しかし、急に激しい運動を始めることは、膝への負担を大きくします。
そのため、まずは自宅でもできる簡単なストレッチや体操から始めてみましょう。血流がよくなることで膝関節が柔らかくなり、痛みが軽減されます。
可能であれば、入浴中にストレッチをおこなうとさらに効果的です。ただし、ストレッチも長期間おこなうと、膝への負担が大きくなります。
痛みが生じた場合はストレッチを中止しましょう。痛みに不安がある方は、医師に具体的なストレッチの方法を相談してから始めると安心です。
杖・歩行器の使用
膝の痛みがひどい場合には、杖や歩行器を使うことがおすすめです。杖や歩行器は膝へかかる負担を大きく軽減できます。バランスを取りやすくなるため、転倒のリスクも少なくなります。
膝に痛みがあると外出が億劫になりますが、家にこもっていると運動不足になり、膝の痛みがさらに悪化しやすくなります。杖や歩行器を使うことで外出の機会が増えれば、長期的に見ても膝の痛みに効果的です。
膝の痛みが続く場合は整形外科で治療がおすすめ
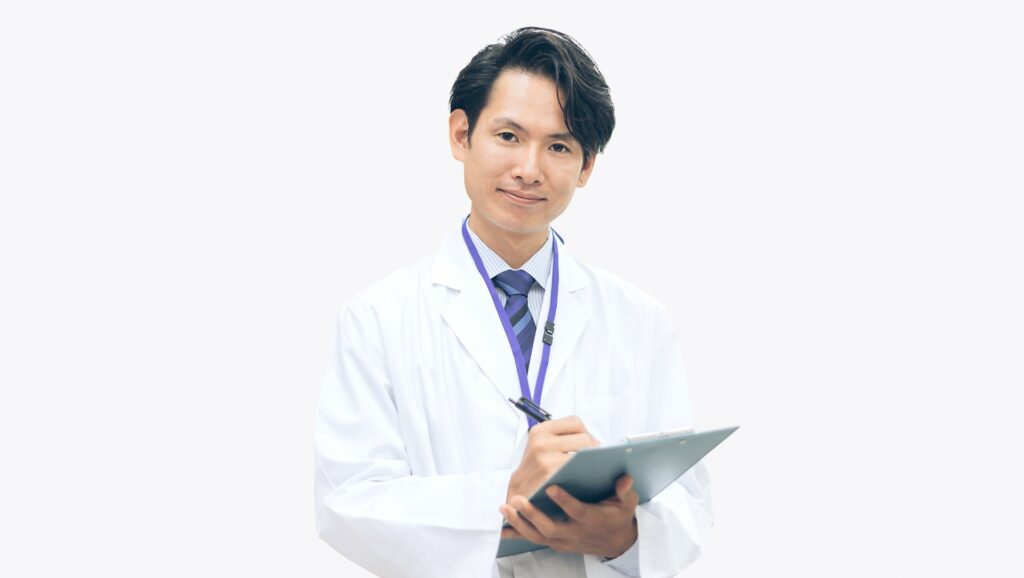
生活習慣の改善やセルフケアでも症状が改善しない場合は、整形外科での治療がおすすめです。早期に治療を受けるほど、症状の進行を遅くできます。
ここでは、整形外科で受けられる膝の痛みの治療方法を4つ紹介します。
薬物療法
1つ目の治療法は、薬物療法です。塗り薬や湿布、内服薬などで患部の炎症を抑え、痛みを軽減します。患部に腫れがある場合や、痛みが激しい場合に用いることが多いです。
ただし薬物療法は基本的に痛みを軽減できるのみであり、根本的な原因の解決はできません。薬を使い続けることで副作用が生じる可能性もあります。
そのため、薬物療法で痛みを軽減しながら生活習慣を見直し、運動習慣を取り入れることも重要です。
外科手術
膝の痛みの治療では、外科手術の前に薬物療法や運動療法が検討されます。しかし、症状が重い場合はこれらの治療法で効果が得られないこともあり、その際は外科手術が行われます。負担は大きくなりますが、より高い効果が期待できる治療です。
外科手術にもいくつかの種類があり、内視鏡を使った治療から、人工関節に置き換える治療までさまざまです。個人の重症度に合わせ、適切な手術がおこなわれます。
運動療法
運動療法は、運動によって身体の機能を回復させ、膝の痛みを軽減する方法です。
上述のように運動は膝の痛みに効果的ですが、個人でおこなうと効果が乏しかったり、無理をして症状が悪化したりする可能性もあります。そのため、適切な運動療法を受けることで、より効果的に膝の痛みを改善できます。
運動療法の内容は整形外科により異なりますが、体操やストレッチの指導を受けることが多いです。また、ウォーキングや水泳をおこなう場合もあります。
一人一人の症状に合わせた運動法を提案してもらえるでしょう。
再生医療
再生医療は、事故や病気で失った身体の機能を回復させる治療です。患者の幹細胞を用いて組織を作り、それを身体に移植します。
日本ではまだ一般的ではありませんが、新しい選択肢として膝関節の再生医療もおこなうクリニックも増えています。膝関節の再生医療は、痛みを軽減して重症化を遅らせられます。
とくに、運動療法や薬物療法であまり改善しなかったものの、外科手術には抵抗がある方におすすめです。入院や手術の必要はなく、リスクを減らして症状の改善ができます。
50代で膝の痛みに悩む方によくある質問

最後に、50代の膝の痛みに関するよくある質問に回答します。
痛みがなくなってもリハビリは必要?
リハビリをおこなう場合は、痛みがなくなったとしても自己判断でやめず、医師の指示に従いましょう。また、自身でもストレッチや体操をおこなうことで、長期的に膝の痛みへの対策ができます。
手術の場合の入院期間は?
膝の痛みで外科手術を受ける場合、入院期間は手術の種類によって変わります。入院期間が最も短い手術は関節鏡視下手術で、2日~3日で退院可能です。
一方、入院期間が最も長い手術は人工関節置換術で、こちらは約1か月かかります。
痛みの少ない治療法は?
症状が軽ければ、薬物療法や運動療法がおすすめです。症状が重ければ外科手術が必要になります。
いずれも麻酔をするため手術中の痛みはほぼありません。関節鏡視下手術は身体への負担も小さいため、気軽に受けやすい治療法です。
治療後いつから運動可能?
薬物療法であれば、痛みがなくなればいつでも運動を再開できます。ただし、急に負担をかけないよう軽めの運動を心がけてください。
外科手術は種類や経過にもよりますが、数週間から数年かかります。治療を受けた医師の指示に従い、無理な運動は控えましょう。
まとめ
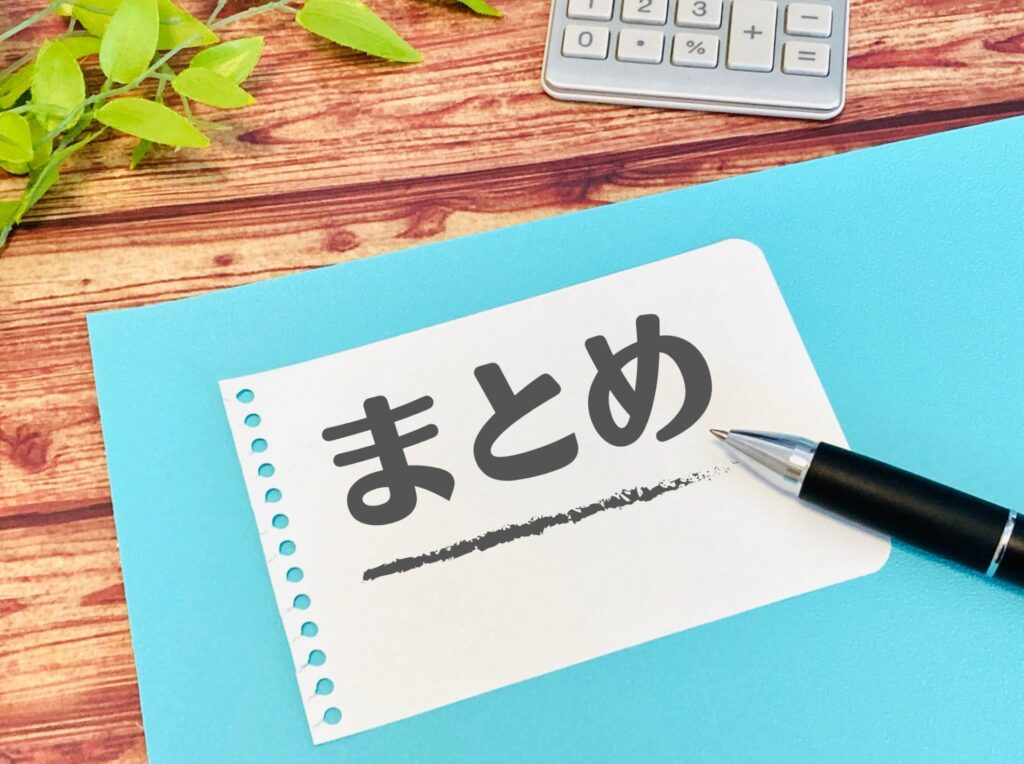
今回は、膝が痛い50代の方に向けて、症状や原因、治療法やセルフケアについて解説しました。中年以降の膝の痛みの原因の大半は、変形性膝関節症だと考えられます。
変形性膝関節症は膝軟骨の摩耗によって引き起こされるため、誰にでもありえる病気です。加齢によって増える他、女性に見られやすい病気といえます。
自身でできる対策は、適度な運動と体重のコントロールです。また、患部を温める処置も効果的です。
ただし、痛みがひどい場合は整形外科を受診しましょう。
※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。