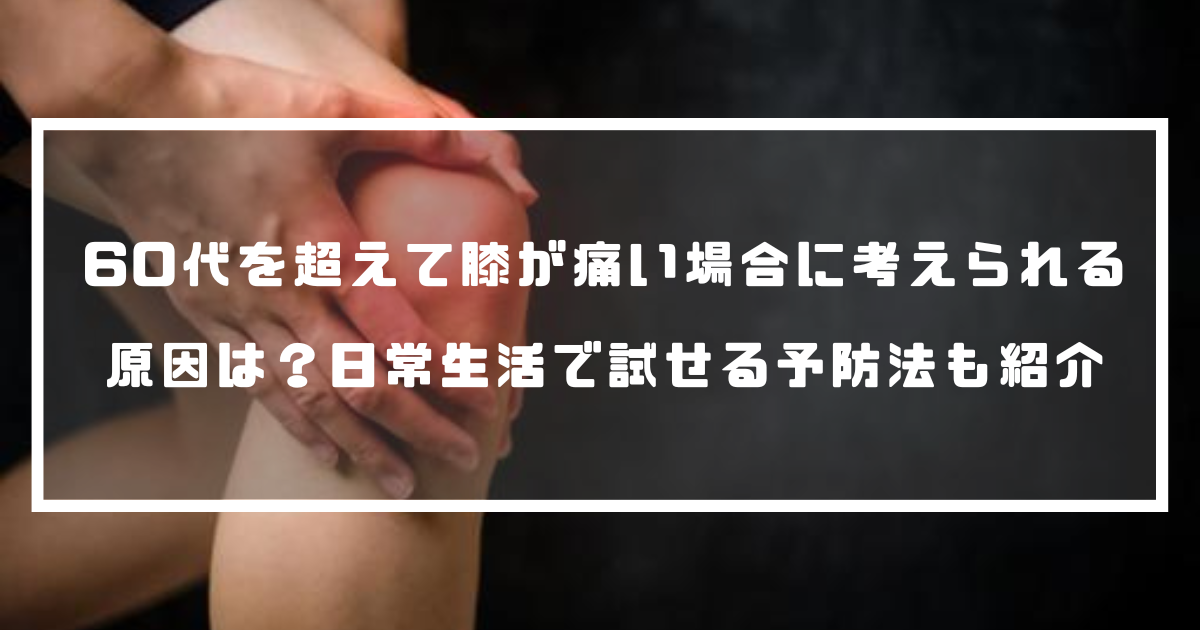60代を超えてから膝の痛みが悪化したと悩んでいる方は、多いのではないでしょうか。
「階段の上り下りがつらい」「健康のために始めたウォーキングが負担に感じる」など、慢性的な膝の痛みは人の行動を狭めてしまうものです。
また一般的に加齢による膝の痛みは、関節軟骨の擦り減りが原因のため、治らないものだと思う方もいるでしょう。しかし実際は加齢による膝の痛みにはさまざまな原因があります。多くの場合、治療法や予防策があるものです。
本記事では、加齢による膝の痛みの症状や原因、予防策などをまとめました。60代を超えてから膝の痛みが悪化した方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
加齢とともに膝が痛む原因は?

加齢と共に膝が痛む原因は、軟骨のすり減りによるものだと思う方が多いですが、実際のところ原因は一つではありません。
さまざまな原因から膝の痛みがでているのです。そのため、まず原因を知ることが適切な対処をするうえで大切になります。
ここでは60代で膝が痛む原因を詳しくまとめました。膝の痛みに日々悩まされている方は、ぜひ参考にしてみてください。
軟骨が擦り減って痛いわけではない
一般的に膝の痛みは、加齢に伴い軟骨がすり減るためだと考えられています。
しかし軟骨が擦り減ることにより、必ずしも膝が痛むわけではありません。膝の痛みにはさまざまな原因が考えられます。
たとえば炎症や腫れ、靭帯の損傷、関節周辺の筋肉の低下など、原因はさまざまです。なかでも変形性膝関節症による膝の痛みを抱えている方が多く、50代以上では二人に一人が発症するといわれています。
しかし大切なのは、膝が痛む原因の正確な特定です。きちんと原因を特定すれば、症状に合わせた適切な治療法もわかるため、膝の痛みを緩和させられる可能性があります。
60代膝が痛むメカニズム
60代の膝が痛むメカニズムには、膝そのものに問題がある場合と、膝以外に問題がある場合の2つがあります。
膝そのものに問題がある場合とは、怪我や関節の変性などの何らかの異常がある際の痛みです。60代は加齢が原因で軟骨がすり減り、関節内で炎症が起きたり、水が溜まったりする変形性膝関節症になる方が増えます。
また膝以外に原因がある場合は肥満やO脚、X脚、股関節の病気、外反母趾、腰の病気などもあります。いずれにしても重症化すると歩行困難になるケースもあるため、専門医の診察を受けることが大切です。
膝が痛くなるメカニズムは人によって異なりますが、予防策や治療法はあります。加齢によるものだからと諦めずに、しっかり予防策や治療をしていきましょう。
膝の痛みには適切な治療が必要な場合も
日常生活に支障がなく、慢性的ではない膝の痛みであれば患部を冷やし、安静にすると改善する場合もあります。
しかし、たとえば関節の炎症や水が溜まったことで痛むのであれば、放置すると症状が悪化する可能性が高くなるでしょう。慢性的な膝の痛みを改善したい方は、適切な治療が必要です。
また膝が炎症している状態であれば、抗炎症薬や物理療法で改善できる可能性があります。靭帯や軟骨、筋肉に損傷が生じている場合は、手術が必要になる可能性もあるでしょう。
どちらにしても治療をおこなわなければ、慢性的な膝の痛みは改善しません。症状が悪化すると歩行が難しくなるケースもあるため、早めに専門医に相談しましょう。
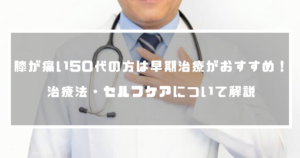
考えられる膝の痛みの症状と原因

膝の痛みはさまざまな原因によって引き起こされます。
膝が痛む原因を正確に特定するためには、痛みの程度や発生時期、痛む場所などの症状をよく観察しましょう。考えられる膝の痛みの原因は、変形性膝関節症や関節軟骨の老化、半月板の損傷、肥満などが挙げられます。
ここでは、考えられる膝の痛みの症状と原因について詳しくまとめました。
順に解説していきます。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、膝の関節軟骨がすり減ることで、骨同士がぶつかり合う状態になる疾患です。変形性膝関節症は加齢や運動不足、肥満、過剰な運動、過去のケガ、遺伝的な要因など、さまざまな原因があります。
慢性的な痛みやこわばる感覚が生じる場合があり、悪化すると歩行困難や日常生活に支障をきたすケースもあるため注意が必要です。
治療法は医師の判断や症状の重さによって異なるものの、まずは悪化させないための処置をおこないます。たとえば痛み止めの薬や、関節の負担が少ない運動、体重の減量などです。しかし重症の場合には、手術が必要になる場合があります。
厚生労働省のデータでは、50代以上のうち約2,400万人が変形性膝関節症を発症し、性別分けでは女性が圧倒的に多いことが判明しています。
変形性膝関節症の初期段階は、動き始めの痛みや階段の上り下りがしづらいなどの症状が一般的です。しかし病状が悪化すると関節部の変形も目立ち、膝を真っすぐに伸ばすことができなくなり、最終的に歩行困難になります。
変形性膝関節症を完治させる方法はないといわれているものの、治療やリハビリテーションをおこなうことで症状の進行を遅らせ、痛みを和らげることは可能です。
関節軟骨の老化
関節軟骨には寿命があり、人によっては40代くらいから変形が始まります。関節軟骨の寿命に個人差があるのは、支える体重や運動量などの軟骨を摩耗させる行動や生活習慣が異なることが原因です。
膝関節を支える軟骨は、時間の経過とともに柔軟性や弾力性が低下して硬化し、徐々に劣化していきます。その結果、関節の可動域が制限され、歩行や日常生活に支障をきたすなど、深刻な状態を招く危険性もあるため注意が必要です。
また関節軟骨の老化が進行すると、関節炎や変形性膝関節症などの疾患を引き起こす原因にもなります。関節軟骨の老化に対しては、運動やリハビリ、栄養補助食品などによるサポートが有効です。
また軟骨に栄養補給できるサプリメントの摂取や、運動によって血流を促進すると、軟骨の再生を促す効果が期待できます。関節軟骨の老化が進んでいる場合は、手術が必要になることもあるため、早めの治療や予防が必要です。
半月板の損傷
半月板は膝関節の内側と外側にそれぞれ1枚ずつあり、膝の関節を安定させたり、衝撃を和らげたりする役割を担います。しかし過剰な負荷や加齢による負担の蓄積に耐え切れず、損傷する場合があります。
膝を曲げ伸ばした際に不自然な引っ掛かりを感じる、膝裏が痛いなどの症状がある場合は、半月板を損傷している可能性があります。半月板を損傷する原因は、スポーツや日常生活での外傷や、膝の長期的な負荷、加齢による軟骨の劣化などが挙げられます。
また半月板の破損が進行すると、膝関節内部の骨が損傷を受け、膝関節炎や変形性膝関節症などの疾患を引き起こす危険性もあるので注意が必要です。
半月板の損傷に対しては、保守的な治療法として冷却、炎症を抑える薬の投与、リハビリテーションなどがあります。半月板の損傷具合が重度の場合は、高確率で手術が必要です。
手術は半月板を切除したり、修復したりする方法があり、症状に応じてどちらかを選択します。

肥満
肥満は膝にかかる負荷を増加させるため、膝の痛みの原因になります。長期的に膝関節に負担がかかると関節軟骨の摩耗が進み、変形性膝関節症になるリスクを高めます。
また脂肪細胞が増加すると、炎症を引き起こすサイトカインという物質が増加し、炎症を起こしやすくなる点にも注意が必要です。これらの炎症反応は、軟骨細胞や骨細胞にも影響を与えるため、膝の痛みがより強くなる傾向にあります。
肥満が原因で膝が痛む場合のよい対処法は減量です。運動や食事制限をおこなうことで体重を減らし、膝に負担をかけない生活を心がけましょう。
日常生活で試せる膝の痛み予防法

膝の痛みは適度な運動で筋肉をつけたり、ストレッチをしたりすると緩和できる場合があります。
ここでは日常生活で気軽に試せる膝の痛みの予防法を紹介します。
医師も推奨している簡単なストレッチや運動なため、膝に過度な負担がかからない範囲で、毎日継続してみましょう。
裏もものストレッチ
ももの裏側の筋肉は疲労しやすく、固くなりやすいため、ストレッチをして柔軟にすることが大切です。
裏ももに柔軟性がないと腰が丸くなり、姿勢が崩れやすくなるため、継続的に膝に負担がかかるようになります。
裏ももを伸ばすストレッチは、椅子に座った状態でも可能です。
椅子に座ってできる裏ももストレッチ
- 椅子に腰をかけ、足を軽く開き、背筋を伸ばす
- 両手を足の付け根部分に置いて、右足のつま先を天井に向けるようにまっすぐ伸ばす
- 背中を伸ばしたままの姿勢で、股関節から体を前方に倒す
- 10秒ほどキープしたら2の姿勢に戻る
- 左足でも同じように裏ももを伸ばす
1〜5までの動作を、5〜10セット程度を目安にやっていきましょう。
ポイントは裏ももが伸びているのを感じながら、ゆっくりおこなうことです。毎日継続すれば、膝の痛みを予防する効果が期待できるので、ぜひ試してみてください。
ひざ周りのストレッチ
膝周りの筋肉をストレッチで柔軟にすると、膝の痛みを予防する効果が期待できます。
とくに太ももの前側にある四頭筋(しとうきん)を伸ばすと、膝の可動域を柔軟にできるため、膝の痛み予防に効果的です。
四頭筋ストレッチの手順は下記のとおりです。
- 壁に片手をついて真っ直ぐ立ち、片足の膝を曲げて、足先を手で掴む
- 足先をお尻の方へ引き寄せ、太ももの前側を伸ばす
- そのまま息を吐きながら30秒ほどキープする
- 反対側の足も同様におこなう
左右2〜3セット程度を目安におこないます。注意点は筋肉を無理に伸ばしすぎないことです。
膝に痛みや引きつりなどの違和感を覚えた場合は、すぐにストレッチを中止しましょう。大切なのは毎日少しずつおこない、膝周りの筋肉の柔軟性を上げていくことです。
適度な運動やウォーキング
膝の痛みの予防には、筋肉を鍛える適度な運動やウォーキングも効果的です。運動不足による筋肉の低下は膝の負担を増やし、痛みを引き起こす原因になります。
ただし無理な運動や過剰な負荷は、膝に負担をかける原因になるため、あくまでも適度な運動やウォーキングを心がけるようにしましょう。
また運動やウォーキングをする際は、クッション性の高い靴を選び、膝や足首に負担がかからないようにする工夫も大切です。
適度な運動やウォーキングを習慣にすれば、膝痛の予防はもちろん、健康な体づくりにも役立つので、毎日少しずつ続けていきましょう。
ひざの痛みがある際の注意点

膝の痛みがある際は、運動やストレッチなどで無理に体を動かすのは危険です。痛みの度合いによるものの、長引く膝の痛みや強い痛みであれば、自己判断せずに専門医に任せましょう。
ここでは、ひざの痛みがある際の注意点を詳しくまとめました。
一歩間違うと悪化させてしまうこともあるため、慎重に判断しましょう。
自己判断しすぎない
膝が少し痛む程度の場合、気にしない方もいるでしょう。
しかし痛みが続いたり、悪化していたりする場合は、自己判断せずに専門医への相談をおすすめします。自己判断では正確な原因がわからないため、無理な運動やストレッチで症状を悪化させる恐れがあります。
また痛みを我慢して放置すると、後遺症が出る危険性も考慮しなければいけません。自身でできる範囲での運動や予防策は大切ですが、痛みが強い場合は自力で対処しようとするのではなく、専門医に相談するようにしましょう。
ひざの痛みがひどい場合は整形外科を受診する
膝の痛みが強く、自己判断で対処できない場合は、整形外科の受診がおすすめです。
整形外科医は骨・関節などの骨格系と、それを取り囲む筋肉や神経系の機能的改善を専門に取り扱います。膝の痛みについて専門的な知識と技術を持つ医師が在籍しているため、短時間で適切な対処が期待できるでしょう。
整形外科は問診や身体検査、X線、MRI、CTスキャンなどを実施し、膝の痛みの原因を特定します。膝の痛みの原因が判明してから、適切な治療をしていく流れです。結果に応じてリハビリや薬物療法、注射、手術など、症状に合わせた治療をおこないます。
自己判断で時間を無駄にしたくない方や、早く痛みから解放されたい方は、多くの症例や治療実績がある整形外科医を受診しましょう。
無理なストレッチは逆効果
膝の痛みの予防に膝周りや裏もものストレッチは有効です。症状が軽い膝の痛みであれば、マッサージやストレッチで軽減できる場合もあります。
しかし膝に痛みがある状態で無理なストレッチをすると、逆効果になる可能性があります。無理なストレッチが膝に負担をかけてしまい、炎症を起こしたり、症状の悪化を招いたりする可能性が高いためです。ストレッチをおこなう際は、痛みの強さに応じて程度を調整し、無理な力を入れすぎないように注意しましょう。
また適切なストレッチ方法がわからない方は、ストレッチや運動療法などの専門知識がある理学療法士や、整形外科医などから教わることをおすすめします。専門家による膝に負担をかけないストレッチ法であれば、毎日安心してストレッチできるでしょう。
60代の膝の痛みに関するよくある質問
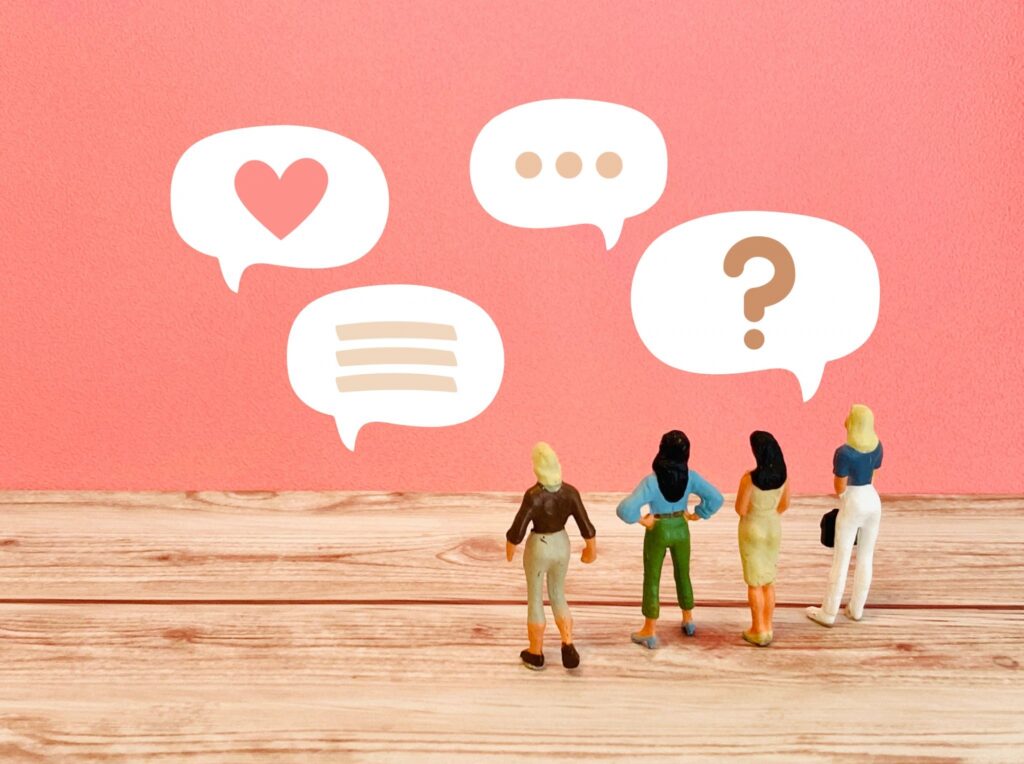
膝の痛みが軽度の際は、湿布で冷やす方もいるでしょう。しかし冷やすか温めるかは症状によって異なります。勘違いしている方も多いので、ここでは60代の膝の痛みに関するよくある質問をまとめました。
痛みが続いている場合の正しい対処法がわかるので、ぜひ参考にしてみてください。
ひざが痛いときにウォーキングをしても大丈夫?
一般的に膝の痛みが軽度である場合、ウォーキングは適度な運動として推奨されています。ただし歩行に支障があるほど痛みが強い場合は、軽いウォーキングでも膝に負荷がかかる恐れがあります。
ウォーキングもストレッチも自身の体調や痛みの状況をよく把握し、無理のない範囲でおこなうようにしましょう。
ひざが痛いときは何科を受診すればよい?
ひざが痛いときに受診するのは整形外科です。整形外科では、膝関節の痛みや障がいに対する専門的な治療をおこないます。
しかし痛みの原因が別の疾患によるものである可能性もあるため、痛みの程度や症状に応じて、内科やリウマチ科などの専門医の受診も検討しましょう。
またクリニックによっては、整形外科の他にスポーツ医学科やリハビリテーション科がある場合もあります。最適な診療科がわからない場合は、まず整形外科を受診しましょう。
診察と検査の結果、医師から正しい治療を受けられる専門医の紹介状が出されます。
ひざの痛みは遺伝性のものもある?
変形性膝関節症による膝の痛みには、遺伝性のものもあることが判明しています。
あくまでも原因の一つですが、変形性膝関節症の発症に関係しているDVWAと呼ばれる遺伝子からSNPと呼ばれるDNA配列が見つかると、発症リスクは通常の1.6倍といわれています。
また膝の関節軟骨や骨の形状に影響を与える遺伝が原因で、膝の痛みが起こることも把握しておきましょう。
ただし遺伝的な原因がある場合でも、日常的な運動やストレッチ、正しい姿勢や体重管理をおこなうことで膝の痛みを軽減できる可能性はあります。
遺伝性だからと諦めるのではなく、正しい知識で予防策や治療を実施しましょう。予防策や治療法がわからない場合は、痛みが強くなる前に専門医を受診して対策の相談をおすすめします。
ひざが痛いときは温めるか冷やすかどちらがよい?
膝が痛い場合、温めるか冷やすか迷うことがありますが、原因によって対処法が異なります。怪我や炎症がある場合は、炎症を抑えるために冷やすことがおすすめです。
しかし関節の痛みやこわばりがある場合は、血流を促進する目的で温めることがおすすめです。ただし、どちらにしても長時間冷やしたり、温めたりすると、反対に痛みを悪化させる場合があるため注意が必要です。
まとめ

60代を超えると慢性的な膝の痛みを発症しやすくなります。加齢による変化や運動不足、肥満など原因はさまざまあるものの、安易に放置せずに早めの対策が大切です。
たとえば、膝周りや裏ももの筋肉を鍛えるストレッチや軽いウォーキングなど、手軽に始められる予防策もあります。ただし膝の痛みが慢性的だったり、少し動いたのみで強い痛みを感じたりするのであれば、すぐに整形外科を受診しましょう。
自己診断で悪化させると最悪の場合、手術が必要になるケースもあります。早期治療や予防をすれば、完治せずとも痛みが緩和し、日常生活を快適に過ごせるようになるでしょう。
※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。