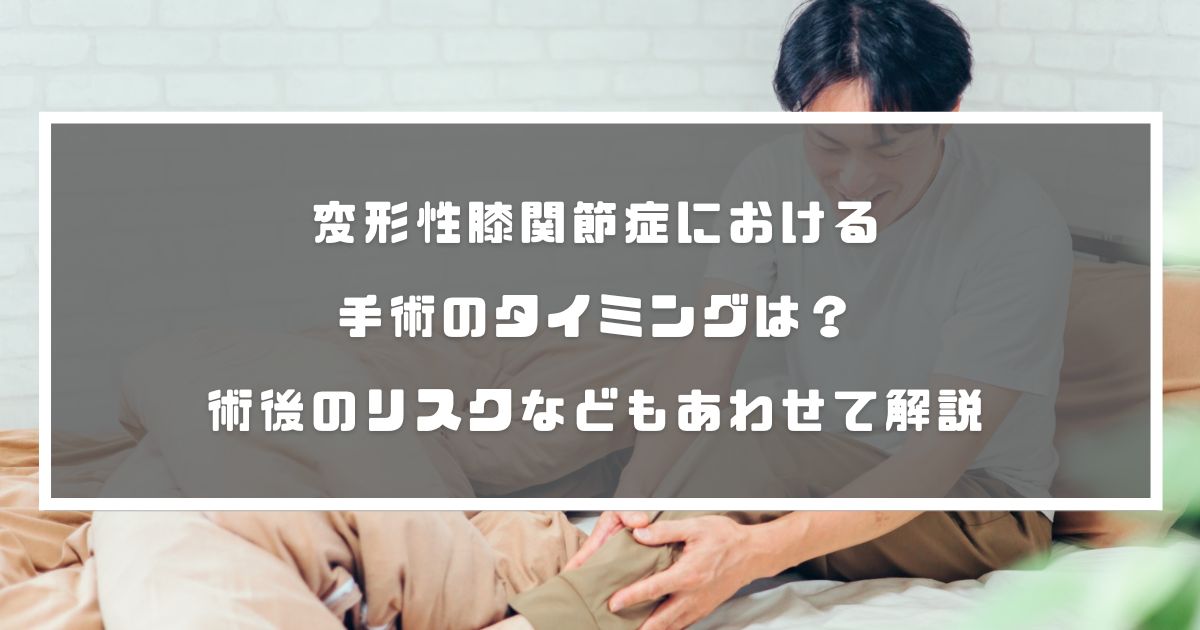膝の痛みは日常生活に影響を与えやすく、改善や完治を目指して治療に励んでいる方も多くいるでしょう。
とくに変形性膝関節症は、症状の重さによっては治療を開始しても中々改善せずに手術の検討が必要な場合もあります。
しかし、もう少し治療を続ければよくなるのではないか、手術以外の方法があるのではないか、手術はリスクが高いのではないかなど多くの不安があり、手術の決断をすることは容易ではありません。
一方、実際に手術を受けた方の感想は異なるものです。株式会社QLife(キューライフ)がおこなった膝変形関節症の手術を受けた方に対する調査では、約96%の方が手術を受けてよかったと回答し、適切なタイミングで手術を受けられたのかの回答には約40%の方が早く手術を受ければよかったと回答しています。
手術を受けるタイミングには悩みますが、手術を終えてみると早く受ければ良かったと感じていることがわかります。
そこで今回の記事では、膝変形性関節症の手術のタイミングやリスクについて徹底解説していきます。適切な手術のタイミングを見分けるために、変形性膝関節症に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
変形性膝関節症とは?

膝関節の痛みは歩行にも支障をきたし、日常生活に直接的に関わるため、確実に治しておきたいものです。
膝関節の痛みの原因は、膝の代表的な疾患である変形性膝関節症とされています。
変形性膝関節症は変形性関節症の一種です。さまざまな原因によって膝関節の軟骨がすりへり、関節内部に炎症が起こることで、少しずつ膝や膝関節周囲の骨が変形してしまい膝関節の痛みや腫れが発症するものです。
発症すると、運動や怪我などによる刺激や、感染症による炎症が加わることでさらに進行し、次第に日常生活に重大な支障をきたすようになるため注意が必要な疾患といえます。
発症する方の割合は年齢が上がるにつれて増加し、60歳以上では男性が約45%、女性は約70%が発症しているとされ、女性の方が発症しやすい傾向にあります。
患者の数は日本で約2,530万人といわれ、多くの方が苦しんでいます。
初期段階の症状では痛みが出ても少し休めば痛みがとれるため気が付きにくいですが、放置してしまい末期になると、安静時にも痛みがとれず歩行が困難になります。
手術のタイミングによって、適した手術方法も異なるため、リスク回避の観点からも早めの受診が必要です。
変形性膝関節症の原因や症状などは次のとおりです。
変形性膝関節症の原因
変形性膝関節症は、発症すると完治が難しいことから、初期症状の段階から医師の診察を受けることや、発症しないための対策が必要といえます。
変形性膝関節症の主な原因とされる3つを紹介していくので、事前に対策して予防や重症化を防ぎましょう。
まず、代表的な原因として加齢による筋肉の衰えがあげられます。年齢を重ねると膝周辺の筋肉の衰えから膝に直接かかる負荷が強まり、膝の軟骨や骨にダメージが溜まりやすくなります。
ダメージにより、クッションの役割を果たしている部位である膝関節の軟骨が摩耗し、軟骨がなくなってしまうこともあるのです。クッションが無くなった膝は痛みを伴うものとなってしまい発症の原因となってしまいます。
次に肥満による体重増加が発症の原因にあげられます。とくに急激な体重増加は、膝への負荷がかかるため注意が必要です。
体重が増加するほど膝にかかる負担は増し、歩行時の膝への負担は体重の約3倍に、階段の昇降時には体重の約7倍にもなるとされています。よって、体重が約1㎏増加すれば、歩行時は約3kg、階段の昇降時には約7kgの負荷が膝に増加するのです。
そのため、急激な体重増加は想像以上に膝への負荷が増し、変形性膝関節症の発症に関して多大なリスクを生みます。体重増加により感じたことのない膝の痛みがあるようであれば体重を落とす意識が必要です。
さらに、体重増加は悪循環を生みやすい傾向にあります。体重増加で膝が痛くなると運動不足になりがちなため、さらなる体重増加の原因となり、ますます膝を痛めてしまう可能性が高まります。
肥満は変形性膝関節症の発症原因となるのみならず、重症化に繋がる恐れがあるといえます。
続いて、O脚も変形性膝関節症の原因になるとされています。
O脚とは、太ももの内側の骨とすねの骨の距離が、通常よりも近い状態を意味します。そのため、体重の負荷が膝の内側に集中し、膝の軟骨や骨を損傷してしまったり変形を起こしたりしやすくなるものです。
また、O脚は女性に多いとされています。原因は女性ホルモンの関係や女性の特徴である広い骨盤に下肢があるため、横揺れを支える筋力が比較的、弱いことにあるとされてます。
O脚の方は歩行や運動の際に下肢が横揺れの動きをしやすく、膝への負担が大きいため、変形性膝関節症を発症しやすいのです。
変形性膝関節症は骨が変形しやすくなるため、進行すると顕著なO脚となり、日常生活に支障をきたしてしまいます。
変形性膝関節症の症状
変形性膝関節症の症状は進行状況によって異なります。具体的には、初期、中期、末期とわけられるため、それぞれの主な症状を紹介していきます。
まず、初期症状は次のとおりです。
- 起床後に膝のこわばりがある
- 起き上がるときや、歩き出そうとするときに膝にこわばりがある
- 膝が重く、動かしずらい
- 少し鈍い痛みを感じる
- 正座をすると膝が痛む
- 階段で膝が痛む
- 方向転換をすると膝が痛む
初期では、しばらくすると痛みが治まるため、とくに気にせず過ごす方が多いですが症状の進行は、痛みがない方もいるほど個々それぞれで異なります。
次に、進行状況が中期になると、膝の痛みが治まらなくなってきます。中期の症状は次のとおりです。
- 正座の動作が膝の痛みで難しい
- しゃがみ込む動作が膝の痛みで難しい
- 階段が膝の痛みで難しい
- 膝が痛いことが明確に意識される
- 膝が曲がりきらない
- 膝が伸びきらない
- 階段の昇りよりも降りが困難
中期になると、膝に炎症が発症し、はっきりとした痛みを感じます。膝周りが腫れ、熱をもつようになり、膝から下がむくんでくることもあります。
膝に水がたまる場合もあり、水がたまると膝が重く感じる症状が出てきます。また、変形が進み、骨同士が当たっているような感覚を受ける症状が現れる場合もあるのです。
最後に、末期まで進行した場合は膝関節の軟骨は大半がなくなり、骨同士が直接当たっていることがはっきりとわかるようになります。末期の主な症状は次のとおりです。
- 歩行が困難
- 座ることが困難
- しゃがむことが困難
- 社会活動に支障がある
- 日常生活に支障がある
生活のさまざまな場面で支障が出るため、ストレスもたまり、動くこと自体が困難なことから、体重増加やうつ病を発症しやすくなります。
また、外出しない生活が続くと高齢者の方は、刺激がない生活が続くため、痴呆症状にも繋がってくるのです。末期では、骨の変形も進行しているため、外見からも変形がはっきりとわかるようになります。
変形性膝関節症が発症しやす方の特徴
変形性膝関節症を発症しやすい方には特徴があります。意識すると予防に繋がるため、確認しておきましょう。主な特徴を4つ紹介します。
まず、肥満であることです。原因でも紹介しましたが、普段から肥満気味の方は発症のリスクが高いとされます。
肥満気味と自覚のある方は、次のことを意識した生活を送ることがおすすめです。
- 毎日定期的な運動習慣を作る
- 栄養バランスのとれた食生活
- BMI22前後を目標とした体重維持
BMIとは肥満度を数値で表したもので、体重からメートルで表した身長を2乗した数字を割った数字で求めることが可能です。
次に、膝への負担が多いスポーツや仕事などをしている方は、負担の大きさや継続期間によって変形性膝関節症を発症しやすくなります。
自覚のある方は、膝への負担を減らしたり、頻度を減らしたりなど予防するほか、違和感を感じたらなるべく避けるようにしましょう。膝への負担が大きいとされる動きは次のとおりです。
- 長距離歩行
- ランニング
- 階段の昇降
- 正座
- しゃがみ込む動作と立ち上がる動作の反復
- スクワット
- 段差の飛び降り
- 頻繁な重い荷物の運搬
続いて、運動不足により膝周りの筋肉が萎縮したり硬直したりすると、変形性膝関節症の原因になります。
適度な筋力トレーニングや膝のストレッチをして、筋力アップや柔軟性アップを図りましょう。
おすすめの筋力トレーニングやストレッチは次のとおりです。
- 太ももの前側の筋力トレーニング
- プールで水中歩行
- 5,000歩程度のウォーキング
などが効果的です。
無理のない範囲で毎日継続しておこなうことが大切になります。
最後に、近親者に変形性膝関節症の方がいる場合も将来的に発症する可能性があります。自覚を持ち、膝に大きな負担がかかる動作を避け、予防を心がけましょう。
変形性膝関節症を発症しやすい方の主な特徴を4つ紹介しましたが、ほかにも持病として糖尿病や骨粗しょう症などの疑いがある方も発症のリスクは高まります。
持病のある方は、医療機関で適切な管理を受け、治療とともに変形性膝関節症の予防をしましょう。
変形性膝関節症の手術のタイミング

変形性膝関節症を発症し、医療機関を受診すると手術以外の方法によって治療がおこなわれますが、膝の痛みが中々改善されない場合は手術の検討も選択肢の1つです。
いざ手術を検討するとなるとなかなか踏み切れないものですが、手術時期を逸すると重症化に繋がる恐れもあるため、適切な手術のタイミングを紹介します。
治療をて3〜6か月経過しても改善が見られない場合
変形性膝関節症の手術のタイミングは、一般的には治療を開始してから約3か月~約6か月間が経過しても痛みがとれず、効果が現れない場合の検討が一般的とされています。
痛みが続けば苦しい時間も長引きます。長引く痛みに苦労されている方は、医療機関への相談をおすすめします。
医療機関に手術の相談をする場合には、痛みによって日常生活に支障をきたしているのか、医師から提示された手術方法によるリスクはどの程度あるのかなどを確認し、失敗しないために総合的に判断するようにしましょう。
変形性膝関節症の手術方法

変形性膝関節症には大きくわけて3つの手術方法があります。
それぞれの手術の特徴や入院期間などを紹介します。
関節鏡視下手術
関節鏡視下手術は、関節鏡を使用して関節内の変形した半月版や軟骨などを除去する手術です。
手術後の傷は小さく、術後は数日で歩行可能ですが、一時的に関節内を整理して症状を和らげる対症療法の要素が強いため、短期的な効果になってしまう場合もあります。
そのため、変形性膝関節症の進行状況によっては、別の手術療法をすすめられることもあるります。
関節鏡視下手術の特徴や入院期間などは次のとおりです。
- 症状が初期の方に向けた手術
- 手術後の傷が小さい
- 身体への負担が少ない
- 再発のリスクが高い
- 入院期間は約1週間程度
- 手術費用は3割負担の場合で約5万円
初期の方に向けた手術のため、比較的低価格で負担が少ないことが特徴な手術方法といえます。
高位脛骨骨切り術
高位脛骨骨切り術は、変形性膝関節症によって変形したことにより、膝の内側に偏った負荷を外側に分散させるために、脛骨と呼ばれるすねの骨を切って矯正する手術方法です。
手術後の回復にはリハビリが不可欠ですが、膝にメスを入れずに温存できる方法のため、スポーツや重労働を引き続きおこなう必要のある方には適した手術方法といえます。
高位脛骨骨切り術の特徴や入院期間などは次のとおりです。
- 症状が中期の方に向けた手術
- 手術により活動的な生活が可能
- リハビリが長期に渡る
- 入院期間は約3週間程度
- 手術費用は3割負担の場合で約10万円~約12万円
松葉杖で歩行できるようになるまでは約1週間〜約2週間程度が目安とされ、退院後もリハビリを継続しておこなう必要がありますが、膝の痛みに苦労していた生活から解放される可能性のある手術です。
人工膝関節置換術
人工膝関節置換術は、変形性膝関節症の末期で大きく変形してしまった膝や、関節の表面を人工的な金属や高分子ポリエチレンでできた部品に置き換えをおこなう手術方法です。日常生活に支障をきたしている方におこなわれる手術といえます。
手術自体に年齢制限はなく、たとえ高齢であってもリハビリ可能な体力があり、手術を理解できる方であれば手術可能です。人工膝関節置換術の特徴や入院期間などは次のとおりです。
- 症状が末期の方に向けた手術
- 手術により痛みの解消が期待
- 歩行が可能になる
- 約20年で再置換が必要な可能性がある
- 身体への負担が大きい
- 入金期間は約2週間~数か月
- 手術費用は3割負担の場合で約24万円
手術に使用する置き換えのための人工的な部品には耐久性がよい素材を使用しますが、摩耗や耐用年数の経過などにより、取り外して付け替える手術が必要となる場合があることがネックといえます。
変形性膝関節症の手術をおこなうメリット

変形性膝関節症の特徴や手術方法を説明してきました。次に、手術によるメリットを具体的に紹介します。
期待できる効果を理解し、自身の身体と向き合って決定しましょう。
痛みが大きく緩和される
上記で紹介した3つの手術方法はいずれも、傷みの原因となっている部分は解消できるため、痛みが大幅に緩和されます。
また、負荷により変形した関節が正しい方向に矯正されることで、膝関節全体へ均等に負荷がかかるようになるため、痛みを感じることなく生活が送れます。
また、膝の曲げ伸ばしに苦労していた方も痛みなくスムーズな曲げ伸ばしが可能になります。
姿勢がよくなる
手術で期待できることは痛みの緩和のみではありません。変形した膝や関節の矯正により正しい姿勢を取り戻せます。
片方の膝が痛いために、片脚をかばった生活を送っていると反対の脚に負担がかかり、結果として両膝を痛めてしまい、姿勢が悪くなってしまうことはよくあります。
また、姿勢が悪くなると腰やほかの関節など、別の部位を痛める要因となります。手術での矯正により姿勢がよくなると、体全体への負担を大幅な軽減が期待できます。
変形性膝関節症の手術で注意するべきリスク

変形性膝関節症の手術には大きなメリットがある一方で、身体にメスを入れるため、リスクも存在します。
主なリスクを2つ紹介するため、メリットとあわせて理解しておきましょう。
感染症
手術に使用するものは滅菌処理がおこなわれていますが、傷を縫い合わせた後も、細菌から感染症を起こすことが少なからずあります。
ただし、感染症のリスクは変形性膝関節症の手術に限らず、どの手術でも伴うリスクです。変形性膝関節症の手術は近年の高齢化に伴い大きく進歩し、感染症の発症リスクは低くなってきています。
たとえば、変形性膝関節症末期の手術方法である人工膝関節置換術では、日本整形外科学会学術研究プロジェクト調査によると、日本での初回の人工関節置換術で手術部位からの感染症発生率は約1.36%とされています。
一方で、糖尿病や肥満などの生活習慣病の持病がある場合は手術による感染症発症のリスクが高まる傾向があるため、医師と相談のうえ、慎重に決断しましょう。
血栓
変形性膝関節症の手術は感染症のほか、血栓と呼ばれる血のかたまりができる可能性があるリスクもあります。
手術前後は安静にしなければならないことから脚を動かせず、そのため血流が悪くなり、血が固まってしまう場合があるのです。
医療機関は血が固まらないように工夫を凝らしていますが、自身でも寝たままで可能な脚の運動も取り入れ、血栓を予防しましょう。
変形性膝関節症の手術以外の治療方法

変形性膝関節症の手術について中心に説明してきましたが、手術以外の治療法についても紹介します。
手術以外の治療法には大きく分けて、保存療法と再生医療に分けられます。
それぞれ詳しく解説します。
保存療法
まず、保存療法についてです。
概要やメリットなどは次のとおりです。
| 概要 | 主に日常生活指導、運動療法、装具療法、薬物療法、リハビリテーションなどを中心に組み合わせて治療をおこなう |
| メリット | ・手術をせずに回復する場合がある ・筋力アップや柔軟性アップなど、予防的効果も期待できる |
| デメリット | ・効果が得られない場合がある ・組み合わせておこなうため、時間がかかることが多い |
保存療法で十分な効果が得られる場合もあります。代表的な保存療法を次に紹介していきます。
薬物療法
薬物療法は、一時的な痛みや炎症を抑える効果が期待されます。
概要やメリットなどは次のとおりです。
| 概要 | 消炎鎮痛剤の内服や外用剤の服用を中心におこない、短期的な痛みの緩和が期待されるもの |
| メリット | ・痛みの緩和 ・炎症を抑える効果 |
| デメリット | ・根本的な改善にはならない ・短期的な効果 ・副作用がある |
薬物療法は長期間の使用は推奨されていません。また、医療機関の指示の元で治療しましょう。
関節腔内注射
関節腔内注射注は大きく分けると、痛み止めと炎症抑制効果があるステロイド、軟骨を保護するヒアルロン酸に分けられる注射薬です。
概要やメリットなどは次のとおりです。
| 概要 | ステロイドとヒアルロン酸の2種類がある注射薬により、痛み止め、炎症抑制の効果が期待できるもの |
| メリット | ・痛みの緩和 ・炎症を抑える効果 ・ステロイドは即効性がある ・ヒアルロン酸は、定期的な使用が可能 |
| デメリット | ・副作用がある ・ステロイドは強い薬のため常用はできない ・ヒアルロン酸は症状が悪化すると痛みを抑えきれない |
根本的な治療までには至らないため、ほかの保存療法と組み合わせておこなうことで効果が期待されます。
運動療法
運動療法は適切におこなうことにより、膝関節周りを支える筋肉が鍛えられることや、身体のバランスが改善される効果が期待されます。
運動療法の概要やメリットなどは次のとおりです。
| 概要 | 膝関節周りの筋力アップや身体のバランスを改善し、痛みの改善に繋げるもの |
| メリット | ・膝関節周りを支える筋力アップ ・身体のバランス改善 ・膝の安定性アップ ・痛みの軽減 |
| デメリット | ・適切な方法でおこなわなければ効果が薄い ・日々の継続性が必要 ・過度におこなうと悪化の恐れがある |
運動療法はO脚の方の矯正にも有効です。適切な運動療法を受けるには、医療機関を受診し、正しい方法でおこないましょう。
再生医療
保存療法ではなかなか改善できず、進行が止まらない方には再生医療により変形性膝関節症の進行を遅らせる効果が期待できます。
| 概要 | 保存療法では止めることのできない変形性膝関節症の進行を遅らせるため、主に2種類の注射で進行を遅らせる治療方法 |
| メリット | ・痛みの緩和 ・変形性膝関節症の進行を遅らせる ・入院が不要な治療法もある ・手術ができない高齢者も可能 |
| デメリット | ・比較的新しい治療方法 ・効果に差がある ・保険適用外 |
再生医療は比較的新しい治療法で、体への負担が少ないものとされていますが、保険適用外であるため高額になることもあります。
検討される方は医師に相談してみましょう。主な再生医療の2種類の概要やメリットなどを解説します。
PRP療法
PRP療法は自身の血液を採取し、血小板を加工して注射する治療方法です。
概要やメリットなどは次のとおりです。
| 概要 | 自身の血液を採取し、自然治癒力を向上させる働きがあるとされる血小板を加工して注射をおこない膝関節の機能改善を目指す治療方法 |
| メリット | ・入院不要 ・手術不要 ・自然治癒力の向上による膝関節の機能改善に期待 |
| デメリット | ・効果に差がある ・保険適用外 ・効果が出るまでに時間がかかることがある |
治療の効果には差があり、効果が出るまでに約1年ほど時間がかかる場合もあります。保険適用外であることからも、事前に医師や周囲と相談した決定をおすすめします。
培養幹細胞治療
培養幹細胞治療は複製する能力と、さまざまな細胞にわかれる能力を持つ特殊な幹細胞を採取して培養後に体内へ注入する治療方法です。
概要やメリットなどは次のとおりです。
| 概要 | 特殊な能力を持つ幹細胞を採取して体外で培養し、注入をおこない膝関節機能の修復や改善を目指す治療方法 |
| メリット | ・炎症を抑える効果 ・痛みの改善 ・膝の機能の改善 ・修復作用に期待 |
| デメリット | ・効果に差がある ・保険適用外 ・効果が出るまでに時間がかかることがある |
培養幹細胞治療は、少量の脂肪から幹細胞を採取しておこないますが、幹細胞は膝の軟骨にも分化できるとされているため、痛めた組織の修復に期待が持てます。
効果には個人差があるため、ほかの治療方法と併行しておこなうことをおすすめします。
まとめ
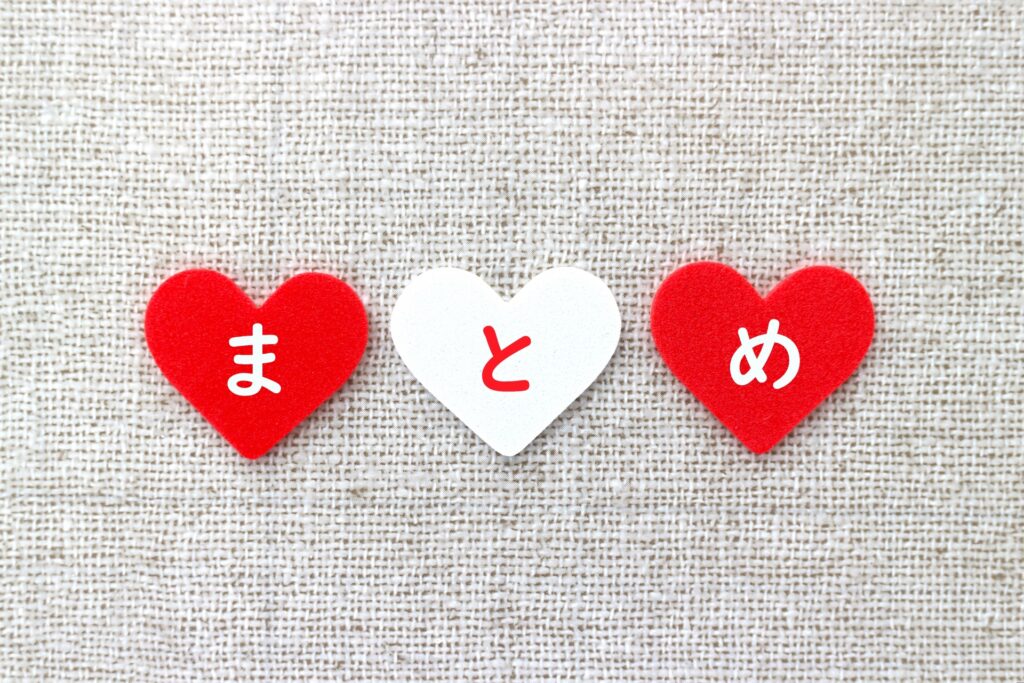
変形性膝関節症は重症化すると歩行が困難になったり、手術を余儀なくされたりと、今まで当たり前にできていた生活ができなくなってしまいます。
治療を開始しても思うように回復しなかった場合、痛みに長期間耐えなくてはならなくなってしまうため、心身ともに辛いものです。
手術を検討されている方は、入院期間や手術後のリハビリのほか、回復の見込み程度、再発の可能性などを確認し、手術後に描く自身の未来と照らし合わせ、主治医と綿密に話し合ったうえで判断をおこなうことが大切です。
手術のタイミングや手術方法を失敗しないように、早めに先々を想定して確認しておきましょう。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。