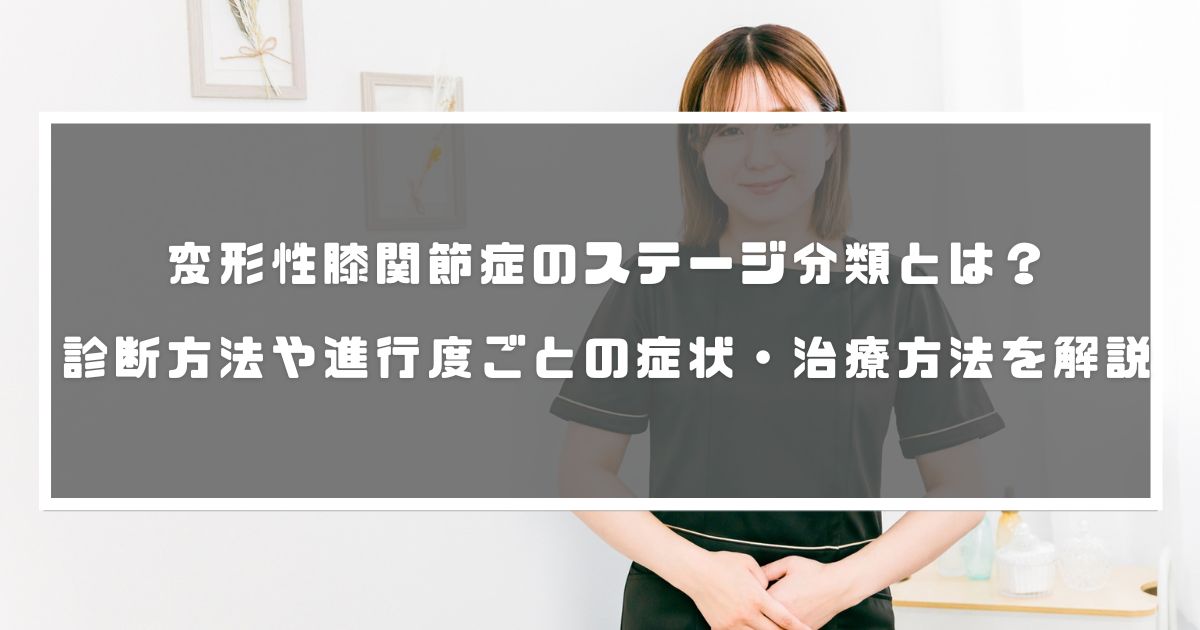変形性膝関節症の治療を始める際は、重症度(グレード)を正確に把握することが大切です。ステージ分類によっては診断方法や治療方法が異なります。
今回は、変形性膝関節症のステージ分類をはじめ、診断方法や進行度ごとの症状、治療方法について解説します。
変形性膝関節症のステージ分類とは?

ステージ分類は、膝の関節に変形が全くない状態をグレード0とし、その後の進行度をグレード1〜4で分類する「KL分類」が用いられています。
そもそも変形性膝関節症は、膝関節にある軟骨の質が低下して少しずつすり減り、歩行時に膝の痛みを生じる病気です。
関節軟骨の老化が多いですが、肥満や遺伝子も原因になります。また、骨折や靭帯、半月板村荘などの外傷、化膿性関節炎のような感染後遺症を発症するケースもあります。
加齢が原因の場合、膝関節の軟骨が年齢とともに弾力性を失い、使いすぎによってすり減って変形します。
進行度を判断するものは次のとおりです。
- 関節のすき間がどのくらい狭くなっているか
- 骨への荷重負荷・摩擦によって棘のような骨(骨棘)がみられるか
- 関節軟骨の下にある軟骨下骨が正常時よりも硬くなっているか
進行するにつれ、上記で挙げた状態が悪くなります。
グレード0
グレード0は、太ももの骨である「大腿骨」とすねの骨である「脛骨」の間にある関節のすき間が十分にあり、関節の変形も全くない正常な状態のことです。
グレード1
グレード1は、軟骨下骨が正常時よりもわずかに硬くなっていることです。また、骨棘がみられる場合もあります。
グレード2
グレード2は、大腿骨と脛骨のすき間が正常な関節より、25%以下の減少がみられる状態です。グレード1と同様、わずかに骨棘がみられます。
- 立ち上がり
- 正座
- 階段の昇降
上記のような場合に、一般的な膝の痛みやこわばりを感じるなどの症状がみられます。
グレード3
グレード3は、大腿骨と脛骨のすき間が正常な関節よりも50〜75%程度減少し、軟骨下骨硬化や複数の骨棘がみられます。膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなり、正座することが難しくなります。
また、階段を昇り降りする際に膝の痛みがひどくなったり、個人によっては膝に水がたまって腫れたりすることもあります。
グレード4
グレード4は、大腿骨と脛骨のすき間が正常な関節より、75%以上の減少がみられる状態です。大きな骨棘や骨端部の変形、骨硬化がみられて関節のすき間が消失することがあります。
- じっとしていても膝が痛む
- 膝が思ったように動かない
上記のように、日常生活に支障をきたすようになります。
変形性膝関節症の自覚症状による進行度分類

変形性膝関節症の自覚症状による進行度は次のように分類されます。
- 前期
- 初期
- 中期
- 末期
それぞれどのような症状か、次で解説します。
前期
前期の場合は痛みは感じず、健康な状態です。軟骨変形である関節軟骨に劣化や痛みが起こることもありますが、外部からは確認できません。ここから長い年月をかけ、少しずつ関節軟骨の弾力が衰えて病気が進行します。
初期
初期の場合は軟骨がすり減り始めますが、X線では膝関節が変形することは少ないです。主な症状は膝の動かしにくさやこわばり、違和感などです。
軟骨変形が進むと関節軟骨のクッション機能が失われ、一箇所に負担がかかることで骨硬化がみられます。
また、滑膜が炎症を起こし、激しい痛みを感じることがあることも初期の特徴です。
中期
中期の場合は初期の炎症が落ち着いて痛みは軽減しますが、膝関節の変形が始まるため、痛みが慢性化し、日常生活の動作に影響が出始めます。
とくに階段の昇降や正座、立ち上がりなど、膝の曲げ伸ばしに関する動作に支障をきたし、動くたびに痛みを感じます。
そのため、痛みをかばうことで膝周囲の筋肉や人体を動かす機会が減り、膝関節の動きが硬くなってしまい、制限がかかります。
末期
末期の場合はさらに変形は進行し、軟骨がすり切れた状態です。
脛骨と大腿骨が直接ぶつかることから、立つ、座る、歩くといった日常生活の動作がまともにできなくなるほど、膝が動かなくなります。
滑膜の炎症が治って痛みが軽減する方もいますが、基本的に動かなくても痛みを感じ、杖や手すりなどの何かを頼りにしないと歩くことも困難になります。

変形性膝関節症の診断方法

診断方法は、「問診、診察」「レントゲン検査」「MRI検査」の3種類です。それぞれくわしく解説します。
問診・診察
問診では、主に膝の痛みをはじめとする自覚症状の確認をします。診察では触診により、次のような症状がないのかを調べます。
- 腫れ
- 変形
- 膝関節の痛み
- 関節可動域
- 関節の不安定性
関節可動域とは、身体の各関節が障害を起こさず、生理的に運動できる範囲(角度)のことです。診察ではどれだけ関節の曲げ伸ばしができるかを確認します。
レントゲン検査
レントゲン検査では、どのステージ分類に当てはまるかを診断します。
- 変形性膝関節症のどのステージ分類にあたるか
- 大腿骨と脛骨のすき間がどの程度あいているか
- 骨棘が形成されているかどうか
関節のすき間には軟骨があり、軟骨がすり減ることは症状の悪化を意味します。そのため、関節のすき間に着目して診察します。
MRI検査
MRI検査では靭帯や軟骨、半月板などの軟部組織の状態や、骨髄浮腫の有無を確認します。
これらが確認されると、変形性膝関節症の進行がはやく、将来的に人工関節が必要となるリスクが高まります。
レントゲン検査とMRI検査を併用して、症状の進行具合を予測するための重要な情報が得られます。
変形性膝関節症のステージ分類ごとの治療方法

ここからは、変形性膝関節症のステージ分類ごとの治療方法を解説します。
グレード1
グレード1では、運動療法をおこないます。
運動療法はすべてのステージ分類において基本です。薬物療法や手術療法をする場合でも運動療法をおこない症状の進行を抑えます。
変形性膝関節症による膝の痛みによって、日頃の外出や運動を避けていると次のような問題が起こります。
- 膝を支える筋肉が衰える
- 膝を曲げ伸ばしできる角度が狭くなる
- 膝を支える筋肉や膝関節への負担が増える
運動不足の場合、筋力低下を引き起こし、より一層膝関節への負担が増えることで変形性膝関節症が悪化する悪循環に陥るリスクがあります。
こうした悪循環を防ぐために、運動療法を継続的に取り組み、膝関節を支える筋肉を鍛えて維持することが大切です。
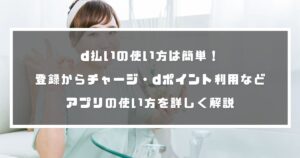
グレード2
変形性膝関節症の初期治療として、薬物療法や注射療法が行われるケースが多いです。
薬を用いて一時的に痛みや炎症を抑えても、膝周囲の筋肉が衰えている状態では、その後も膝関節に負担がかかり続けることとなり、いずれ痛みが生じます。
そのため、薬物療法の場合でも、運動療法を並行しておこなうことが大切です。膝周囲の筋肉を鍛えることで膝の柔軟性が保たれるでしょう。
グレード3
グレード3となると膝が痛む頻度が増えるため、薬で痛みや炎症を抑えます。しかし、次のような場合には手術療法が検討されます。
- 保存療法を続けても症状が改善されない場合
- 症状がひどくて日常生活に支障をきたす場合
ただし、自覚症状には個人差があるため、実際に治療する流れは症状に応じて異なることが大半です。
グレード4
保存療法を実施しても痛みが改善または緩和されず、日常生活に大きな支障をきたす場合は手術が検討されます。
- 膝関節内ですり切れた軟骨片を取り除く「関節鏡視下手術」
- 脛骨の一部を切って足の変形を矯正する「骨切り術」
- 傷んだ膝関節を人工の膝関節に入れ替える「人工関節置換術」
とはいえ、いきなり手術に踏み切れる方は少なく、「できれば手術はしたくない」と考えている方が多いでしょう。
そこで、自身の血小板(PRP)に含まれる成長因子を活用する「PFC-FD療法」、脂肪由来の幹細胞を利用する「ASC治療」などのバイオセラピーが新たな選択肢として活用されています。
手術療法のように入院の必要もなく、身体にかかる負担も手術より少なくて済むことが再生医療、バイオセラピーのメリットです。
【ランキング】変形性膝関節症には専門クリニック
変形性膝関節症の方には専門クリニックの受診がおすすめです。相談も無料で行えるクリニックがあるため、お悩みの方は検討してみてください。
1位:ひざ関節症クリニック
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
変形性膝関節症に関するよくある質問

変形性膝関節症に関するよくある質問について、それぞれくわしく解説します。
変形性膝関節症を放置するとどうなる?
変形性膝関節症を放置すると軟骨がすり減った分、膝関節の骨と骨のすき間が狭くなり、内側の骨があらわになって骨の辺縁に棘のような突起物ができたり変形します。
また、関節を覆っている関節包と呼ばれる線維膜の内側に炎症が生じるため、黄色みかかった粘り気のある液体が分泌されて膝に水がたまった状態になります。
変形性膝関節症は進行性の病気なため、症状が進行すると手術での治療を検討しなければなりません。
時間をかけて進行していくため、徐々に症状が重くなっていくため、違和感を感じた初期段階の時点で早めに治療を始めましょう。
変形性膝関節症の進行速度は?
変形性膝関節症は、5〜10年程度の長い年月をかけて徐々に初期から中期、中期から末期へと進行します。
変形性膝関節症のステージと痛みは比例する?
変形性膝関節症のステージと痛みは比例しません。
軽微な変形でも強い痛みを感じたり、強く変形していても痛みをあまり感じなかったりすることもあります。
変形性膝関節症の再生療法は保険適用?
変形性膝関節症の再生療法は保険適用が認められていません。
なぜなら再生療法は安全性が確立されて効果が立証されているものの、保険診療として認証できるほどのデータが揃っていないからです。
膝軟骨の一部をコラーゲンが入ったゲル状物資のなかで約1か月培養し、ジャックと呼ばれる自家培養軟骨を作成します。
その後、欠損した膝軟骨に移植する再生療法が2013年4月から保険適用になりましたが、変形性膝関節症の再生療法は未だに保険適用外です。
変形性膝関節症のグレード3以上でも手術以外の治療法はある?
グレード3以上で、どうしても手術を避けたい場合には再生療法がおすすめです。
変形性膝関節症の再生療法は次のとおりです。
- 脂肪を採取し、そこから培養した幹細胞を関節内に投与する「幹細胞治療」
- 採取した血液を加工してPRPを抽出して関節に注射する「PRP療法」
- PTPをさらに高濃度にしたPRP-FDを靭帯や関節内などに投与する「PRP-FD療法」
- PRPから関節の健康に関わる成分だけを取りして注射する「APS療法」
血漿や血小板には組織の修復を促す成分が含まれています。
とくに、血小板に含まれる成長因子は人が本来持っている自然治癒力を促す重要な成分で、その成分を患部に注射することで自然治癒を促します。
まとめ
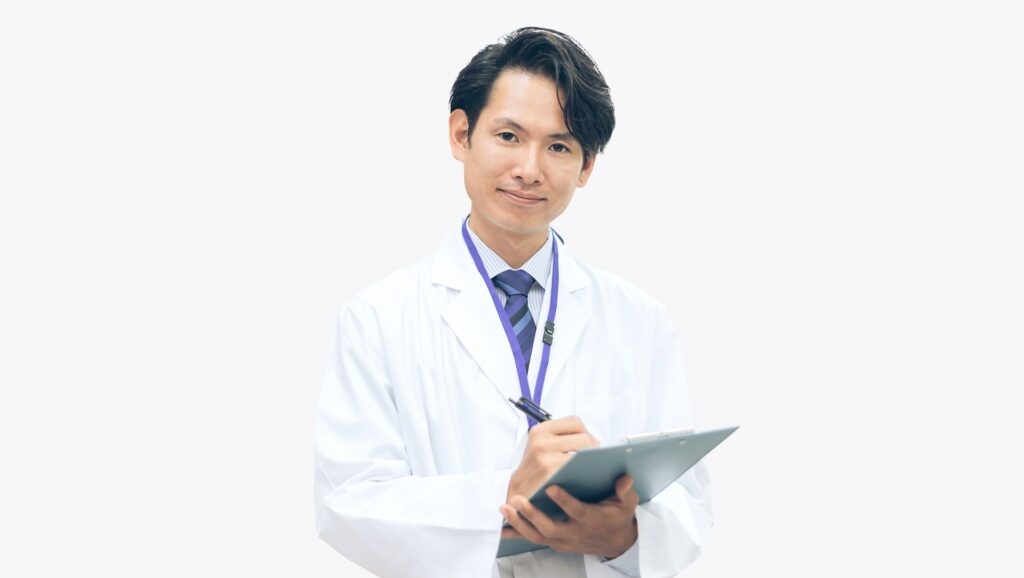
今回は、変形性膝関節症のステージ分類について解説しました。
変形性膝関節症は膝に痛みを感じている方の多くは、膝を支える筋力や膝関節の柔軟性が低下しています。そのため、関節内と関節外、両方の治療が必要です。
早期発見できれば運動療法のみで済む場合もありますが、グレードが上がるにつれて手術療法も検討しなければなりません。
長い年月をかけて進行していく変形性膝関節症ですが、早期の診断や治療が重要です。膝に痛みを感じる場合、膝に関することで困っている場合、我慢せずに医療機関を受診してください。
※本記事の情報は2022年12月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。