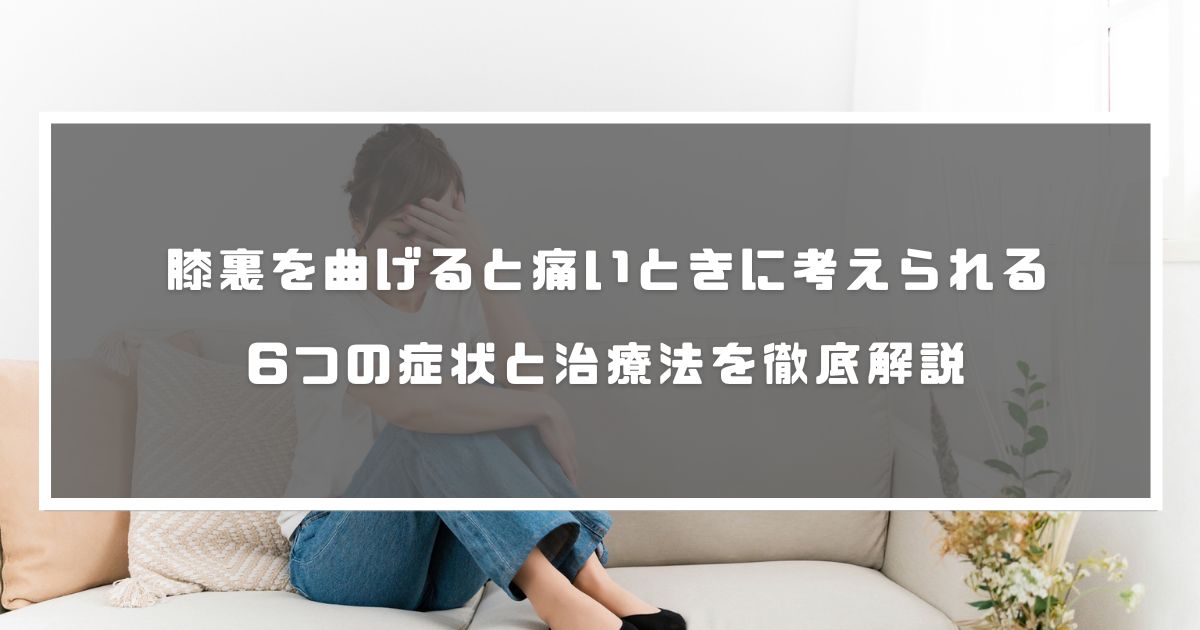膝に何らかの疾患や怪我があると、膝裏を曲げると痛いと感じることが多くなります。膝裏を曲げると痛いと感じることが増えたときは、早めに医療機関を受診したうえで、適切な治療を受ける必要があります。症状を放置すると、最悪の場合歩行困難に陥って日常生活に支障をきたす恐れもあるため要注意です。
本記事では、膝裏を曲げると痛いときに考えられる症状を解説していきます。原因や治療法、すぐにできる治療法をチェックしたうえで、症状悪化を防いでいきましょう。
膝裏を曲げると痛い!考えられる6つの症状

膝裏を曲げたときに痛みがあると、日常生活にもさまざまな影響があります。痛みのせいで歩くことすら大変に感じたり、仕事にも集中できなかったりします。そのため膝の痛みについては、放置せずにしっかりと対処する必要があります。
膝裏を曲げると痛いと感じたときは、次の6つの疾患や怪我の可能性があるため注意しましょう。
- 関節リウマチ
- 靭帯損傷
- 半月板損傷
- ペーカー嚢腫
- 鵞足炎
- 痛風
いずれも放置すると痛みが慢性的に残ったり、ほかの膝の疾患を併発したりするため、それぞれ症状と原因は最低限知る必要があります。もちろん最終的には医療機関の受診が必須になりますが、まずはそれぞれの概要を押さえて、どのような症状に当てはまるのかセルフチェックしていきましょう。
関節リウマチ
膝裏を曲げると痛いときは、関節リウマチを患っている可能性があるため気をつけてください。
関節リウマチは、免疫異常の一つとして知られています。膝の関節に炎症が起こることで、膝周りが痛む特徴があります。症状と原因をそれぞれ見ていきましょう。
症状
関節リウマチになると、膝裏を曲げると痛んだり、膝周辺が腫れたりします。痛みや腫れが明らかに伴う場合は、関節リウマチの可能性を考えてみましょう。
痛みや腫れが出た状態でそのまま放置すると、関節の変形や機能障害の症状も見られるようになります。症状が悪化した証拠のため、症状の進行を防ぐには、速やかに医師に相談したうえで治療を受ける必要があります。
原因
関節リウマチは、免疫異常によって起こります。したがって原因はさまざまなケースが考えられ、次のことが例として挙げられます。
- 遺伝
- 喫煙
- 歯周病
しかしながら、原因について確定的なことはわかっていません。主に40代~60代で発症する傾向にありますが、近年はさらに高齢になってから発症するケースも見られるようです。
靭帯損傷
膝裏を曲げると痛いときは、靭帯損傷の可能性も考えられます。
人の関節は、靭帯というひも状の形をした組織によって骨同士が結合されています。この構造は、関節がずれたり不安定になったりすることを防ぐ役割があります。しかしスポーツや事故で衝撃が加わると、靭帯の一部もしくは全部が切れることがあるため注意が必要です。このように靭帯が切れた状態のことを、靭帯損傷、もしくは靭帯断裂と呼びます。
靭帯損傷は、膝の怪我のなかでも重い症状の一つになるため、放置せず早急に治療を受ける必要があります。
症状
膝の靭帯損傷になると、激しい痛みや腫れを伴います。切れた場合は激痛によって歩くことも難しくなり、日常生活にも支障をきたすため、しばらくは松葉杖を必要とする生活になります。
3~4週間の時間が経つと痛みや腫れは引いてくるため、元どおりに日常生活も送れるようになりますが、スポーツをする場合完全復帰はある程度先になります。何か月もリハビリを繰り返すことで、全治を目指します。
また、通常の生活に戻っても、膝の不安定な感覚は残りやすい点が特徴です。
原因
膝の靭帯損傷は、主にスポーツや交通事故によって起こります。
ジャンプ運動時に足をひねる、タックルや衝突時の膝への衝撃が主な原因になるでしょう。したがって日常的にスポーツをする方は、膝に無理な負担がかからないよう十分に注意する必要があります。
半月板損傷
膝裏を曲げると痛い場合は、半月板損傷の症状の可能性もあります。
半月板損傷は、膝関節の中にある半月板に亀裂が入ったり、欠けたりする怪我のことを指します。年齢関係なく発症する可能性があり、場合によって変形性膝関節症を併発するパターンもあるため要注意です。
膝関節における半月板とは、関節の内側と外側に存在します。主に膝への負担を分散したり衝撃を緩和させたりする役割を持つため、半月板損傷に陥ると、膝に痛みや違和感を頻繁に覚えるようになります。
症状
半月板損傷になると、主に痛みや、曲げ伸ばし時の引っかかりをよく感じるようになります。衝撃吸収や負担分散の役割を持つ半月板が、うまく機能していない証拠です。
症状が重くなれば、膝に水が溜まる症状も見られるようになります。膝に溜まる水とは、関節液にあたります。
痛みや違和感を放置すると、激痛が原因で歩行困難に陥ることも少なくありません。膝が突然動かせなくなる、ロッキングと呼ばれる状態に陥るケースもあります。
原因
半月板損傷は、主に次のような原因によって起こります。
- 無理な膝のひねり
- 膝の酷使
- 外から膝への強い衝撃
- 靭帯損傷からの併発
したがって半月板損傷も、靭帯損傷と同様に、スポーツや事故によって発症するケースが多いといえます。先に靭帯損傷になり、半月板損傷を併発するパターンもあるため気をつけてください。
ベーカー嚢腫
膝裏を曲げると痛いときは、ペーカー嚢腫を発症している可能性もあります。
ベーカー嚢腫は、膝裏の関節液を含む滑液包の炎症を起こすことを指します。炎症によって膝裏が膨らむ点が大きな特徴です。
滑液包は、日常的に負担のかかりやすい膝関節をサポートする役割を持ちます。具体的には、摩擦吸収や軽減をおこない、膝関節への負担を抑えています。
しかし炎症を起こすと本来の機能を保てなくなり、関節液が多く分泌されて滑液包にたまってしまい、痛みを伴います。主に40代くらいの女性に多い傾向にあります。
症状
ベーカー嚢腫になると、主に次のような症状を感じるようになります。
- 膝裏の痛み
- 曲げ伸ばし時の不快感や違和感
- 曲げたときの圧迫感(滑液包が膨らんでいるため)
- 膝下のしびれ
膝周辺のなかでもとくに膝裏が痛いときは、ベーカー嚢腫を患っている可能性は、十分に考えられるでしょう。
また膝裏の痛みや違和感以外に、膝下がしびれる原因は、神経を刺激してしまうためです。膝裏は足先に向けて神経が通っているため、ベーカー嚢腫を発症すると、神経を刺激するせいでしびれを伴うケースがあります。
原因
ベーカー嚢腫を発症する原因は、次のことが考えられます。
- 膝の酷使
- 体重増加
- 別の膝の疾患からくる合併症
日常的に膝を酷使したり、体重増加に伴って膝への負担が増えたりすると、ベーカー嚢腫を発症する可能性があります。
ただしベーカー嚢腫の原因で多いものは、合併症です。関節リウマチや変形性膝関節症、痛風が影響して、ベーカー嚢腫を併発するケースは少なくありません。
鵞足炎
膝裏を曲げると痛いときには、鵞足炎を患っているケースもあるため注意しましょう。
鵞足炎は、膝の屈曲や股関節の内転動作が主に原因となって起こる症状です。滑液包への負担が重なることで、痛みを伴うようになります。主にスポーツが原因で発症する疾患ですが、日常生活のなかの転倒などによって発症する場合もあります。
症状
鵞足炎は、痛みが主な症状になります。鵞足は膝から5cm程度下がったすねの内側に存在するため、押すことで痛んだり、運動をしたあとに痛みが残ったりするパターンが多いです。
また、人によっては痛みとともに腫れたり、患部が熱くなったりする場合もあります。症状が重くなれば、激痛を伴って歩くことがきついと感じることも考えられるでしょう。
原因
鵞足炎になる原因は、次のことが挙げられます。
- 膝に無理な負担がかかるトレーニング
- 準備運動をせずに激しい運動をする
- 急に長い距離を歩く
- 体重増加
- 半月板損傷や変形性膝関節症からの併発
膝に負担を多く与えると、鵞足炎につながる可能性があるため注意しましょう。また、前項で取り上げてきたほかの膝の疾患と同様に、別の疾患が影響して、鵞足炎を併発するパターンもあります。
痛風
膝裏を曲げると痛いときは、痛風を患っている場合も考えられます。
痛風は、足の親指の付け根部分が腫れて痛む病気です。患部は非常に赤く腫れて痛みを伴うため、ときには通常の歩行すらもきつく感じられることがあります。
また痛風を発症すると、足の親指の付け根以外の部位が痛む場合もあるため注意が必要です。たとえば足の甲、足関節、アキレス腱の付け根、膝関節、手関節の部位が挙げられます。主に発症する方は、男性です。
症状
痛風の主な症状は痛みと腫れです。前述のとおり、痛風は足の親指の付け根以外にも膝関節に痛みが及ぶケースがあるため、膝裏を曲げると痛いときは痛風が影響している可能性があります。
痛風は痛風発作と呼ばれることもありますが、発作と呼ばれる理由は、前日まで何も痛みがなかったのに、急に痛みを感じることがあるためです。歩けない、仕事に集中できない、患部が熱いなどの特徴があります。
原因
痛風の原因は、主に次のことが挙げられます。
- 暴飲暴食
- 激しい運動
- 肥満
痛風の原因には重要な仕組みがあります。まず血液中の尿酸値が高くなって飽和溶解度を超えると、関節内には尿酸塩結晶が生成されます。この尿酸塩結晶を白血球が処理するときには、痛風の痛みが生じる仕組みです。
尿酸値が高い状態が長く続くと、尿酸結石が腎臓にできてしまい、腎臓の機能は低下していきます。腎機能低下につながる高尿酸血症(尿酸値上昇)の原因には、上の暴飲暴食や運動、肥満が挙げられます。
したがって痛風の症状を防ぐには、高尿酸血症の状態にならないよう対策することが重要です。
膝裏が痛いときにできる対処法

膝裏を曲げると痛いときは、上記の6つの疾患や怪我の可能性があるため、まずは症状と原因を知ることが大事です。そして最終的には医療機関の受診が必要になりますが、自身でできる対処法があれば、早いうちにチェックしたいところです。
膝裏を曲げると痛いときはまず次の対処法を実践して、症状改善、緩和を目指しましょう。
- 安静にする
- 晴れがある場合は冷やす
- ストレッチ
- 痛みが引かなければ整形外科を受診
では、それぞれの対処法について詳細を解説していきます。
安静にする
膝裏を曲げると痛いときは、気のせいだろうと思って放置しないことが重要です。何らかの疾患や怪我の可能性があるため、まずは安静にして、足を楽な状態にしましょう。
激痛でないときは、場合によってはしばらくすると痛みが収まることもあります。しかし定期的に痛みが出てくることは多いため、膝裏を曲げると痛いと感じた段階で、運動や長時間の歩行は避けるようにしましょう。
腫れがある場合は冷やす
膝裏を曲げると痛いと感じたときは、まず腫れの有無を確認しましょう。
膨らんだり赤くなったりして患部が腫れている場合は、冷やして安静にする必要があります。冷やすときは、濡らしたタオルや氷枕を利用します。時間は30分程度を目安にして、患部に当てましょう。冷やす頻度は1日2~3回が望ましいです。
ストレッチ
膝裏を曲げると痛いときは、ストレッチで痛み緩和を目指すこともおすすめです。簡単にできるストレッチは、ふくらはぎ、膝裏、太ももの後ろをすべて同時に伸ばす方法が効果的です。
まずは椅子に浅く腰かけた状態で、背筋を伸ばします。そして片方の足を床につけて、爪先を立てましょう。伸ばすときは膝裏を中心にして、ふくらはぎや太ももの後ろをしっかり伸ばしていきます。
続いて、上の姿勢から両手を爪先の方へ伸ばして、ストレッチをおこないましょう。これまでの手順を、片方の足でも実践します。左右それぞれで15秒、2回おこなうことが望ましいです。
痛みが引かなければ整形外科を受診
痛み改善や緩和を目指して上記の対処法を実践しても、膝裏の痛みが引かないときは、整形外科を受診しましょう。とくに歩行がきついと感じるほどつらい痛みが残るときは、重大な膝の疾患を抱えている可能性があります。
膝の疾患や怪我を放置すると、次のようなリスクを伴います。
- 日常生活に支障が出る
- ほかの膝の病気を併発する
- 膝をかばうことで別の部位に負担がかかる
- 痛みが原因で仕事に集中できなくなる
とくに注意が必要なリスクは、ほかの膝の病気の併発です。膝の病気を複数患うと、痛みがさらに大きくなったり、歩行が難しくなったりします。
症状が重い場合は、自身でできる対処法にも限界があります。痛みや腫れ、違和感が収まらないときは、早めに近くの整形外科に相談しましょう。
膝に負担をかけないためには?

今回解説した6つの症状のような膝の疾患、怪我を予防するには、普段から膝への負担を抑えるように意識していきましょう。負担をかけないための対策は、次のことが挙げられます。
- 太ももや膝の筋肉を鍛える
- 日常的にストレッチをする
- 太りすぎない
- 関節機能に必要な栄養をとる
いずれも重要な対策になるため、膝の疾患や怪我を防ぐには必須といえるでしょう。では、それぞれの対策について重要なポイントを解説していきます。
太ももや膝の筋肉を鍛える
筋力不足で、膝の負傷や疾患につながるケースは少なくありません。したがって太もも膝の筋肉を鍛えることは、病気や怪我を防ぐうえで重要な対策になるといえるでしょう。
太ももや膝まわりの筋肉が不足していると、あらゆる動作や衝撃に対して支える力が機能しなくなります。必要に応じて筋力トレーニングは実践したいところです。
とくにデスクワークが多い方は、日常的に運動不足に陥りがちなため、注意が必要です。少し長い距離を歩いたり階段の上り下りを頻繁にしたりするのみで、膝を傷める原因につながる可能性があります。
なかなか筋力トレーニングを実践する習慣がつかない、と悩んでいる方は、少なくとも運動不足は解消できるよう努めましょう。ウォーキングやジョギングを意識的におこない、筋力低下を抑えることが大事です。
日常的にストレッチをする
膝裏を曲げると痛いときは、膝への負担が多いと考えられるため、日常的にストレッチを実践して負担を減らしましょう。
膝裏を含めた膝痛緩和に役立つストレッチは、次の方法がおすすめです。
- 壁に片手をついた状態で立つ
- 片足の膝を曲げて爪先をつかむ
- 爪先をお尻に引き寄せたうえで前側の太ももを伸ばす
- 息を吐きつつ30秒間、伸ばした状態を維持
- 1~4を片方の足でも実践
上記のストレッチを、左右それぞれ2~3セットおこなっていきましょう。膝や太ももの筋肉に柔軟性をつけるうえで効果的です。
ストレッチをすれば筋肉がほぐれるため、筋肉の硬化によって引き起こされる怪我も防げるでしょう。短い時間で、かつ簡単に実践できるストレッチのため、積極的に実践していきましょう。
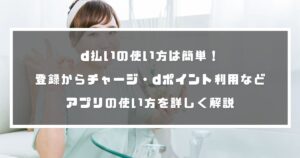
太りすぎない
体重が増加して肥満の状態になると、膝への負担も大きくなります。したがって膝の疾患や怪我を防ぐには、太りすぎないよう意識する必要があります。
太りすぎないためには、主に次のような対策が重要です。
- 間食をやめる
- 高カロリーの食べ物を控える
- 飲酒を控えめにする
- 夜食をやめる
- 食事のリズムを整える
- 運動習慣をつける
- 食事のあとにすぐに横にならない
- ストレスをためない
過度な食事制限や運動を実践する必要はありません。適切な生活習慣に整えるのみで太らないための対策はできるため、総合的な健康維持のためにも、積極的に意識していきましょう。
また、そもそも暴飲暴食は高尿酸血症の状態につながると考えられ、痛風の原因にもなります。膝裏を曲げると痛いときは、よい機会ととらえて、生活習慣を見直していきましょう。
関節機能に必要な栄養をとる
膝への負担を抑えるためには、関節機能に必要な栄養を摂取することも必要です。関節がしっかりと機能するよう体の状態を整えれば、結果として膝への負担も軽減できます。
関節を強くするには、次の栄養が効果的とされます。
- グルコサミン
- コンドロイチン
- オメガ3脂肪酸
上記の栄養を豊富に含む食べ物といえば、次のものが挙げられます。
- ウナギ
- オクラ
- イカの軟骨
- キノコ類
- フカヒレ
- ヒラメ
- やまいも
- 里芋
- 納豆
- なめこ
- 鮭
- サバ
- ブリ
- サンマ
- イワシ
栄養が偏りがちな方は、積極的に食事を見直していきましょう。
【ランキング】おすすめひざの専門クリニック
1位:ひざ関節症クリニック
とくに培養幹細胞治療は、海外のプロスポーツ界も注目する最先端の治療法です。傷んだ組織の修復能力を高める治療効果は持続性が期待でき、ヒアルロン酸注射のように頻繁な通院を必要としない魅力もあります。
さらに
フリーコールによる窓口も開設しているので、「ストレッチで膝裏の痛みが改善しない」「ひざ関節に残る違和感を取り除きたい」とお悩みの方はぜひチェックしてみてください。
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
「膝裏を曲げたときの痛みが慢性化している」「手術はしたくないけど膝の痛みを改善したい」とお悩みの方は、気軽に無料相談から症状を伝えてみてください。
メジャーリーガーも採用するPRP治療や、軟骨再生効果のある幹細胞培養治療などの再生医療なら、低リスクかつ手術不要で痛みの根本解決が期待できます。
治療後には専門スタッフによるリハビリサポートを継続できるほか、土日の柔軟な診療体制も整えているため、膝裏の痛みを改善したい方はシン・整形外科(旧東京ひざクリニック)をチェックしてみましょう。
まとめ

膝裏を曲げると痛いときは、靭帯損傷や半月板損傷、関節リウマチ、鵞足炎などさまざまな症状が考えられます。いずれの症状も放置すると、歩行困難に陥って日常生活にも支障をきたす恐れがあるため、痛みや違和感があった時点で速やかに医療機関を受診することが望ましいでしょう。
膝の病気や怪我と一口にいっても、症状や原因は多くのことが挙げられます。まずはそれぞれの基礎知識をしっかりと理解したうえで、予防につなげることが重要です。
膝はさまざまな動作をサポートする大事な部位になります。膝に必要以上に負担を与えない対策を実践し、疾患や怪我を防いでいきましょう。
※本記事の情報は2022年12月時点のものです。
※本記事は公開、修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス、商品に関するお問い合わせは、サービス、商品元に直接お問い合わせください。