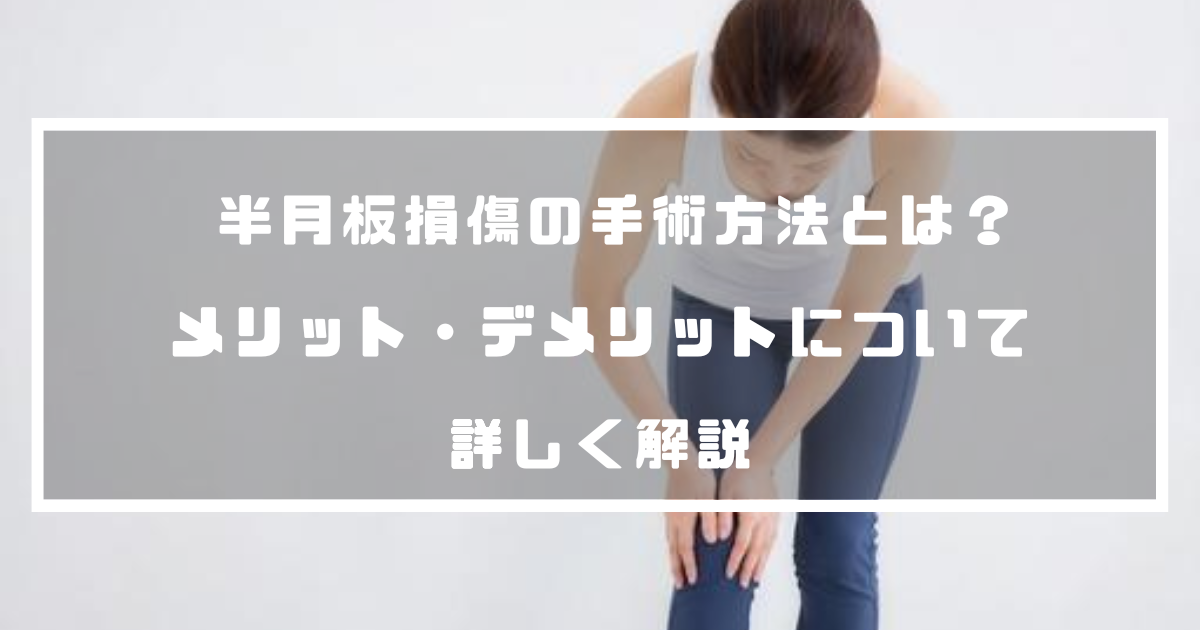膝の痛みが続いていたり、曲げ伸ばしがしにくかったりする場合、半月板を損傷している可能性があります。半月板はスポーツ時の怪我の他、中高年以上の場合は加齢により日常動作でも損傷する場合がある部位です。
半月板損傷の治療は、手術をおこなう場合もあればそうではない場合もあります。どのような治療がおこなわれるのか、手術方法を中心に詳しく解説します。
半月板損傷の症状

半月板は膝の関節の中にある軟骨です。大腿骨とすねの骨の間の内側と外側の両方に1つずつあります。半月板を損傷すると以下のような症状が現れます。
詳しく解説していきます。
膝の曲げ伸ばしの際に痛む
半月板を損傷すると、膝を曲げ伸ばしする際に痛みが出ます。痛みの他、膝の曲げ伸ばしの際に次のような症状があらわれます。
- パソコンのマウスをクリックしたような音やゴキッという音がする
- ゴリッとした感覚がある
- 完全に曲げ伸ばしができない
- 引っかかり感がある
半月板損傷により膝の曲げ伸ばしに引っかかりがある状態はキャッチングと呼ばれています。
膝に水がたまる
膝に水がたまることも半月板損傷の症状の一つです。水がたまると膝に次のような症状が出ます。
- 全体が腫れぼったくなる
- 重さやだるさを感じる
- 突っ張り感が出る
- 曲げ伸ばしがしにくくなる
水とは、関節液のことです。通常は1ml~3mlですが、たまった状態では30mlほどになります。また、関節内で出血した場合は血がたまることもあります。
急に膝が動かなくなる
曲げ伸ばしがしにくいのみでなく、急に膝が動かなくなることもあります。半月板損傷により急に膝が動かせなくなる症状はロッキングと呼ばれています。ロッキングには激痛がともなうことが多いです。
歩けなくなる
半月板の損傷の程度が著しいと、激痛のために歩行ができなくなることがあります。上述のロッキングが起きた場合も歩行が困難になります。
半月板損傷は悪化するとどうなる?
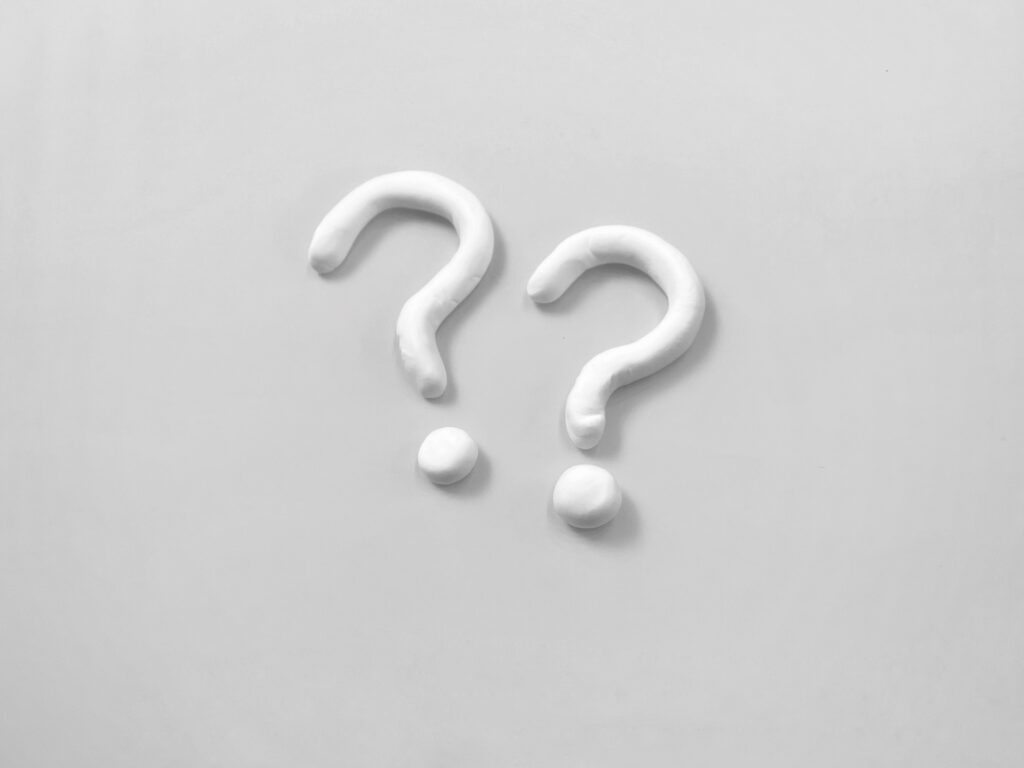
半月板損傷は基本的に自然治癒はしません。組織の修復には栄養素を運ぶ血液が必要であるところ、半月板の周辺は血行がない部分が2/3あるためです。
そのため、損傷した状態を放置していると悪化する可能性があります。
半月板の損傷が悪化するとどのような症状が出るかについて紹介します。
ロッキング現象
半月板損傷の程度がひどくなると、ロッキング現象と呼ばれる症状が現れます。ロッキング現象は膝がロックされたように動かなくなり、激痛をともないます。そのため、ロッキングになると歩行が困難になります。
ロッキングの原因は、損傷した半月板が関節の隙間に入り込むことです。
曲がる方向にゆっくりと慎重に曲げることを繰り返すと、次第に外れることがあります。また、自然に治る場合もあります。
しかし、自身で対処しようとすると余計に悪化する可能性があるため、ロッキングになったらクリニックの受診をおすすめします。痛みが激しい場合は救急車を呼んでください。また、力任せに伸ばそうとすると半月板や関節をさらに傷めるため、無理に伸ばすことは避けてください。
何度も水が溜まる
半月板を損傷すると膝に水が溜まることがあります。クリニックで水を抜くことで改善しますが、膝関節の炎症が続いていると再び水が溜まります。何度も水が溜まる場合は炎症を抑える治療が必要です。
なお、水を抜いた後にまた溜まる原因は水を抜くことで癖になるからであると誤解している方がいます。
しかし、水を抜くことで癖になることはありません。炎症が続いていることが原因です。膝に溜まる水である関節液には炎症を引き起こす成分のサイトカインが含まれています。
そのため、水が溜まったら放置せずにクリニックを受診して適切な処置を受けてください。
まずはMRIで適切な治療をチェック

半月板損傷が疑われる場合、MRI検査をおこないます。半月板はレントゲンやCTには映らないためです。また、靭帯損傷の有無、水の有無、炎症、出血などレントゲンでは得られない情報もMRIであれば得られます。
MRI検査をおこなえば80~90%は診断可能です。一方、断裂の大きさや損傷の部位によってはMRI検査のみでは診断できない場合もあります。その場合は特殊な撮影方法を使用したり、病歴から判断したりします。
治療方針を決めるためにもMRI検査は必要です。半月板損傷の治療法や手術方法は、損傷の部位や断裂の仕方によって異なるためです。
半月板損傷の3つの治療法

半月板損傷の治療法は以下の3種類です。
それぞれ詳しく解説します。
手術療法
半月板を損傷した場合におこなわれる主な治療の一つが手術です。次のような場合には手術が選択されます。
- 断裂部位が1cm以上
- ロッキングの症状がある
- 血流がない部位を損傷しており、自然治癒が見込めない
- スポーツによる損傷で、早期の復帰を希望している
- 保存療法で改善しなかった
手術に使用される器具は、内視鏡である関節鏡です。1cmほどの切開を2~3か所おこなうことで手術できます。傷跡が小さく済み、術後感染のリスクも低い治療法です。
入院期間は1日~2週間で、手術方法やクリニックによって異なります。手術当日に退院できる場合もあります。
手術後は再発を防ぐためにリハビリテーションが重要です。入院中におこなった後は2か月~半年ほど通院によりリハビリテーションをおこないます。
また、手術後は松葉杖を使用します。松葉杖を使用しなくても歩行はできますが、膝関節への負担を軽減して痛みや腫れを抑制するためには松葉杖が必要です。
保存療法
手術療法と並んでよくおこなわれる治療が保存療法です。外科的施術はおこなわず、次のような方法を組み合わせて治療します。
- 注射:ヒアルロン酸、麻酔剤、炎症を抑えるステロイド剤など
- 抗炎症薬、鎮痛剤の服用
- 装具治療:サポーターにより膝関節を安定させる、足底版(インソール)により体重の偏りを補正する
- 運動療法:膝周辺や太腿の筋トレをおこない、膝関節への負担を軽減する
保存療法が選択される場合は次のとおりです。
- 損傷の程度が軽微で痛みが少ない
- ロッキングの症状がない
- 血流がある部位を損傷しており、自然治癒の可能性がある
- 患者が手術を希望しない
- 損傷の原因が加齢
保存療法は1か月~3か月ほどおこないます。治療を継続しても改善が見られない場合は手術療法への切り替えが検討されます。
再生医療
再生医療とは、自身の細胞を培養して損傷した半月板の修復をおこなう治療法です。以前は手術療法と保存療法が主流でしたが、近年の再生医療の発達にともない半月板損傷の治療にも再生医療が取り入れられるようになりました。
体への負担が少なく、施術後は日帰りできます。また、手術のうち半月板を切除する方法が採られた場合は変形性膝関節症になりやすいデメリットがありますが、再生医療の場合はそのような心配がありません。
ただし再生医療は、最新の治療方法であるため施術をおこなうクリニックは多くありません。また、保険適用外であるため、全額自己負担です。
半月板損傷の手術方法

半月板損傷の手術方法は、以下の2種類です。
これらを組み合わせて手術がおこなわれる場合もあります。それぞれ詳しく解説します。
縫合術
損傷した半月板を縫い合わせる手術方法です。断裂部分が繋がれば元の半月板と同様の機能が期待できます。
損傷した部位が半月板の外側1/3である場合は縫合術が選択されます。半月板の外側1/3には血流があり、自然治癒が見込めるためです。また、半月板の断裂の仕方が縦方向である場合も縫合術が適応します。
縫合術の流れは次のとおりです。
①麻酔をおこなう
②膝関節に関節鏡(内視鏡)と手術のための機器を入れるため、0.5cm~1cmの切開を2~3か所おこなう
③関節鏡で半月板の損傷箇所を確認する
④関節鏡の画面を見ながら、断裂部位を手術機器で縫合する
⑤断裂部位によって0.5cm~1cmの切開では縫合ができない場合は、さらに2cm~3cmの切開をおこなう
断裂箇所が複数であったり縫合ができない箇所があったりする場合は、部分的に切除術を併用する場合があります。手術時間は30分~1時間半ほどです。麻酔は全身麻酔、下半身麻酔、局所麻酔のいずれが選択されるかはクリニックにより異なります。
入院期間は1~2日です。再断裂を防ぐために2週間程度松葉杖を使用します。また、ギプスや膝装具(ニーブレス)での固定もおこないます。ギプスや膝装具の装着期間は1週間~6週間です。
リハビリも再断裂を防ぐために重要です。術後すぐは筋力を高めるための運動から始めます。膝関節は動かさないようにしながら、太腿や体幹を鍛える運動をおこなうことが一般的です。縫合箇所に負担がかからないようにするため、膝に体重がかかったり、膝を曲げたりする運動はおこないません。
ギプスが外れたら、松葉杖を使用して体重をかける運動もおこないます。また、膝の可動域を広げるための運動も開始します。リハビリがどのように進むかは断裂の仕方や箇所によって異なるため、定期的な経過観察が必要です。
切除術
切除術は損傷した半月板を切り取る手術方法です。半月板損傷の手術の7割は切除術です。
損傷箇所が半月板の中央2/3である場合は切除術が選択されます。この部位には血流がなく、自然治癒が期待できないためです。
また、断裂の仕方が横方向であったり、半月板の内部で水平に断裂していたりする場合も切除術が選ばれます。
しかし、半月板を切除すると後に膝関節の軟骨が摩耗し、変形性膝関節症を引き起こす要因になることが分かってきました。
そのため、現在は血流がない部位の損傷や横断裂、水平断裂でも縫合術が選ばれます。
また、以前は半月板は全切除されていましたが、同様の原因から現在はできるかぎり半月板を温存する部分切除が主流です。
切除術の流れは次のとおりです。
①麻酔をおこなう
②膝関節に関節鏡(内視鏡)と手術のための機器を入れるため、0.5cm~1cmの切開を2~3か所おこなう
③関節鏡で半月板の損傷箇所を確認する
④関節鏡の画面を確認しながら、切除用のパンチで半月板の断裂箇所を切除する
⑤ささくれだった表面をシェーバーで整える
手術時間は15分~40分ほどです。麻酔は全身麻酔、下半身麻酔、局所麻酔のいずれが選択されるかはクリニックにより異なります。
入院は1日~3日で、部分切除の場合は当日の帰宅も可能です。術後は1日~2週間ほど松葉杖を使用します。ギプスやサポーターによる膝関節の固定はおこなわれません。
切除術の場合、上述のとおり軟骨の摩耗が起こる可能性があります。
そのため、膝関節への負担を軽減するために、術後のリハビリが縫合術同様に大切です。体重をかけることや膝の曲げ伸ばしは、術後すぐでも制限されません。
リハビリでは、術後すぐから膝の可動域を改善するための運動を、痛みを感じない範囲でおこないます。
また、太腿や膝周囲の筋力を高めるための運動もあわせておこないます。

半月板損傷の手術のメリット

半月板損傷の手術のメリットは以下の通りです。
縫合術と切除術それぞれ詳しく解説します。
縫合術
以前は半月板損傷の手術は切除術が主流でした。しかし、近年は縫合術が選択されることが多くなります。ここからは、縫合術のメリットを解説します。
半月板の温存が可能
縫合術のメリットは半月板を温存できることです。縫い合わせた半月板が癒合すれば、元通りの機能が期待できます。
また、半月板が温存されることで膝関節の軟骨の摩耗を防げます。半月板は膝関節にかかる衝撃を吸収する役割があるためです。そのため、将来の変形性膝関節症のリスクの低減ができます。
スポーツのパフォーマンスの維持
縫合した半月板が癒合すれば、半月板は損傷前の機能が回復します。そのため、スポーツのパフォーマンスを維持できます。
切除術
現在おこなわれている半月板損傷の手術のうち約7割は切除術です。切除術のメリットを解説します。
軟骨の損傷を防ぐことが可能
半月板の切除術をおこなう際には、損傷部分を切除するとともにささくれだった箇所を滑らかに整えます。そのため、損傷した半月板が膝関節の軟骨と摩擦を起こさないようにでき、膝関節の軟骨の損傷を防止できます。
回復が早い
切除術は縫合術に比べて回復が早いことが特徴です。縫合術は縫合した半月板の癒合を待つ必要があるのに対し、切除術では問題を起こした箇所を取り除くためです。
切除術では術後すぐから歩行ができます。また、術後約1週間で日常生活に支障がないほどに回復します。スポーツ復帰は早ければ3週間で可能です。
半月板損傷の手術の注意点

半月板損傷の手術はメリットばかりではありません。
デメリットや注意点について、縫合術と切除術に分けて詳しく解説します。
縫合術
近年切除術に代わって増加している縫合術ですが、リスクやデメリットもあります。主なリスクとデメリットは次のとおりです。
痛みが取れない可能性
縫合術を施術しても痛みが取れるとは限りません。手術前よりも痛くなることもあります。また、再断裂するリスクもあります。
術後2週間は足を床につけてはいけない
縫合術をおこなった後2週間は足を床につけてはならず、松葉杖を使用します。半月板の再断裂を防ぐため膝に体重がかからないようにしなければならないためです。
一方、切除術の場合は術後すぐから体重をかけることが可能で、歩行ができます。
また、膝の曲げ伸ばしも2週間はできません。膝関節の可動域を改善するためのリハビリも3週目は90°まで、4週目は120°までと、少しずつおこなわれます。
さらに、しゃがみ込む動作やジョギングは術後1か月半~2か月禁止されます。半月板が癒合するまで待つ必要があるためです。
スポーツ復帰は術後3か月以降
スポーツ復帰は最短で3か月です。長ければ半年かかることもあります。
半月板を温存できるため、癒合すれば損傷前と同じパフォーマンスを維持できますが、復帰時期が遅くなることが縫合術のデメリットです。
切除術
半月板損傷の手術の7割を締める切除術には主に次のようなデメリットがあります。
血栓が形成されやすい
切除術の後は血栓が形成されやすい傾向があります。そのため、肺血栓塞栓症や深部静脈血栓症などの血栓症のリスクがあります。血栓症は半月板の切除術の術後のみではなく、他の脚の手術や骨折時にも起きやすい病気です。
血栓症を防ぐため、手術をした方の脚には血栓予防の靴下や弾性ストッキングを着用します。また、早期から歩行やリハビリを積極的におこなうことも血栓症の予防に繋がります。
関節軟骨が変形する可能性
切除術では半月板の損傷した箇所を取り除きます。半月板は膝関節にかかる衝撃を吸収するはたらきがあるため、半月板が切除されることにより膝関節の軟骨が摩耗し、変形するリスクがあります。
変形性膝関節症になりやすい
切除術のもっとも大きなデメリットが変形性膝関節症のリスクが高まることです。変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨の摩耗により歩行時に痛みが出る病気です。
進行して軟骨のみでなく骨まで損傷した場合は、人工関節に置き換える手術をおこないます。半月板を切除すると、変形性膝関節症を発症する可能性が高くなります。
そのため、切除術は全切除から部分切除が選ばれる傾向にあります。また、できるかぎり縫合術を施術するように、現在は半月板の温存が重視されています。
しびれが発生する可能性
手術後にしびれや腫れ、痛みが出る場合があります。しかし一時的なもので、多くの場合は数日~数週間で軽快します。
まとめ
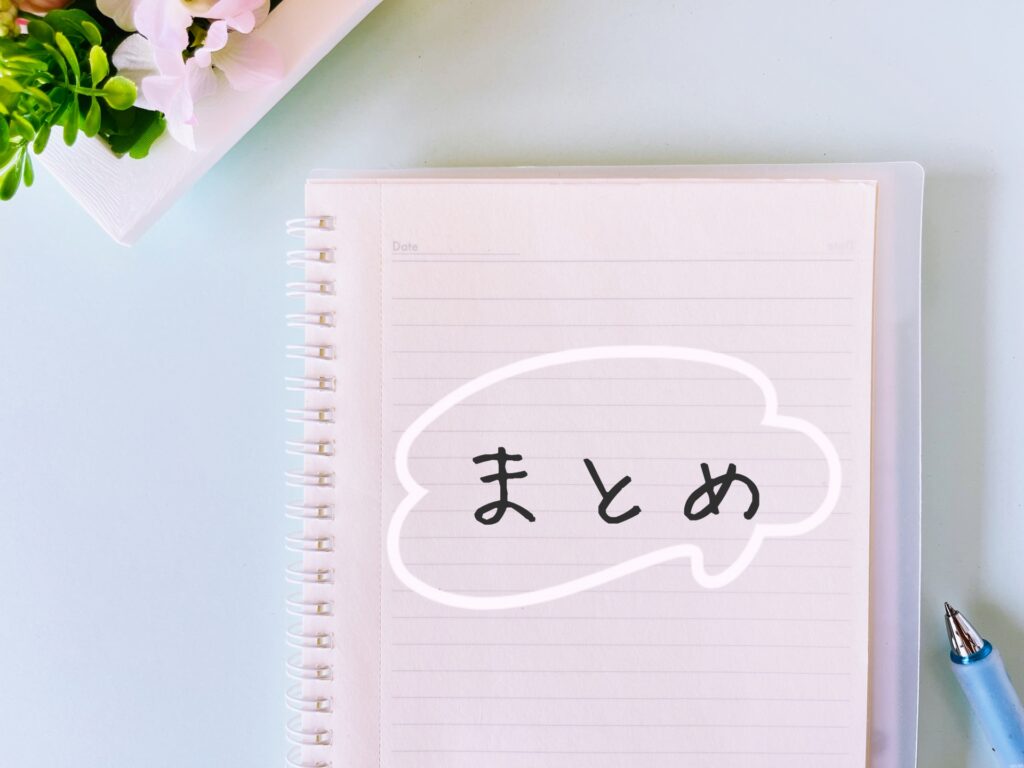
半月板の治療は、現在はできるかぎり温存する方針が採られています。そのため、手術は可能なかぎり切除術ではなく縫合術が推奨されます。また、手術ではなく保存療法が選ばれる傾向にあります。
半月板は自然治癒しにくい部位であるため、医師の診断のもと適切な治療が必要です。膝の痛みや曲げ伸ばしのしにくさがある場合は、早くクリニックを受診するようにしてみてください。

※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。