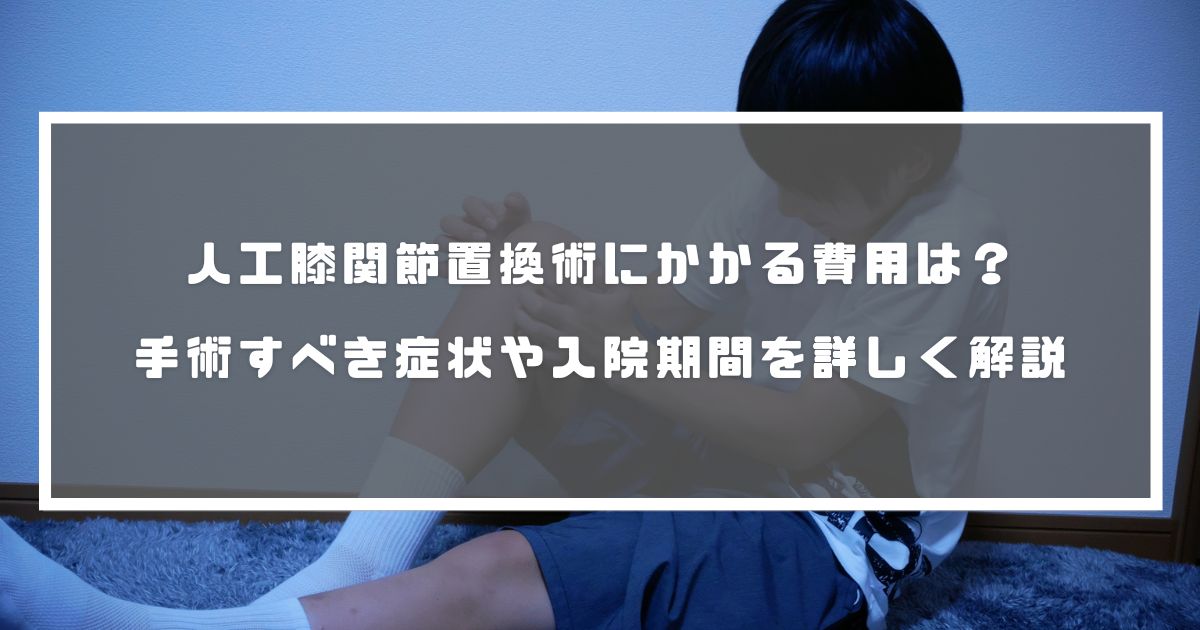変形性膝関節症の後期症状に用いられる代表的な手術として、人工膝関節置換術と呼ばれる方法があります。
変形性膝関節症は、40歳以上の方に多く見られる症状として知られており、ホルモンバランスの乱れからとくに女性に多い症状です。
膝関節の軟骨がすり減ることで痛みが生じ、後期症状になると人工膝関節置換術を用いて関節を置き換えなければなりません。
本記事では、人工膝関節置換術にかかる費用を解説するとともに、人工膝関節置換術の種類や手術に至る症状について解説します。
膝の痛みがある方におすすめの内容であるため、ぜひ参考にしてみてください。
人工関節置換術とは

人工関節置換術とは、傷んだ軟骨や関節を取り除いて金属やセラミック、ポリエチレンで形成された人工関節を入れて痛みを取り除く手術です。
関節が原因となる大抵の痛みを改善できる方法のため、変形性膝関節症や関節リウマチなどに多く用いられます。
人工膝関節置換術の費用の前に、人工関節置換術の流れや耐用年数など、人工関節置換術の詳細を確認しましょう。
関節部分を切り取る
人工関節に置き換えるためには、傷んだ関節や軟骨を取り除く必要があるため、切除します。
変形性膝関節症の場合は、太ももの骨である大腿骨や脛の骨である脛骨などの膝にかかわる関節や骨を切除し、人工関節に合わせて骨を薄く削る方法が主流です。
切り取ったり削ったりするため恐怖や不安が募りますが、全身麻酔して意識がない状態で手術するため、安心して医師に身を任せられます。
人工関節に置き換える
関節を切除したあとに、人工関節に置き換えて固定すれば手術完了です。
固定方法は、物質名がポリメチルメサクリレート、通称骨セメントと呼ばれる樹脂での固定が原則とされています。
骨セメントは、歯科材料としてこれまで利用されてきたものを人工関節に応用したもので、40年以上前から利用されている実例がある素材です。
固定方法の中には、骨セメントを利用しない固定方法や、骨セメントを併用するハイブリッド固定方法などもあります。
人工関節の素材と造りについて
人工関節の素材は、コバルトクロム合金やチタン合金などの金属やセラミック、ポリエチレンから作られています。
人工膝関節の場合は、4つの部品から形成されており、大腿骨部品、脛骨部品、脛骨関節面部品、膝蓋骨部品です。
大腿骨部品がコバルトクロム合金、脛骨部品がチタン合金、脛骨関節面部品と膝蓋骨部品がポリエチレンで形成されており、それぞれの部品の役割に支障が出ないかつ耐用年数が長くなるように配慮されています。
金属アレルギーの方には、金属の代わりにセラミックとポリエチレンにて形成した人工関節に置き換えるため、手術前に医師に申し出ましょう。
前述した固定方法も、骨セメント以外にネジで固定する場合や歯や骨を形成する成分を素材にしたものを利用し、いずれは自身の骨と結合するものなど、人工関節に置き換える部位によって変わります。
耐用年数は約25年
人工関節の耐用年数は、これまで10~15年とされていましたが、現在は医療技術の進歩もあり、約25年とされています。
人工関節は交換できるため、必要に応じて交換しますが、手術を繰り返すことは体に大きな負担がかかることから、これまで65歳以上の方に推奨される手術でした。
しかし、現在は耐用年数が伸びたことで40~50代の方にも適用できる手術として、人工関節置換術が確立しています。
そのため、若い方でも一度人工関節にすれば、生涯そのまま過ごせるようになりました。
人工膝関節置換術にかかる費用の目安

人工膝関節置換術にかかる費用は、検査や手術の費用はもちろんですが、入院や薬にかかわる費用も加算されます。
総額は100万円単位で高額になりますが、医療保険や高額療養費制度などで100万円未満に済ませられると認識しておきましょう。
ここでは、人工膝関節置換術にかかる費用の目安と自己負担額、利用できる制度や適用される保険について解説します。
人工関節置換術の費用相場
人工関節置換術における費用相場は、200~250万円とされており、人工膝関節でも人工股関節でも大きく変わることはありません。
人工膝関節置換術の費用は、診療報酬と呼ばれる厚生労働大臣が定めた料金が適用されるため、どの医療機関でも同じ料金です。
費用がかかる項目の詳細は、検査料、手術料、麻酔料、入院中の食事、薬などに分けられ、個室利用の有無や入院期間によって異なります。
簡単に払える料金ではありませんが、人工関節置換術は公的医療保険が適用されるため、安心してください。
公的医療保険が適用
公的医療保険が適用されるため、人工膝関節置換術の自己負担額は大幅に下がります。
注意しなければならない点は、入院中の食事やベッド代は医療保険の適用ができないため、入院期間が長引くと、その分負担額が増えると認識しておきましょう。
医療保険の適用のみでは払いきれない方のために、高額療養費制度や限度額適用認定制度についても詳しく解説します。
自己負担額は約60~80万円
医療保険にて、人工膝関節置換術の自己負担額は3割負担で約60~80万円とされていますが、年齢や医療保険によって異なるため、自己負担額を確認しておきましょう。
医療保険を適用させても上記の金額となるため、高額医療であるといえますが、高額療養費制度や限度額適用認定制度なども適用されるため、実際に支払う費用はさらに少なくなります。
しかし、年齢によって自己負担額が変わる点や事前に申請が必要な点などの条件があるため、注意が必要です。
人工膝関節置換術を受ける前から入念に準備をおこない、実際に支払う費用を少なく済ませるようにしましょう。
知らないと高額な医療費を支払うことになるため、保険や制度を利用できるようにここで認識しておいてください。
高額療養費制度が適用される
高額療養費制度とは、1か月の自己負担限度額を超えた金額を保険団体が払い戻しされる制度です。
注意点として、高額療養費制度は払い戻しのため、一時的に窓口で医療費を支払う点や払い戻しまで3か月程度かかる点があります。
自己負担額は前述した医療保険の適用で約60~80万円となりますが、高額療養費制度を適用させると大半の金額が戻ってくるため、実質負担額は10万円程度です。
自己負担限度額は、年齢や世帯年収によって異なるほか、2017年から度々見直されているため、自身に適用される高額療養費制度を確認しておきましょう。
自己負担限度額は、日本年金機構が定める標準報酬月額で定められており、標準報酬月額が27万円未満かつ70歳未満の方を例に挙げると、自己限度額は5万7,600円となります。
支払った費用の大半が戻ってくるため、人工膝関節置換術の際は、高額療養費制度を利用しましょう。
限度額適用認定制度の利用
高額療養費制度では、一時的に医療費を自己負担しなければならないため、経済的に余裕がない方は、払い戻しされるまでは厳しい生活を余儀なくされる場合もあります。
限度額適用認定制は、あとから払い戻しとなる制度ではなく、予め申請した認定証を病院に提出すると自己負担限度額までの支払いで済む制度です。
適用させるためには、限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出し、限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。
限度額適用認定証は発行されるまで1週間程度かかるほか、交付される前の月にかかった費用には適用されないため、事前に準備しなければなりません。
しかし、準備しておけば自己負担限度額以上の費用がかからないため、人工膝関節置換術を受ける際は利用することをおすすめします。
ただし、これまで解説した制度は、食事代をはじめとした保険適用外のものは別途費用がかかることを認識しておきましょう。
人工関節置換術の種類

人工関節置換術は、関節の全置換と部分置換に大きく分けられているほか、手術する部位によっても異なるため、確認しておきましょう。
ここでは、人工膝関節置換術にて大別されている2つの種類について解説し、人工膝関節置換術の前に検討すべき再生医療について解説します。
人工膝関節全置換術
人工膝関節全置換術は、膝関節軟骨や骨が大きくすり減っている方やO脚、X脚と呼ばれる直立ができない方に適用される手術です。
ほかにも、靭帯が切れた方や反張膝と呼ばれる膝が大きく後方に反っている方も改善できる手術方法で、痛みや形の改善を目的としています。
膝の状態が悪くなる大抵の病状に対して有効な手術とされており、多くの方に適用可能です。
前述した耐用年数も全置換術によるものであることや、人工膝関節置換術の約90%が全置換術となります。
人工膝関節部分置換術
全置換術と異なり、膝関節の一部を置換する人工膝関節部分置換術は、適用する場合にさまざまな条件があります。
変形性膝関節症でたとえると、関節軟骨のすり減りが内側もしくは外側のみである場合かつ、膝靭帯が健常であり、著しい変形が見られない場合にのみ適用される方法です。
切開範囲が狭いことや部分置換のため手術後の回復が早く、リハビリ期間が短く済むなどのメリットがあります。
しかし、部分的に体重を支えることになるため、耐用年数が全置換術よりも短いことや手術しなかった側が悪化した際に、追加手術しなければならないことなどがデメリットです。
さらに、部分置換術を適用するケースが少ないことから、医師の経験の有無もかかわってくるため、手術できる病院が限られてきます。
体への負担は少ないため、部分置換術を希望される方もいますが、反対側の悪化も視野に入れると、全置換術の適用が望ましいといえるでしょう。
手術の前に膝関節再生医療も検討
人工膝関節置換術を受ける前に、膝関節の再生医療も検討してみましょう。
再生医療は、とくに変形性膝関節症に対する新しい治療法として注目を集めており、手術や入院が不要な最先端の医療技術です。
自身の血液から抽出した細胞組織の再生を促す成分や成長因子を注入する方法が、臨床研究にて、安全性及び治療効果のある方法として確認されています。
しかし、再生医療を取り扱う病院は多くないほか、再生医療等提供計画や特定細胞加工物製造届を厚生労働省から許可されていなければ取り扱えない治療法のため、病院を探さなければなりません。
人工膝関節置換術をすべき症状

ここからは、人工膝関節置換術をすべき症状について解説します。冒頭で変形性膝関節症の後期症状の方に有効であると解説しましたが、ほかの症状も確認しましょう。
自身が当てはまる症状がある場合は、医師に相談してみてください。
膝関節や股関節の痛みが強い
膝関節や股関節の痛みが強い方は、人工膝関節置換術を検討しましょう。
股関節の場合は、人工股関節置換術になる可能性もありますが、両方痛い場合やほかの関節も痛い場合は、関節リウマチの可能性もあります。
関節リウマチは本来、自身を守るための細胞が異常になり、自身を攻撃する病気です。早めの治療が必要なため、すぐに病院を受診しましょう。
早期発見であれば、薬物療法で改善できる可能性が高いため、人工関節に置き換えなくても済む場合があります。
痛みで日常生活に支障が出ている
膝の痛みで日常生活に支障が出ている方は、人工膝関節置換術を検討する必要があります。
日常生活に支障が出るほどの痛みは、変形性膝関節症の中~後期症状に当てはまるため、早急な治療が必要です。
また、痛みのみで判断できない場合は、直立して膝が真っすぐ伸びているのかを確認してみてください。
O脚と呼ばれる膝が外側に向いてしまう症状や、X脚と呼ばれる膝が内側に向いてしまう症状が見られる場合は、人工膝関節置換術を受ける必要があります。
置換術以外の方法で改善できない
すでに通院している中で、リハビリやヒアルロン酸注射などの治療をおこなっていても改善できない場合は、人工膝関節置換術を検討しましょう。
ほかの方法で改善できないと医師が判断した場合は、素直に聞くことが大切です。手術や入院を考えると不安が募りますが、人工膝関節置換術はこれまで多くの実績がある治療法のため、安心してください。
不安な方は手術する医師の経験について聞いてみることがおすすめです。
変形性膝関節症が進行している
変形性膝関節症の後期症状の方は、人工膝関節置換術によって辛い痛みが改善されるため、手術を受けましょう。
変形性膝関節症は、後期症状になると歩くことすらままならない状況になります。痛みに耐えながら車椅子の生活を余儀なくされることになるため、人工膝関節置換術を受けてみてください。
手術後のリハビリに努めれば軽い運動もできる程度に改善するため、これまでは膝の痛みの影響でできなかった運動をはじめられます。
人工膝関節置換術の流れ

実際に人工膝関節置換術を受ける流れは、病院にて検査をおこない、入院してから手術します。
手術後は、リハビリ期間が設けられるため、松葉杖を利用して歩けるようになるまで入院生活となることから、準備が必要です。
人工膝関節置換術を受ける前に、どのような流れになるのかを確認しておきましょう。
1:病院を受診
まずは病院を受診して、医師による診療やレントゲン、MRIによる検査を受けて膝の具合を確認しましょう。
人工膝関節置換術が必要と判断された場合は、入院するための手続きや準備が必要です。さらに、手術にかかる費用の問題があるため、限度額適用認定制度の利用をはじめとした手続きも忘れないようにしてください。
本記事で解説した高額療養費制度や限度額適用認定制度以外に、高額医療費貸付制度もあるため、高額療養費制度を利用する際は、一時的な費用の負担を減らすために検討してみましょう。
2:入院
さまざまな手続きを終えたら、手術に向けて入院となりますが、大抵の場合は手術前日に入院します。
入院してからは、ベッド代や食事代などの費用が発生するため、入院前にできる限りの手続きを済ませておくことがおすすめです。
慣れない環境のため、体調を崩したり眠れなかったりする場合もあります。体調が優れない場合はすぐに看護師や医師に伝え、手術は万全の状態で受けるようにしましょう。
3:手術
注射や点滴などの準備を終えたら手術室へ移動し、手術がはじまります。人工膝関節置換術の手術は、基本的に全身麻酔でおこなわれるため、手術中は意識がない状態です。
麻酔の効果がなくなり目が覚めたら、血圧や体温を測って体調を確認するほか、膝の動作を確認します。
手術後に痛みや内出血が伴う場合もあるため、手術当日は安静にして過ごしましょう。痛み止めや血栓を防ぐために血流をよくする薬を投与されるため、医師や看護師の指示に従って過ごすことが大切です。
4:リハビリ
病院によってさまざまですが、早いところは手術翌日からリハビリがはじまります。
足を動かさなければ血が溜まり、深部静脈血栓症を引き起こす可能性があるため、なるべく早い段階から動かすことが必要です。
しかし、補助があってもいきなり歩けるわけではないため、まずはベッドに横たわったまま膝を曲げたり伸ばしたりする簡易的な運動になります。
人工膝関節置換術のリハビリ期間は、2週間~1か月前後とされているため、退院に向けて徐々に動かせるように努めてください。
5:退院
歩くことやトイレ、入浴など身の回りのことが1人でできるようになり、医師から退院できると判断されれば、退院できます。
しかし、今後も通院や自主的なリハビリが必要なため、怠らないようにしましょう。退院後は日常生活を送るうえで、人工関節に注意しながら過ごすようにしてください。
完全に回復したあとは適度な運動を心がけ、体重の増加に注意しながら過ごすことがおすすめです。
経過観察のために、定期的に通院するとより快適な生活が送れるほか、不安な点や異変があった際も早急に対応できます。
人工膝関節置換術の入院とリハビリ期間

人工膝関節置換術の入院とリハビリ期間は、個人差がありますが、多くの方が1か月前後といわれています。
限度額適用認定制度や高額療養費制度は一月に対する制度のため、月が変わる場合は再度手続きが必要な点も注意しましょう。
多くの患者は約30日間入院
人工膝関節置換術を受けた多くの患者は約30日間の入院とされているため、1か月の入院生活になると認識しましょう。
基本的に抜糸の目安が2週間とされているため、抜糸までに問題ないと判断されれば抜糸直後に退院も可能です。
早ければ2週間で退院できますが、基本的に30日を目安に考えて入院の準備をしてください。
リハビリは約4週間
手術後のリハビリは約4週間と認識してください。病院によって2~3週間としているところもありますが、早期退院を目指して焦ると怪我につながるため、4週間程度見積もっておきましょう。
入院期間は、基本的に手術前日から数え、リハビリ期間は手術翌日から数えると、正確な日数が算出しやすいため、ぜひ参考にしてみてください。
大きな病院で手術した場合、リハビリ期間が長引くとリハビリ専用の病棟へ移動する場合もあります。
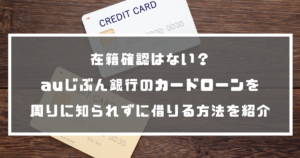
人工膝関節置換術を受けたあとの注意点

人工膝関節置換術を受けたあとは、日常生活を送るうえでさまざまな注意点があります。
膝に大きな負荷がかかるため、重い荷物を持たないようにしたり、ライフスタイルそのものを洋式にしたりして、膝の負担に配慮しながら生活しましょう。
上記以外にも注意点があるため、それぞれ詳しく解説します。
ライフスタイルを洋式にする
人工膝関節置換術を受けたあとは、ライフスタイルを洋式にして過ごすようにしましょう。洋式の生活とは、床に座らず椅子を利用したり、布団ではなくベッドを利用したりする生活です。
高低差があればあるほど、膝を極端に曲げたり伸ばしたりする動作が増えるため、和式の生活は膝に大きな負荷がかかります。
しかし、いきなり家具をすべて揃えることは難しいため、徐々に洋式に移行するようにしてみてください。
和式の生活の場合は、正座やしゃがむ動作をはじめとした、膝を極端に曲げる態勢や、床の拭き掃除のような膝を立てて体重を支える動作を避けましょう。
なるべく膝に負担のない生活を心がけることが大切です。
重い荷物は持たない
膝は、歩くのみでも体重の3~4倍、走ると7倍の負荷がかかるといわれている部位のため、人工膝関節置換術を受けたあとは、重い荷物を持たないようにしましょう。
腕の力で持つため、膝とは関係ないように考えられますが、実際は膝に大きな負荷がかかります。重い荷物を持つ際は、家族や友人の手を借りることがおすすめです。
しかし、頼れる方が近くにいない場合も考慮して、荷物を簡単に運べるカートを用意したり、重い荷物がある場合はタクシーを利用したりするなど、工夫しながら過ごしましょう。
持てる荷物の目安として、10kg以下のものまでと認識してください。
膝を固定する
人工関節は耐用年数が約25年と前述しましたが、激しい運動やライフスタイルによってゆるんだり、すり減ったりするため、膝の固定を意識して生活しましょう。
しかし、まったく動かさないことはできないかつ、健康にもよくありません。ウォーキングのような軽い運動は積極的におこなってください。
ジャンプや走ることを要するテニスやバスケットボールなどの激しい運動は避けることが、人工関節を長持ちさせることにつながります。
ウォーキングも、毎日1万歩以上歩くような過度なものではなく、近所を少し周る程度の軽いものに留めて、膝に配慮しながらおこなうことがおすすめです。
膝を温める
健康にもよいとされる血行促進は、人工膝関節置換術を受けたあとも効果的です。
温めることはよいことですが、こたつをはじめとした近赤外線やマイクロ波などの波長の短い放射線は金属を温める作用があります。
人工関節が熱を持つと、内部でも火傷する可能性があるため、注意が必要です。温める際は、毛布やひざ掛けなどで温めるようにしましょう。
【ランキング】膝を手術せずに治療したいときにおすすめのひざ専門クリニック
ここまで人工膝関節置換術について詳しく説明してきましたが、膝を手術せずに治療する方法もあります。ここでは膝を手術せずに治療したいときにおすすめのひざ専門クリニックをご紹介します。
1位:ひざ関節症クリニック
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
人工膝関節置換術の費用や治療に関するよくある質問

最後に、人工膝関節置換術の費用や治療に関するよくある質問にまとめて回答します。
手術後の運動の可否や手術後に障害者認定を受けるのかについてなど、気になる質問が多くあるため、確認しましょう。
本記事内で解説した内容も含まれていますが、正確に認識するためにもぜひ、最後まで読んでみてください。
手術後は運動してもよい?
人工膝関節置換術を受けたあとの運動は、ウォーキングや水泳などであれば問題ありません。
ジョギングやスキーなど膝に大きな負荷がかかる運動は、人工関節に支障が出る可能性があるため、避ける必要があります。
軽い運動でも膝をねじったり体重がかかったりする運動は避けるようにし、なるべく膝に負荷のかからない内容で運動しましょう。
人工膝関節置換術を受けたら障害者として扱われる?
人工膝関節置換術を受けたあとは、関節の可動域によって認定される場合があります。
2014年4月から身体障害者手帳の認定基準が変わり、人工関節に置き換えた際は、手術後の関節可動域によって、4級、5級、7級、非該当に分けられるため、応じて申請してください。
申請には、医師による診断書や意見書が必要となるため、医師と相談しましょう。
窓口で支払った医療費は返ってくる?
本記事で解説した高額療養費制度を利用した場合は、費用に対して定められた割合の払い戻しがあります。
ほかに戻ってくる可能性として挙げると、確定申告した際の医療費控除がありますが、費用の負担を確実に減らすには限度額適用認定制度の利用がおすすめです。
ただし、限度額適用認定制度は認定証を提出した月の医療費が対象となるため、すでに費用を支払っている場合は高額療養費制度を利用しましょう。
人工膝関節置換術ができる施設数は地方にもある?
在籍している医師の経験や病院の実績によって異なりますが、人工膝関節置換術は全国の医療施設でおこなわれています。
しかし、部分置換術はこれまで症例が少ないため、医師が未経験のことも多いため、大抵の場合が全置換術になると認識しておきましょう。
人工膝関節置換術が必要な関節の痛みとは?
日常生活に支障が出るほどの痛みや、歩くことが困難な場合などの痛みは人工膝関節置換術が必要といえるでしょう。
しかし、軽く痛む程度の場合でも、放置すると悪化する一方であることから、膝に痛みを感じる方は、一度病院を受診してください。
人工膝関節置換術の時間はどれくらい?
病院や医師の腕によって異なりますが、片足で1~1時間半程度とされています。両足の場合は2~2時間程度が手術時間となりますが、基本的に全身麻酔でおこなうため、意識のない間の手術です。
手術自体は早く済む方が体への負担も少なく済みますが、今後の人生を左右する手術のため、失敗のないよう正確な処置が最優先されます。
全身麻酔が必要?
人工膝関節置換術は基本的に全身麻酔ですが、必要ではありません。年齢や体力に合わせて麻酔の方法も異なるほか、病院によって腰椎麻酔で済ませる場合もあります。
患者の希望を加味した医師の判断でおこなわれるため、全身麻酔をしたくない方は医師に伝えてみましょう。
まとめ

今回は、人工膝関節置換術の解説をはじめ、かかる費用や利用できる制度について解説しました。
人工膝関節置換術は、これまで多くの実績があり、豊富な経験を持つ医師が全国各地に在籍していることから、安心して受けられる手術です。
しかし、できる限り手術ではなく、薬物療法や再生医療にて治療できることが望ましいことには変わりません。
膝に痛みがある方は、手術しなければならない症状になる前に一度病院を受診して、治療に努めることが大切です。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。