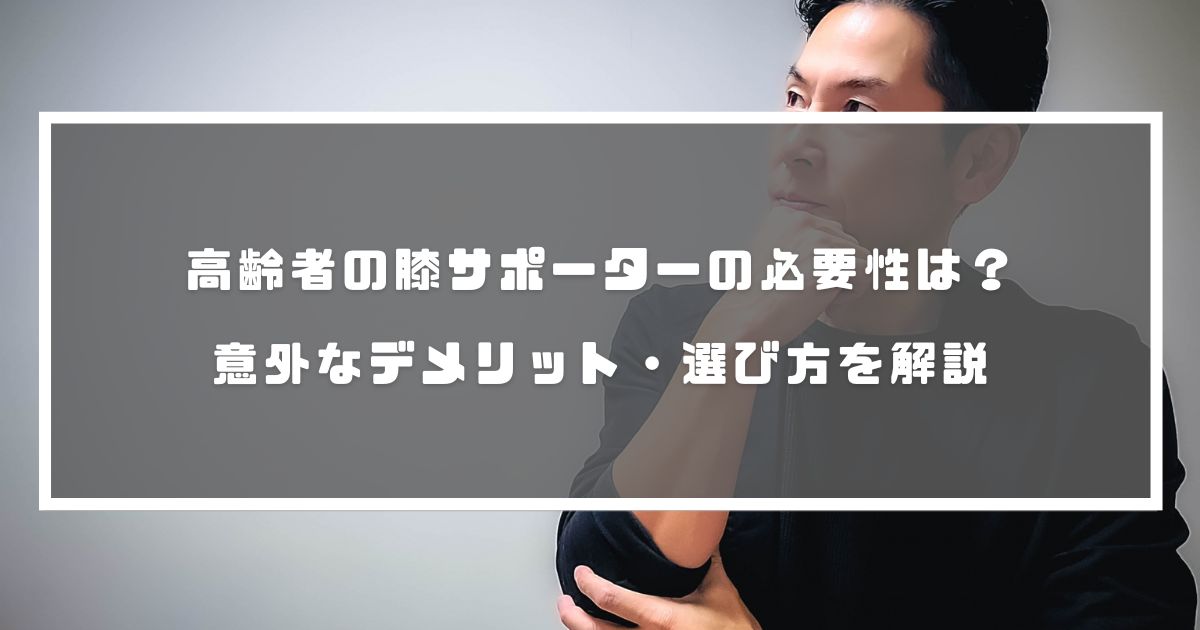膝の安定感を保つため、痛みを軽減させるために膝サポーターは効果的と思われています。しかし、使い方を間違えると症状の悪化を引き起こします。
膝には、神経や軟骨、筋肉など下半身を動かすために必要なものが密集しているからこそ膝サポーターに関する正しい知識が大切です。
この記事では、膝の痛みや違和感を抱えている高齢者に向けて、膝サポーターの必要性、デメリットや正しい選び方について解説します。自身の症状と比較して、本当に膝サポーターが必要なのか、具体的にどのような症状を抱えている方が膝サポーターを使うべきなのかについても言及しています。
なぜ高齢者に膝サポーターが必要?

高齢者に膝サポーターが必要といわれている理由は、次の5つです。
- 過度な動作の抑制
- 衝撃の吸収・軽減
- 関節の動作を助ける
- 膝の痛みの緩和
- 保温の効果
それぞれの理由について解説します。
過度な動作の抑制
膝サポーターは、過度な運動の抑制に有効です。膝関節が無防備な状態になると、動作の衝動によって不適切な方向に膝関節が曲がって、炎症や変形の原因を引き起こします。
膝サポーターは、固定する役割を持っているため、激しい膝の曲げ伸ばしはできません。歩きにくさや動かしにくさを感じるかもしれませんが、膝サポーターは、膝関節の症状を悪化させる原因を防ぎます。
衝撃の吸収・軽減
膝サポーターは、衝撃の吸収、軽減に有効です。ジャンプや下の階段を降りるときなど、強い衝撃が膝関節に加わる動作は、日常生活のうえで欠かせません。
高齢者になると、激しい運動をしていなくても、日常生活レベルの衝撃が蓄積され、膝関節が変形したり、炎症を起こしたりするケースは非常に多いです。
硝子軟骨と呼ばれる関節を覆う部位は、80%が水分で構成されており、骨同士の衝撃を吸収、軽減するためのクッションの役割を果たしています。
年齢を重ねて高齢者になると、硝子軟骨の機能が劣化して、直接衝撃が膝関節に加わりやすくなります。膝サポーターをつけると、本来硝子軟骨がおこなう役割を補助するため、膝の負担の抑制に効果的です。
関節の動作を助ける
膝サポーターは、関節の動作を助けるために有効です。もともと、膝関節は、脊椎、股関節、足関節などとは異なり、4つの骨と4つの靭帯で構成されている部位のため、他の関節と比較すると不安定になりやすいです。
膝関節の周辺にある筋肉は、不安定な膝関節を支えるために重要な役割を果たしていますが、年齢を重ねるごとに筋肉量は低下していきます。
膝関節周辺の筋肉量が低下すると、不安定な状態にある膝関節を支える役割を果たせなくなるため、筋肉の代わりに膝サポーターを使って安定感を保ちます。
血管の通っている骨であれば、損傷しても治療できますが、血管の通っていない軟骨は、一度損傷すると二度と元に戻せません。
関節には、膝を動かすために機能している軟骨があるため、筋肉の代わりに膝サポーターを使って膝を固定すると、関節動作の補助につながります。実際に、膝サポーターを着用して、歩きやすくなったり、上り下りしやすくなったりしたら、効果があったといえるでしょう。
膝の痛みの緩和
膝サポーターは、膝の痛みの緩和に有効です。皮膚に何かが触れたり、圧迫のような感覚が加わると、触圧覚(しょくあつかく)と呼ばれる感覚が刺激されます。
触圧覚は、痛覚よりも早く脳に到達するといわれているため、膝関節に痛みが出ている場合、膝サポーターで触圧覚を刺激すると、痛覚の反応が遅れるのが一般的です。
痛覚よりも先に触圧覚が脳に到達すれば、痛みを感じにくくなると期待できます。ただし、症状が進んでいると効果が実感できなかったり、圧迫する強さによっては鬱血を起こしてしまったりするため、適度な強さを選びましょう。
保温の効果
膝サポーターは、保温の効果に有効です。高齢者の多くが変形性膝関節症を発症して、膝関節の痛みや違和感を訴えますが、変形性膝関節症の場合、膝関節周辺の保温が重要です。
膝周辺が冷えていると、血流の流れが滞り、栄養素や酸素の巡りが悪くなるため、痛みを引き起こすからです。
骨折、靭帯損傷など膝関節に関わる怪我の場合、応急処置として冷却しますが、変形性膝関節症のような病気の場合、応急処置や保存治療として保温すると覚えておきましょう。
膝サポーターの種類によっては、吸湿発熱素材で作られているものもあるため、膝の痛みに悩んでいる方は、膝を温められるサポーターを探してください。
膝サポーターは高齢者用の購入がおすすめ!

膝サポーターは、スポーツをする方が着用するイメージが先行していますが、膝関節に痛みや違和感を抱いている高齢者にもおすすめです。
膝を保温するための吸湿発熱素材で作られた膝サポーターがあるとお伝えしたように、膝サポーターには複数の種類があります。利用用途によって異なる機能、使用感となるため、「高齢者用」に開発された膝サポーターの購入を推奨しています。
また、自身に最適な圧迫度、サイズを選ぶため医療機関を受診して、医療用の膝サポーターを購入する方法もおすすめです。
高齢者用膝サポーターの種類

具体的に高齢者用膝サポーターには、次の種類があります。
- 金属の支柱があるサポーター
- 支柱のないサポーター
- 保温用サポーター
それぞれの特徴を解説します。
金属の支柱があるサポーター
金属の支柱があるサポーターは、膝関節の痛みが原因で日常生活にも影響が出ている方におすすめです。金属の支柱がついていると、通常の膝サポーターよりも強度が強く、破損しにくい点が強みです。
さらに、金属で固定されるため、膝関節を簡単に制御できます。
支柱のないサポーター
支柱のないサポーターは、痛みや違和感など初期症状に悩んでいる方におすすめです。どこでも安価に購入できるため、痛みの緩和に膝サポーターが効果的であるかを知るためのお試しとして検討してみてください。
初期症状がでたうちから、膝サポーターを使って炎症部分の悪化を防いだり、過度な動作を制限したりすると、症状の進行を遅らせます。
保温用サポーター
保温用サポーターは、変形性膝関節症で痛みを感じている方におすすめです。高齢者の膝関節の障害に多い変形性膝関節症は、炎症が原因のため、患部を保温して痛みの緩和を試みます。
膝関節が急激に腫れて熱を帯びているような状態の場合、急性炎症と呼ばれる症状であるため、一般的には冷却で応急処置を行います。
一方、見た目からは腫れや熱などの要素がなく、慢性的な痛みが継続して続く場合、保温が効果的なため、着用することで保温効果のある膝サポーターが効果的です。
高齢者用膝サポーターは用途に合うものを選ぶ

高齢者用膝サポーターには、次の用途に合わせて最適なものを選びます。
- スポーツ用
- 医療用
- 日常動作補助用
- 保温用
それぞれの用途に合わせた膝サポーターについて解説します。
スポーツ用
スポーツ用の膝サポーターは、運動が目的であるため、伸縮性に長けているものが多いです。固定力に注力した膝サポーターの中には、曲げ伸ばしが難しかったり、動きに制限があったり、スポーツに不向きな製品があります。
スポーツ用の膝サポーターを選択すると、ストレッチ素材、伸縮構造など動きやすさが重視されているため、機敏な動きにも順応できます。
医療用
医療用の膝サポーターは、理学療法士や医療スタッフが設計した高機能製品です。膝関節の固定は、痛みの軽減、炎症の抑制など多くのメリットがある一方で、使い方を間違えると圧迫されて、血流の流れを悪くし、症状の悪化を引き起こすリスクがあります。
医療用の膝サポーターには、関節の動きを適切に安定させるクリスタル樹脂ボーンが内蔵されていたり、動きに合わせた伸縮機能の素材が使われていたり、多種多様です。医療機関を受診したうえで、症状に適した医療用の膝サポーターを購入する方法があります。
日常動作補助用
日常動作補助用の膝サポーターは、日常生活での制限の抑制を重視した製品です。激しい運動をしていないにも関わらず、痛みや可動域の制限に悩んでいる方は、日常動作補助用の膝サポーターをおすすめします。
膝の曲げ伸ばし、ひねりなどの動作で膝関節に問題を抱えている場合、ベルトで膝の動きを制限できるタイプのサポーターを使うと簡単に着用できます。
保温用
保温用の膝サポーターは、寒い時期やクーラーなどが効いた部屋で着用するときに効果的です。
変形性膝関節症に悩んでいる高齢者は、できる限り膝関節周辺を冷やさないよう、着用することで保温効果のある膝サポーターをすると痛みや可動域の制限を抑えられます。膝サポーターのため、固定力がありながら、保温効果も期待できます。
高齢者の膝サポーター着用のデメリット

高齢者が膝サポーターを着用するときは、次のデメリットが生じます。
- 他の部分への負担が大きくなる
- 筋肉が衰える可能性
- 湿疹の悪化
それぞれのデメリットについて解説します。
他の部分への負担が大きくなる
本来、膝関節は歩行や登り下りする際に、衝撃を分散させる役割を担っています。膝サポーターを使って関節を固定すると、足首や腰など膝関節と繋がっている他の部位がいつも以上の働きを要求されます。
結果、他の部位への負担が蓄積され、炎症や痛みにつながる可能性が高いです。
筋肉が衰える可能性
膝サポーターを使うと、膝関節周辺は、固定されて動かさなくなるため、筋肉量の低下が懸念されます。
年齢を重ねるごとに筋肉量は落ちているにも関わらず、膝サポーターを使ってさらに動かす機会を減らすと、筋力低下は急速に進みます。激しい痛みがある場合は例外ですが、一般的には膝サポーターに頼りすぎず、適度な運動も大切です。
湿疹の悪化
膝サポーターは、皮膚に直接触れて着用する製品のため、湿疹、かぶれ、かゆみなどの原因を引き起こします。摩擦、素材、汗、汚れなど湿疹を引き起こす原因は、いくつか考えられますが、膝サポーターは、定期的に洗濯をして清潔に維持してください。
また、湿疹が続くようであれば、一時的に膝サポーターを着用せず、保湿クリームで皮膚を守って、症状の回復を試みます。
膝サポーターが必要な疾患

具体的に膝サポーターが必要とされる疾患は、次のとおりです。
- 変形性膝関節症
- ランナー膝
- ジャンパー膝
それぞれの疾患について解説します。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、高齢者が多く発症しやすい病気で、膝関節の軟骨がすり減ると、歩行中に膝の痛みを発症します。軟骨には血管が通っていないため、一度損傷すると完全回復が見込めないため、症状が悪化すると、大きな手術が必要になるほどの深刻な病気です。
年齢を重ねており慢性的に痛みが続く場合、変形性膝関節症の疑いがあります。患部をできる限り温めながら安静にすることに、膝サポーターが効果的であるといわれています。
ランナー膝
ランナー膝は、ランニングやジャンピングを長時間繰り返すと、太もも外側の膝蓋靭帯と太ももの大腿骨の摩擦が起きて発症します。膝下にうずくような鈍い痛みが起こりやすく、完全回復には冷却処置と安静が必要です。
日常生活を送る中で、歩行や上り下りなど、気付かぬうちに膝関節を動かす場面があるため、固定力のある膝サポーターを使うと、患部への刺激を最小限に抑えられます。
ジャンパー膝
ジャンパー膝は、膝蓋腱炎(靱帯炎)とも呼ばれており、バレーボールやバスケットボールなど激しい着地動作のあるスポーツで引き起こされるスポーツ障害です。
痛みや腫れを引き起こした際には、着地動作をやめて患部を安静に保ったうえで、冷却をして症状の緩和を試みます。着地動作では、大きな衝撃が膝関節に加わるため、膝サポーターを着用すると、膝関節に加わる衝撃の吸収と緩和を助けます。
【ランキング】ひざ専門のクリニックで膝の痛みを解消しよう
ここでは膝に痛みを感じた際におすすめのクリニックをランキング形式でご紹介します。痛みを我慢せずに、まずは専門医に相談をしてみましょう。
1位:ひざ関節症クリニック
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
高齢者の膝サポーターに関するよくある質問

ここからは、高齢者の膝サポーターに関するよくある質問について回答します。
サポーターはどのようなときに使用すればよいのですか?
膝サポーターは、本来必要ない方が着用しても筋肉量の低下や圧迫など悪い症状を引き起こしかねないため、次のタイミングを参考にして、着用が必要か否かを検討してください。
- 長距離歩行がしんどいと感じるようになった
- 階段の上り下りで膝が笑う症状がある
- ランニングやウォーキングで膝の痛み、違和感を感じるようになった
- 膝の曲げ伸ばしが欠かせない仕事をしている
上記のいずれかに当てはまる方は、膝サポーターを使って早期予防、早期対策を実施するとよいでしょう。
また、過去に膝関節に関する大きな怪我をした方、変形性膝関節症と診断された方も、膝サポーターを着用すると、膝に関する障害を予防できます。
種類が多くて何を選んでいいか難しいです。
高齢者の方が、痛みの緩和や可動域の制限を改善する目的で着用する場合、「高齢者用」「日常動作補助用」と記載されたものをおすすめします。
どうしても自身に適した膝サポーターを選べない方は、医療機関を受診して、医療用の膝サポーターを購入する方法があります。
サポーターをしたら怪我は治りますか?
結論からお伝えすると、膝サポーターは、保存治療の一種であるため、怪我は完治しません。
ただし、膝サポーターを着用すると、痛みの緩和、炎症部分の固定による安静など、症状の悪化を防ぐ効果が期待できます。
怪我を完治させたい場合、医療機関を受診して、ヒアルロン酸注射のような薬物療法や、人工関節置換術のような手術を検討してください。
サポーターは一日中着けていてもよいのですか?
膝サポーターの長時間着用は推奨しません。膝サポーターは、膝周辺を強く締め付けるため、鬱血や圧迫通を引き起こすなどの血行の流れを乱すリスクが高いです。
また、膝サポーターは、膝周辺の筋肉の動きを補助する役割を担っているため、長時間着用すると、膝周りの筋肉量が低下する可能性もあります。
実際に、多くの膝サポーターの取扱説明書にも「長時間の着用は控えてください」といった内容の注意書きがされているでしょう。
具体的に、1日の最大着用時間は定められていませんが、2時間を目安に膝サポーターを外して、座っているときや睡眠時は着用しないようにしてください。
まとめ

この記事では、高齢者の膝サポーターの必要性、デメリット、適切なサポーター選びについて解説しました。まとめると、膝の痛みや違和感を抱いている高齢者には、膝サポーターをおすすめしています。
ただし、長時間の着用や自身に合っていないサポーターを使用していると、血流の流れが悪くなったり、筋肉量が低下したり、問題が生じるため要注意です。
心配な方は、医療機関を受診して、医療用の膝サポーターを購入できるため、自身に適した方法で膝サポーターを選んでみてください。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。