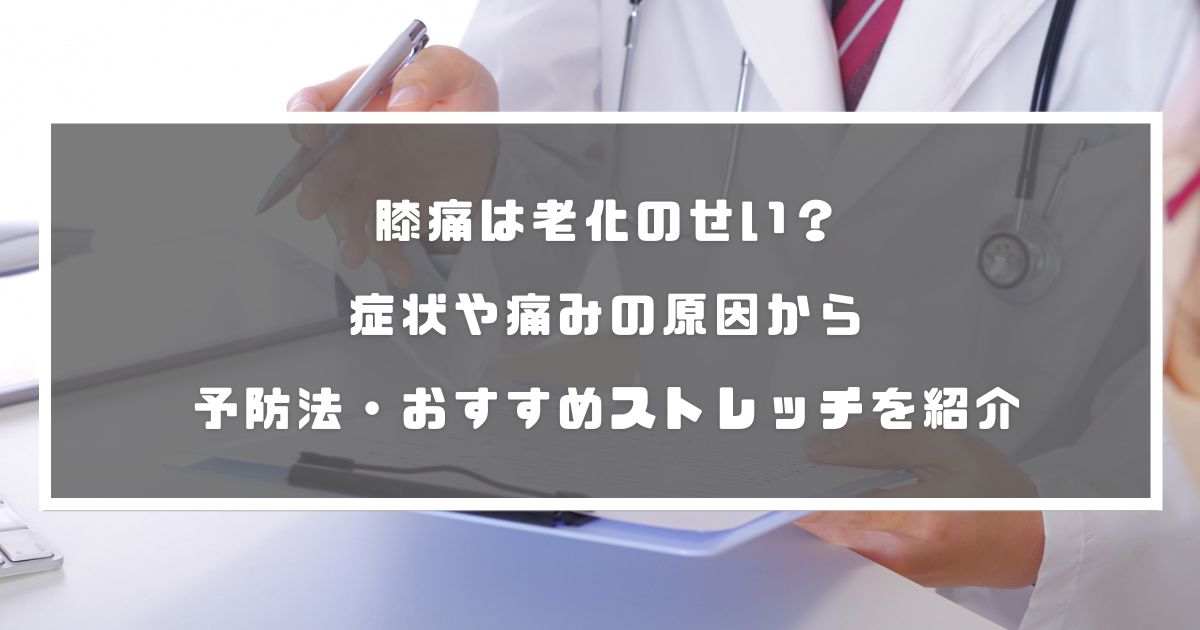老化に伴い、さまざまな箇所が痛む関節痛に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。関節痛の中でも、日常生活を送るうえで大きな障害となる膝痛は、そのままにしておくと非常に危険です。
日常生活に支障が出ている場合は、医師に相談する必要があります。しかし、日常生活に支障がない痛みの場合は、セルフケアやストレッチで改善可能です。
本記事では、老化による膝痛の症状や痛みの原因について解説します。さらに、老化による膝痛を防ぐための予防法や、おすすめのストレッチも紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
膝が痛くなってきたのは老化のせい?

膝痛にはさまざまな原因があり、自身の膝痛が老化によるものであるかどうかなかなか判断できません。とくに40代の方は老化が始まっていることに気づきにくいため、注意が必要です。
膝痛は、関節軟骨の減少によって炎症を起こすことが原因とされ、老化による膝痛を抱える方の多くは、変形性膝関節症と診断されます。とくに、女性は男性よりもともとの筋肉量が少ないため、変形性膝関節症になりやすいことも覚えておきましょう。
膝痛の原因は膝の炎症または関節軟骨の減少
老化による膝痛の原因は、関節軟骨の減少に伴い炎症を起こすことが多くの原因です。健康な状態は、関節軟骨によって円滑に曲げられますが、すり減ってしまうと骨同士が接触する部分が出てきて、痛みにつながります。炎症が起きていなくても、骨にズレが生じて痛みを伴う場合があるため、早めの対策が必要です。
女性は筋肉量の関係以外にも、閉経によってホルモン分泌が減少するため、骨が弱くなりやすいことから、膝痛を引き起こします。自身では老化を感じていなくとも、膝痛が気になる前からの予防が大切です。
関節軟骨は一度減少すると元に戻らない
膝痛の原因は、関節軟骨の減少によるものと解説しましたが、関節軟骨は一度減少すると自然に元に戻ることはありません。また、関節軟骨の減少により靭帯や半月板の損傷、骨折など別の怪我を引き起こす場合もあるため、早めの対策が必要です。
グルコサミンやコンドロイチンなど、関節痛に効果的といわれる成分がありますが、治療としての効果は個人差があり、保証されていません。老化による膝痛は、グルコサミンやコンドロイチンなどのサプリメントを飲んでいても安心できるものではないことと、減少した関節軟骨は元に戻らないことを覚えておきましょう。
膝痛で生活動作に影響が出てきたら病院を受診しよう
膝痛により、日常生活に支障が出ている方は、すぐに医師に相談してください。日常生活がままならない膝痛は、重度の変形性膝関節症である可能性が高く、場合によっては手術する必要があります。
これまで変形性膝関節症に対しての治療は、痛みを和らげることを目的とする治療が主流でした。しかし、現在は軟骨をはじめとした関節組織を修復する治療もおこなわれています。前述したグルコサミンや、コンドロイチンなどの関節痛に効果的とされるサプリメントの摂取も、医師に相談しましょう。
中高齢者の膝痛で見られる「変形性膝関節症」とは?
変形性膝関節症は、老化により関節軟骨が弾力性を失ったため、すり減ることで関節が変形する膝痛の症状を指します。中高齢者とされる40~60代に最も多い症状とされ、男女比は1:4と女性に多い膝痛の症状です。医師は、圧迫による痛みの有無や関節の可動域、レントゲンで判断し、膝の状態にあわせた処置をおこないます。
変形性膝関節症の症状
変形性膝関節症の症状は、初期、中期、後期に分けられます。初期は少し痛みがある程度で、中期は強い痛みがあり、後期になると普通に歩けない痛みを伴う症状です。ここでは、変形性膝関節症の症状別に詳しく解説するため、判断基準として参考にしてみてください。
変形性膝関節症初期
変形性膝関節症の初期症状は、歩くときに痛みが生じますがすぐに痛みが消える状態です。関節軟骨が減少しはじめており、軟骨に亀裂が入っている状態となります。見た目で判断が難しく、膝の骨と骨の間に少し間隔ができている程度です。
主な症状は、朝起きたときに膝がこわばることや立ち上がり、階段の上り下りの際に膝が重たく感じることが挙げられます。
ストレッチや姿勢を正すなど、予防法の実践により痛みを和らげられ、進行を遅らせられるため、早めに医師に相談してください。
変形性膝関節症中期
変形性膝関節症の中期症状は、身の回りのことはできても、強い痛みがあり、痛くて正座ができない状態です。関節軟骨が減少しており、骨と骨の間が狭くなっている状態となります。立ったときに膝が外側に向くため、見た目から判断可能です。
主な症状は、膝がまっすぐに伸びないことや膝に腫れがある、場合によっては膝に水が溜まることなどが挙げられます。早急に医師に相談する必要があり、場合によっては手術が必要です。しかし、ストレッチや姿勢を正すなどの予防法の実践で悪化を防げる場合もあります。
変形性膝関節症後期
変形性膝関節症の後期症状は、身の回りのことが難しくなり、非常に強い痛みであることから通常通りに歩けない状態です。大抵の関節軟骨が消滅しており、骨と骨がぶつかっている状態となります。立っていることが困難なほど、脚が節くれだってしまい、O脚と呼ばれる状態となるため、即座に判断可能です。
主な症状は、膝関節がグラグラしてしまい、膝全体が大きくなります。変形性膝関節症の後期では、手術が必要です。予防法では痛みの緩和や改善はできないため、手術を受けてください。
変形性膝関節症の原因
変形性膝関節症の原因は、老化現象の一つと考えられ、膝の関節軟骨に対する負荷の蓄積や、老化による新陳代謝の低下によるものとされています。膝痛を引き起こす関節軟骨への負荷はさまざまなものがあり、肥満、過去の怪我、冷え、O脚やX脚、筋力の低下、仕事や運動によるものなど、非常に多いことがわかります。
これまでは、関節軟骨が滑らかにして摩擦を和らげることで、膝痛は起きませんでしたが、老化による膝痛は多くの方が悩む老化現象の一つです。
老化による膝痛を防ぐために日常生活でできる予防法

ここからは、老化による膝痛を防ぐために日常生活でできる予防法について解説します。普段から積極的に日常生活に取り入れることで、老化による膝痛を予防できるため、ぜひ参考にして実践してみてください。
ただし、痛みに耐えながら無理しておこなうものではないため、実践できる方法から徐々に慣らしていきましょう。普段から運動していない方は、膝周りの筋肉が固まっているため、急に動かすと、筋肉痛や肉離れなど別の怪我につながります。まずは、膝サポーターを着用したり膝関節に負担をかけないようにしたりして、日常生活を送りましょう。
膝関節に負担をかけない
1つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、膝関節に負担をかけないことです。老化による膝痛の多くは、膝関節に負担がかかっていることで関節軟骨が減少し、膝痛を引き起こします。そのため、普段から負担をかけないように過ごすことが大切です。
膝関節へ負担がかからないようにするには、冷やさないことや正座を避けることなどが挙げられますが、膝をかばうような歩き方や姿勢でいるとかえって悪化するため、注意しましょう。トイレも和式では負担がかかるため、洋式トイレを率先して利用するようにし、長時間しゃがむ態勢は避けてください。
屈伸運動を取り入れる
2つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、屈伸運動を取り入れることです。膝関節を適度に動かしていないと、膝周りの筋肉が凝り固まってしまい、膝痛を引き起こす原因となります。負担をかけないようにするとつい安静にしてしまいがちですが、適度な運動が必要です。
屈伸運動は、主に座った状態で膝を曲げたり伸ばしたりする運動にして、立ったままおこなう際は、ゆっくりと5回程度曲げたり伸ばしたりしてください。ただし、膝が痛む場合は立ったままの屈伸運動は控えましょう。
正しい姿勢や歩き方を学ぶ
3つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、正しい姿勢や歩き方を学ぶことです。歩き方を正しくすると、太ももの筋肉が鍛えられ膝痛の予防に効果的とされています。正しい歩き方のポイントは次のとおりです。
- 背筋を伸ばす
- 踏み出すときに、膝を伸ばす
- かかとから着地する
- 親指を意識して、しっかり地面を蹴り出す
- 腕は自然に振る
参考元:サワイ健康推進課│沢井製薬
歩いている最中に、ショーウィンドウに映る自身の歩き方を見て確認してみてください。反対に、歩幅が狭く、膝が常に曲がっている歩き方は膝痛が起きやすくなるため、注意が必要です。
太りすぎない
4つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、太りすぎないことです。過度な肥満は、膝への負担以外にも健康によくありません。食事の管理や運動をおこない、適切な体型を維持しましょう。体重による膝への負荷は想像以上に大きく、普通に歩いているときでも、体重の約7倍の負荷がかかっているといわれています。
そのため、屈伸運動による筋力トレーニングや体重を軽くするダイエットが効果的です。体重が軽くなることで、膝痛が軽減される可能性もあるため、挑戦してみてください。
O脚の改善
5つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、O脚の改善です。O脚とは、脚を閉じてまっすぐ立った状態でも膝が離れている状態を指します。膝痛になる方の多くがO脚であることから、改善が必要です。
O脚は、骨盤周りの筋肉が衰えや硬さが原因とされており、姿勢や座り方で改善できます。前述した正しい姿勢や歩き方、屈伸運動によるトレーニングをおこない、徐々に改善していきましょう。
O脚のままでいると関節軟骨の内側のみ減少していき、より大きく膝が外側に開きます。変形性膝関節症の中期から後期に見られる状態と同じとなるため、そのままにしないようにしましょう。
膝サポーターを利用する
6つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、膝サポーターの利用です。膝サポーターは着けるだけで、多くの効果が期待できます。膝の冷えを防ぐ、膝を安定させる、痛みを緩和するなどの効果が期待できるかつ、誰でも手軽に着用できるため、非常に便利です。
膝サポーターは、膝に痛みがあり、屈伸運動や歩き方の改善が難しい方におすすめの方法といえます。薬局でも取り扱っていることが多く、簡単に入手でき、予防や痛みの緩和ができるため、膝痛に悩んでいる方は、まず膝サポーターを購入してみましょう。
足にあった靴を選ぶ
7つ目の老化による膝痛を防ぐ予防法は、足にあった靴を選ぶことです。足に合っていない靴を履いていると、足首がもつれることや変な力が入ってしまうため、正しい歩き方ができません。そのため、前述した正しい歩き方をするには、足にあった靴を選ぶ必要があります。
サイズや履き心地など、靴を選ぶ際のポイントはいくつかありますが、おすすめはスニーカーです。クッション性が高く、地面からの衝撃を吸収する靴を選びましょう。
老化による膝痛を防ぐために避けた方がいいこと

ここからは、老化による膝痛を防ぐために避けた方がいいことを解説します。運動は大切ですが、過度なランニングやウォーキングなどはかえって膝に負担がかかるため、運動しすぎには注意が必要です。前述しましたが、正座も膝に負担がかかるため、なるべく避けてください。
過度なランニングやウォーキング
過度なランニングやウォーキングは、膝に大きな負担がかかります。ランニングやウォーキングなどの有酸素運動は、健康によいとされているため、おこなうことで膝痛が防げますが、何事もやりすぎは禁物です。
自身の生活リズムや体調、膝の具合にあわせて実践しましょう。運動の際も、膝サポーターの着用が負担を軽減できるため、おすすめです。
正座
膝を最大限に曲げる正座は、膝痛を引き起こす原因の一つです。そのため、正座は極力避けるようにしましょう。正座と同様に、スクワットやうさぎ跳びなどの動作も膝を最大限曲げる動作のため、おこなわないようにしてください。屈伸運動の際も、膝を最大限曲げないことがポイントです。
仕事上、正座しなくてはならない場合は、回数を減らすことや軽減させる座椅子などを利用しましょう。
老化による膝痛におすすめのストレッチ

最後に、老化による膝痛におすすめのストレッチを紹介します。ストレッチの注意点は、やりすぎないことです。負担にならないようにリラックスできる程度にしておきましょう。
ストレッチの目的は、筋肉を鍛えることとなり、膝痛予防によいとされている鍛えるべき筋肉は、大腿四頭筋や内転筋、大臀筋のような太ももを中心とした筋肉を鍛えます。それぞれ詳しく解説するため、ぜひ最後まで読んでみてください。
太ももの筋肉を鍛える
老化による膝痛におすすめのストレッチは、太ももの筋肉を鍛えることを目的としています。太ももの筋肉を鍛えることで膝にかかる負担を減らせる以外にも、O脚の改善や正しい歩き方にもつながるため、実践してみましょう。
ストレッチによるダイエット効果も期待でき、脚が細くなることやたるんだ脂肪を燃焼させるなど、多くのメリットがあります。セッティングと呼ばれるストレッチ方法が効果的とされ、脚と背筋を伸ばして座り、太ももが盛り上がる程度の力を入れ、5秒間キープする方法です。
膝の前後やふくらはぎ前後を柔らかくする
老化による膝痛におすすめのストレッチの中には、膝やふくらはぎの前後を柔らかくするストレッチも効果的です。膝周りの筋肉が固まっている場合も、膝痛を引き起こす原因となることから、定期的に動かし、柔らかくしておきましょう。
主な方法はカーフパンピングと呼ばれるストレッチ方法で、脚を伸ばして座り、足首を前後に動かすことでふくらはぎを鍛えられるため、実践してみてください。
膝を曲げる筋肉を鍛える
老化による膝痛におすすめのストレッチ以外にも、膝を曲げる筋肉を鍛えることも効果的です。膝を曲げる筋肉は、ヒップリフトと呼ばれるストレッチ方法が効果的とされ、仰向けになり膝を立てて、お尻を上げたり下げたりしていることで鍛えられます。簡単にできるストレッチとなるため、実践してみましょう。
普段動かさない筋肉を動かすことで、太ももの後ろがつる場合があるため、注意が必要です。つりにくくするためには、より深く膝を曲げることでつりにくくなります。
大腿四頭筋をゆっくり伸ばす
大腿四頭筋は、太ももの前部分にある筋肉で、立った状態でゆっくりと膝を曲げるストレッチが効果的です。膝を曲げすぎないことがポイントで、5回を目安におこないましょう。しかし、膝が痛む場合はおこなわず、ほかのストレッチから膝への負担を減らしてください。場合によっては、膝痛が悪化するため、注意が必要です。
足に枕を挟んで内転筋を鍛える
太ももの内側を鍛えることも膝痛におすすめのストレッチの一つです。おすすめのストレッチ方法は、足の間に枕を挟んで3秒ほど力を入れてキープし、3~5回繰り返すストレッチ方法となります。以上の太ももを鍛えるストレッチを定期的におこない、老化による膝痛を軽減、予防しましょう。
お尻を上げて大臀筋を鍛える
最後におすすめするストレッチ方法は、大殿筋を鍛えるストレッチです。大臀筋は、お尻の筋肉を指し、膝痛軽減になる以外にも、お尻の引き締め効果もあります。
ストレッチ方法は、仰向けに寝た状態で、片足のみ地面につけておき、もう片方の脚を伸ばしてお尻と一緒に浮かす方法が効果的です。できる限り3秒間キープするストレッチを3~5回おこないましょう。
【ランキング】おすすめ膝のクリニックランキング
ここでは膝治療におすすめなクリニックをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
1位:ひざ関節症クリニック
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
まとめ

今回は、老化による膝痛の原因や効果的なストレッチ方法について解説しました。膝痛は、太ももの筋力低下や歩き方でも起こる症状のため、老化そのものではなく、老化による筋力低下によって起こりやすいものといえます。
防ぐためには、正しい姿勢や歩き方、日々のストレッチが必要となりますが、過度な運動は禁物です。しかし、すり減った関節軟骨は自然に再生しないため、痛みがある方は医師に相談してください。
健康的な膝を維持するためにも、簡単にはじめられるストレッチや膝サポーターを活用してみましょう。膝痛に悩んでいる方は、本記事を参考にして実践してみてください。
※本記事の情報は2022年12月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。