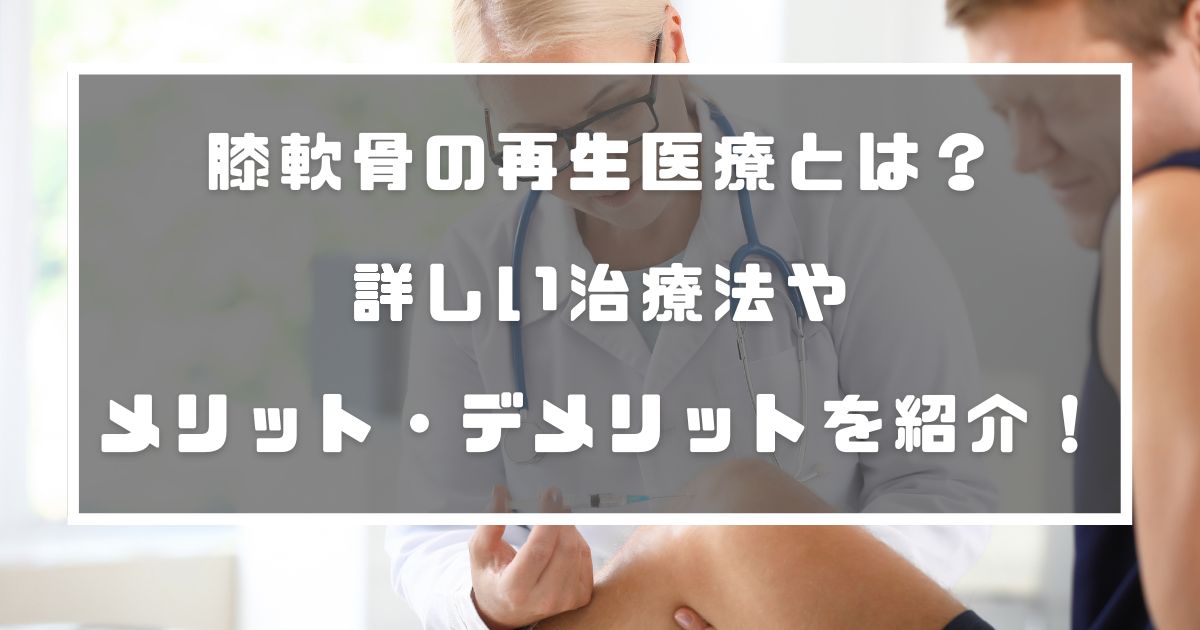再生医療は、膝軟骨における疾患の最新治療として、今最も注目されている治療方法です。
しかし、「再生医療とはそもそもどのような治療方法なのか」、「費用はどのくらいかかるのか」など疑問に思っている方も多いでしょう。
本記事では、そのような方に向けて、膝軟骨の再生医療について解説していきます。
詳しい治療法やメリット、デメリットについても解説していくため、これから再生医療を受けようか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
膝軟骨の再生医療とは?

膝軟骨における再生医療とは、患者自身が本来持っている自然に体の組織を再生する能力を最大限に生かす治療方法です。
拒絶反応やアレルギーのリスクがない安全な治療方法としても注目されている、話題の最先端治療です。
自身の細胞によって軟骨を修復する治療法
膝軟骨の再生医療は、患者自身の細胞を使用して軟骨を修復する治療方法です。
血液中にある血小板や脂肪由来の幹細胞には、傷んだ組織の修復を促進する作用があります。
採取した細胞を濃縮し、膝軟骨に直接注入することで、自己治癒力を高めて痛みや炎症の早期治療が期待できます。
手術なしで膝の痛みを改善
再生医療では、自身の血液や脂肪を採取した細胞を膝軟骨へ注入する治療方法をおこなっているため、手術なしで膝の痛みを改善する効果が期待できます。
持病があって手術をおこなえない方や手術に抵抗のある方でも、安心して治療を受けられます。
一部の疾患は保険適用
再生医療は有効性や安全性が高く評価されてはいるものの、保険適用になるほど臨床データが揃っていません。そのため、基本的には自費治療となります。
ただし条件を満たした一部の疾患に限り、数年前から保険適用が認められました。
軟骨欠損症と離断性骨軟骨炎は保険適用
患者から採取した軟骨をコラーゲンと混ぜ合わせて培養させ、損傷した部分に移植する自家培養軟骨移植術においては、2013年の4月1日から保険適用となりました。
治療対象となる疾患は、スポーツでの損傷や事故が原因となって起こる軟骨欠損症と離断性骨軟骨炎の2種類です。
自家培養軟骨移植術は、日本で2番目に保険が適用された再生医療で、健康保険だけでなく高額療養費制度の対象にもなります。
変形性膝関節症は保険適用外
膝軟骨における疾患のなかでも患者数の多い変形性膝関節症については、保険適用外となります。
変形性膝関節症が保険適用外になる理由としては、全国でも一部のクリニックでしか治療できない状態で保険が適用された場合、治療できるクリニックが近くにない患者は不公平と感じてしまうからです。このような治療の公平性から、保険適用外となっているといわれています。
膝軟骨の再生医療の種類

膝軟骨の再生医療は、自身の体内に存在する組織を使用する点はどの治療方法も同じですが、使用する材料や加工方法の違いによって費用や適用対象が異なります。
膝軟骨の再生医療は、次の3つに分類されます。
・PRP療法
・脂肪由来幹細胞治療
・自家培養軟骨移植術
PRP療法
PRP治療とは、患者自身の血液を使用して膝軟骨の再生を図る方法です。
患者の血液を採取し、その中に含まれる血小板から多血小板血漿(PRP)とよばれる液体成分を抽出します。
多血小板血漿には、細胞を増殖させて物質の修復を促す成長因子が多く含まれているだけでなく、疾患によっては白血球の働きを促進させる作用もあります。
多血小板血漿を膝軟骨に直接注入することで、自己治癒力を高め、痛みや炎症の早期治療が期待できます。
もともと体内にある血液を使用することと、手術をおこなう必要がないことから、大きな副作用が起こりにくい治療方法ともいわれています。
【治療対象となる疾患】
PRP治療の対象となる疾患は次の2つです。
・スポーツ関連の疾患
(上腕骨外側上顆炎、膝蓋腱炎、アキレス腱炎など)
・変形性膝関節症
【治療費用】
PRP治療は疾患や症状によって治療回数が異なる場合があります。
参考までに、治療対象となる疾患別に、おおよその費用を紹介します。
スポーツ関連の疾患:注射1回につき 約3万円
変形性膝関節症:注射1回につき 約5万円
脂肪由来幹細胞治療
脂肪由来幹細胞治療とは、患者自身の腹部から採取した脂肪細胞を使用して膝軟骨の修復を図る方法です。脂肪の中に含まれる幹細胞には、骨や筋肉、血管などの組織に変化できる能力と、失われた細胞を再び生み出す2つの能力があります。
脂肪由来幹細胞治療では、患者の腹部から採取した幹細胞を専門の施設で何倍にも増殖させたあと、患者の膝軟骨に直接注入します。幹細胞が持つ能力によって痛みや炎症を緩和したり、傷んだ軟骨の組織の修復を促したりする効果が期待できます。
【治療対象となる疾患】
脂肪由来幹細胞治療は、関節疾患や後遺症の治療として適用されることが多いです。
治療対象となる主な疾患は、次の3つです。
・変形性膝関節症
・脳梗塞の後遺症
・脊髄損傷の後遺症
【費用】
脂肪由来幹細胞治療の費用は、100万円前後が一般的な価格帯とされています。
クリニックによって異なる場合があるため、治療を考えている方は問い合わせてみることがおすすめです。
自家培養軟骨移植術
自家培養軟骨移植術とは、患者自身の健康な軟骨細胞を使用して膝軟骨の修復を図る治療方法です。
患者から採取した軟骨をコラーゲンと混ぜ合わせて培養させて、損傷した部分に移植します。自家培養した軟骨を移植するため、失った軟骨組織を取り戻すことが可能になります。
ただし、培養した軟骨を移植する際には、全身麻酔を用いた手術と、1か月程度の入院が必須となるため注意が必要です。
【治療対象となる疾患】
自家培養軟骨移植術の治療対象となる疾患は、次の2つです。
・膝関節における外傷性軟骨欠損症
・離断性骨軟骨炎
個人の症状によっては適合しない場合があるため、クリニックに相談してみることがおすすめです。
【費用】
健康保険と高額療養費制度を利用した場合、自家培養軟骨移植術の治療費用は約25万円になります(年収450万円の場合)。
膝軟骨の再生医療のメリット

膝軟骨の再生医療のメリットは、次の3つです。
・従来の治療法より効果が期待できる
・持病により手術ができない方も選択できる
・拒絶反応やアレルギーを起こしにくい
従来の治療法より効果が期待できる
膝軟骨における再生医療の1つ目のメリットは、従来の治療法よりも効果が期待できる点です。
ヒアルロン酸注射や装具療法、リハビリなど、従来の保存療法では改善が見られなかった症状に対しても、再生医療であれば改善が期待できます。
従来の保存療法は痛みの軽減を目的としているのに対し、再生医療は関節の内部組織に直接アプローチをかけて、関節そのものを修復する効果が期待できます。
また、再生療法によって十分な効果を得られた場合、保存療法のように何度も通院する必要はありません。
持病により手術ができない方も選択できる
持病によって手術ができない方も、再生療法であれば選択できます。
膝軟骨の手術には、関節鏡手術や高位脛骨骨切り術、人工膝関節置換術などの方法がありますが、どれもメスを伴う手術になるため、全身麻酔が必要になります。
持病がある方や服用中の薬がある方は、全身麻酔を受けることが難しく、手術を選択できない場合があります。
その点で再生療法は、方法によっては手術をおこなうことも、麻酔を使用する必要もありません。そのため、持病によって手術ができない方でも治療を受けることが可能になります。
拒絶反応やアレルギーを起こしにくい
再生療法は比較的、拒絶反応やアレルギーが起こりにくい治療方法だといわれています。
今までの保存療法では、内服薬や注射薬などが主に使用されていました。
しかし患者によっては副作用に悩まされることもあり、服用を続けられないケースも少なくありません。
再生医療では自身の体内から採取した細胞を使用するため、拒絶反応やアレルギーなどの副作用が起こりにくいです。薬の副作用に悩まされていた方でも、安心して治療をおこなうことが可能です。
膝軟骨の再生医療のデメリット

一方、膝軟骨における再生医療のデメリットは次の3つです。
・一部の治療は自費治療で高額となる
・効果を感じるまで時間がかかることもある
・脂肪を採取する場合は傷が残る
一部の治療は自費治療で高額となる
膝軟骨の再生医療は、効果や安全性が高く評価されているものの、保険適用診察として承認されるほど臨床データが揃っていないのが現状です。そのため一部の治療においては、自費で治療をおこなわなければなりません。(2023年1月時点の情報です。)
PRP治療は約3万円からと比較的低費用で治療をおこなえますが、脂肪由来幹細胞治療では約100万円という高額な費用がかかる場合もあります。
効果を感じるまで時間がかかることもある
再生医療は、手術をおこなわずして膝軟骨の損傷や痛みを改善する効果がある最新の治療方法です。
しかし、他の治療方法と同様に、効果を感じられるまでに時間がかかったり、そもそも効果が感じられなかったりする場合もあります。また、効果が現れるまでの期間にも個人差があり、人によっては数か月かかることも珍しくありません。
早く膝の痛みから解消されたい、すぐにでもスポーツ競技に復帰したいという方は、比較的短い期間で効果が感じられる治療方法を検討してみるのがおすすめです。
脂肪を採取する場合は傷が残る
脂肪由来幹細胞治療では、患者自身の腹部の脂肪を採取する必要があるため、採取した箇所に1cmほどの傷が残ります。
そのため、なるべく傷跡を残したくない場合には、PRP療法を選択するのがおすすめです。
PRP療法では血液を使用するため、傷跡が残る心配はありません。
膝軟骨の再生医療はこんな方におすすめ!

膝軟骨の再生医療は、次のような悩みを抱えている方におすすめです。
・手術に抵抗がある方
・整形外科に通っているが効果を感じない方
・薬やヒアルロン酸が効いていない方
再生医療は、自身の体内にある細胞を使用する最新の治療方法であるため、手術に抵抗のある方や、他の治療方法では効果が感じられない方に最適な方法といえます。上記に該当する方は、一度クリニックで再生医療について相談してみるといいでしょう。
手術に抵抗がある方
従来まで、膝の痛みや損傷を根本から改善させるには、関節鏡手術や高位脛骨骨切り術、人工膝関節置換術などのメスを伴う手術をおこなうことが一般的とされていました。
しかし、患者によっては手術に抵抗があったり、持病などによって手術をおこなえなかったりする方も多く、痛みの改善を諦めて保存療法による治療を続けている方も少なくありません。
再生医療では手術をおこなう必要がないため、手術に抵抗がある方でも治療を受けることが可能です。
整形外科に通っているが効果を感じない方
整形外科に通っているが効果を感じられない方にも、再生医療がおすすめです。
整形外科でおこなわれている治療方法は、装具やリハビリなどの保存療法が大半です。
保存療法を数か月から半年間続けても膝の痛みが改善されない場合は、再生医療を検討してみるといいでしょう。
薬やヒアルロン酸が効いていない方
薬やヒアルロン酸注射で症状の改善が見られない方も、再生医療を検討してみてください。
膝軟骨関連の疾患で処方される薬は、炎症を抑えて痛みを軽減することを目的としています。そのため、疾患そのものを根本から治すことはできません。
ヒアルロン酸注射においても、注射を打ったあとの1~2週間は痛みの緩和が期待できますが、その後も繰り返し通院する必要があります。
また、薬やヒアルロン酸注射は初期の症状には効果的ですが、症状が進行して痛みをコントロールできなくなってしまった場合には、再生医療を検討するのがおすすめです。
おすすめの膝専門クリニック
膝軟骨の再生医療の関するよくある質問
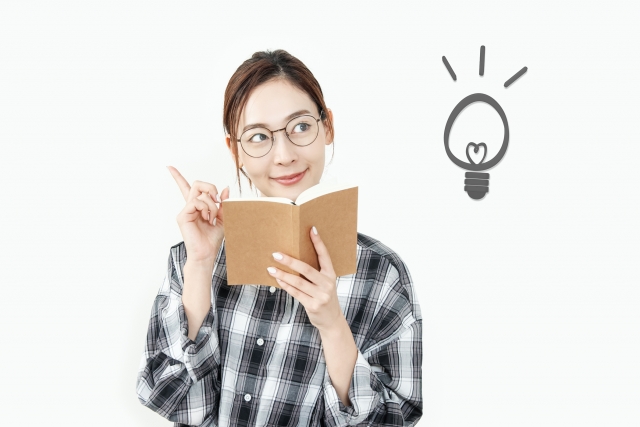
最後に、膝関節における再生医療について、よく寄せられる質問に回答していきます。
これから再生医療を受けるか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
再生治療の安全性は大丈夫?
再生医療は、国際的にも権威のある学術誌において高レベルの科学的根拠を持つ研究結果が報告されているため、安全性、効果ともに高く評価されています。
また、膝軟骨の再生医療では、自身の血液や脂肪など体内にもともと存在する成分を使用するため、重篤な副作用の心配は基本的にありません。
成分を摂取した際や膝軟骨への注入をおこなう際に、患部に腫れや熱感が生じる可能性はありますが、基本的に数日で治まります。そのため、安心して治療を受けられます。
膝軟骨の再生医療はどのような疾患に効果的?
膝軟骨の再生医療がどのような疾患に対して効果を発揮するのかは、
治療方法によって異なります。
PRP治療は、スポーツが原因で起こる疾患や、変形性膝関節症に対して効果的です。
効果を感じられるまでの期間も比較的短いため、早めに日常生活やスポーツ競技に復帰したい方に適用されます。
脂肪由来幹細胞治療は、変形性膝関節症の治療に効果的です。
膝軟骨以外だと、脳梗塞や脊髄損傷の後遺症の治療にも適用されることが多いです。
自家培養軟骨移植術は、膝関節における外傷性軟骨欠損症や、離断性骨軟骨炎などの疾患に効果を発揮します。
| 再生医療の種類 | 効果的な疾患 |
| PRP治療 | ・スポーツ関連の疾患・変形性膝関節症 |
| 脂肪由来幹細胞治療 | ・変形性膝関節症 |
| 自家培養軟骨移植術 | ・外傷性軟骨欠損症・離断性骨軟骨炎 |
膝軟骨の再生医療は入院が必要?
膝軟骨の再生医療では、基本的に入院の必要はありません。
治療自体も数分で終わることが多いです。
ただし、自家培養軟骨移植術においては、培養した軟骨を移植する際に手術を伴うため、術後1か月程度の入院が必要になります。
まとめ

本記事では、膝軟骨における再生医療について解説しました。
再生医療とは、人間が本来持っている自己治癒力を最大限に生かす治療方法です。
拒絶反応やアレルギーのリスクもなく、一部の治療に関しては手術をおこなう必要もないため、持病のある方や手術に抵抗のある方でも安心して受けられます。
しかし、一部の疾患では保険適用外となるため、治療方法によっては高額な医療費がかかってしまう可能性もあります。また、人によっては効果を感じるまでに時間を要する場合もあります。
膝軟骨の再生医療を受けてみたいという方は、取り扱いのある近くのクリニックに相談してみることをおすすめします。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。