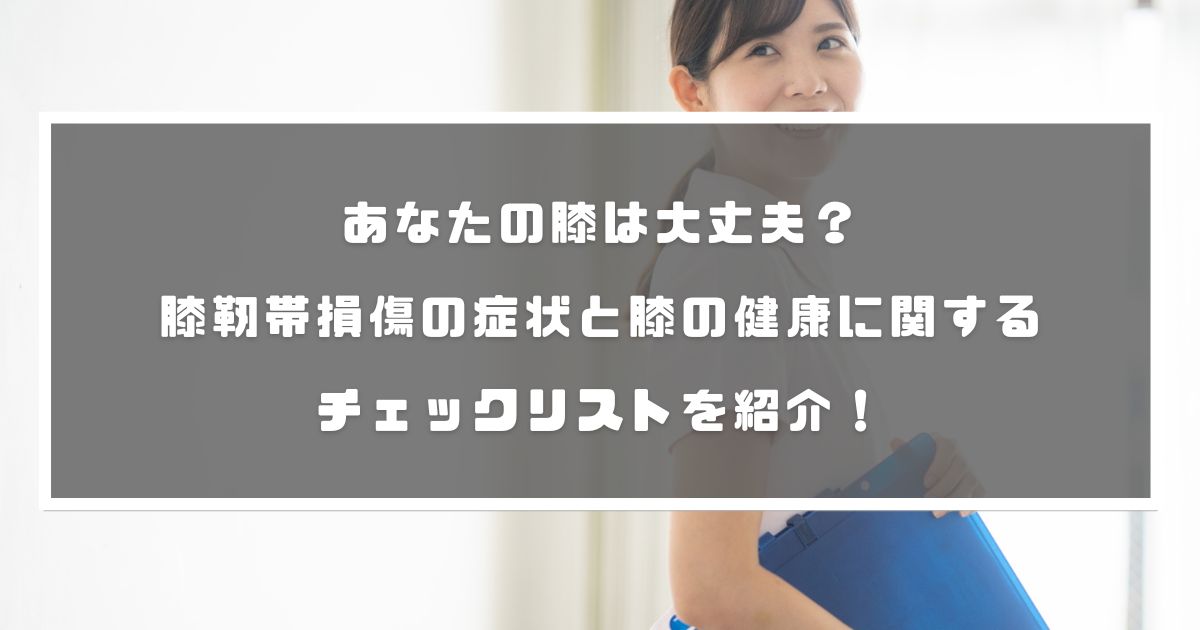「膝が痛い」「膝を曲げ伸ばしするときに違和感がある」と困ったときは、まず膝の健康チェックをおこないましょう。膝靱帯損傷などの疾患があると、人によっては、普段の歩行にすら支障をきたす場合があります。
そこで今回は、膝靱帯損傷などの疾患があるか確かめるための、膝の健康チェックリストを紹介していきます。
あわせて膝靱帯損傷の具体的な症状や治療法、予防・改善策なども解説していくため、膝の痛みや違和感に悩んでいる方は積極的に参考にしてください。
【膝の健康診断】10のチェックリスト

まずは、膝の健康診断の一つとして、チェックリストを見ていきましょう。膝の健康状態を知るには、次に紹介する項目に当てはまるかどうかを確認してください。
「Yes」に該当する項目の個数次第で、膝に疾患を抱えている可能性は高まります。
階段の上り下り時にひざが痛む(Yes/No)
日常的に階段を上り下りするとき、膝に痛みの症状があるかを思い出してみましょう。
膝に少しでも痛みがあり、普段から階段の上り下りがきついと感じる方は、Yesに当てはまるといえます。
ひざが腫れている(Yes/No)
膝に「腫れ」の症状がある方は、Yesに当てはまります。
膝の状態をチェックして、明らかに腫れて膨張していたり、腫れによる痛みがあったりするときは、腫れていると判断して良いでしょう。
荷物を持ち上げる際にひざが痛む(Yes/No)
膝に疾患があると、荷物を持ち上げるときに膝に痛みを伴う場合があります。
荷物の入った段ボールを持ち上げるとき、少々重たい荷物の入った鞄を持ち上げるときなどに、膝に痛みを感じるかを思い出してみましょう。
立ち上がる時、ひざに違和感を感じる(Yes/No)
立ち上がる動作をする際に、膝に違和感があるかどうかをチェックしてみましょう。
座り姿勢から立ち上がるとき、膝に痛みや重み、動作が思うようにいかない違和感などがあるときは、Yesに該当するといえます。
ひざの骨折や靭帯損傷を経験したことがある(Yes/No)
過去に膝の骨折や靭帯損傷などの怪我を経験したことがある方は、チェックを入れましょう。膝の疾患の原因になることがあります。
運動はほとんどしない(Yes/No)
運動不足の自覚がある方も、Yesにチェックを入れましょう。
たとえば在宅かつデスクワーク中心で、普段からほぼ運動しない方などが該当します。運動が少なすぎるせいで、膝の疾患につながるケースは珍しくありません。
ひざを押すと痛い(Yes/No)
膝の健康状態をチェックするときは、膝を押したうえで痛みの有無を確かめましょう。
膝を押したときに痛みがある方は、Yesに該当します。
寝ている時にも痛みを感じる(Yes/No)
「寝ているときに膝の痛みがあり、起きてしまうことがある」と悩んでいる方などは、Yesに該当します。
横になって足を楽にしている状態でも、膝に痛みがあるかどうかを確かめてください。
鎮痛剤を飲んでもひざに痛みを感じる(Yes/No)
膝の健康状態を確かめるにあたって、普段から膝に痛みなどの症状を抱えている方は、鎮痛剤を飲んだ結果痛みが治まるかどうかを確かめてください。
鎮痛剤を飲んだり湿布を貼ったりしても痛みが残る場合は、Yesに該当します。膝には何らかの疾患がある可能性があります。
和式トイレや正座が辛いと感じる(Yes/No)
膝の健康状態が悪いときは、膝を大きく曲げる動作をきついと感じることが多いです。
したがって和式トイレや正座がつらいと感じる方は、チェックを入れましょう。
Yesの数が10〜5の場合
膝の健康状態のチェックリストで、Yesの数が10~5個だった方は、膝に疾患がある可能性が高いため要注意です。
具体的な症状や病名は人によって異なり、軽い生活習慣の見直しで改善するケースもあれば、本格的な治療が必要なケースもあります。そのため多くの項目に当てはまった方は、早めに膝の病気に詳しいクリニックの受診をおすすめします。
またいずれにしても、普段から膝に大きな負担をかけないよう対策することも重要です。和式トイレを避ける、膝に負担のかかる歩き方をしないなどの対処は積極的におこなっていきましょう。
Yesの数が4〜1の場合
Yesの数が4~1個だった方は、場合によっては膝に疾患を抱えている可能性があるため気をつけてください。心配な方は、クリニックを受診することをおすすめします。
症状の重さのみでいえば、上のYesの数が10~5個だった方より比較的軽い可能性はあります。しかしあくまで症状の重さや病名などはケースバイケースのため、膝に何らかの痛みや違和感がある以上、油断できないことは事実です。特に、痛みが少しでも大きい場合は、早めに医者にかかることをおすすめします。
Yesの数が0個の場合
上記のいずれの項目にも当てはまらなかった方は、膝に疾患がある可能性は低いといえるでしょう。少なくとも、「今すぐ対処すべき」といえるような重大な疾患を抱えているケースは少ないはずです。
とはいえ、多くの方は30代半ば以降をめどに、膝に痛みや違和感を抱くようになります。現状気になる症状がなくても、近い将来、膝の痛みに悩むことはあり得ます。
特に運動不足気味の方、膝に負担のかかる仕事をしている方などは要注意です。膝は日常の動作をサポートする重要な部位のため、今後も余計な負担を与えないよう、健康に保つ意識はしっかりと持つようにしましょう。
膝が継続して痛む場合は「膝靭帯損傷」の可能性が高い

前項の膝の健康チェックにおいて多くの項目に当てはまった方や、とにかく膝が継続的に痛んで悩んでいる方は、「膝靭帯損傷」の可能性があるため注意が必要です。
「膝靭帯損傷」とは、膝の靭帯の一部、あるいは全部が切れることを指します。場合によっては「靭帯断裂」の名前で呼ばれることもあります。
関節は膝のみならず、すべて靭帯という紐状の組織でつながっています。このつながりがあることで関節のズレや動きすぎを防げる仕組みですが、何らかの原因によって膝に大きな負担がかかると、靭帯の一部もしくはすべてが切れてしまうことがあります。
膝靭帯損傷の原因はさまざまなパターンがありますが、スポーツなどの激しい運動、転倒、事故などが主に挙げられます。
継続的に膝の痛みがある方は、膝の靭帯が切れている可能性があるため、早めにクリニックを受診するなどの対処が必要です。
膝靭帯損傷の種類

続いて、膝靭帯損傷の種類を詳しくチェックしていきましょう。膝靭帯損傷と一口にいっても種類はいくつかあり、次の4つが挙げられます。
- 前十字靱帯損傷
- 後十字靱帯損傷
- 膝内側側副靭帯損傷
- 膝外側側副靱帯損傷
では、それぞれ具体的にどのような症状になるのか、詳細をまとめていきます。
前十字靱帯損傷
前十字靭帯損傷とは、膝関節の中心部分にある前十字靭帯(ACL)が切れた状態のことを指します。
前十字靭帯は、大腿骨に対して脛骨が前のほうへずれていかないよう支える役割を持ちます。さらに、膝のひねり運動に対して、膝がずれないようサポートする役目も担っています。
主に急激な方向転換や、スポーツなどによるジャンプ運動の繰り返しが原因となって起こる傾向にあります。前十字靭帯損傷になると、膝ががくがくとして上手に支えられない状態に陥ります。
後十字靱帯損傷
後十字靭帯損傷とは、膝部分にある後十字靭帯(PCL)が切れた状態を指します。
後十字靭帯は、膝が後ろへ脱臼した状態にならないよう支える役割を持ちます。前十字靭帯と比較すると強度が高いなどの特徴がありますが、前十字靭帯損傷と同様に、激しいスポーツや無理な運動、事故などで切れてしまうことがあります。
後十字靭帯損傷になると、日常生活の維持にはほぼ問題はないのですが、スポーツでジャンプして着地した際には膝が安定しない感覚を覚えるようになります。
膝内側側副靭帯損傷
膝内側側副靭帯損傷は、膝内側側副靭帯(MCL)が切れた状態を指します。膝靭帯損傷のなかでも頻繁にみられる症状の一つで、多くの原因はスポーツです。
膝内側側副靭帯は、膝関節の中を安定的に保つ役割を持ちます。そのため損傷すると、膝内部の痛みや腫れ、曲げ伸ばし時に違和感、不安定感につながります。
膝内側側副靭帯損傷のみが起こることは珍しく、十字靭帯・半月板などとあわせて症状が起こることが多いとされます。
膝外側側副靱帯損傷
膝外側側副靱帯損傷は、膝外側側副靱帯(LCL)が切れた状態を指します。
膝外側側副靱帯は膝の外側にある靭帯にあたり、外側へのずれを防ぐ役割があります。膝の内側から外方向へ向けて大きな衝撃を受けると、損傷が起こります。あるいは、膝から下を内側へ向けて大きくひねるような運動が原因で、損傷につながるケースもあります。
具体的な症状としては、膝の強い痛みや腫れ、不安定感などが挙げられるでしょう。
膝靭帯損傷の原因

膝靭帯損傷の主な原因は、次の2つがあります。
- スポーツ
- 交通事故
ではそれぞれの原因について詳細を見ていきましょう。
スポーツ
膝靭帯損傷の大きな原因の一つは、スポーツです。スポーツは激しい運動や体の無理な動きを伴うため、膝靭帯損傷を含む怪我の原因になります。
たとえばバレーボールやバスケットボールなどはジャンプを繰り返す傾向にあるため、膝靭帯を損傷するきっかけになり得ます。ほかにはラグビーのタックルなどは、大きな衝撃を伴うため、靭帯が衝撃に耐えられず断裂してしまう場合があります。
交通事故
膝靭帯損傷のよくある原因の一つには、交通事故も挙げられます。
交通事故に巻き込まれると、膝に対して日常生活ではあり得ない方向から衝撃が加わったり、無理なひねりが起きたりします。すると衝撃を抑えきることができず、損傷につながる仕組みです。
膝靭帯損傷の症状

続いて、膝靭帯損傷の具体的な症状を整理していきます。膝靭帯損傷に陥った場合、主に次のような症状が見られます。
- ひざに痛みを感じる
- ひざに不安定感を感じる
- ひざが腫れる
- 歩行が難しくなる
膝靭帯損傷の症状について理解を深めたうえで、適切な対処につなげていきましょう。それぞれの症状について詳しく解説していきます。
ひざに痛みを感じる
膝靭帯損傷が起こると、膝には痛みを感じるようになります。特に継続的に膝に痛みが残る場合は、膝靭帯損傷の可能性は高まります。
膝を曲げ伸ばししたときはもちろんのこと、「寝ているときでも膝が痛む」と困ったときは、早めに医師に相談するようにしましょう。
ひざに不安定感を感じる
膝靭帯損傷の症状の一つには、不安定感も挙げられます。膝靭帯は膝がずれないように支える役割を持ちますが、そのうちの一部もしくはすべてが切れると、支える機能が働かなくなります。
たとえばスポーツでは、ジャンプで着地した際に膝に不安定な感覚を覚えるようになることが多いです。
ひざが腫れる
膝靭帯損傷になると、膝に腫れの症状が見られることも多いです。
腫れは痛みに伴って起こり、腫れた部分を押すと強く痛むなどの症状につながる傾向にあります。
歩行が難しくなる
膝靭帯損傷になると、強い痛みや不安定感により、歩行が困難になる場合も多いです。
歩行困難に陥ったときは、少なくとも症状が緩和するまでは、松葉杖をついて日常生活を送ることになります。
膝靭帯損傷の診断方法

では、膝靭帯損傷かどうかは、どのように診断されるのでしょうか。各医療機関での膝靭帯損傷の診断方法は、次のとおりです。
- レントゲン検査
- MRI検査
いずれかの方法で、医師は膝靭帯損傷かを判断していきます。それぞれの詳細をチェックしていきましょう。
レントゲン検査
レントゲン(X線)検査では、あえて膝に器具などでストレスをかけ、撮影をおこないます。
そのうえでストレスをかけていない通常時のレントゲン写真と比較し、靭帯損傷の有無を確かめます。
MRI検査
MRI検査は、膝靭帯損傷の診断に非常に有効です。MRI(核磁気共鳴画像)検査では、強い磁気が働いた筒内に入り、体の断面図を撮影していきます。
膝靭帯のみならず、半月板や骨、軟骨などさまざまな組織の診断もあわせて可能になる点が特徴です。
膝靭帯損傷の治療方法

膝靭帯損傷の治療には、いくつかの方法が用いられます。具体的には、次の3つがあります。
- 保存療法
- 手術療法
- バイオセラピー
症状の程度などによって適切な治療法は異なります。それぞれの詳細をチェックしていきましょう。
保存療法
保存療法とは、手術などで直接的に措置を施すのではなく、自然治癒や緩和を目的とする治療法を指します。
膝靭帯損傷を保存療法で治療する場合は、サポーターを装着したうえでまず可動域訓練を実践します。膝に負担をかけないよう安静にしつつ、筋力低下を抑えることが狙いです。
手術療法
膝靭帯損傷を手術療法で治療するときは、靭帯修復術、もしくは再建術いずれかの方法で手術を施します。前十字靭帯損傷などの治療には、主に保存療法よりも手術療法が用いられる傾向にあります。
手術をしたあとは最大で半年ほど時間をかけてリハビリをおこなっていきます。
バイオセラピー
バイオセラピーは、自身やほかの方の細胞や血液に由来する成分を利用し、損傷した組織の修復に活かす治療法にあたります。再生医療とも呼ばれ、保存療法でも手術療法でもない、新しい治療法の一つとして近年注目されています。
代表的なバイオセラピーには、PRP療法が挙げられます。PRPとは多血小板血漿のことで、そのなかには血小板・白血球由来の成長因子が含まれます。細胞を培養し、病気治癒につなげていきます。
【ランキング】膝に不安を感じる方は、専門のクリニックを受診しよう
少しでも膝に不安のある方はクリニックの受診を検討しましょう。ここではおすすめのひざ専門クリニックを紹介しています。
1位:ひざ関節症クリニック
手術や入院不要で治療がおこなえるため、現状の生活スタイルを維持したまま健康的な膝間接を手に入れられるメリットがあります。
切らない膝治療の実績は22,900例以上にのぼり、体への負担が少ない治療方針を掲げている点も安心材料の一つです。
また、膝治療に用いる「培養幹細胞治療」は、医学論文にて痛みの軽減効果が報告されている先進的な治療法になります。
痛みの根元へアプローチしながら組織修復を促せるため、スポーツができる健康的な膝間接を手に入れたい方は
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
メジャーリーガーが受けた再生医療を取り扱っており、最先端の治療メソッドで膝間接の痛みを根本解決できる強みがあります。
さらに治療後は熟練スタッフが付きながら、怪我の再発防止へ向けたリハビリも継続可能です。
他院の場合は手術後のケアを自身でおこなうケースも多いため、専門家指導のもとでスポーツができる体の基礎を形成していけるのは大きなメリットになります。
本記事のチェック項目に多く該当した方は、無料相談を活用して膝関節の早期解決を目指しましょう。
半月板損傷にも注意

膝が継続的に痛むとき、常に膝に違和感があるときは、半月板損傷の可能性もあるため注意が必要です。重要なポイントを整理していきましょう。
半月板損傷を併発する可能性もあり
膝靭帯損傷に陥った際には、半月板損傷を併発する場合もあります。たとえば膝の靭帯が切れた状態で放置すると、不安定が残ったままで、半月板損傷につながるケースがみられます。
半月板損傷とは、膝関節のなかにある半月板が欠けたり、亀裂が入ったりすることを指します。半月板損傷になると膝が痛むのみでなく、曲げ伸ばしの運動時に引っかかりを感じることが増えていきます。
さらに症状が進行すると、水が溜まることもあるため注意が必要です。膝に溜まる水は関節液にあたります。激痛のあまり歩行困難に陥ることもあるため、半月板損傷の併発には十分に注意したいところです。
放置せず早めに医療機関で診療を受ける
半月板損傷の併発は、膝靭帯損傷の症状を放置すると起こりやすくなります。
したがって頻繁に膝痛を感じるようになったときは、早めに医療機関を受診するようにしましょう。そもそも、半月板損傷の発症には至らなかったとしても、膝痛の放置は最悪の場合歩行困難にもつながるため危険です。
膝靭帯損傷の予防・改善策

膝靱帯損傷は、予防できるに越したことはありません。予防・改善策としては、次のことが挙げられます。
- 運動前後にストレッチをする
- 太ももの筋肉を鍛える
- 神経筋トレーニングをする
いずれも日常的に実践したい重要なことのため、それぞれ詳細をチェックしていきましょう。
運動前後にストレッチをする
スポーツが原因で膝靱帯損傷に陥ることは多いです。そのためスポーツのような激しい運動をする際には、前後にストレッチをおこない、体をよくほぐす必要があります。
運動によって起こる無理な膝のひねりが、膝靱帯損傷のような怪我につながります。長くスポーツを続けていると、ストレッチのような基本はつい省略してしまうことも多くなりますが、基本だからこそ常に大事にしたいところです。
太ももの筋肉を鍛える
膝靱帯損傷にならないためには、太ももの筋肉を鍛えることも重要です。
太ももの筋肉トレーニングをおこなって鍛えれば、膝の安定性が高まります。安定性が高まれば必要以上に膝に負担をかけることも少なくなるため、膝靱帯損傷をはじめとした膝の疾患予防につながるでしょう。
神経筋トレーニングをする
膝靱帯損傷は、膝が受ける外からの衝撃が原因の場合も多いため、膝の動揺性を抑える対策として神経筋トレーニングもおすすめです。
膝関節は、足関節と股関節に挟まれるかたちで存在します。したがって両方の関節からも影響を受けやすく、膝の動揺性を抑えるには膝を鍛えるのみでは十分でないと考えられるでしょう。
そのためトレーニングをおこなう際には、足関節・股関節・膝関節と連動するかたちで鍛えられる神経筋トレーニングが望ましいといえます。
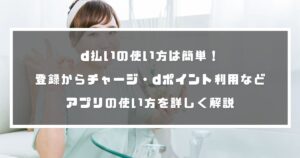
まとめ

膝靱帯損傷は、主にスポーツなどの激しい運動や交通事故が原因となって起こります。症状が重い場合は歩行困難に陥るケースもあるため、まずは症状や治療法についてよく理解し、膝靱帯損傷にならないための対策をすることが大切です。
また、普段から膝が痛む方は、膝の健康状態チェックを積極的に利用してみてください。特に継続的に痛みがある場合は膝靱帯損傷の可能性があるため、その場合はすみやかに医療機関を受診しましょう。
※本記事の情報は2022年12月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。