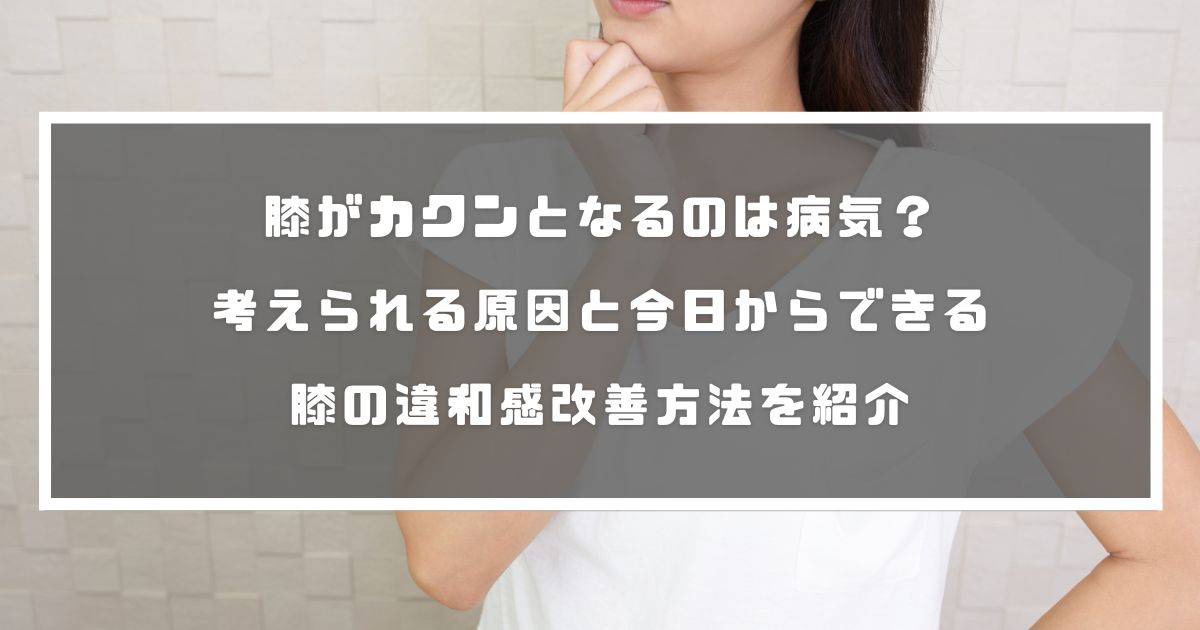膝がカクンとなる症状に悩んでいる方は、放置をせずに痛みや違和感の原因を追及する必要があります。
症状を自覚している方の大半が「半月板損傷」「靭帯損傷」などの怪我をしている傾向が高いです。一方、とくに怪我をしたわけでもないのに膝がカクンとする症状に悩む方もいます。
膝がカクンとなる症状は、放置するのが危険なため、早めに対処する必要があります。この記事では、膝がカクンとなる原因・治療法・改善方法・注意点を紹介します。
膝がカクンとなるのは病気?何科を受診すればいい?

膝がカクンとなる違和感・痛みは、関節や筋肉への負担が主な原因といわれていますが、さまざまです。
一時的な症状で、時間の経過とともに自然治癒するケースがある一方で、「変形性膝関節症」のような病気(怪我)である場合も考えられるため、正しく原因を把握しましょう。
膝の痛みには様々な原因が考えられる
膝がカクンとなる原因は、さまざまですが、主に次の原因が考えられます。
- 半月板損傷・靭帯損傷などのケガの後遺症
- 加齢による身体機能の衰え
- 肥満・O脚による膝への過度な負担
- 軟骨のすり減りが原因となる病気「変形性膝関節症」
膝の関節が痛む・違和感を感じる原因には、膝の関節に加わるダメージを最小限に抑える機能が正常でない可能性が高いです。
とくに、「変形性膝関節症」は、初期症状で膝がカクンとなるようになり、その後、痛み・炎症による腫れと次第に強い症状が出現しますので早期治療が必要です。
膝の関節の仕組み
膝の関節は、主に次の3つの骨が組み合わさって出来ています。
- 大腿骨(だいたいこつ):太ももの骨
- 脛骨(けいこつ):すねの骨
- 膝蓋骨(しつがいこつ):大腿四頭筋(だいたいしとうきん)と膝蓋腱(しつがいけん)に支えられているお皿
歩く・走る・ジャンプするなど体を動かすときには、いつも膝を曲げ伸ばししますが、それは、脛骨の上を大腿骨が前後にすべり転がることで機能します。
骨や筋肉が激しく動いたときに、身体への負担を最小限に抑えるため、衝撃を吸収する役割を担うのが「軟骨」と「半月板(はんげつばん)」です。
「軟骨」は、膝関節を形成する3つの骨の表面をクッションのように覆い、高い弾力性で膝関節の衝撃を最小限に抑えます。
「半月板」は、大腿骨と脛骨の間にあり、膝関節に加わる衝撃を吸収する役割を担っています。
膝の関節は、人間が生活するうえで、必要な動作に深い関わりがあり、毎日繰り返し使う部位です。膝の関節内で起こりうる摩擦や衝撃の負担を減らすためには、それぞれの機能が健康で正常に機能する必要があります。
膝から音がする理由
膝から音がするときは、どのような音がするかによって理由が異なります。
- ポキポキと音が鳴る
- ミシミシ・ギシギシと音が鳴る
まず、ポキポキと音が鳴る場合、クラッキングと呼ばれるもので、指が首を自身でポキッと鳴らすときに出るのと同じ原理です。
本来、膝の関節は、軟骨を保護しながら骨同士の摩擦が生じないようにするための「関節液」と呼ばれる液体で覆われています。
しかし、前触れもなく膝の関節を動かすと、関節液が圧迫されて空洞が生じるため、空洞にできた気泡が破裂する音としてポキッとなると考えられています。
一方、ミシミシ・ギシギシと音が鳴る場合、変形性膝関節症の可能性が高いです。
軟骨同士の摩擦が生じているため、早期治療・改善をしなければ、痛み・炎症・膝の形の変形など悪い症状へと悪化していきます。

膝の違和感は整形外科を受診しよう
膝に違和感を感じた場合、変形性膝関節症の病気である可能性があるため、まずはレントゲンを撮ってもらえる「整形外科」を受診してください。
変形性膝関節症の場合、早期発見・早期治療が何よりも大切ですので、レントゲン検査で半月板の損傷を見てもらう必要があります。
強い痛みが伴う場合、受診した整形外科から大きな大学病院を紹介してもらえるため、MRI検査で半月板・靭帯を念入りにチェックしてもらえます。
ただし、患部で3mm以下の異常が発生している場合、MRI画像では写らない可能性が高いです。
考えられる膝がカクンとなる原因と治療方法

膝がカクンとなる原因は、主に次の4つが考えられます。
- 筋力の低下
- 膝の亜脱臼
- 半減版損傷
- 変形性膝関節症
それぞれの原因によって引き起こされる症状と治療方法について解説します。
筋力の低下
筋力の低下は、膝がカクンとなる原因のひとつです。
筋力の低下は、加齢や運動不足などさまざまな理由によって起こりうる問題ですが、体重を支える筋肉が衰えることで、膝の関節に必要以上の負担がかかってしまいます。
膝の関節に負担がかかると、半月板や軟骨の機能が弱くなってしまうため、膝に痛み・違和感を感じる症状を引き起こします。
筋力の低下は、基本的に食事や運動によって改善できるため日常生活を改めることから初めて変化を実感してください。
膝の亜脱臼
膝の亜脱臼は、膝がカクンとなる原因のひとつです。
膝の亜脱臼は、主に10代の女性に多く見られる障害で、本来は大腿骨のへこみ部分に膝蓋骨があるべきにも関わらず、膝蓋骨(お皿)のいちがズレてしまうことを指します。
膝蓋骨の位置がズレてしまうことによって、歩くときに膝の内側が痛んだり、膝が抜けそうになる不安を感じたり、カクンとなる症状を引き起こします。
膝の亜脱臼は、膝蓋骨の位置を正常に戻す必要があるため、整形外科でのリハビリ、サポーターの装着などで改善を試みてください。
半月板損傷
半月板損傷は、膝がカクンとなる原因のひとつです。
半月板損傷は、膝を動かすときに使う3つの骨へのダメージを吸収する役割を持つ半月板に、亀裂が生じたり、欠けたりすることを指します。
激しい運動、加齢、肥満などさまざまな理由で半月板に一定以上の負荷がかかったとき、痛みや引っ掛かりの症状を引き起こします。
症状が悪化すると、膝の関節に関節液が溜まって、激痛により歩行困難な「ロッキング」を引き起こしかねません。
半月板損傷は、軽度の場合であれば休息や膝の関節の固定などで自然治癒が見込めますが、重度の場合は半月切除術や修復術の外科的治療を検討してください。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、膝がカクンとなる原因のひとつです。
変形性膝関節症は、膝の関節の負担を減らすために機能する軟骨の質が下がることで、少しずつすり減ることを指します。
平地の歩行は問題なくても、階段の上り下りや正座で膝の痛みの症状を引き起こします。
現時点で、変形性膝関節症の原因である軟骨を増やす・若返らせるための治療法はありません。
体重のコントロール、筋力トレーニング、サポーターの装着、生活習慣の改善等で膝の関節への負担を減らして、症状の進行を遅らせる方法を試してください。
今日からできる!膝の違和感を改善する方法3選

膝の違和感を感じている方は、次の3つの改善方法を試してみてください。
- 日常的な運動で筋力アップ
- 大腿四頭筋のストレッチ
- 膝の曲げ伸ばしストレッチ
それぞれの改善方法が効果的な理由と具体的なやり方を解説します。
日常的な運動で筋力アップ
日常生活で運動量を増やせるように工夫すると、膝の違和感を引き起こしている筋力低下を緩和させることが期待できます。
【日常生活の運動量を増やす方法】
- 買い溜めをしない:こまめに買い物をして歩く時間を増やす
- 掃除をする:拭き掃除をすれば足腰を鍛えられる
- 階段を使う:エスカレーター・エレベーターの利用頻度を減らす
【日常生活の運動量を増やす方法(プラスα)】
歯磨きや電話中、テレビをみているときなどの隙間時間を使って、次のエクササイズを取り入れてみましょう。
- 爪先立ち
- 踵の上げ下げ
- スクワット
- 屈伸
ジムや1日に30分ほどのウォーキング・ランニングを取り入れれば、効果を実感しやすいです。
しかし、仕事や家事に追われている方は、ジムやスポーツの趣味をはじめることは難しいのが現状です。
そこで、日常生活の中に運動を組み込むことで、「塵も積もれば山となる」のような効果を発揮することが期待できます。
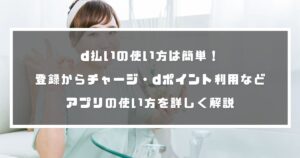
大腿四頭筋のストレッチ
大腿四頭筋のストレッチによって可動域を広げてあげることで、筋力低下や筋力硬直による膝の関節の違和感を軽減させることが期待できます。
大腿四頭筋は、太ももの前側についており「大腿直筋」「内側広筋」「中間広筋」「外側広筋」の4つで構成されている筋肉です。
半月板損傷や靭帯損傷をしたとき、膝の関節の負担をカバーするのが大腿四頭筋の役割であるといわれているため、ストレッチでほぐすほど膝の痛みの負担を減らせます。
【大腿四頭筋ストレッチの手順(仰向けの体勢)】
- 仰向けになって、左膝を直角以上の角度で曲げる
- 右足は伸ばした状態で床からこぶし2個分ほどの高さまで持ちあげる
- 2の状態で5秒間キープする
- 右足を床に戻して2〜3秒休憩する
- 2〜4を10回ほど繰り返す
- 2〜5の流れを左右の足を入れ替えて同様におこなう
- 2〜6を1セットとカウントして1日3回おこなう
【大腿四頭筋ストレッチの手順(座った体勢)】
- 膝立ちの体勢を作る
- 右足の膝が直角になる程度、前に出す
- 左手で左足の踵を桃に引き寄せるように意識して折り曲げる
- 3の状態で10秒キープする
- 1〜4の流れを左右の足を入れ替えて2〜3回くりかえる
【大腿四頭筋ストレッチの手順(椅子に座った体勢)】
- 背もたれにもたれずに浅く腰掛ける
- 少し前屈みになった状態で、片足のみまっすぐ伸ばして踵をつける
- まっすぐ伸ばした方の足をこぶし2個分ほどゆっくりと床から高くあげる
- 3の状態で5秒間キープする
- 高くあげた方の足を床に戻して2〜3秒ほど休憩する
- 2〜5を10回ほど繰り返す
- 2〜6の流れを左右の足を入れ替えて同様におこなう
- 2〜7を1セットとカウントして1日3回おこなう
大腿四頭筋ストレッチをするときは、太ももの前側の筋肉が伸びていることを意識してみてください。
膝の曲げ伸ばしストレッチ
膝の曲げ伸ばしストレッチによって、適度に膝の関節を動かしながら可動域を広げてあげることで、膝の違和感の症状を和らげることが期待できます。
膝の関節が痛むと、安静にしようと下半身を動かさないようにすることが多いですが、安静にする期間が長くなると、膝の可動域がますます狭くなり、症状を悪化させかねません。
症状が重症化すると、初期段階よりも「立つ」「座る」「歩く」などの動作がスムーズにできなくなるため、膝の曲げ伸ばしストレッチで可動域を広げることが大切です。
【膝の曲げ伸ばしストレッチの手順(仰向けの体勢)】
- 仰向けになって、片足の太もも裏を両手で抱える
- 反動をつけずに、痛みの出ない程度の強さで足を軽く胸の方に引き寄せる
- 1〜2を10回ほど繰り返す
- 1〜3を左右反対の足にして同様におこなう
- 1〜4を1セットとカウントして1日3回おこなう
【膝の曲げ伸ばしストレッチの手順(座った体勢)】
- 膝を伸ばした状態で座る
- 片方の踵の下にタオルなどを滑りやすい布を敷く
- タオルを敷いた方の足の踵を滑らせながら手前に引き寄せる
- 膝の痛みが出ないところまでしっかりと曲げる
- 踵をゆっくりと滑らせながら伸ばし切る
- 1〜5を10回繰り返す
- 1〜6の動作を反対の足で同様におこなう
- 1〜7を1セットとカウントして1日3回おこなう
エクササイズではなくストレッチのため、ゆっくりと可動域を広げる意識で曲げ伸ばししてみてください。
ひざの違和感がある場合の注意点

膝がカクンとなったり、違和感・痛みを感じたりしているときの注意点は、次のとおりです。
- 痛いのに無理に動かそうとしない
- 違和感や痛みを放置しない
- 膝にひどい痛みがある場合はすぐ病院を受診する
それぞれの注意点について解説します。
痛いのに無理に動かそうとしない
膝に痛みがあるときは、膝の関節が炎症を起こしている可能性が高いため、無理に動かそうとすると、さらに摩擦が生じて痛みが悪化する可能性が高いです。
痛みがあるときは、できるだけ膝の関節を動かさなくていいように、平地を歩いたり、階段の代わりにエスカレーター・エレベーターを使ったり安静を優先してください。
また、サポーターで膝の関節を固定することで、ダメージを受けた軟骨・半月板の代わりに膝関節の保護を助けます。
膝の痛みは、「摩擦」が原因ですので、動かすことで引き起こされる摩擦を最小限に抑えられるように、「安静にすること」と「固定すること」を意識してみてください。
違和感や痛みを放置しない
膝の違和感や痛みは放置することなく、原因を追求したり、改善方法を試したりして、早期発見・早期回復を試みることが大切です。
とくに、スポーツをしている場合、違和感や痛みを感じているにも関わらず、負荷をかけるようなトレーニングを続けてしまうと選手生命への悪影響も懸念されます。
膝の違和感や痛みが必ずしも大きな病気とは限りませんが、原因が何かをはっきりさせることで、その後の治療や改善方法を適切に選択できます。
そして、少しでも早く症状を自覚して、改善しようとすると回復までの期間を短くできるため、膝の関節の異変を放置しないでください。
膝にひどい痛みがある場合はすぐ病院を受診する
「歩けない」「激痛を感じる」など日常生活に大きな支障をきたすほどひどい痛みがある場合は、すぐに整形外科を受診して検査をしてもらってください。
整形外科を受診すると、レントゲン検査や、より精密なMRI検査が受けられる大きな病院を紹介してもらえます。
半月板損傷の場合は、外科手術をして治さなくてはならないケースもあるため、早期治療で患部の症状を最小限に抑えられます。
病院に行かずにセルフケアをして悪化してしまった場合、後遺症が残るリスクがあるため、軽視することなく、専門医からの診察を受けることが賢明です。
【ランキング】ひざの違和感を感じたら専門クリニックの受診がおすすめ
ひざの違和感を感じたら真っ先にクリニックの受診を検討しましょう。ここではおすすめのひざ専門クリニックをご紹介します。
1位:ひざ関節症クリニック
入院、切開不要のひざ治療を提供しており、ライフスタイルを維持しながら痛みや違和感を改善できるメリットがあります。
開院してからの治療実績は2万例以上にのぼり、全ドクターがひざ間接を熟知した専門医である点も安心です。
再生医療には複数の選択肢が用意されているため、ひざがカクンとなる症状を改善したい方はぜひチェックしてみましょう。
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
とくにトップアスリートが受けたことでも話題の注入治療は、ひざ間接の組織修復とともに変形の遅延効果が期待できる先進医療です。
ヒアルロン酸注射の場合は1週間〜2週間の短期的な効果で終わりやすいですが、シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)の注入治療は6か月〜1年間の持続性が期待できます。
MRIを活用した安心の診断体制も整えているため、まずは無料相談を活用して症状を伝えてみましょう。
まとめ

この記事では、膝がカクンとなる原因や改善方法について解説しました。
膝の関節は、生活をするうえで必要な機能がたくさん備わっているため、負荷がかかりすぎないように、エクササイズによる筋力維持やストレッチによる可動域の拡大が大切です。
無理にジムに行ったり、体を動かすための時間を作ったりしなくても、日常生活の中で運動量を増やす方法もあるため、少しの工夫で膝の関節トラブルを抑えることができます。
さらに、膝の関節の違和感・痛みを感じたときは、少しでも早く対処すると、症状の重症化を防ぎ、回復期間を短くできます。
医療機関を受診するのであれば、レントゲン検査が受けられる「整形外科」を利用して、膝の関節トラブルを解決しましょう。
※本記事の情報は2022年12月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。