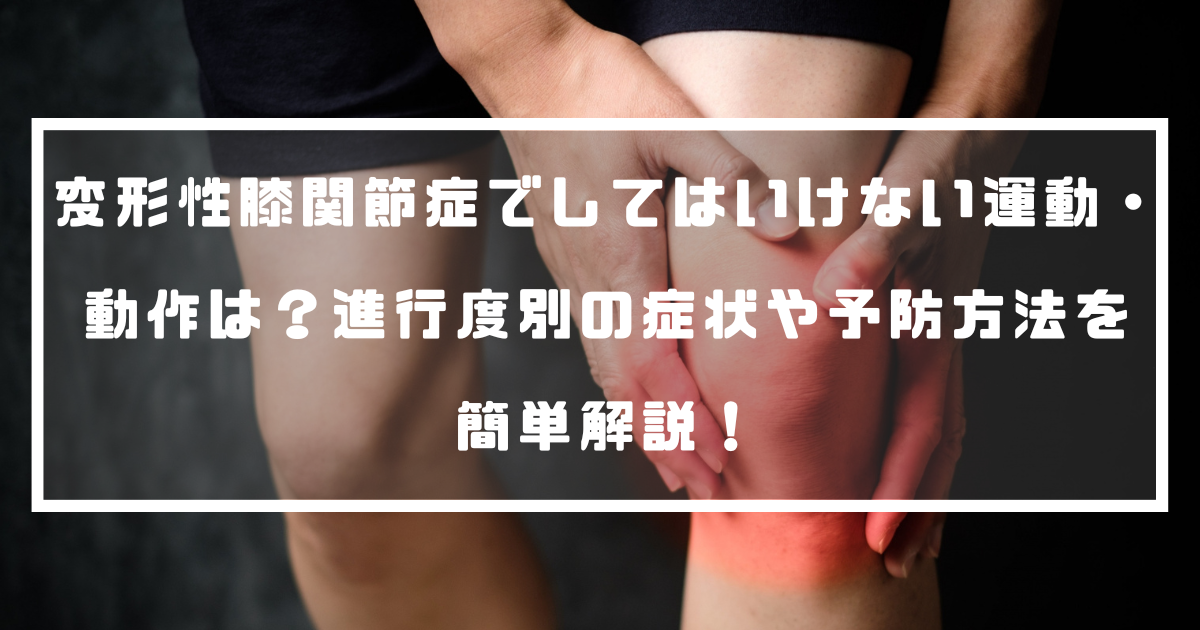年齢を重ねるとひざの痛みに悩む方も多いです。中高年の方は変形性膝関節症の症状が見られる方も多いでしょう。変形性膝関節症には、してはいけない運動や動作があるため日常生活でも注意が必要です。
そこで、変形性膝関節症でしてはいけない運動や動作、すぐに治療を受けるべき症状を紹介します。変形性膝関節症の予防法も紹介するので、ひざの痛みを感じている方は参考にしてください。
変形性膝関節症でしてはいけない運動・動作

変形性膝関節症でしてはいけない運動や動作を繰り返すと、病気が治らずに治療も長引きます。早く改善するためにも、ひざへの負担になる動作をしていないか見直すことが大切です。
まずは、変形性膝関節症でしてはいけない運動や動作を紹介します。
正座
変形性膝関節症でしてはいけない運動や動作として、正座をする、しゃがむといったひざを大きく曲げる動作が挙げられます。
たとえば、和室で生活している方は、正座や和式トイレの利用、布団を畳んで収納するなどの動きに注意が必要です。和室で生活している方は、無意識にひざへ大きな負担をかけている可能性があります。
座る際には椅子を利用する、洋式のトイレを利用する、布団ではなくベッドにするなど、正座をしたりしゃがんだりする動きを減らしましょう。
また、ストレッチは変形性膝関節症の方に最適な運動ですが、特定の動きに注意が必要です。ストレッチのなかにはひざを大きく曲げて正座をしたり、足を組んだりする姿勢もあります。変形性膝関節症になったら、正座やしゃがむ姿勢になる動きはおこなわないことが大切です。
重い荷物を運ぶ
重い荷物を運んだり、荷物の積み下ろしの動もひざに負担がかかります。そのため、農業や運送業、建設業など、職業柄重い荷物を運び、積み下ろしをする業種の方は注意が必要です。仕事や日常生活のなかで重い荷物を運ぶ場面がある場合、キャスター付きのスノコやキャリーバッグなどを利用します。
なお、利用するキャスターは回転するものだと操作しやすいでしょう。ひざに負担をかけずに重い荷物が運べるアイテムを活用して、荷物を持ち上げる動作は避けることが大切です。
さらに、日頃リュックで重い荷物を運ぶケースが多い場合は、リュックの背負い方も工夫する必要があります。リュックの紐がゆるくなっていたり、腰の部分でリュックを背負ったりすると姿勢が前に傾きます。
姿勢が前に傾くと内股になり、ひざが変形してO脚になりやすいです。O脚になるとひざの内側に負担がかかり、内側部分の軟骨がすり減って変形性膝関節症が悪化します。リュックで重い荷物を運ぶことが多い方は、紐をしっかりと締め、背中にリュックが密着するように調整しましょう。
痛みがある中での運動
変形性膝関節症によってひざが痛むにも関わらず無理に運動をすると、炎症が悪化して症状が進行するリスクがあります。さらに、運動の際に無意識でひざをかばう動きをすると、正しい姿勢で運動がおこなえず、ひざへの負担が大きくなるため注意が必要です。
また、ジムに通いトレーニングを習慣にしている方は、決められたメニューで運動をすることが多いです。変形性膝関節症でひざが痛いなか、無理をして同じメニューに取り組もうとすると、症状が悪化することがあります。
運動が習慣になっていても、無理をして同じ運動をおこなう必要はありません。ひざに痛みを感じる運動や動きは休むことが大切です。
過度なトレーニング
過度のトレーニングにより、全身の筋肉のバランスが変わったり、痛みをかばうようにしてトレーニングをしたりすることで、ひざに大きな負担をかけるリスクがあります。トレーニングをしたい場合は、ひざの関節を動かさないようなメニューのみをおこないましょう。
ひざへの負荷が大きいスポーツ
変形性膝関節症がしてはいけない運動として、ひざに負担がかかるスポーツも挙げられます。急に止まる・動くといった動作をすると、ひざへの負担が大きいです。
たとえば、野球やバスケットボール、サッカー、テニスなどの球技は、急に止まる・動きだすというの動作が多いため注意が必要です。さらに、日常生活でも、急に止まる、切り返す、足を踏み込むなどの動作はおこなわないようにしましょう。
変形性膝関節症とは

変形性膝関節症は、年齢を重ねると発症する確率が高い病気です。変形性膝関節症の症状は、ひざに水が溜まる、痛みが生じるなどが挙げられます。
軟骨がすり減って炎症を起こし痛みを感じる病気
年齢を重ねるとひざの軟骨の弾力性がなくなり、軟骨がすり減って関節が変形します。ひざ関節に炎症を起こし、動いた際に痛みを感じるようになり、悪化すると慢性的に強い痛みを感じるため生活に支障が出ることが多いです。
また、変形性膝関節症の主な原因は軟骨の老化によるものですが、肥満や遺伝子も関連してることがわかっています。
さらに、骨折や半月板の損傷、靭帯損傷などの外傷や、化膿性関節炎の後遺症でも発症するケースがあります。
変形性膝関節症の進行度別の症状

変形性膝関節症になると、ひざに水が溜まったり、炎症により痛みを感じたりすることが一般的です。たとえば、椅子から立ち上がる、歩き始めるといった動作をおこなった際に痛みを感じ、休むと痛みがなくなります。
変形性膝関節症の症状が悪化すると、正座をする、階段を昇り降りする動きが困難になることが特徴です。
症状が進行すると、ひざが伸びなくなり、変形が目立つなどで、歩行が困難になります。変形性膝関節症は、徐々に進行して症状も重くなる病気です。変形性膝関節症の初期症状、中期症状、末期症状を紹介します。
【初期】立つときや階段でひざに痛みを感じるがすぐ治る
変形性膝関節症の初期症状は、起床時に足を動かした際、ひざの動きにくさを感じます。布団やベッドから起き上がる、歩き出すといった動作をする際に、ひざがこわばるほか、痛みを感じることも多いです。
しかし、起床後、身体を動かしているとひざのこわばりや痛みが取れるため、変形性膝関節症の初期症状だと気づくことは少ないです。
初期症状が出てから少し悪化すると、階段の昇り降りや正座、急に立ち止まる・歩き出す・方向転換をするなどの動きで痛みを感じるようになります。
【中期】痛みが治らず日常生活に支障をきたす
変形性膝関節症の初期症状では一定時間休んでいるとひざの痛みが治りますが、中期になると少し休んでもひざの痛みが消えません。ひざの痛みが強くなり、正座やしゃがむ、階段を昇り降りするといった動きが辛くなります。
ひざ関節内部の炎症が進行するため、ひざが腫れたり熱を帯びたりも多いです。ひざの関節液の分泌量が増えると、脚の変形が目立ち、軟骨がすり減って摩擦が大きくなり、歩く際にひざから音が鳴ります。
【末期】安静にしていても痛みが続く
変形性膝関節症の末期症状は、関節の軟骨が少ない状態になり、骨同士がぶつかります。変形性膝関節症の末期になると、初期や中期の段階で出ていた症状が悪化して、歩行や座る、しゃがむといった動きは困難になります。
動作や行動が制限されるため、日常生活にも影響が出て精神面にも悪影響を及ぼすことが多いです。
変形性膝関節症の原因

変形性膝関節症は、加齢や肥満が原因で発症するケースが多いです。また、変形性膝関節症は遺伝することもわかっています。なぜ変形性膝関節症になるのか、主な原因を紹介します。
加齢・老化
変形性膝関節症の主な原因は、加齢や老化です。年齢を重ねると、ひざに圧力がかかって骨や軟骨への負担も積み重なります。軟骨は関節のクッションや潤滑剤ですが、すり減って変形性膝関節症が悪化することで、軟骨がなくなるケースもあります。
ひざの軟骨がすり減って薄くなったり、なくなったりすることで、変形性膝関節症の症状が現れます。変形性膝関節症が悪化すると、軟骨を被っていた骨への負担が大きくなり、骨が増殖することで棘状の骨、通称「骨トゲ」ができることもあります。
また、加齢や老化により徐々に筋力も弱くなることが一般的です。ひざを支えている筋力も弱くなり、ひざの周辺の筋肉がカバーしていた体重の負担が骨や軟骨にかかるため、骨や軟骨の組織がすり減って変形性膝関節症を悪化させます。
とくに変形性膝関節症を発症してからひざが痛いと感じる方は、運動や大きな動きを避けるようになるでしょう。
ただし、運動を避けることで更に筋力が衰えて、症状を悪化させる悪循環に陥ることが多いです。数十年間のひざへの負荷、筋力低下など、加齢や老化が変形性膝関節症の発症や悪化の主な原因といわれています。
肥満
肥満が原因の場合は、年齢を問わず発症する可能性があります。とくに、急に体重が増えるとひざに負担がかかるため注意しましょう。体重1kgあたりのひざへの負担は、歩行時には体重の約3倍、階段を昇り降りする際には約7倍といわれています。
肥満によりひざが痛いと感じるときは、無理のない程度にダイエットをしましょう。肥満によってひざが痛くなると運動やトレーニングはおこなわない方が多いですが、運動不足でさらに肥満が悪化するという悪循環にならないよう注意が必要です。
ひざの負担が大きい動作
普段からひざの関節に負荷がかかるような生活をしている方、仕事に就いている方は、変形性膝関節症になりやすいです。しゃがむ作業が多い、重い荷物を積み下ろしをする、荷物を運ぶ、長時間立ったままで仕事をしている方は、ひざに大きな負担がかかります。
また、急に止まったり走ったりするスポーツをおこなっている方も、ひざへの負担が大きいです。仕事や趣味によって、変形性膝関節症を発症して、症状が進行することがあります。
遺伝
変形性膝関節症の原因のひとつとして、遺伝も挙げられます。変形性膝関節症に関係する遺伝子が発見されており、特定の遺伝子を持っていると発症する確率は1.6倍になるといわれています。
他のひざの病気・怪我
変形性膝関節症は、怪我や病気など原因が特定されない一次性と、半月板や靭帯の損傷、捻挫やリウマチ、ひざの骨折など原因が特定できる二次性に分けられます。ひざの病気や怪我をしている方は、二次性の変形性膝関節症を発症しやすいです。
変形性膝関節症にならないための予防

変形性膝関節症は、食生活を見直したり、正しい方法で筋肉を鍛えることで予防できます。そこで、変形性膝関節症にならないようにするため、また、治療後に再発させないための予防法を紹介します。
体重管理をする
体重管理は、変形性膝関節症の痛みを緩和したり予防したりするだけではなく、健康を維持するためにも大切です。摂取するカロリーを抑えながら、1日3食しっかりと食べましょう。
主食・主菜・副菜を用意して、バランス良く栄養を摂ることがポイントです。基礎代謝を上げるためのミネラルやビタミンを含んでいるキノコ・野菜・海藻などの食材を多めに取り入れましょう。変形性膝関節症を予防するためには、肥満につながる脂肪が多いものや甘いものを摂らないことも重要です。
また、時間をかけてゆっくりと食べることで満腹感を得やすいため、噛む回数を増やしましょう。過度なダイエットはせず、食事の内容を変える必要があります。
ひざに負担をかける動作はしない
変形性膝関節症を予防するためには、前後左右のどこかに体重をかけないことが大切です。身体の芯が真っ直ぐになっておらず傾くと、ひざへの負担が大きくなります。
加えて、ほかの部位のゆがみにもつながるため、顔と背骨が垂直になるように意識しましょう。階段では一段ずつゆっくり昇り降りしたり、手すりをつかむ方の手に体重をかけたりすることがポイントです。
階段を昇るときは、手すりを利用して痛みがない足から上げ、痛みがある足は同じ段に乗せます。また、階段を降りる際は手すりを利用して、痛いほうの足を先に降ろして、痛くないほうの足を同じ段に乗せます。
床に座らなければならない場合は、正座やあぐら、足を横にする座り方はしないことが大切です。どうしても正座をしなければならない場合は、ふくらはぎとお尻の間に座布団やクッションを挟みましょう。
椅子から立ち上がる際には、机や椅子に手をつき、頭を前に出してから身体を前に出して立ち上がります。椅子に座るときよりも、立ち上がる際はひざに負担がかかりやすいです。椅子から立ち上がるときは、足を前に出して体重を乗せないことを意識しましょう。
スポーツ・運動の前はストレッチを行う
変形性膝関節症を予防するためには、体重管理が重要です。体重管理にはスポーツや運動でカロリーを消費する必要があります。また、筋力が衰えることにより変形性膝関節症が進行するのを防ぐためにも、適度にスポーツや運動をする方法が有効です。
ただし、スポーツや運動する前はストレッチを忘れないようにしましょう。身体を動かす準備をせず、急にスポーツや運動をおこなうと、変形性膝関節症の原因になる怪我をする可能性があります。
スポーツや運動の前にストレッチで筋肉をほぐして、血行を良くすることで、筋肉の温度が上昇します。結果、弾力性や柔軟性が向上して関節の可動域が広くなり、怪我の予防につながるためです。
なお、これまで少しも運動していなかった方が急に運動を始めても長続きせず、慣れない動作で変形性膝関節症を悪化させる可能性があります。
スポーツ・運動は、無理なくおこなうことが大切です。水泳や軽いウォーキングなどの有酸素運動と、筋力トレーニングといった無酸素運動を両方おこなうと効果をやすいでしょう。
下半身の筋肉を鍛える
日常生活のなかで、ひざの痛みを感じない程度にストレッチをしたり軽い運動をしたりなど、下半身の筋肉を鍛えることが大切です。
とくに、太ももの筋肉を鍛えると、ひざの関節が安定して痛みを軽減する効果が期待できます。ひざの関節周辺の筋肉を柔らかくすることで、ひざを曲げたり伸ばしたりする動作もおこないやすくなるでしょう。
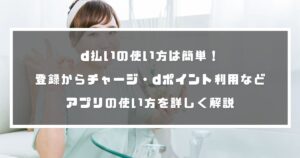
変形性膝関節症のケア・治療法

変形性膝関節症は、正しいケアをして適切な治療を受けることで、症状を緩和させられる可能性が高いです。そこで、自宅でできるケアと、病院での主な治療法を紹介します。
膝を温める
ひざの関節が冷えて筋肉や腱がこわばり、固まったり血流が悪くなったりすると、筋肉疲労を起こします。ひざの関節は冷やさないように、しっかり温めることが大切です。
入浴で血行を良くするほか、膝用サポーターを利用しましょう。ただし、ひざの関節が炎症を起こして腫れている場合は、温めずに冷やす必要があります。
リハビリ
変形性膝関節症のリハビリは、筋肉を伸ばすストレッチや、ひざの曲げ伸ばしなどをおこないます。ひざにテーピングをしたうえで、正しい方法でリハビリをすれば、弱った筋肉を活性化できます。
また、リハビリで歩くことによってひざの関節の安定性を高めて、筋力アップにもつながるでしょう。
薬物療法
変形性膝関節症の薬物療法は、消炎鎮痛剤の内服薬や、湿布を貼る方法が挙げられます。また、関節内注射でヒアルロン酸を注入する方法もあります。ヒアルロン酸注入は、ひざの軟骨を保護して軟骨の修復や痛みを抑制する効果が期待できる方法です。
ヒアルロン酸は、関節の内部にある関節液の成分のひとつです。変形性膝関節症になると炎症が起こり、関節液が増えるため、ヒアルロン酸が分解され、結果としてヒアルロン酸の濃度が低くなります。関節液の弾力や粘りがなくなり、変形性膝関節症が悪化します。
薬物療法のヒアルロン酸注入は、関節液の弾力や粘りを回復させて変形性膝関節症の症状を緩和させる方法です。ただし、薬物療法はあくまでも短期的な治療方法であり、長期間継続する治療法ではありません。
装具療法
装具療法は、足底装具を利用する、不安定なひざに支柱が入ったサポーターを巻くなどの方法が挙げられます。日本人はO脚の方が多く、O脚はひざの内側に体重がかかりやすいです。ひざの内側の半月板や軟骨がすり減り、変形性膝関節症を引き起こします。
装具療法は、靴や足に装具を付けて、体重がかかる箇所を変えることによって変形性膝関節症を治療する方法です。
足底板を利用すれば、ひざの内側に体重がかかりにくくなります。健康用品として市販されていますが、専門医に相談したうえで自身専用の物を作成・利用するのがおすすめです。
自己判断で市販されている商品を利用すると、症状がさらに悪化するリスクがあるため注意しましょう。
手術
変形性膝関節症の初期症状や中期症状が見られても、日常生活で常に痛みを感じていないと薬物療法やひざを温めるセルフケアを続ける方が多いです。
変形性膝関節症の手術をおこなず、ひざの痛みを我慢しながらケアを継続するよりも、手術をしたほうが良いケースもあります。
変形性膝関節症の痛みを感じてから約3か月~半年間、ケアをおこなっても症状が良くならない場合は、手術を検討する必要があるでしょう。
変形性膝関節症の手術は、早い段階でおこなったほうが良い結果になるといわれています。とくに、糖尿病や心疾患といった合併症がある場合、内科医に相談して手術をしたほうが良い場合が多いです。
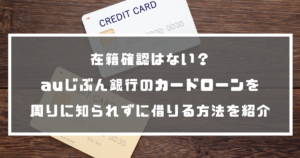
こんな時はすぐに病院・クリニックを受診しましょう!

変形性膝関節症の可能性があると思っていても、病院・クリニックを受診すべきか迷っている方も多いでしょう。しかし、痛みの感じ方によってはすぐに病院を受診しなければ症状が悪化することがあります。病院・クリニックに行くべき2つの症状を紹介します。
休んでも改善せず痛みが続く
ひざの痛みを感じて座ったり、運動やトレーニングを休んだりしても痛みが続くケースがあります。休んでもひざの痛みが続く場合、強い炎症を起こしている可能性があるため、すぐに病院を受診しましょう。
一時的に症状は治るが慢性的に痛みがある
ひざを伸ばす曲げるなどの動きをした際に、痛むものの、少し休むと痛みがなくなるため、治療を受けずに様子を見ている方も多いでしょう。しかし、一時的に痛みがなくなっても、慢性的に痛みを感じる場合は注意が必要です。
軟骨はひざの関節への衝撃や負荷を緩和する役割があり、炎症が進むと痛みのほか関節の変形や骨の損傷につながり、歩くのも困難になります。ひざの慢性的な痛みがある方は、早めに病院を受診しましょう。
ひざに違和感を感じる
変形性膝関節症の初期症状のひとつに、ひざの違和感が挙げられます。ひざに違和感がある状態で歩きすぎたり、ひざに負担をかけたりすると、炎症が悪化して痛みも強くなるため注意が必要です。
ひざに違和感があるにも関わらず、治療をせずに放置すると、痛みが強くなるほかひざが変形するなど症状が悪化します。ひざを動かしにくい、痛いといった違和感を覚えるときには、医師に相談しましょう。

【ランキング】おすすめしたい!ひざ専門クリニック
ここ数年で人気が出てきているのがひざ専門のクリニックです。膝のプロフェッショナルがあなたの痛みを診断してくれるため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
1位:ひざ関節症クリニック
変形性膝関節症の方も多く来院しており、再生医療の「培養幹細胞治療」によって人工関節以外の選択肢を見出しています。
こちらは痛みの発生源にアプローチして、組織修復を促す治療法です。治療時に入院の必要がなく、ヒアルロン酸注射よりも長期的な持続効果を見込めるメリットがあります。
全国14拠点のドクターはひざ治療を熟知した専門医のため、症状に応じて適切な治療を受けられる体制も安心材料の一つです。
ひざの痛みで運動が制限されている方は、
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
提供する注入治療は、ひざ関節の変形を遅らせ、傷ついた組織の修復効果が期待できる再生医療になります。切開、入院ともに不要のため、生活スタイルを維持して治療にあたれるのは大きなメリットです。
また、治療後は熟練スタッフが寄り添い、痛みの再発防止へ向けたリハビリを継続できます。他院では治療のみで終わるケースが多いため、ひざの症状に応じて適切なケアを続けたい方にはとくにおすすめです。
治療メニューや再生医療について疑問があれば、
変形性膝関節症に関するよくある質問

変形性膝関節症はどのくらいで治るのか、再発する可能性はあるのかなど、よくある質問を紹介します。
完治するまでどのくらいかかる?
現段階でひざの軟骨を元に戻す治療方法はないため、完治することはありません。変形性膝関節症の進行を防ぎ、症状を緩和・改善できるまでには約2~3か月かかります。
変形性膝関節症の治療を開始してから数か月間は、リハビリのために通院するケースが多いです。変形性膝関節症の治療では、ひざを曲げ伸ばしする、筋力トレーニング、階段の昇り降りや歩行の練習、日常生活での動作に慣れるなどリハビリがおこなわれます。
なお、変形性膝関節症の状態や治療方法によって、症状が緩和・改善するまでの期間は異なります。
再発の可能性はある?
変形性膝関節症は再発する可能性があります。変形性膝関節症の原因になる動作をする、体重の増加などで再発することがあるため、変形性膝関節症の予防に努めましょう。
変形性膝関節症は女性に多いと聞いたけど本当?
変形性膝関節症の患者数は女性が約1,670万人、男性が約860万人と、女性のほうが多いです。変形性膝関節症が女性に多い主な原因は、ホルモンの分泌量が減少する、筋肉量が少ない、ひざが内側に入るような歩き方をしていることが挙げられます。
骨や軟骨、筋肉を健康に維持するためには、女性ホルモンの一種であるエストロゲンが関係しています。エストロゲンの分泌量が減少する閉経後は、変形性膝関節症になりやすいといえるでしょう。
50歳以上の女性は、同じ年代の男性と比較すると約3倍の速さで軟骨がすり減ることがわかっています。
また、変形性膝関節症の女性患者が多い理由は、ひざへの負担を軽減するための筋肉量が少ないうえに、体脂肪率が高いためです。
さらに、女性は歩く際や運動をする際など、ひざが内側に入る方が多いです。ひざが内側に入ると怪我をする可能性が高いことも、女性が発症しやすい理由のひとつだといえます。
軟骨の維持に良い食べ物はある?
軟骨はプロテオグリカンが主成分であり、プロテオグリカンの元になるのはコンドロイチンと呼ばれる成分です。コンドロイチンのもとになるのはグルコサミンであり、甲殻類に多く含まれています。
そのため、ひざの軟骨がすり減らないようにするためには、グルコサミンとコンドロイチンを摂取する方法が有効です。グルコサミンはエビやカニ、コンドロイチンはオクラ、納豆、山芋、なめこなどに含まれます。
まとめ

変形性膝関節症は、長い期間をかけて少しずつ症状が進行します。年齢を重ねると、変形性膝関節症になる可確立が高いです。
変形性膝関節症の治療法は薬物療法、装具療法などが挙げられますが、症状に合わせて医師に提案してもらう必要があります。
ひざに痛みや違和感がある場合は病院で受診して、変形性膝関節症だと診断されたら症状に適した治療をしましょう。
※本記事の情報は2022年11月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。