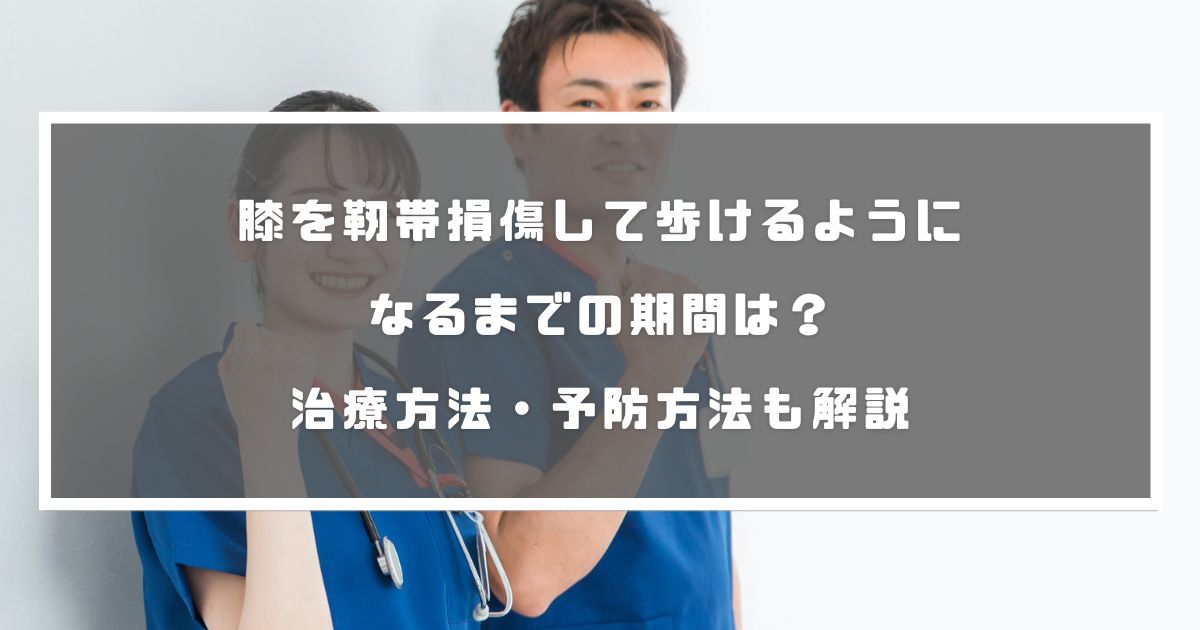膝の靭帯損傷に陥ると、場合によっては歩行困難になることもあるため注意が必要です。そのため靭帯損傷の可能性がある方は、靭帯損傷の症状や原因を知るのはもちろんのこと、歩けるまでにかかる期間についても理解を深めることが重要となります。
本記事では、膝の靭帯損傷について症状や原因、治療法など基礎知識をまとめつつ、歩けるようになるまでにかかる期間もあわせて解説していきます。靭帯損傷については十分に理解を深めたうえで、予防につなげていきましょう。
靭帯損傷とは?

膝の疾患の一つに、靭帯損傷が挙げられます。靭帯損傷は、膝の靭帯をスポーツや事故などの原因によって損傷してしまうことです。
膝靭帯損傷になると、症状の重さ次第では、歩行困難に陥るケースもあります。また歩けたとしても、膝は継続的に痛むため、日常生活の維持に支障をきたす場合は多いです。
まずは、膝靭帯損傷について理解を深めるための基礎知識として、次のことを順にまとめていきます。
- 膝の靭帯の種類
- 靭帯損傷の症状
- 検査
- 診断基準
- 捻挫の違い
- 歩けるようになるまでの期間
膝靭帯損傷について知るには、症状や捻挫との違い、理解すべきことがさまざまあります。詳細を一つ一つチェックしていきましょう。
膝の靭帯の種類
膝の靭帯には、次の4つの種類があります。
- 前十字靭帯(ACL)
- 後十字靭帯(PCL)
- 外側側副靭帯(LCL)
- 内側側副靭帯(MCL)
したがって膝靭帯損傷とは、上記のいずれかの靭帯を損傷した状態を指します。
前十字靭帯はすねにある骨が前方に向けて外れないよう支える役割を持ち、後十字靭帯は、反対に後方に向けて外れないよう支える役割を担っています。いずれも膝を前後に安定させるために必要な重要な部位です。
外側側副靭帯は膝関節の外側を安定させる役割を持ち、内側側副靭帯は、膝関節の内側が開きすぎないよう防ぐ役割を担っています。
靭帯損傷の症状
膝の靭帯を損傷すると、主に次の症状が見られます。
- 膝の痛み
- 腫れ
- 膝を曲げ伸ばし時に違和感を覚える
- 膝の可動域が狭くなる
- 膝に不安定感が出る
- 歩行困難
したがって膝の痛みや腫れが継続的に続く場合は、膝靭帯損傷の恐れがあります。痛みや腫れの症状が出ているにもかかわらず放置していると、半月板損傷や軟骨損傷の疾患につながるケースも少なくありません。
靭帯損傷の検査
膝の靭帯損傷は、次の方法で検査を実施します。
- 医師による不安定性テスト
- レントゲン撮影(X線撮影)
- MRI
医師による不安定性テストといえば、ラックマンテストがあります。ラックマンテストでは、主に膝前十字靭帯損傷なのかをチェックしていきます。あおむけの状態の患者に対して、膝関節を20度~30度の角度で前方へ向かって屈折させることで、チェックが可能になります。
ほかにはレントゲン撮影やMRIが利用されることも多いです。膝靭帯損傷かもしれないとなった感じた際には、上記のいずれかの方法で検査がおこなわれることを理解しておきましょう。
靭帯損傷の診断基準
靭帯損傷かどうか診断する際には、主に膝関節にストレスを加えたときの緩み具合を、正常な膝と比較していきます。緩み具合を数値化して診断が可能な場合もあります。
MRIやレントゲンで画像診断するとき、より精度が高い方はMRIです。MRIでは靭帯がはっきり写るため診断しやすく、半月板損傷を併発しているかどうか診断できます。
レントゲン検査で診断する場合は、ストレスをかけた状態で撮影をおこないます。徒手もしくは器具でストレスを加え、靭帯損傷時に起こる骨のズレの有無をチェックする流れです。
靭帯損傷と捻挫の違い
捻挫は、足をひねることで関節や腱、軟骨が傷つくことを指します。しかし捻挫をすると、ときに靭帯を傷つけ、靭帯損傷(靭帯断裂)の状態になってしまうこともあるため注意が必要です。
軽くひねったのみと思っていたときでも、靭帯損傷の状態になっていることは十分にあり得るため注意が必要です。
よく捻挫すると足をひねる癖がつくといわれることがありますが、これは靭帯損傷により、関節の不安定が残って起こることと考えられます。靭帯損傷はしっかりと治さない限り不安定感は残るため、捻挫したのみと考えず、医療機関を受診するようにしましょう。
歩けるようになるまでの期間
靭帯損傷に陥った場合、専用のサポーターでまず膝を保護する必要があります。保護したうえで、松葉杖をついてしばらく生活することになります。
一般的に、痛みが取れて日常生活に戻れるまでには3~4週間の時間がかかります。通常どおり歩けるまでにはある程度時間がかかることを理解しておきましょう。
膝の靭帯損傷の主な原因

膝の靭帯損傷は、主に次のような原因によって起こります。
- スポーツ
- 交通事故
- 転倒
では、それぞれの原因について詳細を見ていきましょう。
スポーツ
膝の靭帯損傷でよくある原因の一つは、スポーツです。
- ジャンプした際に無理な体勢で着地した
- ぶつかったことで外から膝に衝撃が加わった
- 急な方向転換をした
上記のような状況になると、膝の靭帯を傷める場合があります。とくに前十字靭帯損傷は、バレーボールやバスケットボールのスポーツで受傷しやすい傾向にあります。
交通事故
交通事故によって膝の靭帯損傷になる方も多いです。
事故に遭って、外から膝に大きな衝撃を受ければ、靭帯損傷につながることがあります。たとえば後十字靭帯損傷は、脛骨が後ろの方向へ押し出されるようなかたちでダメージを受けると、靭帯の支える力を超えることで受傷してしまいます。
転倒
転倒したことにより膝の靭帯が切れてしまうケースもあります。
もちろん、一般的には軽くつまずく程度では膝の靭帯損傷に陥るケースはありません。多いケースは、運動をしている最中の転倒です。膝をひねるかたちで転倒すれば、膝に無理な力が加わり、靭帯を傷めることも少なくありません。
膝の靭帯損傷の治療方法

膝の靭帯損傷の治療方法は、大きく分けると次の3つになります。
- 保存療法
- 手術療法
- 再生療法
膝靭帯損傷について知るためには、どのような治療方法があるのかも十分に理解する必要があります。治療方法を一つ一つ整理していきましょう。
保存療法
保存療法は、再生療法を除いて、手術療法に対するかたちで利用される言葉です。手術によって直接的に手を加えて治すのではなく、治療、症状改善、痛み緩和を目指す治療法になります。
保存療法は、主に次の3つに分けられます。
- 運動療法
- 装具療法
- 薬物療法
それぞれのどのような治療法なのかをチェックしていきましょう。
運動療法
運動療法は、運動をおこなうことによって、症状改善や緩和を目指す治療法を指します。有酸素運動や無酸素運動、筋トレ、ストレッチが代表的な例です。いわゆるリハビリテーションのことを指すといってよいでしょう。
症状改善に効果的な運動をおこなうことで、関節の可動域拡大、痛み緩和、血行促進を目指します。さらに筋力を高めることで、その後の怪我の予防にもつなげていきます。
装具療法
装具療法は、専用の装具を着用し、痛みの緩和や症状改善を目指す治療法です。
膝靭帯損傷に陥ると、靭帯は膝を安定的に支えられない状態になるため、安定性を高める目的と症状改善のために専用のサポーターやギプスを利用していきます。
薬物療法
薬物療法は、薬を利用することで症状改善、緩和を目指す治療法になります。
塗り薬や貼り薬の外用薬、内服薬、座薬の種類があります。膝の靭帯損傷に陥った場合は、痛み緩和の目的で外用薬や内服薬が処方されます。
手術療法
膝の靭帯損傷のなかでも前十字靭帯靭帯損傷は、普段の生活でどの程度膝を使うのか加味し、状況に応じて手術療法を検討していきます。手術療法には、次の2つのパターンがあります。
- 靭帯修復術
- 再建術
一般的には再建術を採用して手術をおこなうことが多いです。手術が必要な場合は、関節鏡を利用し、低侵襲な手術を施します。低侵襲とは、従来の手術よりも患者の体への負担を抑えられる方法を指します。
再生療法
再生療法は、保存療法と手術療法に対して、新しいタイプの治療法になると近年注目されている治療法になります。再生療法には、自身の細胞を利用して治療につなげる特徴があります。
具体的な治療法はさまざまありますが、代表的な方法はPRP療法です。自身の血液の血小板の成分を治療に利用する方法になります。血小板には成長因子が多く含まれるため、培養して患部に注入すれば、自然治癒や炎症抑制を促せる仕組みです。
したがって再生療法では、保存療法や手術療法よりも早期回復が望める点が大きなメリットになります。
膝の靭帯損傷の予防方法

では、膝の靭帯損傷を未然に防ぐにはどのように過ごすことが望ましいのでしょうか。ここからは、膝の靭帯損傷の予防方法を紹介していきます。主な予防方法は次のとおりです。
- 適度な運動
- 運動前の準備運動
- 膝に負担をかける運動・動作を控える
では、それぞれの予防方法の具体的なポイントを解説していきます。
適度な運動
運動不足になると、筋力が落ちることから、膝靭帯損傷に陥りやすくなります。したがって運動不足の状態でスポーツや激しい運動を急におこなうと、膝靭帯損傷につながりやすくなる仕組みです。
そのため膝靭帯損傷を防ぐには、日常的に適度な運動を心がけ、筋力低下を抑える必要があります。
運動前の準備運動
膝靭帯損傷を予防するには、運動前の準備運動も必須です。
準備運動なしの状態でいきなり体を激しく動かすと、体全体がほぐれていないせいで、足をひねるけがをする恐れがあります。結果として膝靭帯損傷につながることもあるため、準備運動は忘れずにおこないましょう。
膝に負担をかける運動・動作を控える
膝に負担をかける運動や日常動作も、できる限り控えたいところです。
- 筋トレでスクワットばかりをおこなう
- 仕事で膝を酷使する
たとえば上記のような行動が目立つと、膝を傷めやすくなります。靭帯損傷に陥る可能性も十分にあり得るため、必要以上に負担をかける行動はやめましょう。
【ランキング】靭帯損傷の改善のために受診すべき専門クリニック
靭帯損傷などご自身ではどうしようもできないものは、専門のクリニックを受診するようにしましょう。ここではおすすめのクリニックを紹介します。
1位:ひざ関節症クリニック
とくに自己組織の修復を促す「培養幹細胞治療」は、先進的なバイオセラピーとして多くの注目を集めています。痛みの根元にアプローチできるため、長期的な治療の持続効果を期待できるのも魅力的なポイントです。
また
完全予約制で待たずに診察が受けられるため、スポーツができる健康的な日常生活を取り戻したい方はぜひチェックしてみてください。
| 施術内容 | ヒアルロン酸注射、PRP-FD注射、培養幹細胞注射、APS再生治療 |
| 費用 | 初診:3,300円 MRI検査:8,000円~12,000円 |
| 拠点数 | 14拠点 |
| 診療時間 | 9:00~18:00 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード、デビットカード |
2位:シン・整形外科(旧東京ひざクリニック)
痛みの根本解決を目指せる再生治療は、自身の血液や細胞を活用する低リスクな先進医療です。入院や手術をせずに治療がおこなえるので、現状のライフスタイルも維持できます。
さらに、治療後は膝間接を熟知したスタッフのもとで、怪我の再発防止へ向けたリハビリを継続可能です。
施術詳細についての無料相談も可能なため、膝の靭帯損傷から早期回復を目指す方は気軽にチェックしてみましょう。
膝の靭帯損傷に関するよくある質問

最後に、膝の靭帯損傷に関してよくある質問と回答をまとめていきます。今回ピックアップする質問は、次のとおりです。
- 靭帯損傷は自然に治る?
- 靭帯損傷は全治するまでどれくらいかかる?
- 靭帯再建手術後はスポーツに復帰できるまでにどれくらいかかる?
- 靭帯損傷で鍼治療は効果ある?
- 靭帯損傷を放置するとどうなる?
- 靭帯損傷の診察には何科を受診すればいい?
靭帯損傷について理解を深める際に、実際に上のような点に疑問を持ったことがある方は多いのではないでしょうか。回答を一つ一つ見ていきましょう。
靭帯損傷は自然に治る?
靭帯損傷は、自然に治るわけではありません。時間が経つとひどかった痛みも引いてくる場合がありますが、完治しているわけではないため注意しましょう。膝の不安定な状態は残っていると考えられます。
したがって膝を傷めたとわかった時点で、医療機関は必ず受診するようにしましょう。
靭帯損傷は全治するまでどれくらいかかる?
軽い症状であれば1週間ほどで完治することもありますが、重症の場合は、全治まで非常に長い期間を要することがあります。
たとえば前十字靭帯損傷の場合は、全治して運動に復帰できるまでには、8~10か月かかるケースもあるため注意が必要です。もちろん日常生活には3~4週間で復帰できますが、スポーツをする方の場合は、8~10か月の長いリハビリテーションを経てようやく元どおりにスポーツが可能になります。
靭帯再建手術後はスポーツに復帰できるまでにどれくらいかかる?
靭帯再建手術をおこなった場合、スポーツに復帰できるまでには最低でも半年の期間が必要になります。一般的な目安は6~10か月ととらえておきましょう。
手術後は筋力トレーニングやストレッチ、可動域訓練でリハビリテーションを重ねて復帰を目指します。
靭帯損傷で鍼治療は効果ある?
鍼治療は主に、靭帯損傷の症状の根本改善や症状再発の防止に効果的とされています。
したがって、たとえば手術を受けたのにもかかわらず痛みが収まらない、と悩んでいるときには鍼治療が有効な場合もあります。
靭帯損傷を放置するとどうなる?
靭帯損傷に陥った場合でも、安静にしていれば、問題なく歩けるようになることもあります。そのため靭帯損傷については症状を放置してしまう方も多いですが、治療を受けずに放置すると、半月板損傷や軟骨損傷などの症状を併発する場合があります。
併発によって痛みが慢性的に残るケースも考えられるでしょう。膝に痛みがあるときは放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。
靭帯損傷の診察には何科を受診すればいい?
靭帯損傷に陥ったときは、整形外科を受診しましょう。
ほかには、スポーツによって受傷したときは、スポーツクリニックやスポーツ整形外科の受診も望ましいです。
まとめ

膝の靭帯損傷は、放置すると半月板損傷や軟骨損傷などの症状にもつながるため、十分に注意が必要です。膝の痛みを感じた段階で、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
靭帯損傷を含む膝の怪我を防ぐには、症状や原因、治療法などを詳しく理解する必要があります。歩けるまでにかかる時間も事前に把握したいところです。膝の靭帯損傷について正しい知識をつけたうえで、予防のための行動につなげていきましょう。
※本記事の情報は2022年12月時点のものです。
※本記事は公開、修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス、商品に関するお問い合わせは、サービス、商品元に直接お問い合わせください。