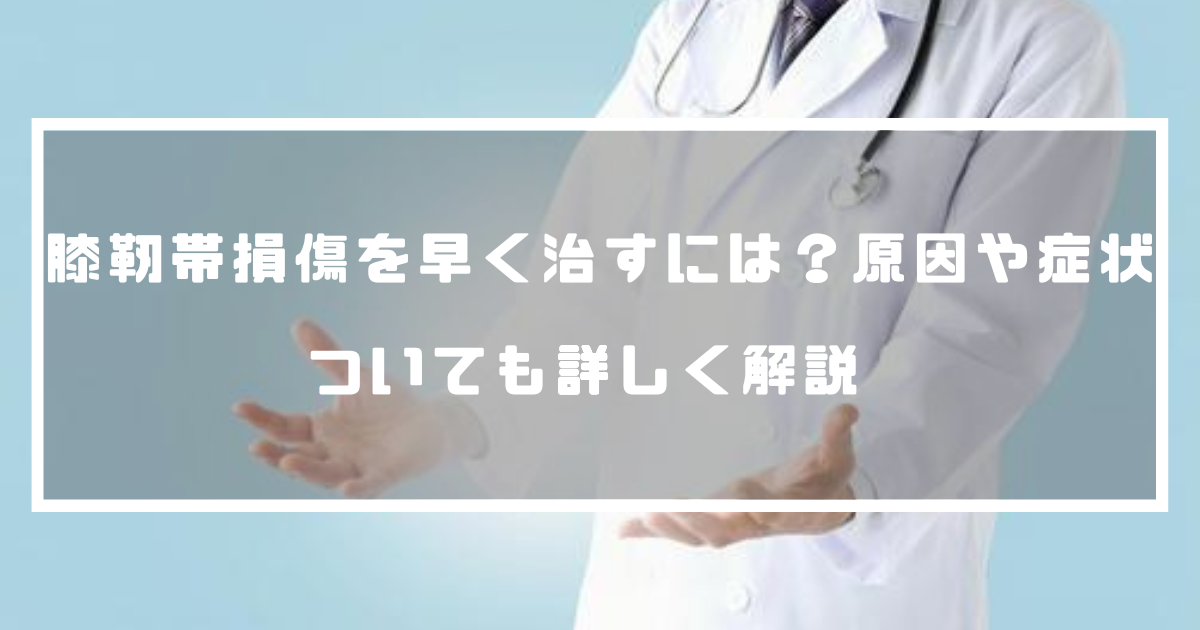膝の靭帯損傷を早く治す方法はあるのでしょうか。膝の靭帯損傷は強い痛みや歩行困難を伴います。日常生活に支障が出るため、なるべく早く治したいと思うことは当然です。
またスポーツで膝の靭帯を損傷してしまった場合、選手として早く復帰したいと思うでしょう。膝の靭帯損傷を早く治すには、適切な治療とリハビリを実施することがポイントです。
しかし膝の靭帯損傷を負っても、捻挫と勘違いしてそのまま放置するケースがあります。
今回の記事では膝の靭帯損傷と捻挫の違い、原因や症状そして膝の靭帯損傷を早く治す方法について紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
4つの膝靭帯損傷と捻挫との違い

一口に膝の靭帯損傷といっても膝には4本の靭帯があり、それぞれ靭帯損傷の原因が異なります。
膝の靭帯損傷を早く治すには、傷病名の特定は欠かせません。ここではまず膝の靭帯損傷の種類やそれぞれの症状、特徴について解説します。
膝外側側副靱帯(ひざがいそくそくふくじんたい)損傷
膝外側側副靱帯(ひざがいそくそくふくじんたい)は大腿骨(太ももの骨)と脛骨(脛の骨)をつなぐ靭帯の一つで、膝の外側に位置します。
膝外側側副靱帯損傷の原因は主に次の2つです。
・内側から外側に強い力がかかった
・膝から下の部分を内側に強く捻った
膝外側側副靱帯損傷は強い痛みや腫れを伴います。
ただ膝外側側副靱帯のみの損傷は珍しく、多くのケースで膝外側側副靱帯以外に他の膝靭帯や半月板の損傷、靭帯付け根部分の剥離骨折を伴います。
膝内側側副靭帯損傷
膝内側側副靭帯は前述した膝外側側副靱帯のちょうど反対側、膝の内側に位置する靭帯です。膝内側側副靭帯は英語でMedial Collateral Ligament(MCL)といい、クリニックによってはMCL損傷とよばれることがあります。
膝内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)損傷は膝靭帯損傷のなかでもっとも起こりやすい怪我です。膝内側側副靭帯損傷を負う原因は交通事故もありますが、サッカーやラグビーなどのタックルによって起こることが多いようです。
また膝内側側副靭帯損傷は膝の捻挫だと思って「安静にすれば大丈夫」と放置されることがよくあります。
しかし膝内側側副靭帯損傷は適切に治療をおこなわないといけません。膝の半月板損傷のような合併症が発生する場合があります。内膝への衝撃で強い痛みを感じたときは、クリニックで適切に治療を実施することをおすすめします。
前十字靭帯損傷
前十字靭帯は膝の正面前方で大腿骨と脛骨をつないでいる靭帯です。後十字靭帯とクロスするように配置されているため前十字靭帯と呼ばれます。
また前十字靭帯は英語でAnterior Cruciate Ligament(ACL)といい、前十字靭帯損傷のことをACL損傷と呼ぶこともあります。
前十字靭帯損傷の多くはスポーツによる怪我が原因です。前十字靭帯は大腿骨に対して脛骨が前に出すぎないように、また膝を捻りすぎないようにストッパーのような役割をしています。
前十字靭帯が損傷すると適切な治療を行わなければ、膝がはずれたように感じる亜脱臼を頻繁に起こすようになります。いわゆる「癖になる」と言われる症状です。
亜脱臼を繰り返すと膝の他の部分に負担がかかり損傷するため、自己判断せずクリニックで適切な治療を実施することが重要です。
後十字靭帯損傷
後十字靭帯は前十字靭帯と逆で、膝が後に亜脱臼しないように大腿骨と脛骨をつないでいる靭帯です。後に向けて膝に強い衝撃を受けたときに傷つけることが多く、強い痛みを感じます。
しかししばらくすると症状がなくなることもあり自然治癒したと勘違いするケースが多いようです。ここで気を付けなければいけないのは、膝靭帯損傷はどの靭帯でも自然治癒はないということです。
靭帯を損傷したまま放置していると、自覚症状がないまま他の部位に負担をかけることになります。結果として十年後、数十年後に膝にトラブルを抱えることになりかねません。
とくに後十字靭帯損傷は専門の医師でないと診断しにくい部位です。膝の痛みや階段歩行時に膝がグラグラするなど不安定さを感じる場合は、すみやかに専門医に相談しましょう。
膝靭帯損傷と捻挫は違う
膝靭帯損傷と捻挫は厳密には異なりますが、捻挫には膝靭帯損傷も含まれます。膝靭帯損傷は前項で触れたとおり、膝にある4本の靭帯のいずれかもしくは複数を損傷した状態のことです。
一方捻挫とはレントゲン(X線)で診断できない関節の怪我を指します。骨折や脱臼以外の怪我はすべて捻挫です。
そのため捻挫には膝靭帯損傷も含まれますし、半月板や軟骨の損傷も含まれます。一般的に捻挫というと、靭帯損傷よりも軽い怪我で「安静にしていれば治る」と勘違いする方が多いようです。
しかし膝靭帯損傷も捻挫の症状の一つであり、自然治癒はありません。放置しておくと後々歩行困難になったり、膝に不具合を生じたりします
膝靭帯損傷には症状に応じて治療方法やリハビリの方法が変わるため、必ず自己診断せず適切な治療を実施することが重要です。
膝靭帯損傷の原因

膝靭帯損傷の原因は主にスポーツによる衝撃、そして交通事故による衝撃による2つです。
順に解説していきます。
スポーツによる損傷
スポーツは膝靭帯損傷の大きな原因の一つです。膝靭帯損傷は膝に過剰な負荷がかかったときに、膝靭帯が断裂して起きます。
スポーツの中でもいわゆるコンタクトスポーツと呼ばれるものが膝靭帯損傷を起こしやすい傾向です。たとえばサッカーやラグビー、柔道などでよく起こります。
また膝を軸に素早い動きをするスポーツも膝に負荷がかかりやすく、膝靭帯損傷を負いやすいでしょう。
ラグビー
サッカー
柔道
アメリカンフットボール
バスケットボール
テニス
バレーボール
レスリング
スキー など
スポーツで膝靭帯を損傷した場合、怪我の程度にもよりますがスポーツ復帰はリハビリを経て非常に時間がかかります。
しかしきちんと治さなければ、また怪我をしてしまいます。時間をかけてゆっくりと復帰を目指すことが重要です。
交通事故による損傷
膝靭帯損傷は交通事故で起こることもあります。車やバイク、自転車のみでなく、歩行中にぶつけられることもあるでしょう。
交通事故による靭帯損傷では膝にとても強い衝撃を受けていることが多く、適切な治療を続けても後遺症が残ることがあります。後遺症には痛みが残ること以外に、膝の稼働域に問題が出るなどさまざまな不具合が考えられます。
膝靭帯損傷の症状

膝靭帯損傷の症状には痛み以外にもさまざまなものがあります。それぞれ症状別にどのようなことが考えられるのか見ていきましょう。
順に解説していきます。
膝の痛み
膝靭帯損傷には痛みがつきものです。膝に大きな衝撃を受けて靭帯を損傷すると、強い痛みが走ります。
場合によってはパンっと靭帯が切れる音がして、靭帯が切れたことがわかる場合もあるでしょう。膝靭帯損傷の急性期(怪我をしたばかりの時期)には強い痛みがありますが、慢性期になると痛みは徐々に引いていきます。
しかし痛みが引いたからといって油断していると、徐々に膝に負担がかかり数年後、数十年後に痛みが出ることもあるため注意しておきましょう。「昔の古傷が痛む」のは、怪我をしたときに適切な治療を行わなかったことが原因です。
膝の靭帯損傷は痛みがない状態でも、当分ハードなスポーツはできません。医師の指導の下、ゆっくりと治すことが重要です。
膝が腫れる
膝靭帯損傷は痛みとともに腫れることもあります。一般的に靭帯を損傷したときに急激に晴れることが多いのですが、痛みがある程度ひいてから腫れてくるケースもあります。
腫れの原因は炎症によるもの、そして内出血が原因です。膝靭帯損傷で患部が腫れるときは、炎症しているため発熱を伴うことが多いです。
膝が腫れたときは腫れが引くまで患部を冷やすことをおすすめします。膝靭帯損傷を負ったときは、まずしっかり冷やすことで炎症や腫れを抑えることが可能です。
凍傷にならないよう注意しながら、しっかりと数日間患部を冷やすようにしましょう。数日して痛みや腫れがおさまってきたら、今度は血行を良くするために温めると傷の回復が早くなります。
膝の不安定感
膝靭帯は大腿骨と脛骨をつないでいる靭帯です。膝関節を滑らかに動かすために重要な部位であるため、膝靭帯を損傷すると膝が不安定になります。
たとえば素早く方向転換しないといけないときに膝がぐらつく、階段の上り下りで膝がカクつくなどです。また胡坐をかく動作も不安定に思うでしょう。
膝の不安定感は慢性期に起こりがちです。急性期には痛みと腫れが強く、歩行自体が困難なため膝の不安定感はあまり感じないのかもしれません。
しかし痛みが治まる慢性期になり、動くようになるとたちまち膝のグラつきを感じるでしょう。膝の痛みや腫れがひいて安心すると治療やリハビリをやめる方がいますが、膝のぐらつきを悪化させるため自己判断はやめてください。
放置していると歩行時や動くときに膝に力がはいらなくなる膝くずれを起こします。膝のぐらつきの放置は半月板損傷や軟骨のすり減り、膝関節の変形などの合併症の元です。
膝靭帯損傷はなるべく早い受診によって、その後の膝の不具合を予防できます。
膝靭帯損傷の治療方法

膝靭帯損傷の治療には次の2つがあります。
保存療法、手術療法のどちらを選ぶかは、膝靭帯損傷の状態によります。
保存療法
保存療法は手術に頼らず、膝靭帯損傷を治療する方法のことです。この場合必要な筋肉を鍛えて膝をサポートする方法や、患部を固定する方法があります。損傷した靭帯は自然に元に戻ることはありません。
しかし、筋力をつけることで膝靭帯のサポートは可能です。保存療法はそのための治療だと考えてください。
サポーター
膝靭帯損傷の保存療法ではまず、サポーターで膝を固定します。サポーターによる膝の固定によって、不安定な動きを抑制し膝周りの部位への負担を減らすのです。
保存療法では筋力をつけることによって膝の靭帯の動きをサポートしますが、急性期ではまだ安静にしなければいけません。そのためある程度動けるようになるまでは、サポーターで動きを補助するのです。
サポーターにはいろいろな種類があり、膝靭帯損傷の箇所や状態によって適切なサポーターを選びます。急性期、慢性期でサポーターを付け替えることで効果的に治療を進めることも可能です。
リハビリ
保存療法のリハビリでは、膝靭帯をサポートするための筋力をつけます。急性期に動かすと炎症が悪化するため、リハビリは慢性期になってからおこないます。
それまでは炎症を抑えるためのアイシングや、膝に水がたまっている場合は水を抜くなどの治療が主です。
そしてリハビリは怪我の状態を見ながら段階的におこないます。リハビリの目的は主に次の3つです。
・膝関節の可動域を柔軟にする
・膝靭帯をサポートする筋力をつける
・バランスを鍛える
具体的には膝関節のストレッチや、大腿筋の筋力トレーニング、バランス運動などです。ほかに電気治療や超音波治療を平行して実施することもあります。
手術療法
膝靭帯の損傷は基本的に自然に完治しない怪我です。とくに複数個所の靭帯損傷や前十字靭帯損傷では保存療法よりも手術療法をすすめられるケースが少なくありません。
またスポーツ選手がスポーツ復帰するためには、休養期間が長くなるものの手術療法がすすめられます。
靭帯再建術
靭帯再建術では他の部位の腱を切り取り、内視鏡で切れてしまった靭帯に移植します。靭帯再建術のほかに靭帯縫合技術という切れた靭帯を縫い合わせる手術もあります。術後は2日後から歩行が可能です。
その後徐々にリハビリをおこない、膝関節を動かす訓練をします。スポーツ復帰には半年以上かかりますが、怪我以前の動きまで回復のも可能です。
半月板損傷の合併症にも注意

膝靭帯損傷は半月板損傷の合併症を引き起こすことがあります。半月板とは膝にある繊維軟骨で、大腿骨と脛骨の間の内側と外側に一つずつ存在します。
半月板と呼ばれる所以は、半月板の形がアルファベットのCのような形をしているためです。半月板の役割は膝関節への体重負荷を分散させること、そして関節の位置を安定させることです。
強い衝撃によって膝靭帯を損傷すると、半月板も同時に傷つくケースが多く見られます。半月板損傷にはリハビリやヒアルロン酸注入などの保存療法や、半月板切除や修復術などの手術療法があります。
半月板損傷を併発する可能性もあり
膝靭帯損傷と半月板損傷は同時に怪我をするケースが多いのですが、膝靭帯損傷で後発的に半月板損傷を起こすこともあります。その原因は膝靭帯損傷で適切な治療を行わなかったためです。
膝靭帯損傷を放ったまま生活すると膝が安定せず、半月板や膝軟骨に負担がかかります。そして徐々に半月板がすり減り、半月板損傷の症状が出始めるのです。
また前十字靭帯損傷の場合、放置すると亜脱臼を繰り返すことで半月板損傷を引き起こします。

早めの治療が肝心
怪我をして半月板に異常がなくても、膝靭帯損傷のせいで徐々に半月板が傷つくことがあります。半月板損傷は将来の歩行困難を招きます。
半月板損傷のような合併症を引き起こさないためにも、膝靭帯を損傷したときは迅速にクリニックを受診し適切な治療を受けてください。
まとめ
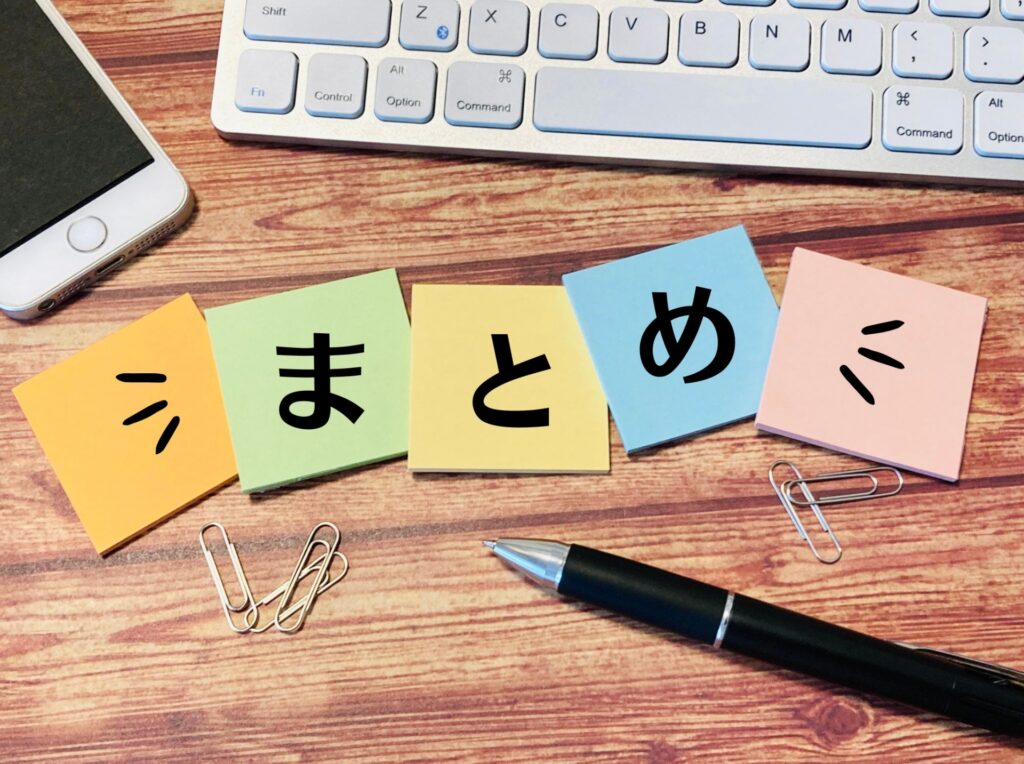
膝には4つの靭帯があり、それぞれ損傷の状態やどの靭帯が切れたのかによって治療方法は変わります。
靭帯損傷はレントゲンでは移らないためMRIで診断をおこないますが、専門医でなければ正しい診断ができないこともあります、膝靭帯損傷はしっかりと治療を行えば、怪我をする前のような動きまで回復できるものです。
自己判断で放置せず、専門医の指導のもと正しい治療を行ってください。
※本記事の情報は2022年11月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。