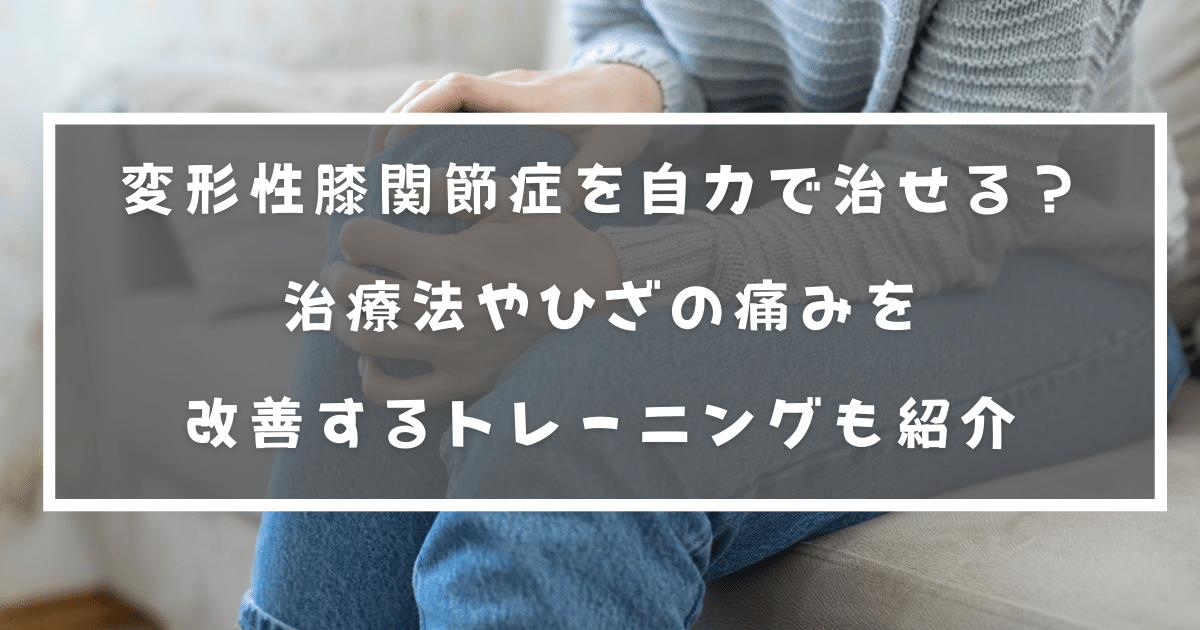「膝が痛い」「膝が重たい」などの症状に困ったときは、変形性膝関節症の可能性があります。変形性膝関節症にはさまざまな治療法があり、症状が著しく出ているときは専門のクリニックで治療を受けることが通常です。
しかし症状がまだ軽いうちは、自力で治すことも検討したいところです。トレーニングなどで症状が和らげば治療費の負担も抑えられます。健康意識を高めるきっかけにもなるでしょう。
そこで今回は、変形性膝関節症は自力で治すことができるのか整理しつつ、具体的なトレーニング方法を紹介していきます。
変形性膝関節症について

変形性膝関節症は、膝に起こる病気の一つです。主に年齢を重ねることで発症する病気ですが、若い年齢の方でも症状に悩むケースはあるため、症状の特徴や原因については十分に理解を深めたいところです。
特に「膝が最近痛い気がする」と悩んでいる方は、症状を少しでも改善する方法もチェックしておきましょう。
ひざに現れる症状
変形性膝関節症は、膝に現れる症状です。具体的には歩行しているとき、正座などで膝を曲げるときなどに、強い痛みを感じるようになります。症状が進行すれば安静にしているときでも強い痛みが残り、通常の歩行すら困難に感じるようになります。
痛みが出る理由はまず、膝の関節の軟骨が、加齢などが原因ですり減るからです。ほかには骨折や半月板損傷などの怪我の後遺症として、変形性膝関節症を発症する場合もあります。
変形性膝関節症を自力で治すことはできない
変形性膝関節症で膝に大きく痛みを感じるようになったときは、自力で治すことを考える方も多いでしょう。しかし結論からいうと、変形性膝関節症を自力で治すことはできません。
自力で治すことが難しい理由は、そもそも関節軟骨の劣化・損傷は、人が持つ自然治癒力では改善できないからです。自然治癒には血液の巡りが必須ですが、軟骨は体の中でも血管の通らない部位にあたります。
したがって変形性膝関節症で膝の痛みを感じたときは、自力で治すというよりは、自身で気をつけて膝への負担を減らすことが重要になります。変形性膝関節症の症状との、適切な付き合い方を考えていきましょう。
変形性膝関節症の原因
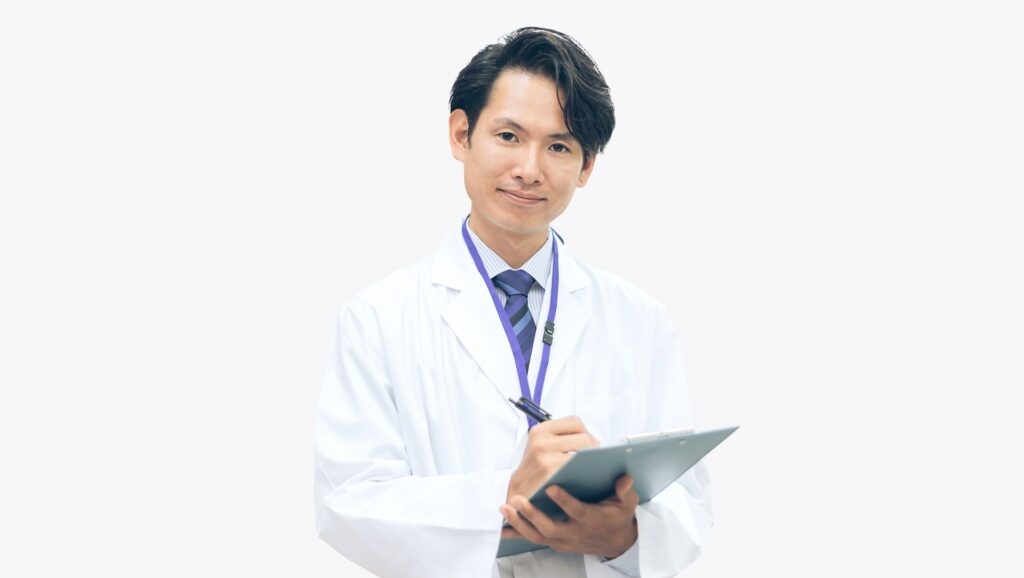
続いて、変形性膝関節症の原因として考えられることを解説していきます。変形性膝関節症は次の2つに分けられます。
・2次性の変形性膝関節症
1次性・2次性、それぞれで変形性膝関節症の原因は異なります。原因の詳細を順にチェックしていきましょう。
1次性の変形性膝関節症
1次性の変形性膝関節症の原因は、主に次のとおりです。
・肥満
・職業や生活による膝の酷使、過度な負担
・遺伝
まず変形性膝関節症は加齢(老化)が関係していることが多いため、40代以降の方に発症しやすい特徴があります。また肥満が原因になりやすいのは、重たい体重が膝に負荷を与えやすいからです。
ほかにも、職業柄膝を普段から酷使している方も症状が出やすい傾向にあります。ときには遺伝的な要因により発症するケースもみられます。
2次性の変形性膝関節症
一方で2次性の変形性膝関節症の原因は、次のとおりです。
・炎症性疾患(関節リウマチ、化膿性関節炎)
・腫瘍性疾患(滑膜性骨軟骨腫症、色素性絨毛結節性滑膜炎)
・壊死性疾患(大腿骨頸部壊死)
上記の原因を見てもわかるように、2次性の変形性膝関節症は怪我や疾患によるものです。なかでも特に多い原因は、骨折や半月板損傷などの外傷になります。いわゆる怪我の後遺症として、症状が表れるケースです。
変形性膝関節症の治療法

変形性膝関節症にはさまざまな治療法の選択肢があります。どのような治療法で症状緩和を目指すかは症状の程度などによって異なりますが、ここではまず、治療法の種類を整理していきましょう。
大きく分けると変形性膝関節症の治療法は次の3つに分けられます。
・手術療法
・再生医療
では、それぞれの治療法の特徴を解説していきます。
保存療法
保存療法では、膝に負担を与えないための過ごし方・工夫を指導しつつ、適切な運動(トレーニング)の習慣化を促していきます。薬物療法や装具療法も必要に応じて組み合わせていく点が特徴です。
保存療法における運動療法、薬物療法、装具療法の特徴を見ていきましょう。
運動療法
変形性膝関節症の症状を必要以上に進行させず、痛みの緩和を目指すには、膝に負荷をかけないための生活改善が重要になります。なかでも生活改善において重きを置くポイントは、適切な運動(トレーニング)の習慣化です。
そのため運動療法では、まずトレーニングをおこなうことで、膝周りの筋力を増強します。筋力が備われば膝への負担が減るため、痛みの緩和につながる仕組みです。
薬物療法
保存療法では、薬物療法も組み合わせるかたちで治療がおこなわれます。薬物療法とはその名のとおり、薬物を用いて痛みや炎症を抑制していきます。
薬物療法は、次の3つのパターンに分けられます。
・外用薬(湿布薬、塗り薬など)
・関節内注射
関節内注射をおこなう場合は、強力なステロイド剤を利用する特徴があります。それぞれの症状の程度・進行具合などを見ながら、適切な薬、治療パターンを見いだしていきます。
装具療法
装具療法は、サポーターなどを活用し、膝への負担を軽減させる治療法です。ほかには足底装具、機能的膝装具、杖などが挙げられます。
装具を用いることにより膝への負荷が少なくなるため、歩行や立ち上がりなどに支障をきたしていた方でも、症状の緩和につながります。
手術療法
続いて手術療法では、患部の手術をおこなったうえで症状の緩和を目指すことが特徴です。一般的に変形性膝関節症では、症状が軽ければまず保存療法を試しますが、人によっては保存療法では効果があまり得られないこともあります。
保存療法で思ったような効果が実感できなかったときに検討する治療法が、手術療法です。主な手術には次の3つが挙げられます。
・高位脛骨骨切術
・人工関節置換術
それぞれどのような手術なのかをチェックしていきましょう。
関節鏡視下滑膜切除術
関節鏡視下滑膜切除術では、内視鏡を関節のなかに入れたうえでおこなう手術です。症状の程度に応じて軟骨片を取り除く、半月板を一部切開するなどの対処をおこないます。
主に、膝関節の変形がそこまで著しくなく、半月板損傷などが要因となって痛みにつながっているときに用いられる手術です。
高位脛骨骨切術
高位脛骨骨切術は、簡単にいうとO脚の状態を矯正する手術になります。脛骨の一部を切ることでO脚矯正につなげ、膝の内側部分に負担が集中していた状態を改善していきます。負担が分散されるため、痛み緩和につながります。
切った部分が完全に接合するまでには安静が必要ですが、膝関節の温存が可能で、接合後は問題なく日常生活が送れると期待できます。スポーツなどの激しい運動も可能です。
人工関節置換術
老化や膝の酷使などが原因で軟骨がすり減り、歩行が困難なほどの強い痛みにつながっているときは、人工関節置換術という手術をおこないます。まず痛んでいる関節の表面を切除してから、人工的な関節を入れていきます。
関節の置き換えは、全体的におこなう場合と部分的におこなう場合があるため、いずれの手術になるかは症状の程度によります。
手術を終えたあとはリハビリを経て、日常生活が送れるようになります。ただし激しい運動や、しゃがんだり正座したりする行動は原則NGです。
再生医療
変形性膝関節症の治療には、現代における先端医療である再生医療が用いられることもあります。自己治癒力を利用し、痛み改善につなげることが特徴です。再生医療の治療を受けるには、変形性膝関節症の再生医療に目を向けて診療をおこなっているクリニックへ通う必要があります。
変形性膝関節症の治療で用いられる治療法は、具体的には次の2つがあります。
・培養幹細胞治療
再生医療の多くは保険適用外の高額な治療ですが、先端医療だからこそ、効率的で、かつ高い効果が望める点が魅力です。それぞれの治療法の詳細を解説していきます。
PRP(多血小板血漿)療法
PRP(多血小板血漿)療法は、保存療法やヒアルロン酸注射などで効果が得られなかった方に向けておこなわれます。また再生医療であれば、入院やインプラント(人工関節)も避けられます。
PRP療法では、自身の血液からPRP(多血小板血漿)を作って患部に注射していきます。血小板にはさまざまな種類の成長因子が含まれるため、自然治癒の力で痛み改善につなげられる仕組みです。
培養幹細胞治療
培養幹細胞治療では、自身の脂肪から幹細胞を抽出し膝関節のなかに注射していきます。注入された幹細胞が痛み・炎症改善をうながすため、大幅に痛み・炎症の症状が緩和される可能性があります。
再生医療と聞くと複雑な治療法をイメージしがちですが、培養幹細胞治療で利用するものはわずかな脂肪のみです。治療の流れもシンプルなため、短い治療時間と少ない手間で高い効果が望めることは大きな強みといえるでしょう。
治療法を選択する際の確認ポイント

変形性膝関節症を完全に自力で治すことは、正直難しいです。しかしながら症状としっかり向き合っていくにはどのような治療法が良いのか、理解を深める必要があることは事実です。
前項でも触れてきたように、変形性膝関節症の治療法には多くの種類があります。どのような治療法が適切なのか、選択に迷う方は多いでしょう。
そのためここからは、変形性膝関節症の治療法を選択するときのポイントを紹介していきます。
・治療にかかる費用
では、それぞれのポイントにおける詳細や注意点などを解説していきます。
変形性膝関節症の進行状況
一般的に変形性膝関節症の治療法は、それぞれの症状の進行状況によって決めていきます。症状が軽度で初期段階のものであれば、保存療法がまず用いられる傾向にあります。
しかし保存療法でも思ったような効果を得られないときは、手術療法や再生医療を検討する流れになります。
ただし特に手術療法は、膝関節にメスを入れるため、大がかりな治療になります。入院も必要です。そのため「入院したくない」「人工関節になることは嫌だ」と考える方も少なくありません。
いずれにしても症状によっていずれの治療法が適切なのか、自身で判断することは難しいです。専門家である医師とよく相談しながら、適切な治療法を見いだしていきましょう。
治療にかかる費用
変形性膝関節症の治療法を選ぶにあたって一つの基準になるものは、治療にかかる費用です。運動療法や装具療法ではリハビリテーションや装具、その他生活改善のアドバイスの費用のみのため高額な医療費はかかりません。保険も適用されます。
しかし保存療法で効果が得られなくなってきたときには、高額になりやすい手術療法や再生医療が選択肢に上がってきます。手術療法は保存療法と比べると大がかりな治療になり、医師側にも高い技術が求められるため治療費は高くなります。
再生医療は変形性膝関節症のさまざまある治療法のなかでも、最も治療費が高額になりやすい点が特徴になります。一般的に健康保険の適用対象外のため、全額自己負担となるからです。
高額である分、高い効果にも期待ができる点が再生医療の利点です。保存療法で良い効果が得られず困っているときは、再生医療での治療も検討したいところです。
ひざの痛みを改善するストレッチと筋力トレーニング

変形性膝関節症を自力で治すことはできませんが、膝の痛み改善を目指すには、ストレッチや筋力トレーニングを実践することが重要です。筋力と柔軟性が備われば、膝への負担軽減につながります。
おすすめのストレッチとトレーニングは次のとおりです。
・足あげ運動
・横あげ運動
・スクワット
・有酸素運動
それぞれの具体的な実践方法と注意点などを紹介していきます。
仰向けストレッチ
変形性膝関節症で膝の痛みがつらいときは、仰向けストレッチをまず実践してみましょう。寝ながらできるストレッチのため、気軽にできる点が魅力です。
2.止まったら5~10秒ほど体勢を維持
3.1~2を続けて5~10回実践
4.反対の足も同様におこなう
※1日あたり3セットが望ましい
上記の手順を、仰向けで寝る状態でおこないます。
足あげ運動
膝が痛いときは、足あげ運動もおすすめです。足あげ運動も、仰向けで横になった状態でおこないます。
2. 反対の足を伸ばした状態でゆっくり上げていく
3. 下から10cmほどの高さで、足を上げた状態を5秒前後キープする
4. ゆっくり足をおろして3秒ほど休憩をはさむ
5. 1~4を20回、両方の足で繰り返す
横あげ運動
同じく寝た状態でおこなう運動では、横あげ運動も膝の痛み改善にはおすすめです。今度は仰向けではなく、横向きに寝た状態で足を動かしていきます。
2. 上の足を延ばした状態でゆっくり上げていく
3. 下から10cmほどの高さで、足を上げた状態を5秒前後キープする
4. ゆっくり足をおろして3秒ほど休憩をはさむ
5. 1~4を20回、両方の足で繰り返す
スクワット
軽く膝に痛みがあるときには、筋力トレーニングのためにスクワットの実践もおすすめです。階段がつらいときに望ましいトレーニングの一つといわれています。
2. 膝が爪先よりも前に出ないようにしながらゆっくり腰を下ろす
3. 痛みが出る寸前のところまで曲げる運動を20回おこなう
ただしスクワットは、膝の痛みが強く出ていて通常の歩行すら困難な方は、かえって膝の痛みを悪化させる可能性があります。無理のない範囲でおこなうトレーニングにしていきましょう。
有酸素運動
有酸素運動をすれば、体力・筋力低下を防げるため、結果として膝への負荷を減らせます。おすすめの有酸素運動は、次のとおりです。
・サイクリング
・ラジオ体操
・スイミング
ほどよく疲れる程度が望ましいです。週2~3回、1回につき30分ほどの有酸素運動を心がけましょう。
【参考】変形性膝関節症の予防策

最後に、変形性膝関節症の予防策として実践したいことを紹介していきます。変形性膝関節症は自力で治すことが難しい症状のため、日常的に膝の痛みに悩まないためには、次の対策が重要になります。
・栄養バランスの良い食事
・定期的な運動
・膝への負担を減らす
・生活習慣の見直し
では、それぞれの重要なポイントや注意点などを解説していきます。
体重管理
肥満が原因で、膝への負担を大きくしているケースは多いです。そのため適切な体重管理は、普段から積極的に実践したいところです。
体重管理には、やはり適切な運動とバランスの取れた食生活が重要になります。反対に過度な食事制限や激しい運動で痩せようとすると、健康を害する恐れがあります。リバウンドにもつながるでしょう。
日常的な運動とバランスの取れた食生活を習慣づけ、生活習慣を正すことで適切な体重をキープしていきましょう。
栄養バランスの良い食事
軟骨がすり減ったり筋力が全体的に低下したりすることには、栄養バランスの乱れも関係しています。一方で栄養バランスの良い食事を心がけていれば、軟骨がすり減る、筋力・体力が低下するなどの状態も最低限防げるでしょう。
栄養を意識して食生活を改善するときは、一部の栄養に偏らないよう意識する必要があります。体に良いものでも、同じものばかり食べていると栄養バランスが乱れるため、野菜、肉、魚などさまざまなものをバランス良く摂取していきましょう。
定期的な運動
運動習慣を普段から身につけていれば、変形性膝関節症になるリスクを抑えられます。運動不足は筋力・体力低下を促すため、結果として変形性膝関節症の症状につながる可能性があります。
ストレッチや筋トレ、散歩(ウォーキング)などが日常的に実践しやすい運動です。重要なのは運動習慣を持つことなので、無理なく運動を習慣化させることを目標にしましょう。
膝への負担を減らす
変形性膝関節症を予防するには、膝への負担を減らせるよう、普段から気を付けることが望ましいでしょう。
・和式トイレを利用しない
・膝を曲げすぎる歩き方をしない
・デスクワーク中心の方は適度に立つ(膝を曲げた状態が続きやすいため)
・膝を酷使する運動を続けない
たとえば上のような対策がおすすめです。膝への負担が普段から多ければ多いほど、変形性膝関節症は発症しやすくなります。
生活習慣の見直し
毎日の生活習慣を全体的に見直して、変形性膝関節症のリスクをなくしていくことも大事です。
・運動不足を解消する
・バランスの取れた食生活を意識する
・ストレスを溜めすぎない
・過度な間食を減らす
・姿勢の悪さを正す
上記のように、生活習慣改善のために実践できることはさまざまあります。特に運動不足が変形性膝関節症につながるケースは多いため、生活習慣を見直し、健康的な生活が送るようしっかりと普段から意識していきましょう。
まとめ
変形性膝関節症を自力で治すことは難しいため、膝の痛みがつらいときは、まず専門のクリニックに通いましょう。そして医師に相談したうえで、普段から実践できる保存療法や運動のポイントなどを理解する必要があります。
膝の痛み改善の効果に期待できるストレッチ・運動はさまざまあります。症状が軽度のものであれば自力である程度痛みを緩和させられるため、膝の痛みがある方は積極的に参考にしてみてください。
※本記事の情報は2022年11月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。