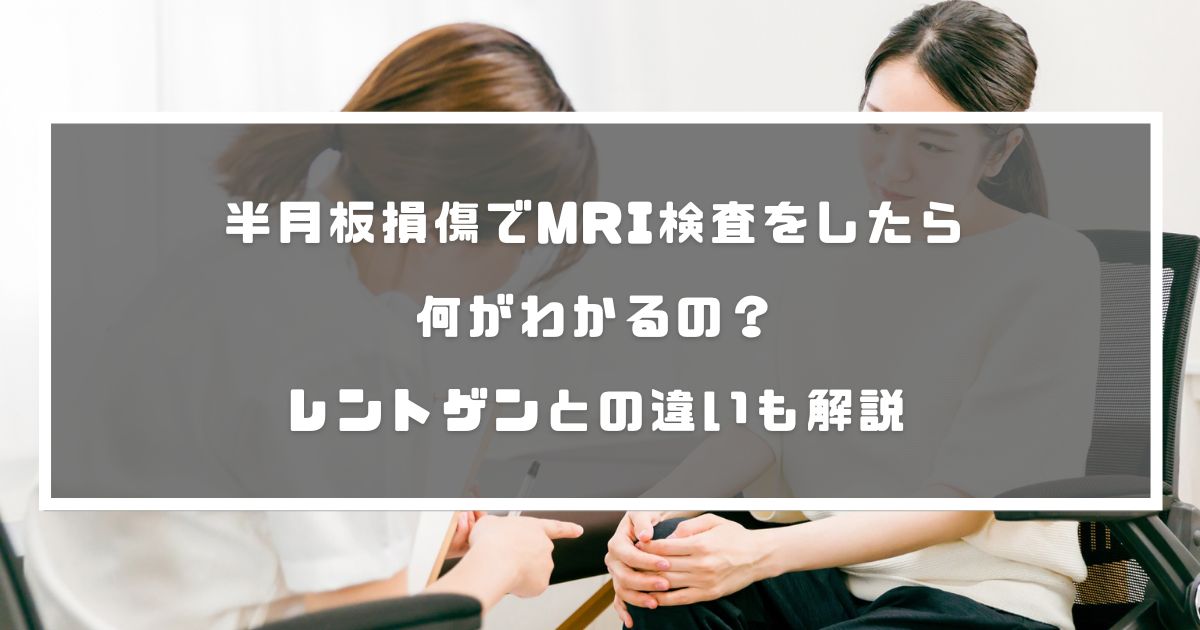半月板損傷とは、半月板に亀裂が生じたり、欠けたりした状態のことを指します。
膝の負荷を分散させる役割と衝撃を吸収する作用のある半月板が損傷し、痛みや腫れが生じる仕組みです。半月板はCTやレントゲンには写らないため、症状の経過と診察から半月板損傷が疑われると、MRI検査が必要になります。
しかし、MRIと聞いて「具体的に何がわかるのか」「何のために検査するのだろう」などの疑問がある方は多いでしょう。またレントゲンとの違いも気になるところです。
本記事では、半月板損傷でMRI検査を受けると何がわかるのか、併せてレントゲンとの違いについて触れていきます。
本記事を読むことで、半月板損傷やMRI検査に対する疑問を解決できるでしょう。半月板損傷でMRI検査を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
半月板損傷の主な症状について

半月板損傷になると、どのような症状が現れるのでしょうか。
ここからは、半月板損傷の主な症状を6つ紹介します。
膝関節の痛み
半月板損傷になると、歩き始めや膝の曲げ伸ばしの際に痛みを感じます。
半月板損傷の痛みの原因は、半月板が損傷したときの衝撃による筋収縮や炎症です。痛みを抑える目的で湿布や消炎鎮痛剤、電気療法などが挙げられますが、痛みが持続する場合は手術が必要になります。
膝の腫れ
半月板損傷の初期段階に関節液がたまり、膝が腫れることがあります。
また半月板損傷が靭帯損傷と合併すると関節血腫を伴い、腫れが強くなるといわれています。膝に負担がかかる動作は、腫れや痛みを悪化させる原因になるため、患部を安静に保つことが重要です。
1週間以上腫れが続く場合は、膝の状態を医師に診察してもらいましょう。
曲げると引っかかる感じがする
キャッチングと呼ばれる引っかかり感も、半月板損傷の特徴的な症状です。
キャッチングは、主に膝を曲げ伸ばしした際に出現し、膝関節に何か挟まるような感覚があります。半月板が損傷すると、膝関節の滑らかな動きを阻害するため、膝が引っかかるような感覚が生じる仕組みです。
膝を曲げられない
半月板損傷の症状の一つとして、膝の曲げ伸ばしが困難になることが挙げられます。膝を曲げたり伸ばしたりした際に、痛みが伴うようになります。
症状が悪化すると、断裂した半月板が関節内に入り込むことで膝が動かなくなるロッキング現象が起こり、激しい痛みが生じるでしょう。
膝に水がたまる
膝の水とは、関節液のことを指します。半月板損傷になると滑膜が炎症を起こし、関節液が余分に出てしまう仕組みです。
一般的には関節液が余分に出ている状態のことを、膝に水が溜まると表現されています。膝の関節液が貯留した状態を放置すると、炎症と痛みが悪化する可能性が高くなるため、医療機関を早急に受診しましょう。
階段昇降時に異常な音がする
半月板を損傷していると、階段の昇降や膝の屈伸時に、膝から異常音がする場合があります。
膝の異常音は、半月板損傷の初期から進行期に現れます。初期は軟骨の水分が減ることで音が鳴り、進行期は骨同士がぶつかり合うことで音が鳴る仕組みです。
半月板損傷の場合MRI検査でわかること

半月板の損傷形態はさまざまあり、MRIは治療方針を決定するために必要な検査です。
MRIが半月板の断裂を検出する感度は、約95%といわれています。半月板損傷の疑いでMRI検査を受けた場合、何がわかるのでしょうか。膝のMRI検査でわかる主な症状は以下の通りです。
順に紹介します。
靭帯や半月板の損傷
MRIを撮ることにより、靭帯や半月板の損傷具合が把握可能です。しかし、小さな断裂や半月板の外側が損傷している場合は、MRI検査での診断が難しいといわれています。
また半月板損傷により痛みが強く、歩行困難で膝の曲げ伸ばしができない場合は、手術が必要になることもあります。
変形性膝関節症の疑い
MRIは骨の内部まで撮影できるため、変形性膝関節症の進行状態も確認できます。変形性膝関節症の初期から進行期、末期までの進行具合が把握可能です。
また変形性膝関節症の疑いでMRI検査を受けると半月板損傷を合併している場合が多く、半月板損傷の有病率は60%といわれています。
軟骨のすり減り具合
加齢や年齢による軟骨のすり減り具合もMRI検査でわかります。MRIの画像はコントラストが強いため、レントゲンでは見られない軟骨の状態を鮮明に見られる点が特徴です。
また軟骨のすり減り具合によっては、変形性膝関節症と診断される場合もあります。
骨の内部の炎症
MRIは骨の中の状態が精密に確認でき、骨内部にまで損傷や炎症が及んでいるかどうなのかが調べられます。
また骨内部の炎症や損傷のみならず、骨髄浮腫や骨壊死、骨嚢胞、ガングリオンなどのレントゲンやCTではわかりにくい存在も見つけられます。
半月板損傷のMRIとレントゲンの違い

MRIとレントゲンは、どちらも体内の状態を見られる検査ですが、それぞれ特徴が異なります。
MRIとレントゲンは、具体的に何が異なるのでしょうか。2つの違いについて解説します。
MRIでは骨の内部や骨以外の組織の撮影が可能
MRIでは半月板や靭帯、軟骨などの骨の内部や骨以外の組織の撮影が可能です。
MRIは膝の骨の状態を詳しく調べられるため、レントゲンではわからない膝の怪我や疾患を見つけられます。レントゲンでは膝に異常がないケースでも、MRI検査によって膝に疾患が見つかることも少なくありません。
レントゲンでわかるのは骨の外見のみ
レントゲンは骨の形状のみ確認できるため、軟骨や筋肉、半月板などの損傷は、レントゲンには写りません。
骨の内部や骨以外の組織は写らないものの、レントゲンは骨同士の隙間を見て軟骨のすり減り具合を評価できます。骨の異常を確認できることに加え、MRIと比べて検査時間が短い点も特徴の一つです。
半月板損傷でMRI検査をうけるメリット

MRI検査を受けることで得られるメリットはさまざまです。ここではMRI検査のメリットを大きく分けて2つ紹介します。
順に紹介します。
骨以外の組織の状態を把握できる
MRI検査は、骨の形状のみわかるレントゲンと異なり、骨以外の組織の状態を精密に把握できるメリットがあります。
またMRIは骨内部の状態も見られるため、膝の疾患により骨内が痛んでいないかまで確認可能です。MRI以外の検査では確認できない膝の疾患や、怪我を見つけられるでしょう。
放射線被曝しない
放射線検査のレントゲンとは異なり、MRIは磁気を使用して撮影するため、医療被曝がありません。
強力な磁気の中で検査がおこなわれますが、磁気自体が人体に悪影響を及ぼす可能性は低いとされています。身体への影響が少ないことで、妊娠前や妊娠中、子供でも安心して検査を受けられる点がメリットです。
半月板損傷でMRI検査をうけるデメリット
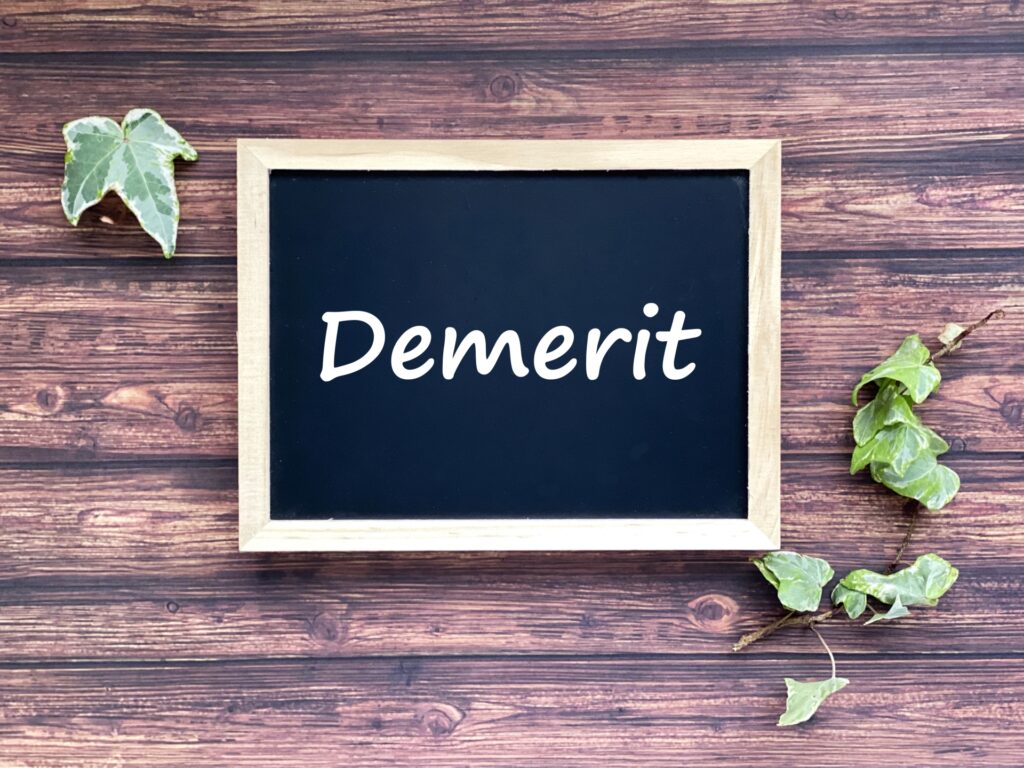
MRI検査はメリットもあれば、デメリットも存在します。
命にかかわる場合もあるため、医師や看護師の指示に従いましょう。
検査時間が長い(30分~1時間程度)
MRIは検査時間が30分〜1時間程度かかるデメリットがあります。
部位にもよりますが、膝のMRI検査の所要時間は、片脚あたり20分程度です。撮影以外に受付や注意事項の説明、待ち時間などがあることも把握しましょう。
また狭い空間で大きな音が聞こえるため、閉所恐怖症の方や大きな音が苦手な方は長時間の我慢が必要です。
体の中に金属がある場合は検査できない
体内に金属がある場合は、MRI検査を受けられません。
検査室内では強い磁場が発生しており、金属がMRIに引き寄せられてしまいます。そのため、手術で体内に金属や電子機器を入れている方は、MRI検査ができないケースが大半です。
他にも磁力の影響を受けるものとして、湿布や貼付薬、化粧などが挙げられます。
半月板損傷の治療方法

半月板損傷の治療方法について紹介します。
半月板損傷を放置して症状が進行した結果、変形性膝関節症を発症する恐れもあるため、早期の治療が大切です。
軽度症状の場合は保存療法
半月板損傷の症状が軽度の場合、保存療法をおこないます。
保存療法には、薬物療法や物理療法、装具療法、運動療法などがあり、組み合わせて治療することが大切です。半月板の外側は自然治癒能力が高く、保存療法でも症状の改善が期待できます。
しかし、半月板の損傷具合により効果が得られない場合は、医師に手術療法を提案される場合もあります。
将来的なリスクを減らすなら手術療法
手術療法は、保存療法で効果が得られない場合に検討される治療方法です。
半月板損傷を放置すると変形性膝関節症に移行するため、手術療法は将来的なリスクを減らす目的もあります。半月板損傷の手術は、半月板を縫い合わせる縫合術と、半月板を切り取る切除術の2種類が挙げられます。
手術療法は入院やリハビリなどのデメリットがあるものの、早急な痛みの緩和が期待でき、変形性膝関節症の発症リスクを減らせる点がメリットです。
自己組織を使用する再生医療
再生医療は、自身の幹細胞を膝に直接注射する最先端の医療です。
再生医療は自己組織を使用するため、手術や入院の必要がなく、体に大きな負担をかけない治療として注目されています。膝の動きや痛みの改善のみならず、半月板損傷の拡大や悪化を予防できるメリットもあります。
長期間治療しても症状が改善されない方や、手術に抵抗がある方は、再生医療を検討するとよいでしょう。

まとめ
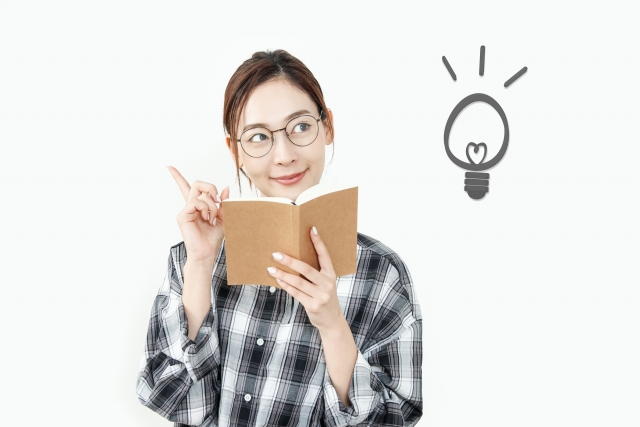
MRIは半月板の損傷具合のみならず、変形性膝関節症や軟骨の状態、骨内部の炎症などが高精度で診断できる検査です。
また骨の形状のみわかるレントゲンとは異なり、MRIは骨内部や骨以外の組織が撮影できる特徴があります。半月板の損傷形態はさまざまあるため、最適な治療法を考えるうえでもMRIは有用です。
MRIは多くのメリットがありますが、注意点を十分理解しなければ命にかかわる可能性もある検査です。半月板損傷の方は、デメリットを踏まえたうえでMRI検査を受け、自身に適した治療方針を決定しましょう。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。