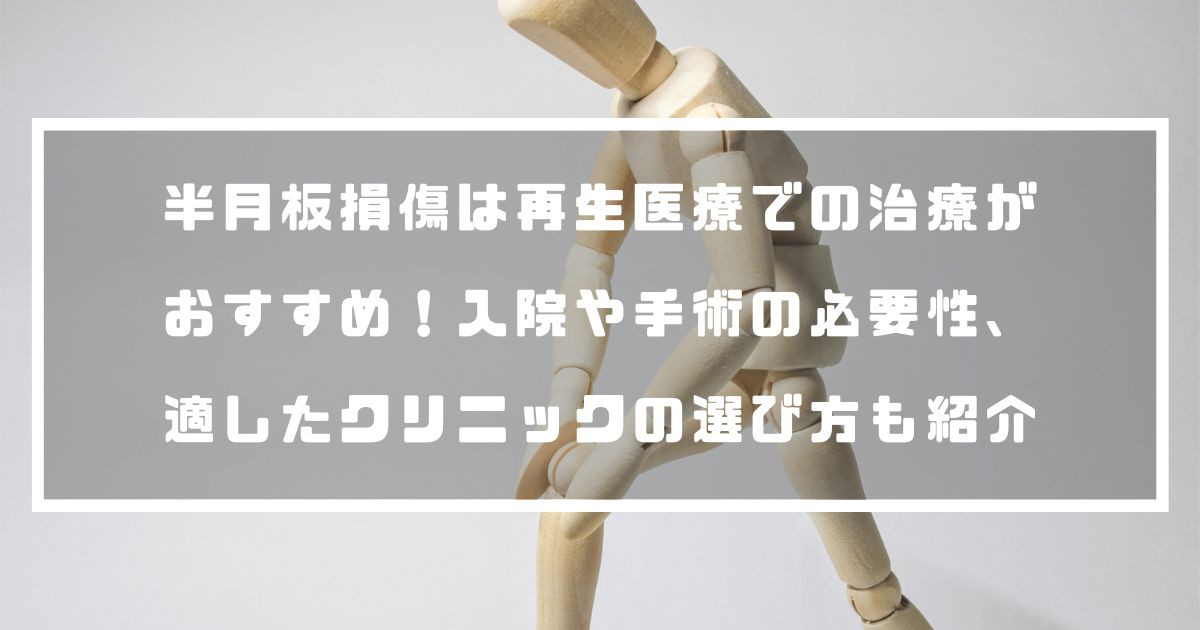半月板損傷は、文字どおり半月板の損傷によってひざの痛みや、ずれるような違和感が現れる病気です。症状が重い場合は手術療法が検討されますが、半月板の機能が失われ、変形性ひざ関節症に移行するリスクがあります。
リスクを含めて手術を受けるか悩んでいる方には、再生医療による治療もおすすめです。
本記事では、半月板損傷の基本情報や、再生医療のメリット、デメリットを紹介します。再生医療の種類もわかるため、半月板損傷で手術を躊躇ってる方は、ぜひ参考にしてみてください。
半月板の傷は自然にはほぼ治らない

半月板の損傷は、そのまま放置しても自然に治ることはありません。なぜなら、半月板の内側3分の2には血管が存在しておらず、欠損すると修復が困難になるからです。
半月板の損傷をそのまま放置すると、軟骨が少しずつすり減り、数年後には変形性ひざ関節症に移行する可能性もあります。
半月板とは
そもそも半月板とは、ひざ関節の大腿骨と脛骨の間にあるC型の線維軟骨で、内側と外側の2箇所に存在します。主な役割は、関節の位置を安定させ、関節にかかる体重や衝撃による負荷を吸収、分散させることです。
半月板が損傷すると、歩行時の痛みやひざの曲げ伸ばしが困難になるなど、さまざまなトラブルが起こります。
半月板が損傷する原因
半月板の損傷には、次のような原因が挙げられます。
・加齢による軟骨の劣化
・スポーツによるひざへのダメージ
それぞれの原因について詳しく解説します。
加齢による軟骨の劣化
年齢を重ねると軟骨は劣化し始めます。半月板も、クッションとしての役割が少しずつ衰え、小さな衝撃でも損傷しやすくなるため日常生活でも注意が必要です。
たとえば、立ち上がったり、小さい段差から飛び降りたりする動作でも半月板損傷を起こす可能性があります。
とくに、40代以降は勢いよく踏み込まないようにしたり、太ももの筋肉を鍛えたりして、関節に負担をかけないように心がけましょう。
スポーツによるひざへのダメージ
若い方でもスポーツによってひざにダメージを受けると、半月板損傷を起こす場合があります。
とくに半月板損傷のリスクがあるのは、バスケットボールやバレーボール、サッカーなど、ひざに強い負荷や捻るような衝撃が加わるスポーツです。
世界的に活躍するスポーツ選手の多くが半月板損傷を経験しており、保存療法で症状が軽快する場合もあります。
半月板損傷の症状
半月板損傷の主な症状は次のとおりです。
・歩いたときにひざが痛い
・階段を登ったときにひざに引っ掛かりを感じる
・ひざの曲げ伸ばしができない
・ひざに水が溜まる
症状によって適切な治療は変わるため、詳しく解説します。
歩いたときにひざが痛い
半月板損傷の代表的な症状は、歩行時の痛みです。症状が悪化すると足を動かせないほどの痛みがあらわれます。
これらの痛みは、半月板損傷そのものではなく、筋収縮や炎症によるものです。筋肉収縮は、半月板損傷を起こすほどの強い負荷からひざを守るためにおこりますが、反対に筋肉を傷めてしまいます。
傷んだ筋肉を修復するために炎症反応が起こり、痛みの原因になります。
階段を登ったときにひざに引っ掛かりを感じる
半月板損傷の症状には、階段を登ったときにひざが引っ掛かることも挙げられます。
また、ひざがガクッとずれるような違和感が現れることもあり、転倒するリスクがあるため注意が必要です。
ひざの曲げ伸ばしができない
半月板損傷が進行して軟骨がすり減ると、ひざの曲げ伸ばしが困難になります。
重症化すると半月板の一部が関節内に挟まり、激痛とともに急に曲げ伸ばしができなくなる「ロッキング」という症状が現れることもあります。
ロッキングが起こると挟まった半月板を戻すための処置が必要になり、日常生活にも支障がでるでしょう。
ひざに水が溜まる
ひざ関節は関節包と呼ばれる組織に覆われており、内側にある滑膜から、ひざの動きをスムーズにする関節液が分泌されます。
半月板を損傷すると滑膜が刺激され、滑液を過剰に分泌して関節包にたまってしまいます。水がたまると痛みや腫れ、熱感などが現れるため治療が必要です。
必ずしも痛みを感じるわけではない
半月板の内側には神経が通っていないため、必ずしも痛みを感じるわけではありません。
しかし、半月板損傷を放置すると、筋収縮によって傷ついた筋を修復するために炎症がおこり、強い痛みを感じるようになります。
とくに、加齢によって半月板損傷を起こす場合は、大きなきっかけがないため、ただのひざ痛だと思い込み、発見が遅れてしまう場合もあります。
痛みがない場合でも、ひざの曲げ伸ばしがしづらくなったり、引っかかったりするような違和感がある場合は、早めにクリニックを受診しましょう。

半月板損傷をした場合

半月板損傷が起こった場合、症状にあわせて保存療法もしくは手術療法が行われます。
軽症であれば、リハビリテーションや抗炎症薬などの保存療法で改善が期待でき、半月板の温存が可能です。
一方、重症や保存療法でも改善が見られない場合は、手術療法が選択され、損傷部分を切り取る切除術や損傷部分を縫い合わせる縫合術が行われます。
以前は切除術が半月板損傷の主な治療法でしたが、現在はリスクの観点から保存療法が重視されるようになりました。
必ず手術をする必要はない
保存治療で効果が得られない場合や、日常生活に支障が出るほどの痛みがある場合は、手術による治療が一般的です。
しかし、現在は損傷部分を再生する再生医療の選択肢もあるため、必ずしも手術する必要はありません。
また、手術には合併症や変形性ひざ関節症をきたすなどのリスクもあるため、慎重に検討しましょう。
半月板損傷は放置すると危険
半月板損傷は必ずしも痛みがあるわけではありませんが、放置していると状態が悪化し、合併症や変形性ひざ関節症に移行する可能性が高くなります。
重症化すれば手術と長期的なリハビリテーションが必要となり、早期の社会復帰が難しくなる場合もあります。
早期に治療を始めれば、保存療法で後遺症のリスクを軽減できるため、早い段階で適切な処置を受けることが大切です。
手術はリスクも大きい
半月板損傷の手術には、次のようなリスクがあります。
・縫合術をした方の3割が再断裂している
・半月板の切除手術でひざ関節症の確率が高くなる
・リハビリに数か月かかる
半月板損傷の手術には縫合術と切除術の2種類がありますが、どちらも数年後には再発やひざ関節症に移行するリスクがあります。
また、手術をおこなうとリハビリに数か月かかるため、仕事復帰が遅れ生活に支障が出る場合もあるでしょう。
状態によっては手術が必要となるケースもありますが、他の治療法が選択肢にあるうちは慎重に検討する必要があります。

半月板損傷は再生医療で治療する

以前は、手術が半月板損傷の主な治療法とされていましたが、現在では半月板を温存しながら治療が期待できる再生医療が注目されています。
ここでは、半月板損傷における再生医療の基本情報とメリット、デメリットを解説します。
再生医療とは
再生医療とは、事故や病気などによって失われた機能を、体の再生する力を利用して取り戻す医療です。
生きた細胞や人工材料、遺伝子を含む細胞などさまざまな再生医療があり、疾患に応じて選択されています。半月板損傷の治療も再生医療を用いれば、体の負担を抑えながら損傷部分の修復が可能です。
また、合併症やひざ関節症に移行するリスクも低く、スポーツ選手や手術に抵抗がある方に適しています。
半月板損傷を再生医療で治療するメリット
半月板損傷を再生医療で治療するメリットは次のとおりです。
このように、再生医療は手術でかかる負担を抑えて治療できる点が大きなメリットといえます。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
半月板を切除しなくてよい
再生医療は、半月板を切除せず治療が可能です。半月板損傷の手術を受ける方の7割は切除術を選択しているデータがあります。
しかし、半月板を切除すると数年後には変形性ひざ関節症に移行するリスクが高まり、新たな治療が必要になる可能性も0ではありません。
再生医療であれば、どのような症状でも半月板を残しつつ治療できるため、変形性ひざ関節症に移行するリスクを軽減できます。
拒絶反応やアレルギー反応などの副作用が少ない
再生医療は自身の細胞を使用して治療をおこなうため、拒絶反応やアレルギー反応などの副作用が少ないとされています。
治療後に自己細胞を注射部位が腫れたり痛んだりする場合がありますが、2〜3日経てばおさまり、日常生活にもあまり支障は出ません。
入院する必要はない
再生医療による半月板損傷の治療は、入院する必要がない点もメリットです。
半月板損傷の再生医療は、注射器で脂肪や血液を採取し、患部に注入するシンプルな治療法であるため、日帰りで受けられます。
術後に入浴や飲酒は控える必要はありますが、歩行や日常生活上での動作などに制限はなく、普段どおり過ごせるでしょう。
患者が受ける痛みが少ない
再生医療のメリットは、患者が受ける痛みが少ないことです。
脂肪細胞の採取や注入は局所麻酔を打ったあとにおこなわれるため、施術中に痛みを感じることはほぼありません。痛みがあったとしても局所麻酔をする際の注射によるものであり、数分で終わります。
どうしても痛みが不安な方は、あらかじめ医師に相談しておくといいでしょう。
半月板損傷を再生医療で治療するデメリット
半月板損傷の再生医療にはメリットが多い反面、次のようなデメリットもあります。
上記のデメリットを知らずに治療を受けると、望む結果が得られない場合もあるため、しっかり確認しておきましょう。
治療効果に個人差がある
再生医療の治療効果には個人差があり、すべての方が望む100%の結果を得られるわけではありません。
治療を受けてからすぐ改善がみられる方がいる一方で、1か月以上の時間がかかる方もいます。また、体質によって効果を得られない場合もあります。
そのため、個人差があることをしっかり理解したうえで治療を受けることが大切です。
特定の方には効果が出にくい
半月板損傷の再生医療は、特定の方には効果がでにくいとされています。
具体的には、肥満の方や、重症化して変形性ひざ関節症に移行している方などです。とくに変形性膝関節病は、膝の軟骨がすでにすり減った状態であり、なくなった軟骨を作ることは再生医療でもできません。
再生医療を検討するのであれば、早期治療と体重管理が必要です。
半月板損傷への再生医療は大きく2つ

半月板損傷の再生医療は大きく2つに分けられます。
・幹細胞治療
・PRP(Platelet Rich Plasma)治療
それぞれの治療内容や流れを詳しく解説します。
幹細胞治療
幹細胞治療は、新しい細胞を作り出し補充する幹細胞を利用した再生治療です。
幹細胞を用いた治療は比較的新しい技術であり、活用できる分野や効果など、まだ解析されていない部分もあります。
しかし、臨床実験の積み重ねにより、半月板損傷を含む一部の疾患に安全性や効果が確認されており、厚生労働省から個別に治療認可が与えられています。
自身の脂肪を使う治療法
半月板損傷の幹細胞治療は、自身の脂肪の中にある幹細胞を採取、培養した後、関節に注射して欠損の修復を目指します。脂肪由来の幹細胞を利用する治療には、幹細胞を培養するASC治療と、培養しないSVF治療の2種類があります。
幹細胞を培養するASC治療は、脂肪採取から注入までに4〜6週間の時間が必要です。一方で幹細胞を培養しないSVF治療は、当日中に注入でき、日帰りで治療を受けられます。
どちらも効果に大きな差はありませんが、SVF治療は多量の脂肪が必要となり、患者に負担がかかる場合があります。クリニックによっても導入している治療法は異なるため、事前にしっかり説明を受けることが大切です。
治療の流れ
半月板損傷における幹細胞治療の流れは、次のとおりです。
1.血液検査
2.局所麻酔をして脂肪細胞を採取
3.幹細胞の抽出、培養(4〜6週間)
4.幹細胞を関節内に注入
5.アフターカウンセリング、帰宅
治療後は、経過観察のために通院が必要です。効果の現れ方には個人差がありますが、数か月~数年にわたって効果の持続が期待できます。
PRP(Platelet Rich Plasma)治療
PRPとは、血液の中の血小板を凝縮した多血小板血漿のことです。血小板には成長因子が多く含まれており、傷ついた組織の修復を促進し、痛みを軽減する効果が期待できます。
半月板損傷のみでなく変形性ひざ関節症の治療にも利用されています。
自身の血液を使う治療法
半月板損傷におけるPRP治療では、自身の血液から血小板を凝縮し関節に注入します。幹細胞治療と同様、自身の組織を使用するため、感染やアレルギーなどの副作用のリスクが低く、日帰りで受けられる治療です。
ただし、血小板には半月板自体を修復する作用はなく、筋収縮による筋損傷の修復や、炎症の抑制で痛みの緩和を促します。あくまで対症療法であり、根本的な治療には幹細胞治療やほかの治療の併用が必要です。
治療の流れ
PRP治療の流れは次のとおりです。
1.採血
2.遠心分離で血漿成分を抽出
3.関節に注射
上記の工程は短時間で終了するため、日帰りで受けられます。注射後は1週間程度、痛みや腫れが続く場合もありますが次第におさまります。
大谷翔平選手も受けた治療
PRP治療はメジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が、右肘靭帯の部分断裂を患った際に受けたことでも知られる治療です。
症状によってはPRP治療が適さない場合もありますが、手術よりも短期間でプレー復帰が期待できることからアスリートの怪我の治療に多く活用されています。
また、欧米ではPRP治療の有効性や安全性が数多く報告されており、副作用が少ない点もアスリートの怪我治療で注目される要因でしょう。
再生医療は保険適用外
再生医療は一部の疾患で安全性や効果が認められています。しかし、臨床データがまだまだ少ないことから、大半の疾患で保険適用されていません。
半月板損傷も例外ではなく、幹細胞治療は100万円前後、PRP治療は3万円〜と、高額な費用が必要です。
ただし、クリニックによって費用は異なるため、予算があまりない方はよく比較しながら選択してみてください。
自身に適したクリニックを見分ける方法

半月板損傷における再生医療は、クリニックによって治療内容や費用が異なります。そこで、自身に適したクリニックを見分けるためには、次のポイントを確認してみてください。
それぞれ詳しく解説します。
明確な費用の説明がある
自身に適したクリニックを見分ける方法は、明確な費用の説明があるのかをチェックしましょう。
先述したように、半月板損傷の再生医療は保険適用外となっており、費用はクリニックによってさまざまです。場合によっては高額な治療費が必要になる場合もあり、事前に把握しておかないと予算をオーバーする可能性があります。
そのため、カウンセリングや診察を受けた際に、施術費用や麻酔代、薬代などトータルでかかる費用を明確に説明されるのかを確認しましょう。
医師から手術以外の治療法を提案がある
クリニックを選ぶ際は、医師から手術以外の治療法を提案があるのかも注目しましょう。医療技術が進歩している現在では、半月板損傷の治療は手術のみではありません。
再生医療を含め、症状や副作用などを加味して一人一人にあった治療法を提案されるクリニックを選ぶことが大切です。
再生医療は生きたままの細胞を培養している
再生医療を検討する場合は、生きたままの細胞を培養しているクリニックを選びましょう。幹細胞治療の中には、細胞を冷凍保存して利用する方法と、生きたままの細胞を培養する方法があります。
生きたままの細胞の方が治療効果が高いとされているため、カウンセリングの際に治療の詳細を確認してみてください。
幹細胞の数は1億個以上を培養している
幹細胞治療を検討している場合は、1億個以上の幹細胞を培養しているクリニックを選ぶのもおすすめです。一般的な幹細胞治療は、1千万個程度の幹細胞を投与しますが、クリニックの中には1億個以上培養するところもあります。
海外の実証データでは、幹細胞の数が多いほど治療効果が高くなることが確認されているため、どのくらいまで幹細胞を培養して投与するのかも確認しましょう。
まとめ

半月板損傷の再生医療は、手術に比べ副作用が少なく、手軽に治療を受けられます。
効果には個人差がありますが、損傷した半月板を修復して根本的な改善が期待できるため、手術をためらっている方も一度は検討したい治療法です。
ただし、クリニックによって治療内容は異なり、保険適用外で費用が高額になるデメリットもあります。
再生医療を検討する方は、本記事で紹介した内容をぜひ参考に、自身にあっている治療やクリニックを探してみてください。
※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。