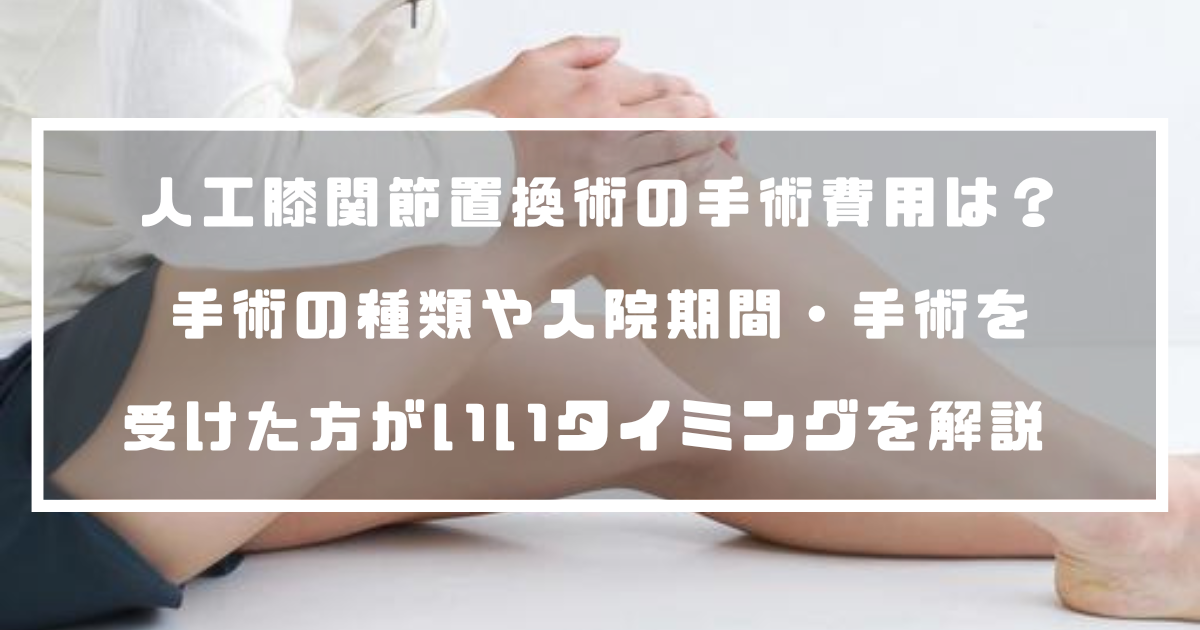人工膝関節置換術は手術費用のみならず、診察料金やリハビリ、入院費などが発生するため高額になりますが、健康保険が適用されます。
医療費用の自己負担額は1〜3割のみで、経済的な負担を最小限に抑えられます。また高額療養費助成制度や、限度額適用認定制度などを活用すると、さらに自己負担額を減らせる点がメリットです。
本記事では人工膝関節置換術を検討している方に向けて、手術の費用や種類、注意点、治療方法について解説します。人工膝関節置換術の手術について不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。
人工膝関節置換術とは?

人工膝関節置換術は、40年ほど前から日本国内で実施されている膝関節に関連した手術です。一般的な治療方法として定着しつつあり、整形外科での手術件数は年間9万例以上に達しています。
さらに厚生労働省が発表したデータによると、人工膝関節置換術の患者の平均年齢は75歳で、若年層よりも高齢者が手術を受ける傾向にあります。
人工膝関節置換術が必要な疾患
人工膝関節置換術が必要な疾患は、主に次の2つです。
それぞれの疾患について解説します。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、加齢や肥満、遺伝などの原因で膝関節が変形し、痛みや腫れ、炎症をきたした状態を指します。
膝関節の正面にある軟骨が劣化すると、関節内部にある滑膜が炎症を起こし、次第に関節周りの骨が変形します。骨が変形するまでに数十年かかりますが、症状を放置すると日常生活が送れなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
厚生労働省は、日本国内に自覚症状のある患者が約1千万人、潜在的な患者(X線診断によるもの)は約3千万人いると推定しています。
関節リウマチ
関節リウマチ(Rheumatoid Arthritis)は、免疫異常が原因で関節に炎症や痛み、腫れを引き起こす状態を指します。免疫異常の原因は具体的に解明されておらず、遺伝要因や喫煙、歯周病などが考えられると指摘されています。
血液検査やRF、抗CCP抗体、炎症反応、症状持続期間などをスコア化して症状の進行度を判断するため、見た目のみで関節リウマチと判断できません。
厚生労働省は、日本国内のリウマチ関節を発症している患者が人口の0.6〜1%を占めており、患者数は60万〜100万人に上ると推定しています。
人工関節置換術の種類と費用
人工関節置換術の種類は、次のとおりです。
それぞれの手術内容と費用を解説します。
人工膝単顆置換術(UKA)
人工膝単顆置換術(UKA)は、患部の中で症状が進行している一部分のみ人工物に置き換える手術方法です。
一般的には、膝関節の内側にある軟骨が劣化するケースが多く、外側の軟骨が維持できると判断された場合、人工膝単顆置換術(UKA)が実施されます。
すべての膝関節を除去しなければ、前十字靱帯と後十字靱帯を温存できるため、膝関節の生理的な動きを残せる点がメリットです。
また、人工関節のサイズが小さいため、皮膚の切開を最小で済ませられます。
人工膝関節全置換術(TKA)
人工膝関節全置換術(TKA)は、膝関節のすべてを人工物に置き換える手術方法です。
膝関節の内側と外側どちらの軟骨も劣化していると判断された場合、部分的な置換術ではなく、膝関節をすべて人工物に置き換える人工膝関節全置換術(TKA)が実施されます。
大きな手術ですが、リハビリを終えると1日5,000〜6,000歩を目安に長時間歩行が可能になります。痛みが酷く歩行が困難な方は、日常生活の不自由さが大きく改善されるでしょう。
人工膝関節置換術にかかる費用
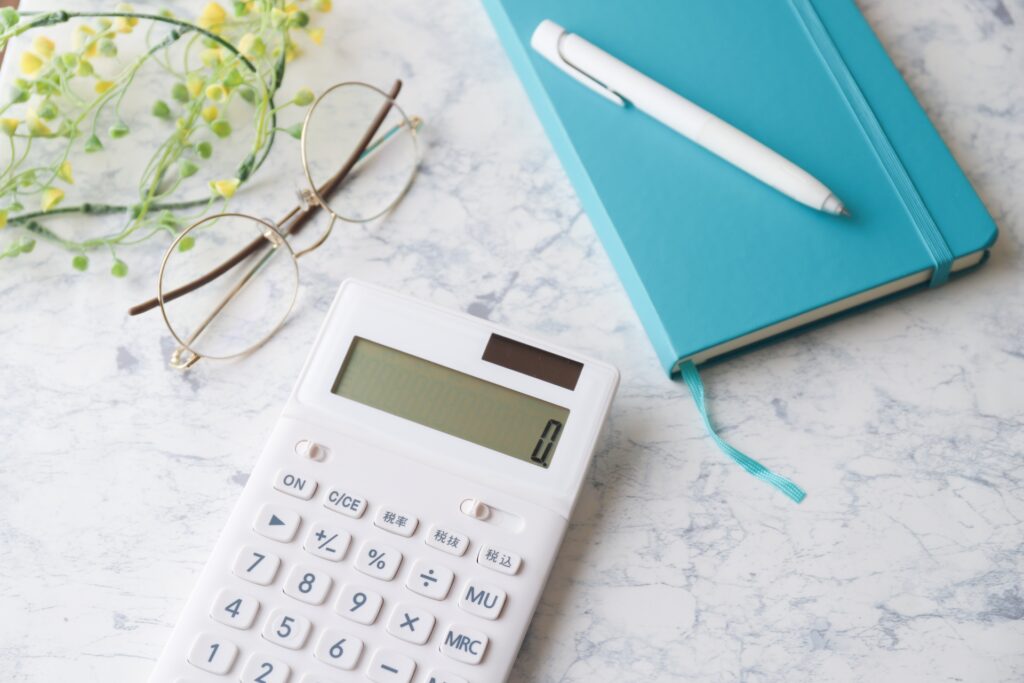
結論からお伝えすると、人工膝関節置換術の医療費は約200万〜250万円です。
ただし人工膝関節置換術は、基本的に保険が適用される手術方法のため、3割負担の場合は約60万〜80万円、1割負担の場合は約20万〜250万円になります。
医療費に含まれる項目は次のとおりです。
- 手術治療費
- 入院費
- 看護費
- 室料
- 食事代
一般的に人工膝単顆置換術(UKA)は約2週間、人工膝関節全置換術(TKA)は約1か月の入院が必要です。具体的な支払い費用は、保険の有無や手術の種類、診療内容、入院期間により大幅に変動します。
また、人工膝関節置換術は高額療養費制度が適用される手術のため、制度の指示にしたがって申請を出せば、収入に応じた一部の自己負担額が環付されます。
人工膝関節置換術手術で受けられる医療制度や助成
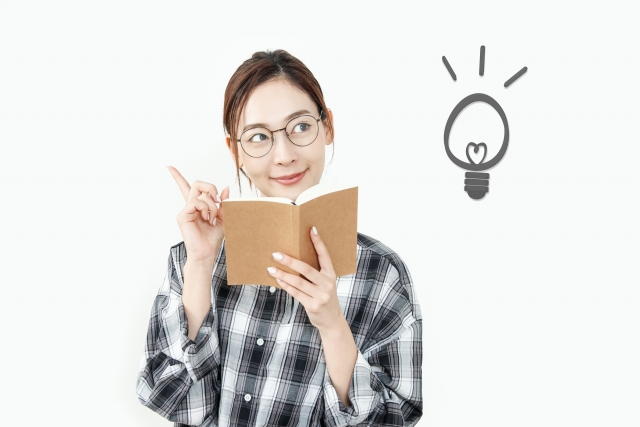
人工膝関節置換術で受けられる医療制度や助成は、次のとおりです。
それぞれの医療制度や助成の条件や内容、限度額、申請方法などを解説します。
高額医療制度
高額医療制度(高額療養費制度)とは、数十万〜数百万円の医療費が発生した場合、一定の医療費(自己負担限度額)を超えた分を払い戻しする制度です。
原則、1か月間(同月の1日〜末日まで)で発生した医療費が自己負担限度額を超えたとき、自己負担額を超えた費用分が後から払い戻されます。
70歳以上もしくは69歳未満の年齢と所得水準によって自己負担額が変動するため、全国健康保険協会の公式サイトから確認してみてください。
また保険上限額は設けられておらず、個人の自己負担額以上の医療費の払い戻しが受けられます。
申請方法は、加入している公的医療保険によって異なるため、具体例を2つ紹介します。
- 健康保険(協会けんぽの場合):健康保険証に記載されている協会けんぽの支部に書類を提出
- 国民健康保険(東京都港区の場合):自己負担限度額を超えた3〜4か月後に自宅宛に申請書が郵送
さらに、事前に高額医療制度の申請を済ませておけば、一時的に医療費全額を立て替える必要はありません。
限度額適用認定制度
限度額適用認定制度は、69歳以下の方を対象に、高額な医療費が発生して実際に支払いをしたあとに申請を出すと、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻しされる制度です。
年齢と年収水準によって定められる自己負担限度額は個人差があるため、全国健康保険協会の公式サイトから確認してみてください。
保険上限額は設けられておらず、個人の自己負担額以上の医療費の払い戻しが受けられます。高額医療制度は事前申請が可能ですが、限度額適用認定制度は一度医療機関への支払いをしてから医療費の払い戻しがあるため、一時的に経済的な負担が発生します。
申請方法は次のとおりです。
- 協会けんぽの各都道府県支部に限度適用認定申請書を提出
- 限度額適用認定証の交付
- 医療機関窓口で限度額適用認定証を提示
- 後日払い戻し
医療機関を受診するまでに、限度額適用認定証が交付されるように準備を進めましょう。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、障害者手帳が交付された18歳以上を対象に、障害を軽減させる効果のある手術や、治療の高額医療費を一部負担する制度です。原則として自己負担額は医療費の1割ですが、世帯所得に応じて1か月ごとの自己負担上限額が定められます。
人工膝関節置換術は、自立支援医療制度の対象となるため、実施主体である市町村の役場に相談してみてください。市町村によってはインターネットでの申請ができず、すべて郵送でのやりとりになる場合もあります。
更生医療
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する患者を対象に、障害を軽減させる効果のある手術や、治療の高額医療費を一部負担する制度です。
税金の所得額によって自己負担額が決まる制度で、各市町村の窓口もしくは役所の公式サイトから確認できます。人工膝関節置換術は、身体障害者福祉法第4条に該当するため、実施主体である市町村に申請の相談をしてみてください。
障害年金
障害年金は、20歳〜64歳で病気や事故で障害を抱えた方の医療費を国が支援する制度です。人工膝関節置換術は、障害等級3級に該当する病気のため障害年金を受けられます。
ただし障害年金を受け取るためには、初診日までに厚生年金保険への加入が必須です。
初診日までに国民年金に加入している場合は原則として受給できませんが、次の条件を満たせば障害年金が認可される可能性があります。
- 状態が悪化した場合
- 社会的治癒が認められた場合
日本年金機構もしくは各市町村の窓口に相談してみてください。
傷病手当金
傷病手当金は被保険者を対象に、病気や怪我で仕事が困難な被保険者と、その家族の生活を保障するための制度です。
病気や怪我が原因で会社を3日間以上休んだうえ、事業主から報酬を受けられなかった場合、4日目以降の休んだ日数分に手当が支給されます。1日あたりの金額は、支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(3分の2)で計算できます。
人工膝関節置換術の場合、手術で2週間〜4週間ほど会社に行けなくなるため、全国健康保険協会の公式サイトから申請してみてください。
介護保険
介護保険とは、介護が必要な60歳以上の方を対象に、生活を支えるための制度です。
人工膝関節置換術が必要な慢性関節リウマチは、介護保険が受けられる特定疾患に含まれているため、症状の深刻さに応じて約5万円〜36万円の支援が受けられます。
ただし、具体的な支援額は、サービスの種類や地域により変動するため、各市町村の窓口で確認してみてください。
人工膝関節置換術の後に気をつけること

人工膝関節置換術後に気をつけるポイントは、次のとおりです。
それぞれのポイントについて解説します。
人工関節に負担をかける運動・動作を控える
人工膝関節置換術後は、痛みや可動域の制限が改善されることで活発な動きをしたくなることもありますが、膝への負担を控えることが大切です。軽いウォーキングや水泳などは問題ないものの、ジョギングやスキー、球技などの膝に負担かかる運動は避けましょう。
また日常生活においても、次のような工夫をして膝への負担を最小限に抑えましょう。
- 布団の代わりにベッドで寝る
- 座布団の代わりに椅子に座る
- 2階の寝室を1階に移す
日常生活でも人工関節への負担を抑えると、周りの筋肉や骨への過剰な負荷を軽減させられます。
膝を冷やさない
人工膝関節置換術後、膝の痛みが多少残るケースがありますが、膝を温めると痛みが軽減します。
膝が冷えると血流の流れが悪くなり痛みを感じやすくなるため、入浴やサポーターの装着などでできる限り保温する工夫をしてみてください。
重い荷物を持たない
人工膝関節置換術後は、人工膝への負担を抑えるために重い荷物を持たないようにしましょう。
買い物をするときはカートを使用したり、エレベーターやエスカレーターで重い荷物を持ち歩いたりする時間が長くならないようにするなどの工夫が必要です。
膝が安定する靴を履く
人工膝関節置換術後は、安定感のある靴を履きましょう。サンダルやヒールなどは、転んだときに踏ん張れず、膝を大きくひねる恐れがあります。
また同じスポーツシューズでも、靴紐タイプではなくマジックテープタイプを履くと、途中で靴紐を結び直すために屈む手間が省けます。
人工膝関節置換術を受ける前に考えたい手術以外の治療方法

人工膝関節置換術を受ける前に、検討するとよい手術以外の治療方法は次のとおりです。
それぞれの治療方法について解説します。
保存療法
膝関節の保存療法は、炎症を抑えて痛みや可動域の制限を最小限に抑えるための療法であり、初期症状から手術を検討する患者が実施します。
人工膝関節置換術を検討している方も、まずは保存療法を一定期間おこない、症状が緩和されるか様子をみるケースが一般的です。
具体的に保存療法には、次の方法があります。
- 運動療法
- 装具療法
- 薬物療法
それぞれの保存療法について解説します。
運動療法
運動療法はリハビリテーションのことを指し、痛みの原因が筋力低下や肥満の場合に効果が期待できます。
| 筋力訓練 | 太もも前にある大腿四頭筋を中心に、膝への負担を分散するための筋力トレーニング |
| 可動域訓練 | 変形性膝関節症の場合は、適切な方向に膝を曲げ伸ばしできなくなるため、可動域の維持改善を試みるストレッチ |
| 生活指導、減量 | 肥満で膝への負担が大きくなっている場合、体重を減らすと症状が緩和するケースが多いため、食事管理や適度な運動の生活指導 |
上記の方法で患者の症状に合わせた運動療法を取り入れると、膝の痛みや可動域の制限が緩和されるケースが大半です。
装具療法
装具療法は、安定と負荷の分散を目的としてサポーターや中敷き(インソール)を使用し、痛みや可動域の制限を緩和します。
高齢者向けやスポーツ用など、用途にあわせてさまざまな種類の装具が販売されているため、膝への不安がある方はすぐに始められる療法です。
自身に最適な装具が分からない方は、医療用装具を用意してもらえる医療機関への受診をおすすめします。
薬物療法
薬物療法は、主に変形性膝関節症と診断された患者がおこなう療法で、患部にヒアルロン酸を注入して痛みや可動域制限を緩和します。
膝関節は潤滑油の役割を担う滑液が減少すると、障害を引き起こすといわれています。滑液の主成分であるヒアルロン酸ナトリウムを直接患部に注入し、不足した栄養素を補い関節機能を補助できる流れです。
再生療法
再生療法は、保存療法の効果がなかったものの手術は避けたい方に最適な自費診療の療法です。
患者自身の血液や脂肪などを採取したあとにキットから細胞を抽出し、関節部分に直接注入すると損傷した組織や機能を修復できる最新療法です。
再生療法にはいくつかの種類があるため、それぞれの治療方法と特徴を解説します。
| 治療方法 | 期待できる効果 | |
| 幹細胞治療 | 患者自身の脂肪を採取して幹細胞を培養し、関節内に注入する | 脂肪由来幹細胞は炎症を抑える物質を生成するといわれているため、関節の炎症や痛みを緩和できる |
| PRP療法 | 患者自身の血液を採取してPRPを抽出し、関節内に注入する | 血漿や血小板には組織の修復する成分が含まれているため、本来の自然治癒力を促進する |
| APS療法 | 専用APSキットを用いて、PRPから抗炎症成分を取り出す | 関節治療に特化したもので、PRPの効果に加えて、関節の炎症物質と抗炎症物質のバランスを整える |
| PRP-FD療法 | 血小板を濃縮したPRPをさらに高濃度化して関節内に注入 | 一般的なPRP療法の2倍以上の修復が期待できる |
再生療法は入院せずに膝関節の痛みや可動域の制限にアプローチするものの、実費療法のため高額な医療費が発生する点がデメリットです。
また、再生療法を実施している医療機関も限られています。
保存療法の効果が実感できない場合、費用や身体への負担を加味したうえで手術か再生療法のどちらかを選択してみてください。
人工膝関節置換術の手術に関するよくある質問
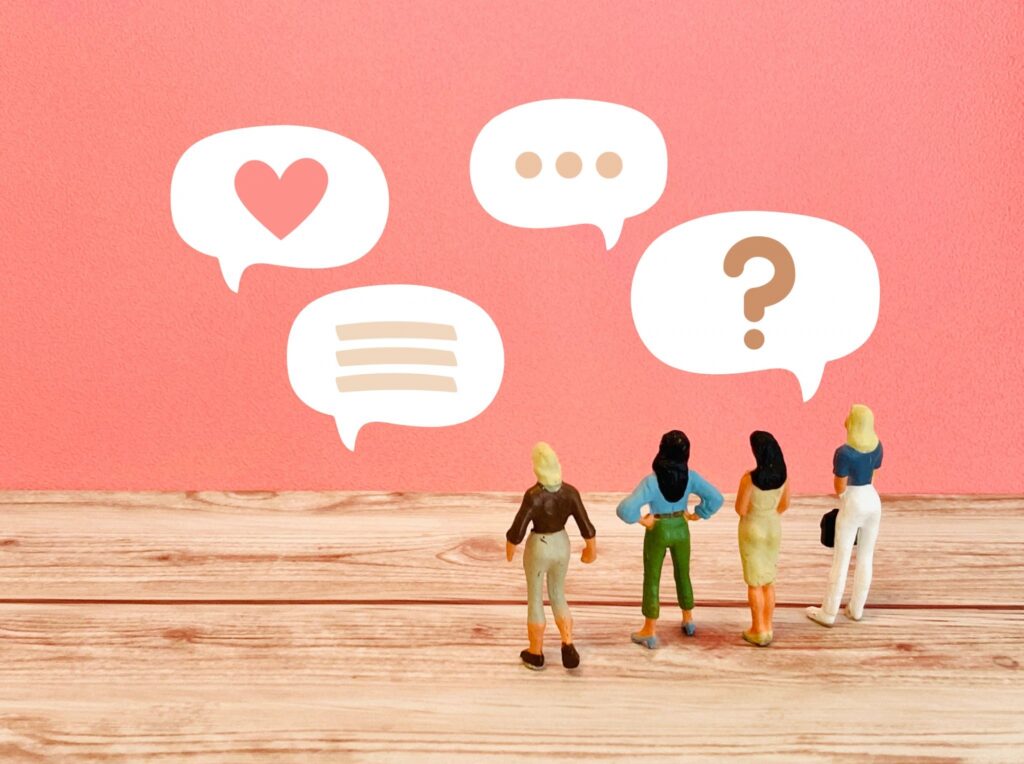
人工関節置換術に関するよくある質問に回答します。
人工膝関節置換術の手術後の痛みはどのくらい?
人工関節置換術の手術後の痛みは、個人差があるものの、一般的には痛みのピークは術後〜手術当日夜といわれています。手術後は時間の経過とともに痛みは緩和され、2〜3日で強い痛みは落ち着きます。
手術の痛みを緩和するための方法として、痛み止めの飲み薬や座薬、注射などが挙げられますが、手術当日は飲む動作ができないため、使用可能な痛み止めは座薬のみです。
さらに手術後の安静期間を終えたリハビリでは、手術による傷口が曲げ伸ばしの動作で強い痛みに耐える患者が多いとされています。
ただしリハビリによる痛みも数日経つと軽減され、徐々に痛みのない生活が送れるようになります。
人工膝関節置換術の入院期間はどのくらい?
人工関節置換術の入院期間は、一般的に約2週間〜1か月といわれています。手術方法によって入院期間は異なり、人工膝単顆置換術(UKA)は約2週間、人工膝関節全置換術(TKA)は約1か月の入院が必要です。
ただし入院期間はクリニックによって異なるため、手術の計画を立てる際に確認してみてください。
人工膝関節置換術のリハビリ期間はどのくらい?
人工膝関節置換術のリハビリ期間は、一般的に3〜4週間といわれています。
手術方法によってリハビリ期間は異なり、人工膝単顆置換術(UKA)は約3週間、人工膝関節全置換術(TKA)は約4週間のリハビリが必要です。年齢や筋肉量、患部の症状により、リハビリ期間は異なります。
とくに人工膝関節置換術を受ける前から歩行困難な状態の場合、筋肉が減少しているケースが多く、歩行機能の回復に時間がかかります。
病棟を移動してリハビリを継続する患者もいるため、リハビリ期間は目安として把握しましょう。
人工膝関節置換術の手術後は何日で歩けるようになる?
人工膝関節置換術の手術後は、大半の患者が約2〜3週間で歩けるようになります。
一般的には、手術翌日から直立したり歩いたりする簡単な動作の練習を始め、1週間ほど経つと杖を使用して歩けるようになる患者が多いです。
ただし、歩けるようになるまでの期間は個人差があるため、自身のペースでリハビリを継続していきましょう。
人工膝関節置換術にリスクはある?
年間7万人ほどの患者が人工膝関節置換術を受けているものの、リスクを伴う手術です。
そもそもリスクゼロの手術は存在せず、人工膝関節置換術の場合は、膝関節に細菌が侵入する合併症のリスクが1〜3%とされています。
とくに、糖尿病や関節リウマチで薬物治療中、ステロイド治療中の方は、通常よりも感染リスクが高くなります。
原則、人工膝関節置換術を実施するクリニックでは、感染症対策や万が一発生した際のアフターケアを徹底していますが、心配な方は医者に確認しておきましょう。
まとめ
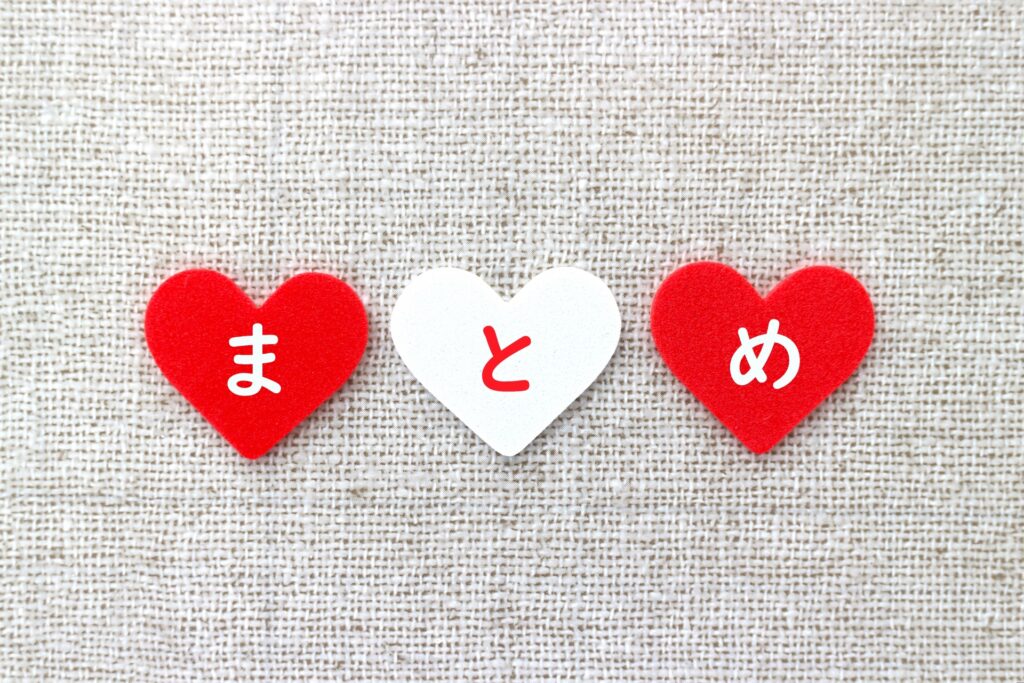
本記事では、人工膝関節置換術の手術費用や入院期間、手術を受けた方がよい方の特徴、タイミングについて解説しました。人工膝関節置換術は高額医療費が発生するものの、保険や制度、助成金などの支援を受ければ最小限の出費に抑えられます。
また人工膝関節置換術を受ける前に、保存療法や再生療法の選択肢もあるため、医師や家族と相談しながら最適な治療方法を選びましょう。
※本記事の情報は2023年1月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。
キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。
<参考>
全国健康保険協会